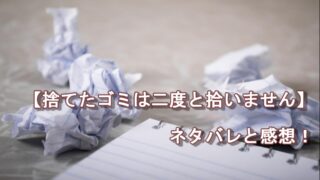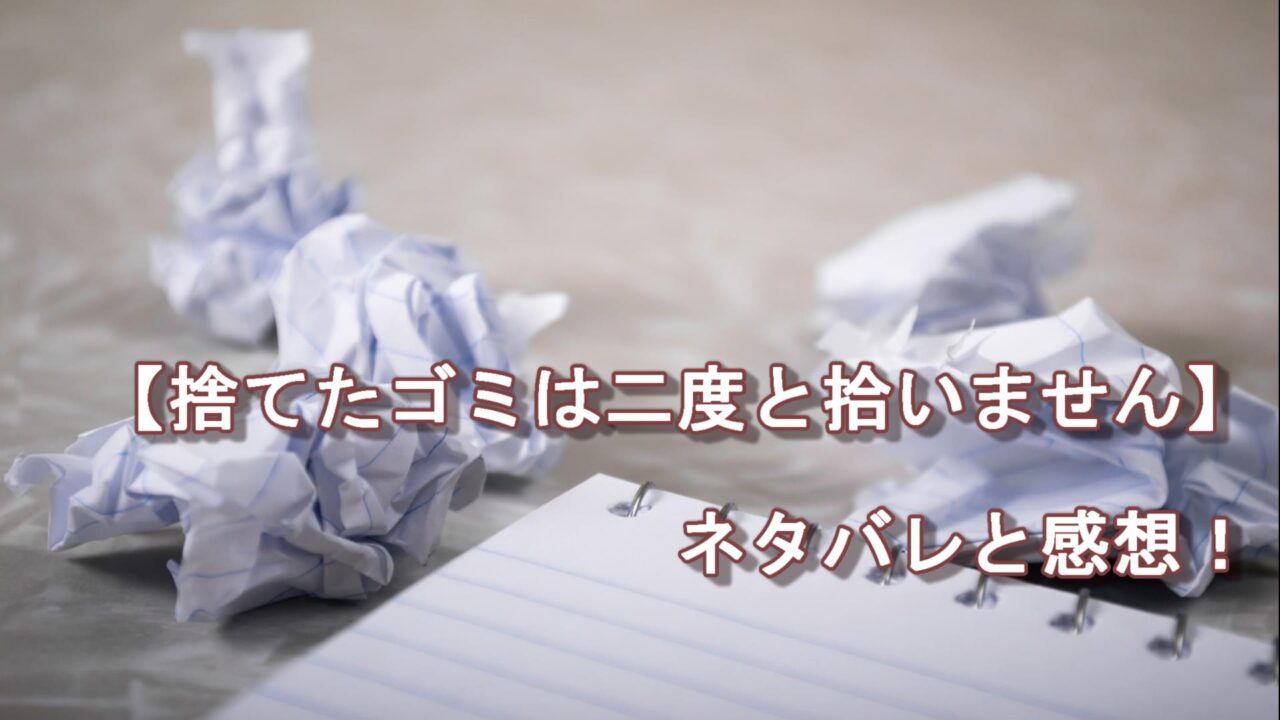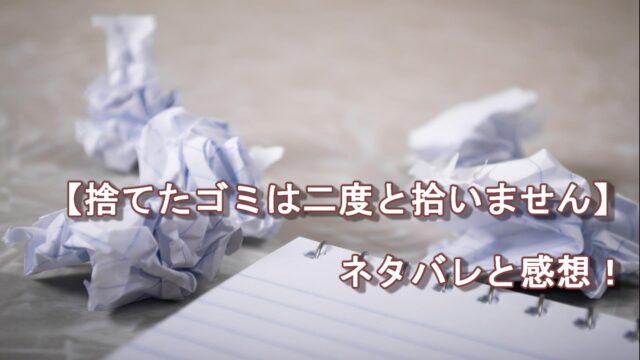こんにちは、ちゃむです。
「捨てたゴミは二度と拾いません」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

104話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 新年祭④
あの視線だけどうにかできたらいいのに。
いっそ「やめてくれ」と言いに行こうか。
フィレンがこれ以上見つめないように―
言葉を交わしたくなかったが、どうしてもダメならそうするしかないと考えていたそのとき、デロント男爵がそっと席を移した。
「えっ……?」
今デロント男爵が立っている場所は、フィレンの視線をちょうど遮る位置だ。
もしかして私が不快に感じているのを察してそうしたのだろうか?
デロント男爵を見上げると、彼は柔らかく微笑んだ。
「しつこく呼びかけているみたいなので、止めておこうかと思って。」
ああ、やっぱり予想通りだった。
私は心から感謝の気持ちを込めて言った。
「ありがとうございます。」
「どういたしまして。皇帝陛下が遅れていらっしゃるようですね。そっちへ行って、軽く何か食べながらお話でもしませんか?」
「……そうですね。」
「レイラ!」
席を立とうとしたそのとき、後ろから誰かが勢いよく抱きついてきた。
ダイアンだった。
「やっぱり帝国だけあって、パーティーが本当に華やかですね!私たちナトゥシャ王国とは比べ物になりません!」
「そう言ってくれて、ありがとう。」
「お世辞なんかじゃなくて、本当に素敵です!すっごくかっこいいですよ!」
ダイアンは特有の陽気さで私の腕をぎゅっと掴んだ。
デロント男爵は戸惑いながら一歩下がった。
ダイアンを見つめた。ああ、デロント男爵はダイアンを見るのが初めてだったのか。
「このがっしりした方は誰?」
それはダイアンも同じだ。
私は微笑みながら、ダイアンにデロント男爵を紹介した。
「こちらは私と一緒に皇帝陛下にお仕えしている補佐官の、ベルン・デロント男爵です。」
「初めまして、ベルン・デロント男爵です。」
「ああ、皇帝陛下の補佐官なのですね。」
ダイアンがデロント男爵に手を差し出した。
「お会いできて光栄です。ダイアン・アンドリナと申します。ナトゥシャ王国で外交官をしています。」
手の甲にキスするのではなく、握手を求める仕草だ。
帝国では、女性から握手を求めるのは非常に稀で、礼儀知らずとされることもあった。
なのに先に握手を求めるなんて——。
周囲の人々も驚いた様子でダイアンを見つめていた。
「お会いできて光栄です。」
反対に、デロント男爵はまったく気にする様子もなく笑顔で手を握る。
その姿を見つめるダイアンの瞳が、わずかに輝いた。
「二人の補佐官ともに、ハンサムで美しい方ばかりですね。帝国の皇帝陛下も、補佐官を選ぶ際には顔を見ていらっしゃるのかもしれませんね。」
一瞬、皮肉に聞こえたが、そうではなかった。
ダイアンは純粋に感嘆しているのだった。
けれども「美しいだなんて」。
「デロント男爵がハンサムなのは確かだけど、私は違うと思います、ダイアン。」
「そんなことないですよ。前から思ってたんですが、レイラさんはとても謙虚ですね。」
「その通りです。」
デロント男爵がダイアンの言葉に同意するように頷いた。
「私もアステル男爵に可愛いって言ったことあるんですが、いつも冗談だと思って信じてくれなかったんです。」
「デロント男爵まで……。もう、その冗談はやめてください。見ましたよね?毎回こうなんですよ。」
「まあまあ、退屈だったでしょう。」
今日初めて会ったのに、デロント男爵とダイアンは昔からの知り合いのように息がぴったりだった。
そんな二人と会話をするのは少し気を使ったが、とても楽しかった。
笑いが絶えなかった。
フィレンがいるという事実もいつの間にかすっかり忘れていた。
「デロント男爵。」
しばらく楽しく話していると、下人が深刻な顔で近づいてきた。
「何事だ?」
「それが……。」
下人はデロント男爵の耳元に顔を近づけてささやいた。
下人の話を聞いたデロント男爵は小さくため息をついて、私とダイアンに言った。
「少し問題があって、ちょっと行ってきます。お二人で話していてください。」
「はい、いってらっしゃい。」
デロント男爵が立ち去ると、私は乾いた喉を潤すために下人にシャンパンを二杯持ってきてもらうよう頼んだ。
お酒に弱いので、アルコール度数の低いものにしてもらう。
「ダイアンもどうぞ。」
「ありがとうございます。」
喉が渇いていたのか、ダイアンはシャンパンを一気飲みした。
もう一杯持ってこなきゃ。
下僕を呼ぼうとしたところで、ダイアンが手を差し出した。
「シャンパンじゃなくて、気になることがあるんだけど、聞いてもいい?」
「もちろんです。」
「デロント男爵、今年おいくつですか?」
突然、デロント男爵の年齢をなぜ聞くのだろう?
まさか?
「ダイアン、デロント男爵に興味あるの?」
「はい、あります。」
ダイアンがデロント男爵に興味があることを、こんなにも堂々と言うなんて。
そのことにもう一度驚いた。
「すごく驚いた顔ね。私がデロント男爵に興味があるのが変なの?」
「そうじゃなくて、ちょっとびっくりしました。関心があっても、そんなに堂々と話す人はあまりいなかったので。」
「誰かを好きになることが悪いことでもないのに、堂々と話せない理由なんてある?」
ダイアンは空になったシャンパンのグラスを通り過ぎるハインに差し出した。
「それで、デロント男爵って、何歳なんですか?」
「年が近いってことしか知らなくて、詳しい年齢はわかりません。」
「じゃあ、恋人はいますか?」
「うーん、多分いないと思います。」
「“多分”ってちょっとあいまいですね。デロント男爵について何かご存じないんですか?」
「お仕事がすごくできるっていうのは知ってます。ああ、それに洗練されていて親切な方です。」
「つまり、あなたたちはごくごく事務的な関係ってことですね。」
そういう話になるのか。
「お役に立てずごめんなさい。」
「大丈夫です。むしろレイラが何も知らないってことのほうが気に入りましたから。」
気に入ったって?どうして?
「興味があるって言うから、ふと気になっちゃって。レイラは気になる男の人いないの?」
「えっ?」
なんの話!?と戸惑ってダイアンを見つめると、ダイアンはくすくす笑いながら手を振った。
「そんなに驚かないで。ただ、レイラも結婚を考える年頃かなって思って聞いてみただけ。」
結婚を考える年齢じゃなくて、適齢期はとうに過ぎたんだけど。
「で、気になる人はいないの?」
「特にはいないです。」
「えっ?本当に?見てるだけでドキドキするような人とかも?そんな男の人、いないんですか?」
「いな……いです……」
「レイラ。」
ふいに耳元でかすれた声が聞こえた。
私を見つめる深い青の瞳と、控えめな微笑み。
そしていつも私を包み込んでくれた優しくて温かい手の感触までが思い浮かんで、言葉が詰まった。
ダイアンは私がためらうのを見て、手を叩いた。
「いるのね!」
「い、いませんって!」
私は両手を振って慌てて答えた。
「ドキドキするような相手なんていないので、そういう質問はやめてください。もしそういう人がいたとしても、私、結婚なんてできませんから。」
「しないんじゃなくて、できないの?」
ダイアンはグラスを唇に持っていきながら、ゆっくりと首をかしげた。
「どうしてできないって思うの?レイラみたいに魅力的な女性が結婚できないなら、世の中の誰も結婚できないと思うけど。」
「それはダイアンが私のことをよく見てくれてるからですよ。」