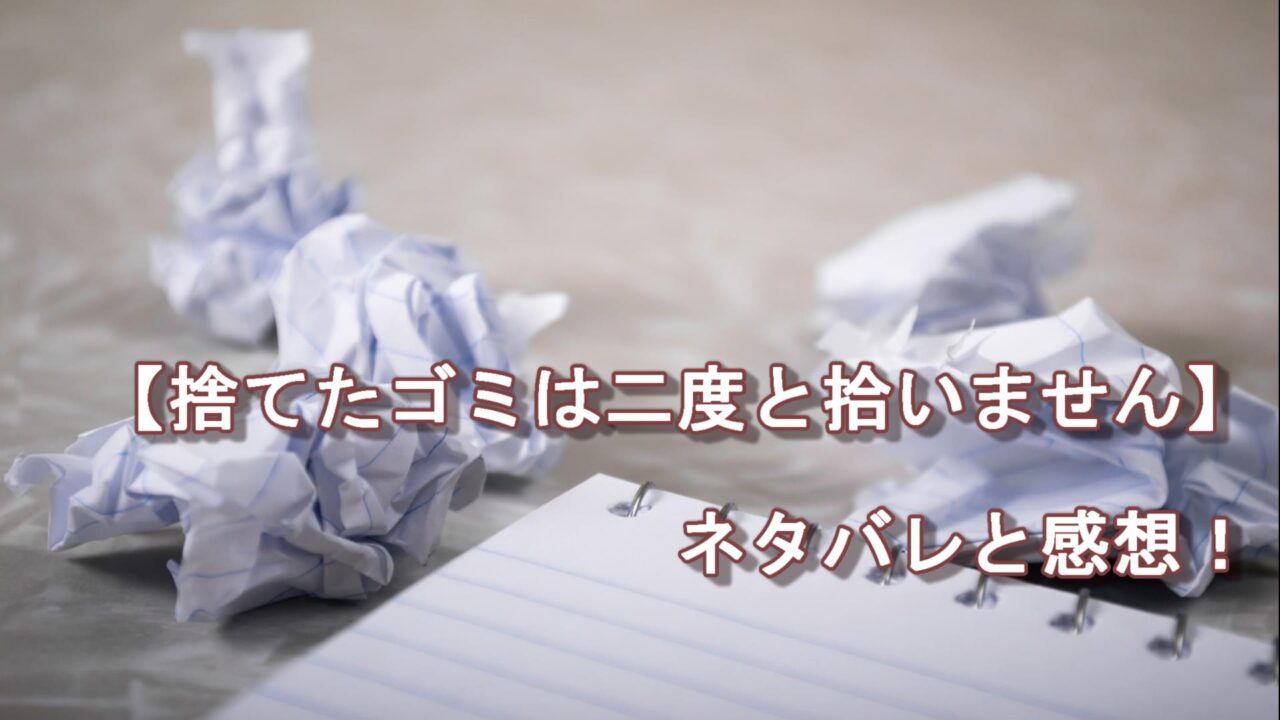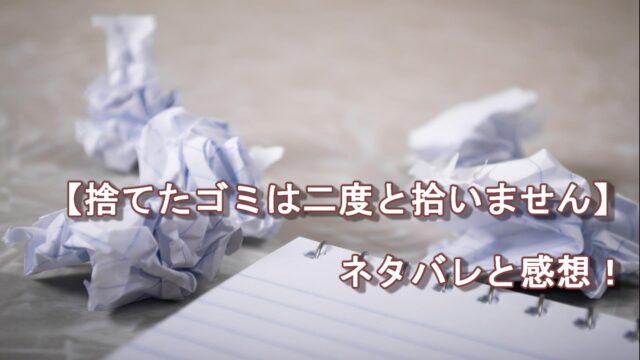こんにちは、ちゃむです。
「捨てたゴミは二度と拾いません」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

108話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 新年祭⑧
貴族や皇族がパーティーや貴族会議のような公式の席に出ることができるのは、18歳、成人式以降だった。
もちろん、フィレンのように不慮の事故で両親を亡くし、爵位を引き継いだ場合は例外だ。
その場合、成人でなくても公式の席に出ることができた。
しかしフィレンは出席しなかったが、それもまた例外の一つだった。
一方、ヘス皇子は今年14歳で、まだ成年式を迎えておらず、公式の席に出たことがなかった。
そのため、皇帝の補佐官として長く仕えてきたにもかかわらず、ヘス皇子を見るのは初めてだった。
ヘス皇子はクラウド公爵夫人のように、目がくらむほど明るい青い髪をしていた。
「投げるよ!」
髪の色や明るい青の瞳が、澄んだ少年の姿とよく似合っていた。
異母兄弟だからか、カリアンとはあまり似ていなかった。
「あっ、落としたらどうするの!」
そう思ったけれど、笑顔を見て確信した。
ヘスとカリアンは確かに血のつながった兄弟だと。
「すみません。ボール拾ってきます」
私は落ちたボールを拾いに行きながら周囲を見回した。
普通、皇子なら侍従や侍女が誰か一人は付き従っているはずだが、誰も見当たらなかった。
見つからないのかと思い何度か辺りを見回しても同じだった。
もしかしてこっそり出てきたのか。
もしそうなら、皆あわててヘス皇子を探しているだろう。
「皇子殿下。」
のんびりとお手玉している時ではないと気づいた私は、謹んでヘス皇子に話しかけた。
「皇子殿下がこちらにいらっしゃることを知っている方はいらっしゃいますか?」
話を切り出す前に、まずは事実確認から。
「うん、知ってるよ。」
あれ、私、早とちりした?
「誰が知ってるんですか?」
ヘス皇子は明るく笑いながら私を指さした。
「アステル男爵は知ってるじゃないか。」
ああ、そういう意味か。
私は気まずく笑いながら、ヘス皇子の目線に合わせて少し膝を曲げた。
「私以外の人は?」
「うーん……」
ヘス皇子は目をぐるぐると動かしながら私の視線を避けた。
やはりこっそり抜け出してきたらしい。
「皇子殿下、そろそろ宮へお戻りになった方がよいかと。」
ヘス皇子は眉間にしわを寄せ、深いため息をついた。
「でも戻ったら、またつまらない帝王学の授業を受けなきゃいけないんだ。」
帝王学だって?
皇太子でもないヘス皇子が、どうして帝王学の授業を受けてるんだ?
皇太子がまだ決まっていない場合、皇太子になれる資質を見つけるために、すべての皇子に帝王学を教えるのだという。
しかしヘス皇子はカリアンの息子ではない。
今はカリアンに後継者がいないため、ヘス皇子が皇位継承順位1位ではあるが、後継者ができた瞬間すぐにその座は奪われるだろう。
もうすぐシンソン王国の王女と政略結婚をするとも聞いたし……。
突然、心臓の左側が針で刺されたように痛んだ。
私が黙って唇を固く噛んでいると、ヘス皇子が心配そうに尋ねた。
「男爵、顔色が良くないよ。どこか痛いの?」
「いいえ。ただちょっと疲れているだけです。」
私は何でもないふりをして笑いながらヘス皇子に尋ねた。
「それで帝王学の授業を受けたくなくて出てこられたんですか?」
「うん、それもあるけど。外国から来た使節たちにも興味があって……」
どうやら本当の目的は後者のようだ。
気になるのも無理はない。
新年祭で帝国全体が賑わう中、成人していないという理由でずっと宮の中にいるだけでは退屈だっただろう。
その上、嫌いな帝王学の授業まで受けなければならなかっただろうし。
「外国から来た使節たちは、あちらの宮殿に行けばご覧になれます。」
私が指し示した方向にくるっと体を向けたヘス皇子の顔に、明らかに好奇心の色が浮かんだ。
「でも困りましたね?今日は特別行事があって、大半の方々は宮殿にいらっしゃいません。」
「……ああ。」
私の言葉に、ヘス皇子はすぐにしょんぼりしながら肩を落とした。
まだ幼いからだろうか。
カリアンやクラウド公爵夫人は表情の変化がほとんどないが、ヘス皇子はすぐ顔に出る。
不思議で可愛らしかった。
もし年の離れた弟がいたらこんな気持ちなのだろうか。
「残念ですが、今日はこの辺でお戻りになって、次は皇帝陛下とご一緒にいかがですか?」
成人式を済ませていないため公式の席には出られないが、だからといって外出してはいけないというわけではなかった。
法的保護者であるカリアンが許可すれば、自由に出歩くこともできた。
私の言葉に、ヘス皇子はふっとため息をついた。
「兄さんが許してくれたら、僕だってこんなことにはならなかったのに。」
すでにカリアンに断られたようだ。
「それでも、こっそり外出されたら他の方々が心配なさいますよ、殿下。」
「それは分かってるけど……」
ヘス皇子はつま先で地面を蹴りながら少し考えて、私に尋ねた。
「じゃあ、外国の使節たちがいるあの宮殿だけ見て戻っちゃだめ?」
「誰もいないと思いますけど。」
「一人くらいはいるかもしれないじゃん。」
ヘス皇子が私の腕をつかんで、哀願するように私を見上げた。
「ちょっとだけでいいから。ちょっとだけ見て帰ろう。」
どうすべきか迷った。
「じゃあ、もう二度とこっそり抜け出したりしない、ね?」
「……本当ですか?」
「もちろん。皇族は二言は言わない!」
ここまで言われたら、丁重に帰ってほしいとは言えなかった。
仕方がない、一度戻るしか。
「おっしゃった通り、少しだけ行ってすぐ戻るんですよ?」
「うん!」
「そして戻ったら、周りの人たちに心配かけてごめんなさいって、ちゃんと謝ってくださいね。」
ヘス皇子はしばらく考えた後、うなずいた。
「わかった。男爵の言う通りにするよ。」
「ありがとうございます。」
「じゃあ、行ってもいい?」
「はい。」
ヘス皇子は明るく笑いながら私の手をぎゅっと握った。
手をつなぐ必要はなさそうなのに。
私は少し驚いてヘス皇子を見つめたが、握られた手を離しはしなかった。
その理由は、ヘス皇子がしっかり握っていたからというのもあるけれど——
「行こう、行こう。」
誰かとこうして手を取り合うのは本当に久しぶりだったから、手のひらに触れるあたたかさがとても心地よく、離したくなかったのだ。
・
・
・
カリアンは儀礼的な行事を終えて皇宮へ戻ってきた。
「へ、陛下!」
ラヘルが取り乱した様子でカリアンに駆け寄ってきた。
その後ろには中年の女性の姿も見えた。
ヘスがいる別宮を担当している侍女長のカタラだ。
「ヘスに何かあったのか?」
そうでなければ、カタラがあんなにも取り乱すはずがない。
カタラは青ざめた顔でカリアンを見つめ、震えながら話し始めた。
「はっ、皇子殿下がいなくなりました。」
「それはどういうことだ?」
カリアンが鋭い声で問い返した。
冷ややかな視線にカタルは目をぎゅっと閉じ、言葉を継いだ。
「はい、帝王学の授業中にお手洗いに行くとおっしゃって……それっきり戻っていらっしゃいません。」
「……また抜け出したのか。」
まだ成年式を終えていない上、安全上の理由から外出は禁じられていた。
にもかかわらず、ヘスはたびたび脱出を試みた。
以前は年に1〜2回ほどだったのが、成長するにつれ頻度が増し、今では半年に1回、最近では月に1度は必ず抜け出しているようだった。
「も、申し訳ありません、陛下!」
カタラが床にひざまずき謝罪した。
カリアンは苛立つように手を振り下ろして言った。
「いい、あなたのせいじゃない。」
もしヘスが普通の人間であれば、カタラを叱責すべきだったが、そうではないため、カリアンは彼女を責めなかった。
『また能力を使って抜け出したんだな。』
ヘスも皇族であるだけに水を扱えるとは思っていたが、その能力はカリアンよりもはるかに優れていた。
皇后の異母弟である嫡統皇子ではなかった。
しかし、一般人であるカタラがヘスを止められるはずがなかった。
「皇宮の外には出ていないはずだ。一緒に探そう。」
カリアンが手を上げると、気配を殺して彼の後ろに控えていたヒルタインとクラウド騎士団たちが姿を現した。
「ヘスを探せ。魔力の流れが強い場所を中心に探せば、見つけやすいはずだ。」
ヘスは人に気づかれないよう、水を使って気配を隠す能力に長けていた。
そのため、魔力の動きを感じ取れる者にとっては、痕跡をたどる手がかりになる。
「外宮に行ったとすれば……」
それ以外にヘスが行きそうな場所を思い浮かべながら命令を下していたカリアンの視線が、
遠くから近づいてくる2つの人影を捉えてぴたりと止まった。
2人のうち背の高い方はレイラで、背の低い方はヘスだった。
「殿下!」
ヘスを見るなり、カタラは彼のもとへ駆け寄った。
「カタラ……」
ヘスは戸惑いながらも逃げずに、素直にカタラを抱きしめた。
「どうかお出かけの際には私に一言お伝えくださいと、何度も申し上げたのに……!」
カタラは泣きそうな声で叫んだ。
ヘスは申し訳なさそうにしながらレイラの目をうかがった。
レイラはそんなヘスを優しく見つめながら、襟元を直してやった。
「……ごめん。」
ヘスはカタラの腕をしっかりと握ったまま、レイラと約束した通り、心からの謝罪を口にした。
「心配かけてごめんね、カタラ。もうこんなことはしない。」
カタラの目が揺れた。
カリアンも少し驚いたようにヘスを見つめた。
これまでヘスが自分から過ちを認めて謝る姿は一度も見たことがなかった。
カリアンは、彼女が涙をこぼすほど叱られても、謝罪しなかった記憶しかない。
『外で何かあったのか?』
もしかして精神的な変化でもあったのか?
それとも何かが彼女の心を変えたのだろうか?
あれこれ考えていたカリアンの目に入ったのは、ヘスを見てにこやかに笑っているレイラだった。
彼女と目が合ったヘスもまたにっこり笑った。
──レイラのおかげか。
どうやら彼女がヘスに良い影響を与えたようだ。
理由は分からないが、その事実だけで気分が良くなったカリアンは明るく笑いながらヘスとレイラのもとへ歩いていった。
「に、兄さん。」
遅れてカリアンに気づいたヘスは、きりっとした顔で彼を呼んだ。
「陛下。」
レイラも礼儀正しくカリアンに挨拶した。
カリアンはヘスの肩に手を置いて、自分の横へと引っ張られながら、レイラに向かって言った。
「君が今までヘスを世話してくれたみたいだな。大変だったろうに、お疲れさま。そして、ありがとう。」
「いえ、皇子殿下が私の話をよく聞いてくださったおかげで、楽でした。」
「楽だったなんてことはないだろう。僕はヘスの頑固さをよく知っているんだから。」
「兄上……」
ヘスは恥ずかしそうにカリアンを「兄上」と呼びながら彼の服の端を握った。
カリアンは優しく笑いながら、そんなヘスの頭を撫でてやった。
誰が見ても仲の良い兄弟だ。
異母兄弟であっても。
彼らがこんなに仲良くなるのは簡単なことではないのに、不思議だった。
見ていて気分もよかった。
レイラは自分でも気づかぬうちに、微笑みながらカリアンとヘスを見つめていた。
そして、カリアンと目が合った瞬間、ふいにカリアンが自分に告白してくれたあの時のことが思い出されたのだった。
「私が君を愛している。」
あの時、自分を見つめてくれた優しい眼差しと、そっと触れられた手の感触が自然とよみがえり、頬がほんのり赤くなった。
心臓がドキドキし始め、真っ赤になった自分の顔をカリアンに見られたくなくて、レイラはとっさに顔を背けた。
「では、これで失礼します。」
「レイラ。」
逃げるようにその場を離れようとしたとき、カリアンが呼び止めた。
レイラは深く息を吸い、すぐに表情を整えてからカリアンの方を向いた。
「はい、陛下。」
相変わらずカリアンの顔はまともに見られなかった。
差し込む夕日がまぶしくて見えないという、都合の良い言い訳を用意していた。
「明日は君の休みの日だったよね?」
元々、週末は休みの日だったが、今のようにやることが多いときには、ベロと交代で休んでいた。
「はい、そうです。」
もしかして出なければいけないのだろうか?
明日は出ても構わないけど、日曜日には別の予定があった。
ダイアンに首都を案内してあげることになっていた。
「どうせ休むなら、ゆっくり休んできて。」
もし日曜日にも来るように言われたらどうしようかと心配していたけれど、それは杞憂だった。
「では、次の週の月曜日にしましょう。」
「はい、陛下。」
でも、陛下は本当に落ち着いている方だ。
まるであの日、自分に告白したことを忘れてしまったかのようだ。
「気にするな」と言っていたのだから、そういうことなのだろう。
私も会うたびに動揺しているわけではなく、陛下のようにもっと堂々としていなければならないのに。
「そうしないと……。」
そうできないような悲しい予感がして、レイラは少しずつ遠ざかっていくカリアンを見つめながら、両手をぎゅっと握りしめた。