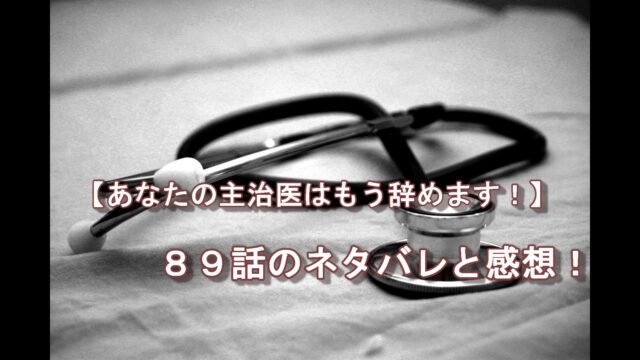こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

158話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 幼いころ②
私は物心つく前から保育院で育ったので、当然のようにそこでの生活に馴染んでいた。
エルベン先生は「お前は四歳か五歳くらいの頃に、ひとりで文字を覚えた」と言っていたけれど、正直なところ自分が文字を学んだ記憶はなかった。
ただ、いつの間にか本を一人で読むようになっていた。
「院長先生、支援金はそのままなのに、子どもの数が倍に増えてしまって……。」
「城に連絡してみたら、来年からは支援金を増額してくれるそうだ。今年の冬だけはどうにか耐えないといけないな……。とにかくまずは食べ物を買うことだ。」
院長先生は、「子どもはよく食べなければならない」という信念を持った人だった。
「じゃあ、余った予算は服や石けんに……」
「何を言ってるんだ?服なんて少し古びても着られるし、石けんだって多少我慢できる。でも成長期は二度と戻ってこないんだ。そのお金で肉をもっと買え。」
改めて言うけれど、私たちの院長先生は本当に合理的で、良い人だった。
「子どもは十一歳になったらどうしても独り立ちしなきゃならん。そのあとは自分で生きる術を身につけるんだ。だが、私たちの庇護下にいる間だけは、できる限り体に良いものをたくさん食べさせておかないといけない。小さい頃から飢えたまま育つと、世の中に対して恨みばかりを抱くようになってはいけないからな。」
十一歳にもなれば、どこかの助手や見習いとして働きに出られる年齢だった。
人手が足りたり専門の人材が必要な場所では、いつも保育院から賢い子どもたちが推薦された。
手先が器用な子は工房や台所へ行き、頑丈だったり体を動かすのが得意な子は傭兵団へ入った。
どちらにも当てはまらない子は、貴族の家の小間使いとして雇われることもあった。
もちろん、私の場合は幼い頃から進むべき道が決まっていた。
私はとても頭が良く、記憶力も優れていたうえに医学書を読むのが好きだったから、当然のように医師の助手になると思われていたのだ。
〈ジェハ保育院〉は少し粗末で、服は十分に支給されず、寄付されたものを着るしかなかったけれど、それでも図書館があった。
だから私は小さい頃から、図書館に置かれた医学書を読み漁りながら過ごしていた。
私にとってはかなり幸運なことだった。
だが、限られた資源で運営される保育院で、すべてが満ち足りることなどありえなかった。
「うーん、賢くてかわいい子を養子にしたいんだが。」
ごくたまに、養子を望んで保育院を訪れる人たちがいた。
親のいない私たちにとっては、大きなチャンスだった。
いくら保育院が悪くない場所だといっても、私たちは決まった時間に食事をし、日に二度以上着替えることもできなかったのだから。
寝る時も大勢で同じ部屋に詰め込まれて、一人でも夜中に泣き出せば、その部屋全員が眠れなくなるのは当然のことだった。
私は赤ん坊のころから保育院で過ごしていたが、もとは家族と一緒に暮らしていたものの、何らかの事情でそうできなくなった子もいた。
実際、そこに入った子どもたちは「家族がいたらいいのに」と毎日のように口にしていた。
「はい、ご覧になって気に入った子がいたら、どうぞおっしゃってください。」
そのたびに院長先生は誇らしげに私たちを並べたけれど、養子を望む人々の顔にはどうしても曇りが浮かんでいた。
着古した服に、小さな傷や痕。
さらには痩せた体つきで、元気そうには見えない顔色……。
〈ジェハ保育院〉の欠点は、養子縁組に結びつく率が極端に低いということだった。
「ええと……まあ、特別に運命的な子、というのは見当たりませんね。」
――私たち皆が似たような境遇だったのだから、それも当然のことだった。
養子を迎えに来た男は困惑した表情で私たちをぐるりと見回したあと、院長先生に助けを求めるような視線を送った。
「おすすめいただける子どもはおりませんか?」
「ふむ、魂が呼びかけてくるような子はいない、ということですね。では、まずご希望の条件を教えていただけますか。」
院長先生が真剣な表情で促すと、男は冷静に答えた。
「まず、我々には娘がいませんので、女の子が良いです。」
「女の子をご希望なのですね、ふむ……」
「それから、十歳以上の子が望ましいです。うちの子どもたちと年齢差が大きすぎると馴染むのが難しいと思うので……ああ、ちなみに我々は下級貴族でして。」
私は幼い頃から養子縁組に特別な関心はなかった。
ただ一日でも早く年齢を重ねて、自分の力で医師のもとで働きたいと願っていただけだった。
だから養子にすると言って人々が訪れるときには、いつも冷めた表情で他の子どもたちの中に紛れて、存在感を消すように立っていた。
うっかり農家のような場所に引き取られてしまえば、医学の道とはまったく別の人生になってしまうと思ったからだ。
それに、そもそも私には「家族」というものがなかったので、それを必要だと思うこともなかった。
ただ漠然と、自分はひとりでも十分にやっていけるだろうと考えていた。
帰郷する前も、家族を探そうなんて思ったことはなく、ただ一生懸命にお金を貯めて、大人になったら――それはまた、彼らが診療所を開いていた理由でもあった。
「我々は平民ではありますが、フェレル……ああ、こう言ってもわからないかもしれませんね。ともかく帝国で最も大きな薬草商団の支部のひとつを任されています。食べることに困ることはありませんよ。」
特に気にも留めずに立っていた私は、「薬草商団」という言葉に思わず耳を傾けた。
医学と薬草は切っても切れない関係にあるからだ。
私はそこで初めて、女の子を養子にしたいと言って訪ねてきた中年の男性をじっくりと見た。
背が高く、赤みがかった髪を持つ、穏やかな印象のある人物だった。
「うちの末息子がもう十一歳になるのですが、賢さが目立って商団主の目に留まったようでして。それで支部の仕事を手伝うことになったのです。ですから、一緒に字を学べるような、聡明な子だと助かりますね。」
おじさんが誇らしげな顔で胸を張った。
なぜ末っ子の話がそこで持ち出されるのかと、私は心の中でため息をついていたが、隣に立っていたプルが小声でささやいた。
「末っ子たちがとても賢いって自慢したいんだよ。院長先生がすぐにその子たちを気に入ってくれれば、機嫌が良くなって養子縁組もしやすくなるでしょ?」
けれども、プルほど気が利かないうちの院長先生は「末っ子たちは本当に賢いんです!」などとは言わず、全く的外れなことを口にした。
「そうですねえ。少し忙しくても、ご飯を食べる時間くらいは与えてくださいますよね?」
プルは大きなため息をつきながら、
「まったく……こんなんじゃ、この子たち、養子に行けないかもしれない……」とぼやいた。
すると、その赤茶色の髪の男性は「ふむ」と咳払いをしながら口を開いた。
「もちろんです。その点は心配なさらなくて大丈夫です。」
「私たちの子どもたちは、一日に必ず一度は肉を食べています。薬草商団といっても草ばかり食べているわけではありませんよね?」
「我が商団の薬草は、むしろ肉より高価なものも多いんですよ。」
「だからといって、野菜を食べないのは良くありません。便秘にもなりやすいですからね。特にほうれん草やブロッコリーは鉄分が豊富で……」
院長先生が食事の説教を延々と続けている間、エルバン先生は難しい顔をして私たちをじっと見回していた。
一方そのころ、院長先生は成長期の子どもたちのための理想的な食事について、延々と講義を始めていた。
「リチェ。」
エルベン先生が私にそっと近づいて、小声でささやいた。
「どうだい?君はいつも医療院に行きたいって言っていたじゃないか。シェムも得意で、頭も良くて、もう十歳を超えているし……」
「結構です。」
私は肩をすくめて、あっさりと答えた。
「医療院の補助と、薬草相談所の補助じゃ、まったく別物ですから。」
私が答えると、隣に立っていたプルが私の背中をドンと叩いた。
「何を言ってるの!今、院を支えてくれるって人の養子縁組を断るつもり?あの人、見た目からしてお人好しで、いい人に見えるじゃない!」
プルは私がためらっているのを見て、さらに熱心に続けた。
「今、院長先生の話を熱心に聞いているのが見えない?あの人は根っからの善人よ、家族に迎え入れるにはぴったりだってば!」
「そんなにいいと思うなら、あんたが行けば?」
「私は男でしょ、バカね。」
「それは残念なことね。」
その後もプルはしばらくの間、私を説得し続けた。
養子縁組は滅多にない大きなチャンスであり、特にあのしっかりとした薬草相談所の末娘として迎えられるなんて、とても大きな恩恵だと皆が言っていた。
「リチェ、家族ができるんだよ。家族ができるってどういうことか、わかる?」
「別に必要だと思ったことはないわ。もともといなかったんだもの。ねえ、あなたは一度も食べたことのないご馳走を、食べたいって思う?」
「君は恵まれた性格だからわからないかもしれないけど、つらくて苦しい時に家族がいるっていうのは、本当に心強いことなんだよ。」
「でも私はきっとつらくも苦しくもならないわ。賢くて真面目で、ちゃんと分別もあるから。」
私はあと数か月で十一歳になろうとしていた。
その年になればすぐにでも医療院で働けるのに、わざわざ薬草相談所でシェムを扱いながら暮らす理由なんてなかった。
ただ、「家族」というものが良いものだということは理解していたけれど。
けれど、それはあまりにも漠然とした感情だった。
本気で自分の人生を変えてまで得たいとは思わなかった。
「でもな、人生はお前の思い通りにはならないんだ。どんなに頭が良くても、何が起こるかわからない。」
プルは大人びた口調で言ったが、私は聞く耳を持たなかった。
「それでも、私には自分の身を立てるだけの力はあるはず。」
そうして私は首を振った。
エルバン先生が戸惑っている間に、院長先生はその男を連れて厨房へ向かった。
だが、その日、中年の男は誰一人として養子に迎えることはなかった。
院長先生と一緒に食事を取り、健康的な食事の大切さを身をもって体験しながら深い議論を交わしているうちに夜が更け、そのまま帰ってしまったのだ。
養子縁組がなかなか決まらなかった私は、特に気にすることもなく、ただ平凡な日々を過ごしていた。
プルの助言も聞き流していた。
けれど幼かったせいか、その言葉を胸に刻みはしなかったものの、内容自体は忘れずに覚えていた。
数年後、ある日突然反乱が起こり、私は突如として死刑宣告を受けた。
何の罪も犯していないのに、ただ死を待つしかなかった牢獄の冷たい夜に、私はふと昔のあの助言を思い出したのだ。
――賢く、真面目に生きれば、つらく苦しいことは起こらないだろう――そう信じていた自分の思い上がりが滑稽に思えた。
プルの言った通り、人生は私の思うようには進まなかった。
反乱という混乱の中で下された皇室の死刑宣告は、私がどれだけ聡明であろうと逃れられるものではなかったのだから。
誰ひとり訪ねてくることのない牢獄の中で、初めて家族について深く考えようとしなかったことを、少し後悔していた。
今ではよく思い出せないあの家に養子に入っていたらどうなっていただろう……。
薬草商団の仕事は退屈だったかもしれないが、それなりに暮らしてはいけたはずだ。
けれど、そうなっていたらエルアンのお父様にも会えなかっただろう。
そして、そうであれば、この世で最も大切なわが子たちにも出会えなかったに違いない。
やはりあのとき「行きます」と答えなかったのは正しい選択だったのだろう。
髪を優しく撫でるエルアンの手のぬくもりを感じながら、私は心地よく眠りに落ちていった。
数日後。
「ディエル!いらっしゃい!元気にしてたかい?」
久しぶりに母に会ったディエルは、にっこりと笑みを浮かべた。
彼の腕にはぎっしり詰まったショッピングバッグが抱えられていた。
「いくら忙しくても、顔ぐらいはもう少し見せておくれ。それが一番の孝行だよ。ほかに何が孝行になるっていうの?」
ディエルの母、モルレキン夫人は、望んでいた通りの息子の顔を見て、うれしそうに目を細めた。
「それでも『両親の日』には顔を見せに来てくれるんだね。」
実際、ディエルはいつも忙しかったが、今日は「両親の日」だったので、時間を割いて来たのだった。
もう子どもではないから手紙を書くことはしなかったが、それでも久々に顔を合わせるには良い口実となったのだ。
モレキン夫人はため息をつき、寂しげに言葉を続けた。
「年を取るとね、子どもたちの顔がどれほど恋しくなることか……。あなたが会いたくて、毎晩毎晩、涙で枕を濡らしているのよ。とりわけあなたは、わずか七歳のときにフェレルマン子爵に見初められて、真っ先に私たちの元を離れていったでしょう……。」
「申し訳ありません、お母様。」
ディエルは気まずそうにモレキン夫人の顔を見つめながら答えた。
「最近は出張も多くて仕事が少し立て込んでいるんです。ご存知でしょう?最近はセレイオス公爵家の仕事も一緒に引き受けているので。」
「仕事が多すぎるなら、いっそやめてしまったらどう?最初からセレイオス公爵家と雇用契約を結んで――」
「これはお土産です。」
「まあ、来てくれるだけでよかったのに、こんなものまで……」
「今日は『両親の日』じゃないですか。」
「そういえば、あなたが拙い字で手紙を書いてくれたこともあったわね。あの時からこんなに大きくなって……。でも、私の腕の中で育ってくれたあの頃が、本当に懐かしいわ。」
モルレキン夫人は深く息をつきながらショッピングバッグを受け取り、中を覗いて驚きの声を上げた。
――それは、都でも高価すぎてなかなか手に入らない、エディナ洋装店の限定スカーフだった!
「こ、これは……!まあ、なんてこと!とても高価なものじゃないの!」
「ええ、それからその中には、ヨングブレ美容室のスキンケアセットも入っています。管理権も含まれていますよ。おそらく3年間は十分に使えるはずです。」
「まあ……そこは貴族夫人しか行けない場所だと聞いていたのだけれど。」
「平民でも受け入れるという話が出るまで、格式を少し上げて差し上げたんです。」
「はぁ……でも、あなたがどこからそんな大金を工面して、こんな高価なものを……。」
管理権を握りしめたモレキン夫人の手が震えた。
実際に記された金額は、到底口に出せないほど高額だったのだ。
「セレイオス公爵夫人が、仕事が多いからと追加の手当をたっぷりくださったんです。この前もフェレルマン子爵様が大幅に給料を上げてくださいましたし、セレイオス公爵様も、息をつく暇のないときには必ずボーナスを下さいます。」
ディエルは気まずそうに咳払いをした。
友情や感謝はお金で示せという言葉を、リチェは確かに守っていた。
モルレキン家が裕福な平民とはいえ、ディエルが贈った品々の価値は到底想像できないほど高価なものだった。
「確かに、やっていることに比べて破格の報酬をいただいていますよ。ですが、お母様がやめろとおっしゃるのであれば、孝行もそこで終わってしまいますから……」
「いや。」
モルレキン夫人はきっぱりと答えた。
「破格の報酬をいただいているのなら、その場にふさわしくあればいい。それをやめるなんてあり得ない。」
ディエルは内心で、母が新しい世界に目を開いたのだと気づいた。
それはまるで、自分が大金を手にしたときに味わった感覚と同じだった。
「ふむ……。次の『親の日』には、こんな立派な贈り物よりも、子どもの頃のようにただ手紙を書いてくれれば……。」
「もう大きくなって、からかうんだから。」
そしてこの世に生まれ落ちた以上、以前のように戻ることはできないのが道理だった。
(ふふ。)
ディエルは静かに笑いながら思った。
(私は母に似たのだな。)
ボーナスを受け取ったとき、自分の表情もきっとあのときの母の顔と同じだったのだろう。
「うちの末っ子、さあ早く入りなさい。ご飯にしましょう。お父さんがあなたが来ると聞いて、一生懸命食事を用意してくれたのよ。」
モルレキン夫人は息子ではなくショッピングバッグを抱えて、ゆっくりと屋敷の中へ歩みを進めた。
「末っ子だなんて、私もういくつだと思ってるんですか。ちょっと恥ずかしいですよ。」
「それでも、私たちにとってはいつまでも末っ子なのよ。ああ、実を言うと、あなた以外にも末っ子を迎えようと思ったことがあったの。」
「……え?何ですって?」
ディエルはまったく初耳で、思わず目を大きく見開いた。
モルレキン夫人はにっこり笑い、落ち着いた声で続けた。
「あなたがフェレルマン子爵家に嫁いでいったあと、商会の仕事が増えて、私も少し寂しくなったから、女の子をひとり養女に迎えようと思ったのよ。だから近くの孤児院に、直接足を運んだこともあったわ。」
「でも、なぜしなかったんですか?」
「私のせいじゃない?」
モレキン夫人は肩をすくめながら言った。
「その保育院で食事だけはたらふく食べて……そのうち食べ物に対する自分の哲学が変わったんだと、第2の人生を生きてみたいと言い出してなかったかしら?その過程で養子の話なんてすっかり忘れ去られたのよ。」
父が歩み始めた第2の人生のことなら、ディエルもよく知っていた。
健康食と料理にのめり込んだ父は、その後、食料品流通にまで手を広げていったのだから。
「とにかく衝撃的ですね。私に妹ができていたかもしれないなんて……。」
「まったくだ。お前の性格からして、その子の世話を一生懸命してやっていたに違いない。」
「ええ、お母様。そのようなことを言わないでください。私は誰かの口添えを受けたことなんて一度もありません。今の公爵夫人とも、ただ純粋な友情だけで……いえ、お金ではなく本当に友情だけでお付き合いしてきたんです。それに孤児院のことですが、今回、公爵様が孤児院関連の予算をまた大幅に増額してくださいました。」
「まあ、本当にあの方はお金持ちなのね。」
ディエルとモルレキン夫人はそんな話をしながら連れ立って食堂へと向かった。
そこには、ディエルとよく似た赤みがかった髪を持つ背の高い父が、きちんと整えられた完璧な食事を用意して待っていた。