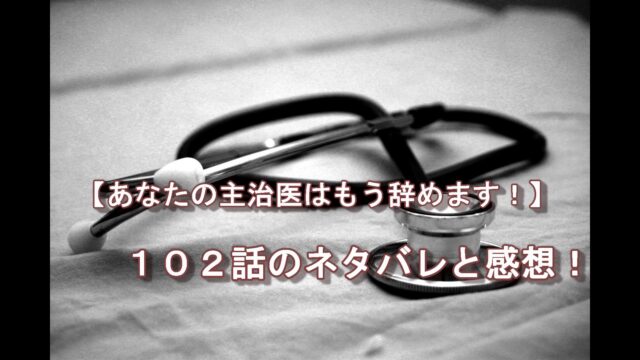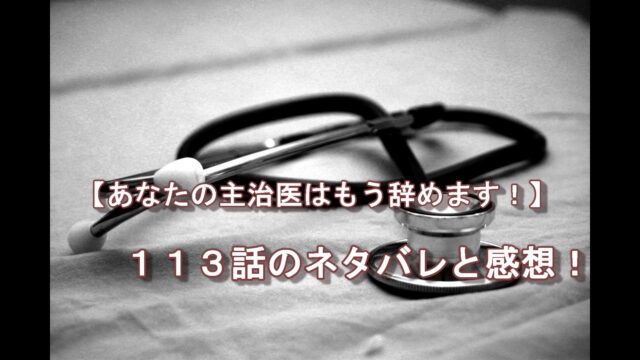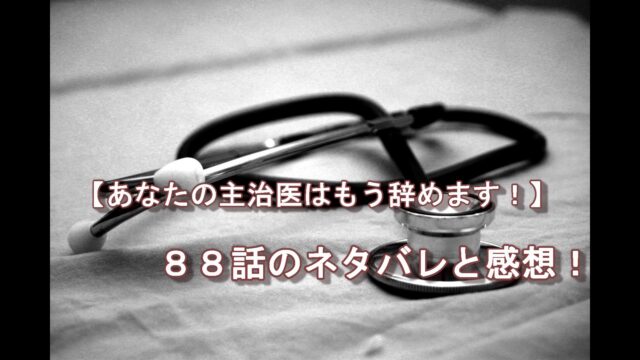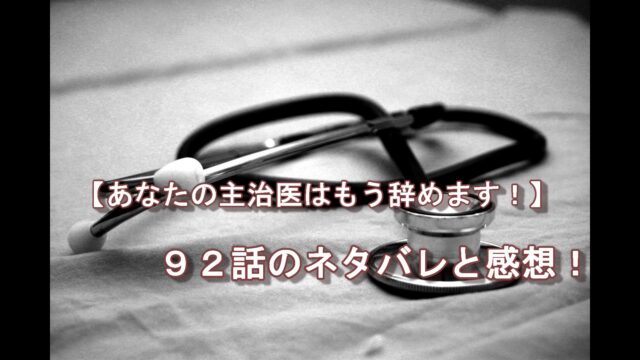こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

134話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 皇室裁判⑤
ハエルドンは王族であるため、所持品検査を受けずに裁判所へ直接入った。
まだ尋問を受けていない彼は、ずっと以前にセルイヤーズ公爵領で投与された菓子型の毒が、今になって明るみに出るとは夢にも思っていなかった。
それは非常に昔のことであり、当時、あの一件を厳重に管理していたイシドール男爵がなぜ今さら?
こうして大勢の人々の前で弁解の余地なく全てが暴かれつつあった。
もう本当にどうにかして抜け出せる方法も見つからないかという希望も消えたも同然だった。
彼はむっつりとした顔で娘を見つめながら立ち尽くしていたアルガを見つめた。
結局彼は、手に入れたいと思っていたすべてのものを持ち去り、生涯の破滅をもたらした……。
半ば狂ったように宮殿をかき乱していた頃は、自分がすべてを手に入れたかのような錯覚に陥っていたが、今ではアルガが自分を見て、そんな風に喜ぶ姿を想像すると、胸の奥がねじれるような嫉妬が込み上げてきた。
自分だけが不幸になることに耐えられなかった彼は、いつも携帯していた護身用の短剣を取り出し、その幸福を壊そうと決心した。
リチェは皇后のそばにいたため、短剣を投げてもアルガの胸元に届く距離ではなかった。
その時、遠くの傍聴席から、チーターのような動きで飛び込んできた大男がアルガをかばうようにして助け出し、短剣を取り上げた。
その瞬間を見逃すことなく駆け寄ったのは、皇室の近衛隊だった。
・
・
・
ハエルデンを捕縛し、皇后の命令に従い、即座に彼を皇宮の拘禁施設に連行した。
しかし、間一髪で助けられたアルガは、まだ気持ちを落ち着けられずにいた。
アルガと共に倒れたエルアンが、簡単には体を起こせないでいるのが理由だった。
以前から何度も警告されていた副作用が現れたのである。
「お願いだ!公爵様!目を閉じないでください! 緊急治療が終わるまで目を閉じてはいけません!」
アルガはエルアンを抱きしめながら叫んだ。
エルアンが自分を守るために副作用を無視して、あの遠くから走り寄ってきたことを理解し、彼の行動を目の当たりにしていた。
「特効薬はどこだ! 一級の解毒剤はどこにある! 今すぐ持って来い!」
しかし、もともと手に入れるのが困難な一級解毒剤を、この再審の場で調達できる可能性はほとんどなかった。
ケインズ卿が急ぎ侍従に何かを指示したが、時間がかかることは明らかだ。
だんだんとぼんやりしていく彼の瞳を見て、アルガは彼の頬を叩いた。
いつの間にか、その声にわずかな反応が現れ始めた。
「意識を失うと幻覚状態に陥り、治療法を見つけるまでいつ目覚めるかわからなくなる!おい! しっかりしろ! 一級解毒剤もないのに!」
エルアンは彼の言葉を聞いて目をしばたいていたが、その顔にはだんだんと痙攣が現れ始めた。
アルガが狂ったように彼の頬を叩き続けていると、いつの間にかセイリンが息を切らして駆けつけてきた。
皇后と一緒に立っていたリチェもすぐさま駆け寄り、エルアンの腕を掴んで引き止めた。
倒れかけたエルアンの体の支えがリチェの失態だったのか、一瞬で気を引き締めた。
リチェはエルアンのそばに立ち、涙を必死にこらえながら早い息を吐き出しつつ言った。
「エルアン様!」
リチェの声が届いた瞬間、エルアンの目がわずかに揺れ動いた。
「本当に気が狂ったんですか?走るなって言ったじゃないですか!」
エルアンはかすれた声で、荒い息をつきながら答えた。
「どうしても見つけたかったんだ、家族だからね、リチェ。」
「応急処置に入る間も、ずっと意識を保ってくださいね。話すのが助けになるなら、続けて話してください。いったいどうしてそんなことをしたんです?」
「君が悲しむ姿を、もう二度と見たくなかった。」
リチェは震える唇をかみしめ、アルガに尋ねた。
「あの、先ほどお持ちになった1級毒って、廃棄されたものですよね?でも、主成分は抜かれていないんですか?」
「おぉ!あるよ!それは抜かれていない!」
1級毒をそのまま摂取することはできないので、当然のことだった。
アルガは狂ったようにエルアンの頬を叩いていた手を止め、その腕を掴みながら怒鳴りつけた。
「エルアン・セルイヤーズ!お前、ついに俺を道連れにする気か?おい!おい!正気を取り戻せ!話を続けろ!」
ただそのまま幻覚状態に落ちていくよりも、1級毒を抑えつけてそれを解毒する方がマシだと、アルガとリチェは判断したのだ。
しかし、医療支援を目的とする控えの部隊には1級毒物を所持している者はいなかった。
リチェは震える手でアルガのジャケットのポケットから注射器を取り出した。
「幼い頃、お前を救ったことを後悔したと一度も思ったことはないのに……。」
アルガはリチェに向かってお守りのような微笑みを浮かべた。
彼女がこの差し迫った状況で注射器の意味を問いただすリスクを理解していたからだ。
「ならば私の血を使えばいいでしょう。ただし、驚かないでくださいね。私はE型血です。」
「そ、それは……ヒリカ麻酔治療をしていない状態でE型血を輸血すると、どうなるんですか?」
「ショック症状が現れるか、最悪の場合、脳死状態に陥るでしょう。」
アルガのE型血は、1級毒物に匹敵するほどの高い毒性を持っていた。
「まったく、また人を救うことになるとは。正気を保ちながらも、これでまた娘に叱られる羽目になるんだろうな……。」
リチェは歯を食いしばりながらアルガが差し出した腕から直接血を採る。
その場にいた人々のほとんどは、なぜリチェがアルカの血を採るのか理解できなかったが、この状況下でその理由をすぐに尋ねることは不適切だと悟っていた。
そばでその様子を見ていたセイリンは、恐怖と混乱が入り混じった表情を浮かべながら、震える声で呟いた。
「くそっ、どうしてあんなにも徹底的に一貫しているんだ?あれって本物の狂人じゃないか?」
かつての会話を思い出しながら、彼女は呆れたように呟いた。
「死を覚悟するって言っていたけど、本当にその覚悟のまま死のうとしてるなんて、どうするつもりなの?」
実際に階段を駆け上がるエレナの姿を確認しながら、セイリンはようやく安堵の息を吐いた。
エレナがどこかへ走り去る前に、セイリンはその背中をじっと見つめていた。
「どうやったらあの皇子をこんなにも苦しめることができるのでしょうか。本当にこのままジェイド皇太子が死刑宣告を受けて処刑されて終わるなんて、あまりにもひどい話です。シオニーはあんなに苦しんで死んだのに、私たちの家族は長い間罪悪感に苛まれてきたのに。」
「そうですね。」
「ましてや、ハエルドン皇子は子どももいないので、アルガが彼の気持ちを知るはずもありません。」
「いや、それは大した問題ではありません。私が考えた方法は……」
エレナの言葉を聞きながら、セイリンは自分が決して共感できない冷酷な人物だという現実に直面していた。
しかし、ほんの少し前まで冷静に自分と会話していたあの冷酷な人間が、アルガのために身を投げ出し、あんなにぐったりしている姿を目にして驚かざるを得なかった。