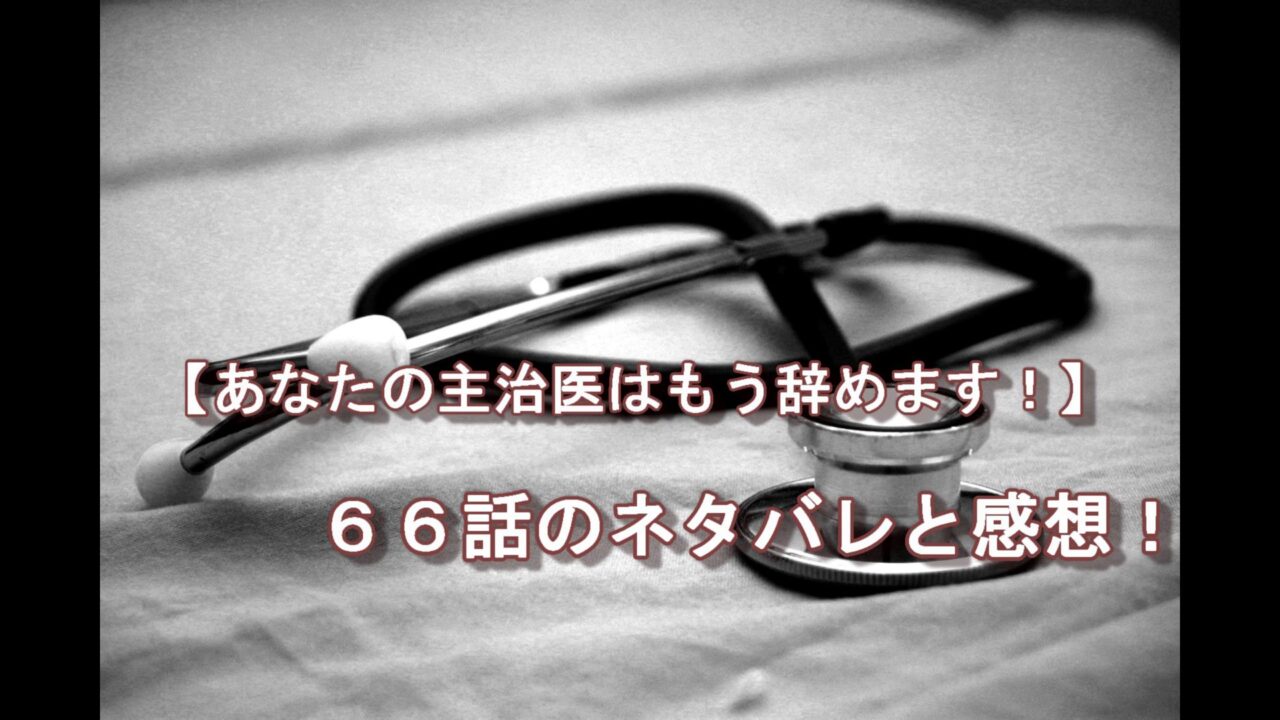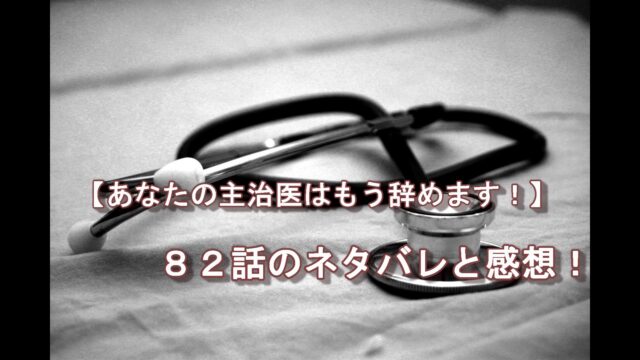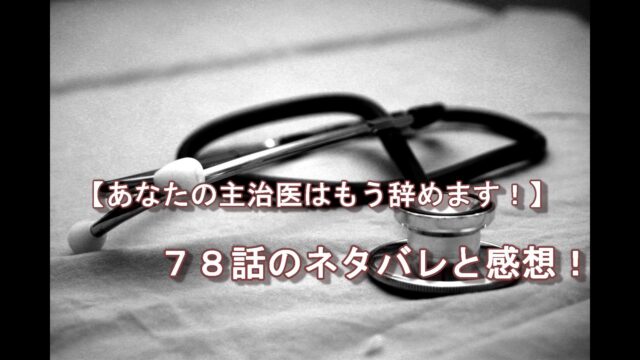こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
今回は66話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

66話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- side アーロン
アーロンは興奮して死にそうだった。
久しぶりに味わう自由が、これほど素晴らしいとは知らなかった。
どうせ明日は閉会式なので、今日が実質的に狩猟大会の最終日。
そのため、ついに手入れしなければならない薬草がないとし、ディエルが自由を与えたのだ。
『まあ、見物でもしなさい。意外と見るものが多いですよ、華やかで。夕方までにお戻りください』
過ぎた時間を思うと、本当に涙が目の前を遮る。
「ウェデリック様が、公爵領を占めたら・・・」
彼は歯ぎしりしながら考えた。
「二人とも私が直接最後まで苦しめて苦痛に殺す」
その「二人」とはディエル・モレキンとリチェ・エステルだった。
リチェ・エステル、魔女のような女は逹成感のない退屈な仕事を狂ったようにさせた。
そして、その後ろには徹底的に自分を監視する憎らしいディエル・モレキン。
ずっと閉じ込められていた彼の心は燃えそうに焦っていた。
再び公爵城に入って、あの恐ろしいことを繰り返したくなかった。
薬草を手入れして、分厚い本の内容を何度も書き写した記憶はゾッとするほどだ。
もちろん、それで役に立ったこともあったが。
「早く、最大限早くウェデリック様がセルイヤーズを獲得してこそ・・・」
普通の人とほとんどコミュニケーションが取れない彼の目には、狂気さえ幼かった。
誰も監視せず、強迫のように与えられた仕事から抜け出すと、ついに息を少し吸えそうだ。
彼は静かな森の中に入り、鳥の鳴き声をかけ始める。
かつてケインを呼んでいた、まさにその音だった。
そのように鳥の鳴き声を休む間もなく出しながら時間がかなり流れると、ウェデリックが何人かの護衛を連れて現れた。
「アーロン、久しぶりだね」
ウエデリックは気取りながらアーロンの肩を軽く叩いた。
「あの邸宅で助手の助手として認められたという話は聞いた」
アーロンは満足そうにうなずく。
その認定を受けるためにどれだけ自分が努力したのか、ウェデリックは知らないだろう。
それだけ、もう成果を上げたいという気持ちが大きかった。
彼の右腕になることは、自分の身分回復のための第一段階でもあるのだから。
「ところで・・・ケインさえもバレたんだって?」
「はい」
アーロンはため息をついて首を横に振った。
「公爵城の雰囲気はどう?」
アーロンは実際にそのような雰囲気を全く知らない。
温室か、あの部屋に閉じ込められていたからだ。
しかし、どんな答えがウェデリックを喜ばせるかは知っていた。
「良くないです。エルアン様はあまり徳がなく、公爵城を掌握できずにいます」
「性格が汚くなったのは事実だからな」
ウェデリックはにっこり笑ってうなずいた。
「それに兄の女を欲しがる悪い癖まである」
「もしかしてベティア令嬢と何かあったのですか?」
「宴会の時、堂々と最初のダンスを申し込んでいた」
「典型的な劣等感ですね」
アーロンはすぐに機嫌を取りながら言った。
「幼い頃からウェデリック様が持っている全てのものが羨ましかったようです」
「そういうこともある」
ウェデリックは傲慢にうなずいた。
「やっばり、あの城の主は私のほうが似合っているな」
「ところで・・・」
アーロンはウェデリックの後ろを見ながら尋ねる。
「イシドール男爵様はいらっしゃいませんか?」
「おばさんが病気だって。エルアンに頼まれて、今、セルイヤーズ領地に行かれたんだ」
「まさか?」
「違うよ」
ウェデリックは首を横に振った。
「あっちにはこれ以上つける人がいない。本当にどこかちょっと良くないみたいだね。もともと体が弱いから」
「そうなんですね。では、もしこの機会に・・・」
「父さんは考えすぎだ」
臆病で極度に気を使うイシドール男爵とは違い、ウェデリックはまだ若くて覇気がある方だ。
そのため、彼は父親の過度な心配がもどかしく感じられる時が多い。
「指令を受ければ分からないが、直接何か仕事をされる方ではない。しかし、今回の皇太子暗殺に成功すれば・・・」
ウェデリックは遠くを見た。
「そうすれば仕事がもっと早く簡単になるかもしれないし」
「もっと簡単な方法を私が見つけました」
アーロンはにっこり笑って彼に近づく。
「主治医の助手をしているので、アクセスできる情報があったのです」
「どういうことだ?」
「皆隠していますが、エルアン公爵は今持病を患っています」
ウェデリックの目が輝いた。
アーロンは意気揚々と腰に手を当てる。
「こんな情報を知って来いと私を入れたのではないですか?」
「そうだね」
ウェデリックは興奮して答えた。
「平民3人を十数年間投入しても成果がなかったが、やはり君を投入すると数ヶ月も経たないうちにこのような成果を出してくれるね」
「リチェ・エステルが私に今までずっと薬草の手入れをさせました。わざわざここまで連れてきて」
アーロンは頭をもたげて言った。
「ベイガ、キリッチ、ビギダプールです」
「それって・・・何の意味があるんだ?」
「この3つの草がものすごくたくさん入る処方はたった1つだけです」
アーロンは医学にあまり興味がなかった。
ただ、リチェの助手として入らなければならないため、他人がする分だけ浅く広く勉強していったのだ。
それにもかかわらず、大まかに用語や原理は全て知っていて、本程度は読めば全て理解が可能だった。
自分が500回も書き写した「下半身特殊疾患の理解」で大事に扱っている病気を知らないはずがなかったのだ。
「ロイカ症候群です」
「何それ?」
「左膝の上に現れる疾患で、先ほどお話しした3つの草で作った環をたくさん食べてこそ日常生活が可能なのです」
「う一ん、今エルアンは狩猟大会で1位だが」
ウェデリックは歯ぎしりしながら呟く。
「だからみんな、セルイヤーズ先代公爵が生きて帰ってきたようだと大騒ぎだよ。幼い時のその劣等感に疲れた若造の姿は一つも知らずにね」
あちこちでエルアンに対してひそひそ話す姿を見ると、ウェデリックは胃がむかむかするようだった。
あまりにも長い間、セルイヤーズ公爵の上に対する熱望を持っていたためか、今はエルアンが自分のものを奪ったように感じられた。
エルアンと宴会で初めて踊った後、密かに自分に距離を置くベティアのことを考えると、さらに歯ぎしりする。
「その為替だけ飲めば、ロイカ症候群は何の症状も現れません。そんなことと関係ありません」
アーロンは熱心に説明した。
「しかし・・・左膝に鉄が触れるだけでそのまま即死してしまいます。南部地方の風土病気なので帝国では珍しい病気なのです」
「そうなの?イルビアからかかってきたみたいだね」
ウェデリックは乾いた唾を飲み込んだ。
折しも彼には弓がある。
剣術には弱くても弓はかなり上手だった。
「よく見ると、エルアン公爵は足だけは木を重ねた鎧で囲んでいるはずです。他の人と確かに違います」
「・・・そうだったようだね。うん。上半身はほとんど保護具がないけど、下半身は確かに違った」
「ですが、夏の鎧の特性上、足を曲げる時に膝の下が出てくるしかないですね。その時短剣を突いたり矢を命中させさえすれば・・・」
アーロンはニッコリと笑う。
「即死なのです」
狩猟大会であるだけに、言いたいことは多かった。
護衛騎士がウサギを撃とうとしたが、誤ってかすった、急所ではないので危険だということも知らなかったと言い張れば良いのだ。
誰が見ても死ぬほどの負傷を負わせなければいいのだから。
「この事実は公爵城の誰も知らないようです。確かに、リチェ・エステルがそのような弱点になるような事実を広める性格ではないですよね。私も助手の助手なので分かったのです」
「そうなんだ」
アーロンとウェデリックが密会をしましたね。
エルアンの傷は本当のこと?それとも・・・。