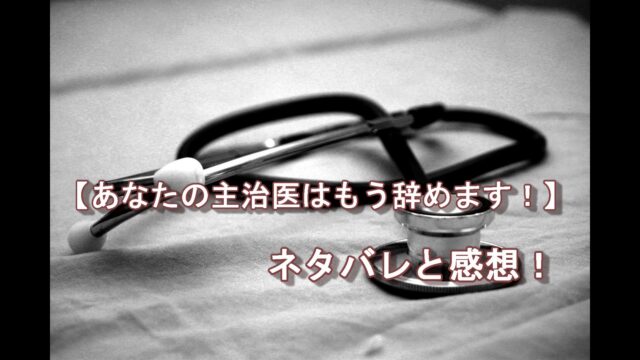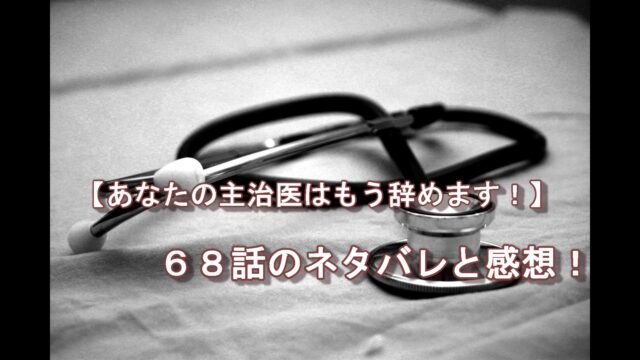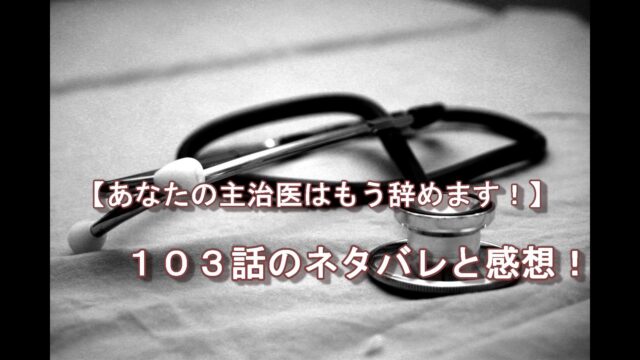こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

164話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- カンシアと子供たち
「さあ、セドリアン。」
ある星の美しい午後。
リチェとエルアンは旅の準備をすべて終え、庭の前で子どもたちと一人ずつ別れの挨拶をしていた。
エルアンは息子の目をしっかりと見つめ、真剣に言った。
「長くはならないだろうが……それでも、万が一に備えて最後にもう一度、非常時の対応方法を確認しておこう。」
「はい!」
「もしお母さんやお父さんがいないときに、予想もしなかった奸臣たちがやって来たら、どうすればいい?」
セドリアンは母に似た澄んだ緑の瞳をきらめかせながら答えた。
「お祖母さまのところに行ってください!そして『ついにこの“スルプケド”が役目を果たすときが来ました!』って言うんです。」
「でも、そんなふうに言ったのにお祖母さまがぐずぐずして、ベッドから起き上がらなかったらどうする?」
「大きくため息をついてから、 『仕方ないわ……お祖母さまの愛らしくてか弱い孫娘が、この狼のような奸臣どもの前に出て、惨めに翻弄されるしかないのね……』 と、震える声で証言するんです。」
「とてもいい。」
エルアンは満足げに微笑むと、再び口を開いた。
「じゃあ、もしお父さんとお母さんがいないときに、どこか具合が悪くなったら?」
「執事に言ってください。それから、万が一に備えて外祖父に手紙を書きます。手紙を受け取ったらすぐに駆けつけてくださるはずだから、症状は書かなくても大丈夫です。」
「それから……もしお父さんとお母さんがいないときに、困ったことや自分では処理できない厄介なことが起きたら?」
「ディエルを呼びます。そんなことはないと思うけど、万が一ディエルが面倒くさそうな態度を見せたら『母は友情を必ず表現する人だ』って伝えます。」
「そう言っても、もし本当に急ぎの用事で言い訳をされたらどうする?」
「そのときは『たぶんお父さんは、お母さんよりも何倍も大きく感謝を表してくださると思うよ。きっと数字も大きいはずだから』と言って、顎を軽く上げて笑ったんです。」
「ああ……」
エルアンは感嘆して、息子をぎゅっと抱きしめた。
「うちの息子はどうしてこんなに賢いのか?」
もちろん、セドリアンはそんなエルアンの感嘆に対しても冷静に答えた。
「生まれつきですから。」
セドリアンは外見的にもリチェにそっくりだった。
柔らかい茶色の髪に、澄んだ緑の瞳、そして丸みを帯びた可愛らしい顔立ち。
それに加えて幼いころから医学方面で抜きんでた才能を見せていたので、アルカはセドリアンを見るたびに、
「リチェも幼いころはこんなふうだったのだろうな」と感じずにはいられなかった。
「クジラよりも記憶力や応用力が優れているでしょう。だから、お父さんとお母さんが少し外出しても心配しなくて大丈夫です。生まれつき賢く生まれたのですから。」
「お父さんとお母さんだけ外出して、さびしくなったりしないの?」
「大人には大人の事情があります。一緒に行けたらいいけど、待っていればまた一緒に過ごせるから大丈夫です。」
大人のように答えるセドリアンを見て、エルアンは思わず笑った。
はっきりと話す様子が、幼いころのリチェを見ているようだったからだ。
本当にリチェにそっくりな彼の息子は、愛おしくて仕方がなかった。
誇り高く、少し生意気なところまでがとても可愛らしかった。
「さあ、じゃあ。」
エルアンはセドリアンの髪を撫でながら、からかうように尋ねた。
「最後に……もしお母さんやお父さんがいないときに、遊びに来た男の子の一人がユリアにしつこくしたら?」
これまで迷いなく答えていたセドリアンの瞳が、そのとき初めて揺れた。
リチェに似てひたすら清らかで優しく見えていた緑の瞳に、エルアンに似た鋭さが一瞬だけ走ったのだ。
「人がいなくなれば困るんですよね?でも大丈夫。毒薬くらいなら一人でも作れますから……」
それまで柔らかかった顔が、たちまち冷たく鋭い表情に変わった。
ちょうどそのとき、ユリアの手を引いて部屋に入ってきたリチェが、不意をつかれたように耳にしてしまった。
「セドリアン!医学は人を救うための学問であって、人を死なせるための学問じゃないのよ!」
リチェは厳しい顔でセドリアンを見つめながら言った。
「優れた医師には慈悲の心が必要なの。セドリアン、エルアンに似た顔をするんじゃなくて、目に力を宿しなさい!」
「……でも……」
セドリアンの言葉に応えたのは、エルアンだった。
「そんなことが起こったら、セドリアン、お父さんに連絡すればいいんだ。」
エルアンは優しい眼差しでしっかりとした言葉を口にした。
「お父さんは医者じゃないから、良心の呵責なんてないんだ。これくらいは自分で片づけられるから。」
「もう、本当に!」
リチェがエルアンの背中を軽く叩いた。
「あなたは見た目が怖いから、そんなこと言うと冗談に聞こえないのよ。」
エルアンは「冗談だと思うか?」と言いかけて、言葉を飲み込んだ。
幸いユリアが割って入ったからだ。
「私がやりますから、みんな心配しないでください。」
最近剣術を習い始めたユリアは、常に身につけている木剣をトンと示しながら、自信満々に言った。
「若いころのお父さんが剣を習っていたら、きっとこんなふうに上手だったんだろうって、ホアキン団長が毎日のように褒めてくれるんです。」
エルアンは幼い頃よく病気をして、十歳を過ぎてようやく剣術を始めたのだった。
だからホアキンがユリアを通じて幼い頃のエルアンを重ねて見ているのも、あながち間違いではなかった。
黒髪に緑色の瞳を持つユリアは、リチェよりもエルアンに似ていて、昔から満足のいくほど不思議ではなかった。
幸い、表情や雰囲気までエルアンに似て少し大人びて見えても、愛らしさを失うことはなかった。
「もちろん、ホアキン団長がただの戯言を言っているわけではないと思います。」
ユリアは目をそらし、考えに沈みながらつぶやいた。
「たまにちょっと信じがたい話をするんです。父さんにも性格的に未熟だった時代があったなんて……本当に信じられない。」
リチェとエルアンは、ユリアの無垢な顔を見て一瞬冷や汗をかいた。
ホアキンの言葉は、実際のところ間違ってはいなかった。
エルアンはリチェがアレガの娘だと知る前までは、人格教育をほとんど受けていない……いや、かなりの無鉄砲だったのだ。
けれど、その後大きな悟りを得て人が変わった。
だからユリアの目には、エルアンはそんなに悪い人には見えていなかった。
むしろエルアンは我が子たちにとても誠実だったので、ユリアがエルアンを「母には少し生意気な態度をとるけど、それ以外は立派な人」と思うのも当然で、性格を疑う余地など全くなかった。
たまに使用人たちが驚くのも、それくらいのことだった。
エルアンがあまりにも不細工だったからだと思った。
だが、人相が少しきついくらいなら大丈夫じゃない?
それでも格好よかったのだから……。
しかも、人相がきついのはまだ幼いユリアも同じだったから。
使用人たちがいつも察して支えていたので、実際ユリアはエルアンが目下の者たちに怒鳴る姿を見たことがなかった。
「お父さんは本当に寛大で優しいじゃないですか。怖い顔をするときも、本当に真剣なときだけですよ。とても誠実で柔らかい公爵さまなんです!」
ユリアの抗弁に、セドリアンも思わずうなずいた。
実際、子供たちの目に映るエルアンは、穏やかで気さくな父であり、欠点のない有能な公爵だった。
少し困ったようなエルアンの顔を見ながら子どもたちはさらに声を張り上げ、彼の人柄を疑う余地はないと訴えた。
「お父さまが他人に横柄に振る舞ったり、乱暴な言葉を使ったりするなんて……そんなこと想像すらできません!」
「お父さまは前向きで、世の中を優しい目で見つめる方ですから!」
子どもたちの主張には揺るぎない信頼が込められていた。
それは、愛する両親への無条件の尊敬と、盲目的なまでの信じ切った心だった。
「ふむ……」
エルアンはどこか照れくさそうな顔でつぶやいた。
「まあ、リチェと結婚してから、世界が美しく見えるようになったのは事実だけど……」
少し自信なさげな言葉に、リチェが慌てて言った。
「まあ、子どものころは誰だって少し未熟なものだわ。そう考えれば、私だってとんでもなく生意気だったんだから。」
リチェはどうにかしてこの気まずい話題から抜け出そうと必死に言葉を続けた。
「私だって…… うーん、人にとってあまり良い人間じゃなかったと思うわ。私、口うるさいところがあったから。」
「でも、泣いたりはしなかったですよね?」
「え?そうね……でもどこか無愛想に見えていたかもしれないわね。」
その言葉にセドリアンがしっかりとうなずいて答えた。
「お母さまがそんなことをなさるはずありません!お母さまはいつも実力の分だけを誇っているんです。だから、実際以上に見せようとするなんてありえません!」
普通の人々は「実力以上にずっと謙虚だ」と評されるものだが、少なくともエルアンにはリチェがそう見えたことはなかった。
実際、リチェの性格は変わっていなかった。
幼いころはまだ若く未熟だったせいで、力を証明しなければならない場面が多く、自分から実績を宣伝するしかなかったのだ。
しかし今では誰もがリチェの実力を認めており、もはや「私は天才です」などと口にする必要はなかった。
帝国中の誰もがその事実を知っていたからだ。
「それでも……間違ったことを言う人を寛大に受け止められるくらいにはならなければいけなかったのに、私、世間での立ち回りは少し未熟だったわね。」
リチェが笑いながら話すと、ユリアがしっかりとうなずいた。
「お母さんは誰にでも親切じゃないですか。平民として暮らしたことがあるから、人を見下したりしないんですよ!」
「うーん……それは平民とか貴族とかの問題じゃなかったけれど……」
「お母さんとお父さんは、一人の人間として見れば完璧なんです。本当に。」
セドリアンは確信に満ちた声で結論を下した。
リチェが戸惑ったような目でエルアンを見つめたが、エルアンはただ微笑むだけだった。
むしろ普段よりも澄んだ光を帯びたその瞳は、平素よりもさらに清らかに見え、あえて真実を教える必要もないと語っているかのようだった。
それでも、エルアンの誠実な人柄についての結論はすでに出ているようなものだった。
とはいえリチェも、今になって真実を知るべきだといいながら、かつてやんちゃだった父の過去の姿を子どもたちにわざわざ教える気にはなれなかった。
「まあ……子どもは見えるものしか信じないからな。」
リチェは少し冷ややかに呟いた。
妙に胸がチクリと痛んだけれど、結局いくら「私たちはそんなに完璧じゃないのよ」と言ったところで、子どもたちが信じるはずはないだろう。
大きな変化が起きない限り、今のように暮らしていくなら、子どもたちの評価が変わることはないはずだ。
「とにかく、私たちは行ってくるわね。」
リチェはもう一度、セドリアンとユリアをぎゅっと抱きしめながら言った。
「次は家族みんなで一緒に行こうな。」
「はい!」
リチェとエルアンは急遽ラベリ島へ行くことになった。
リチェの遠い親戚が結婚式を挙げることになり、リチェ夫妻を招待したからだ。
子どもたちを連れて行きたい気持ちはやまやまだったが、距離があまりにも遠く、幼い子どもたちには無理な旅になると思い、置いていくことにしたのだ。
しかもラベリ島まではかなり長い航海をしなければならなかった。
どう考えても子どもたちは城に残して行くのが正解だった。
イサベルも「私がちゃんと見ていてあげるから心配しないで」と胸を張って言ってくれたし、城の中には子どもたちをよく世話してくれる人がたくさんいた。
こうしてまだ幼い子どもたちを残して、リチェとエルアンは公爵城を空け、長期の旅に出ることになった。
幸い子どもたちもだいぶ成長し、夫婦そろって出かけるのは問題ないと判断されたのだ。
とはいえ、二人がそろって城を留守にするのは初めてのことだった。
「大丈夫よね?お母さまもいらっしゃるし、お父さまも時々見に来てくださるって言っていたし。」
城を出ながらリチェが心配そうに後ろを振り返った。
「そうだ。特に問題になりそうな客の予定もないし、国としての大きな行事もない。」
客観的に考えても、特別な変化は何一つない状況だった。
「どう考えても、何か変わったことが起きるはずないわ。本当に細かいところまで確認したでしょう?」
「そうですね。」
リチェはため息をつきながら一度うなずき、さりげなく話題を変えた。
「でも、子どもたちが私たちをあまりに理想化しているように見えませんか?まあ、まだ幼いから仕方ないですが……」
「俺は悪くないと思うけど。」
エルアンはにっと笑いながら肩をすくめた。
「むしろ子どもたちが本当のことを知ってしまったら、もっと悲しくなる気がする。子どもたちの前では完璧な父親でいたいんだ。」
「今の様子じゃ、その日が来ることはなさそうですね。」
リチェは彼を見て、柔らかく微笑み、二人は目を合わせた。
馬車は穏やかに進み続けた。