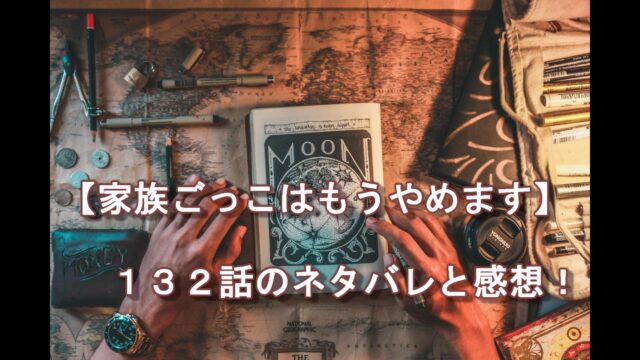こんにちは、ちゃむです。
「家族ごっこはもうやめます」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

187話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- あの時、私たちが家族だったら
モニカ皇帝が即位してからすでに2年が過ぎた春。
ナビアは早くに両親を亡くし、スムレ家に引き取られて以降、現在までスムレ家の庇護のもと無事に過ごしてきた。
家門の仕事もすべて安定していたため、周囲ではひそかにナビアとクリードの結婚を話題にしていた。
ゴシップ誌でも2人の結婚日を予測する記事が頻繁に掲載されるほどだ。
そうして現在、4月。
花々が咲いては散り、芽吹いた木々が柔らかな光に染まる日。
ナビアは家族たちと共に賛美歌を歌っていたそのとき、口を開いた——。
「9月に式を挙げる予定です。」
すでに今日の食事の席で結婚の話をしようと決めていたクリードは、嬉しさで少し恥ずかしそうに微笑んでいた。
エルキンをはじめ、マーガレットやシュレマンも予定していたことのような表情で特に驚きはしなかった。
「あと5ヶ月ですか?特に準備することは多くありませんが、それでもあっという間ですね。」
マーガレットの言葉に、シュレマンが答えた。
「年末になる前に式を挙げるほうがいいでしょう。暇な冬は旅行する親戚も多くて、仕事も忙しくなりますから。」
「そうですね。9月なら天気も涼しくて、庭には花がいっぱい咲いてきれいでしょう。夜も外でパーティーをするのにちょうど良い季節ですね。ピロエンが工房で準備いたします、当主様。」
「はい、お願いします。」
カラン!
ぼんやりしていた表情のラルクが手に持っていたスプーンを取り落とした。
「旦那様、まだ三歳にもならないのにこんな失態をなさるとは。」
マーガレットは舌打ちして、召使いに新しいスプーンを持ってくるように指示した。
だがラルクにはその騒ぎが耳に入っていなかった。
彼は席から勢いよく立ち上がり、叫んだ。
「たかがスムレ家の二十歳の小娘が何の結婚だって?お前はまだ子どもじゃないか!」
二十歳が子どもだなんて――。
とんでもない話にナビアは呆れた表情を浮かべた。
「お父さんとお母さんはちょうど成人式を挙げた時に私を産んだじゃないですか。」
「お父さんは帰還したでしょ!」
「私も帰還しましたよ。」
彼らの奇妙な会話に、シュレマンはナプキンで口元を拭きながらため息混じりに言った。
「お願いだからお二人とも、他にも聞いている人がいるかもしれないってことを少しは気にしてください。」
ラルクは眉間にしわを寄せながらささやいた。
「他の人が会話を聞けないように魔法で防御してあるし、うるさいな。それに今それがそんなに重要?」
シュレマンは、悔しそうに唇を引き結んだ。
「今一番取り乱しておられるのは旦那様ですけれど……」
ラルクは聞く耳も持たず、不満げにナビアを見つめた。
「もう一度よく考えてみろ。家を出たら大変だぞ。」
ナビアはきっぱりと言った。
「結婚を延ばせば、噂話が悪化するだけです。今がちょうど良い時期ですし、家を出るのではなく、新たな家庭を築くのです。」
普通、婚約後に結婚するまで約2年の期間を置くのが通例だった。
ナビアとクリードもその2年を満了しており、ちょうど結婚すべき時期だった。
だがラルクは、ナビアが結婚するのは「せめて30歳になってから」だと、勝手に決め込んでいたのだ。
『うちの娘は私のことを一番愛しているんだから、当然私と長く一緒にいたいと思うよな。』
しかし突然結婚だなんて。
乾いた空に木の葉が落ちるほうがよっぽど驚くだろう。
いや、今はラルクが自ら乾いた空に木の葉を落とすところだった。
ナビアとクリードの結婚に反対しているわけでは決してなかった。
むしろ賛成するほうだった。
クリードは実の子ではなかったが、自分の弟子であり、直接世話をして育てたので息子のように思っていた。
しかも二人は互いに信頼し、愛し合っており、誰が見てもお似合いのカップルだった。
二人がいつか結婚することはわかっていたし、大きくなった子どもは親の元を離れるものだということも理解していた。
わかっている。
全部わかっているのに、いざ結婚の話が出ると心がぽっかりと寂しくなった。
ずっとそばにいてほしかったのだ。
抱きしめて、ただ愛だけを与えて育てたいと思っていた娘が、子どもらしく駄々一つこねないことが寂しかった。
ラルクは唇をぎゅっと噛み、自分がすでに手放す立場になっていたことを痛感した。
ナビアは席を立ち、彼にすっと歩み寄った。
礼儀としては完全にふさわしくない行動だったが、ナビアはもはや礼儀よりも時には大胆さが必要であることを身に染みて知っていた。
「お父さん、結婚しても私はお父さんの娘ですよ。家にもよく顔を出しますから。」
ナビアはラルクを抱きしめ、甘えるように頬をすり寄せた。
にっこりと笑った彼女の丸い頬は、幼い頃のふっくらとした可愛らしさをそのまま残していた。
星明かりのような輝きを宿した赤い瞳は、まるで彼の写し鏡のようで美しかった。
こんな栗の実ほどの小さくて可愛い娘を、もう手放さなければならないなんて――
ラルクは、まるでしがみつくように娘の髪をそっと抱きしめた。
ため息をつきながら、どうしようもないというような表情をした。
「毎週お父さんと遊んであげないとね。」
マーガレットとシュレマンは冗談めかした無茶なお願いに恥ずかしさを感じたのか、黙って食事に集中した。
じっと様子を見ていたエルキンが一言。
「本当に大人げないですね。」
「エルキン、お前は娘を持った父親の気持ちがわからないんだ。」
「はぁ……。」
ナビアのような娘がいたら自慢したい気持ちは理解できるが、本当に執念深いものだと感心した。
クリードはラルクのしつこさに何でもないような穏やかな顔で言った。
「毎年、秋と冬はエセレッド公爵家で過ごす予定です。」
「そうか?」
その言葉に、ラルクはいつの間にか機嫌が良くなった。
「ここは部屋がたくさんあるから、好きなように使え。いや、それとも別荘でも一つ建ててやろうか?」
「結構です。別荘は、私が使っていた所で十分ですから。」
クリードには、別荘に住むのと大公邸で生活するのとで何が違うのか理解できなかった。
ラルクだけの、ラルクにしか分からない基準があるようだ。
ともかく、なんだかんだで結婚の許可は下り、二人は翌日、モニカ皇帝に挨拶することとなった。
それぞれの家門を治める家長同士の結婚なので、呼称と爵位をどうするか議論しなければならなかったからだ。
この問題はモニカがあっさりとまとめた。
「爵位も呼称も両方使いなさい。」
公式の場ではナビア・エセルレッド公爵、クリード・アイルツ大公として活動するが、それ以外の場ではどう呼んでも許容するという意味だった。
議論はこれで終わりではなかった。
「ただし、後継者に爵位をすべて継がせるわけにはいかない。一方の爵位が自然に空席になるならまだしも、大公と公爵だからね。他の貴族たちは嫌がるだろう。」
つまり、ナビアとクリードの爵位があまりにも高いので、それだけ多くの権限を持っていたということだった。
一人に爵位を与えると、他の人々の目が気になるという意味だった。
モニカはこの点が少し気に障ったように、観察するように問いかけた。
クリードはまるで悩む必要もないというように答えた。
「エセルレッド公爵位を譲るのがよいかと思います、陛下。」
アイルツ大公家は血縁者がいないため、クリードただ一人だけが存在する家門だった。
実質的に家門と呼ぶには物足りないほどに乏しかった。
それゆえ、家族もいて家臣も多いエセルレッド家のほうが好ましい。
「まあ、いいだろう。跡継ぎを2人以上もうけたら分け与えればいい。この問題はまた後日話すとしよう。」
結婚の準備は順調に進んだ。
ミネルバは一生の傑作を作ると言って、二人の婚礼衣装に全力を注いだ。
リカードもウェディング馬車を用意した。
二人の結婚に帝国がざわつくほどの話題。
ナビアの大切なウサギの人形、チェサレが手でじわじわと地面を転がりながらエセルレッド公爵邸をうろついていた。
ところがチェサレの目が変だった。
本来なら澄んだ青い光を放つ宝石が、まるでオニキスのように真っ黒に染まっていた。
― ふふん、結婚だって?こんな時に私が関わらないわけがない。
チェサレが少年のような声を出した途端、空間が混沌に染まったが、すぐに元に戻った。
―ラルクがいる場所だからか、混沌の影響力が弱いな。本当に怪物みたいな子だ。
チェサレに現れたのは、他でもないカオスだった。
カオスは軽やかな足取りで階段を四段ずつトントンと駆け上がった。
あっという間に3階に到着したカオスが立ち止まったのは、エセルレッド家当主の寝室。
ナビアが家門を引き継いではいたが、その寝室はラルクが引き続き使っていた。
カチャ。
ドアがやわらかく開き、小さなさえずりのように、カオスがトントンと歩いてソファへ向かった。
ラルクは昼寝をしていた。
—寝てる姿は、本当にかわいいな。
カオスはまるで父親のように穏やかな声で、ラルクの頭をなでた。
「うん」
するとラルクが眉間をしかめながら寝返りを打った。
眠りは覚めなかった。
もしニクス程度の神だったなら、ここに強引に侵入したときラルクが気配を察してすぐ目を覚ましただろうが、相手はカオスだったのでそうはいかなかった。
いや、むしろカオスが隣にいたおかげでさらに深く眠りについていた。
ラルクはナビアのおかげでだいぶ穏やかになったとはいえ、この世界の不純物のような存在だった。
完全な神でもなく、完全な人間でもない彼は、もしかするとカオスに最も近い存在だったのかもしれない。
―お前は混沌のほうが居心地がいいだろうな。
ポンポンと。
カオスは恋人を知らなかったが、ラルクとナビアを見ていると、なぜかその感情が少しわかる気がした。
だからこの子を見ると、なぜか寂しさを感じ、胸が痛んだ。
人間界に深く関わろうとすれば、それだけ多くの代価を払わなければならないのに。何一つ成し遂げられず、悔しさすら感じなかったほどだった。
―それほどに、お前にはあまりにも残酷な世界だった。それでも幸運だったと思わないか?お前にナビアという、最も気高く、美しく、愛おしい子どもが生まれたのだから。
そしてまた、トク・トク・トク。
カオスのやさしい足音が続いていたそのときだった。
トントン。
誰かが寝室の扉をノックした。
「お父さん。」
ナビアだった。
「……お父さん?眠ってますか?」
ラルクは眠っていても気配に敏感で、すぐに目を覚ます人だった。
だから、これほどしっかりノックされ、名前まで呼ばれても返事がないのはおかしいことだった。
ナビアは困惑した表情で寝室のドアを開けた。
明るい日差しが差し込む部屋の中は、以前とは違って明るく華やかだった。
ナビアの写真がきちんと飾られている几帳面な寝室は、普段通りの姿そのままだった。
「お父さん?」
ナビアは眉間を少しひそめて周囲を見回し、ソファで眠っているラルクを見つけた。
さらに自分をじっと見つめる黒い目のチェサレも。
『チェサレの目がなぜああなの?』
ニクスが憑依するとき、チェサレの目は星のようにきらきら輝いた。
では、今チェサレに憑依している存在はニクスではなく、別の神だということか。
「……どなたですか?」
警戒するようなまなざしで尋ねるナビアに、カオスが手を軽く振った。
―こんにちは、ナビア。ちょうどよかった。
「カオス様?」
―すぐに気づいたね。
その言葉を発すると同時に空間が揺らぎ、もはや何が起きているのか判別できなかった。
「ここに何のご用ですか?いえ、人間界にこんなふうに干渉していいんですか?」
―もちろん本来はダメだが、君の結婚にあたって贈り物をしたくてね。
ナビアはなぜか少しばかり後ろめたさを感じた。
「いえ、そんなことをしていただかなくても……」
―いい結婚祝いを思いついたんだ。もともとナビア、君にだけ渡そうと思っていた贈り物なんだけど、ラルクもお前も同じ傷を抱えているから、二人とも与えるのが正しいだろう。
気まずさがさらに大きくなった。
「やっぱりいただかないほうがいいと思います。受け取ったことにします。」
―帰還者だからこその痛みがあるはずだ。気になるだろう。
「ありません。全く。」
―そんなはずが。
「ないって言ってるじゃないですか?」
―見てろ。
カオスの黒い両目が妖しげな紫の光に染まった。
ナビアが彼に向かって慌てて手を伸ばしたが遅かった。
寝室は形を失い、混沌に包まれた。
「ちょっと、今何をしようとして……!」
次の瞬間、淡い光がラルクをやさしく包み込んだ。
続いて、ナビアもその光に包まれた。
―いってらっしゃい。
意識を失う前に聞こえたのは、微笑を含んだその言葉だけだった。