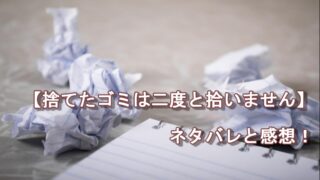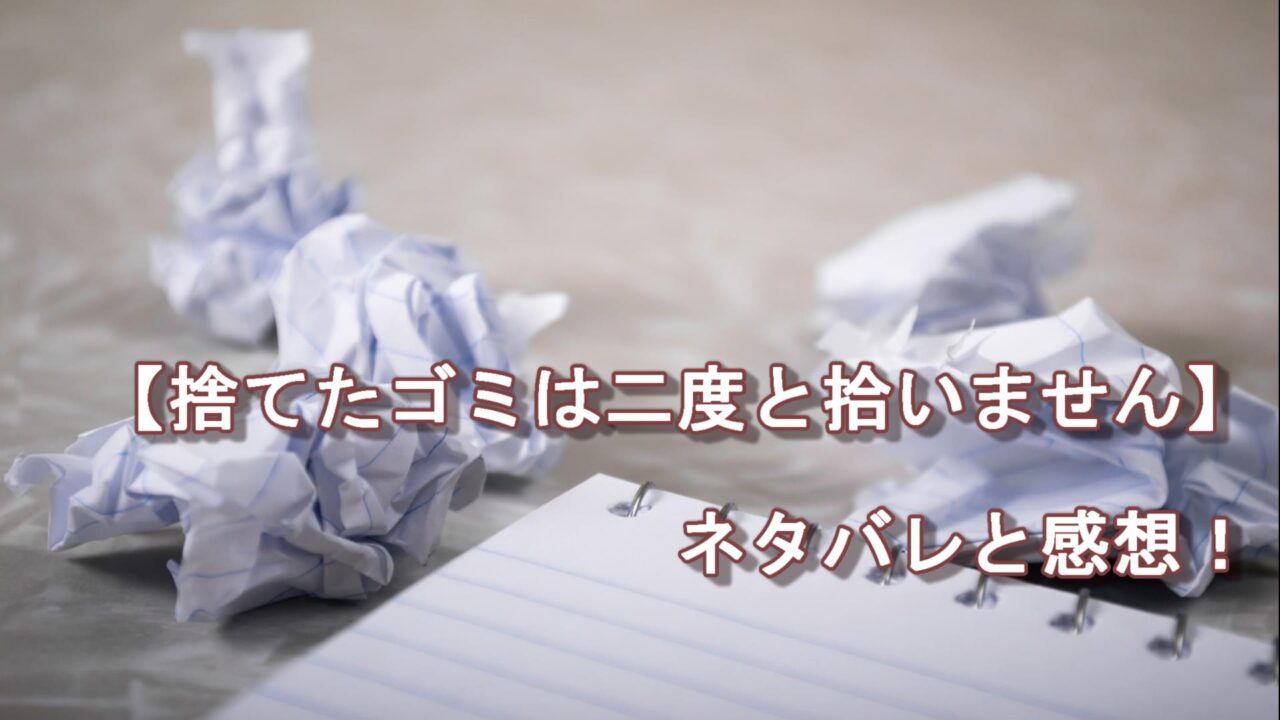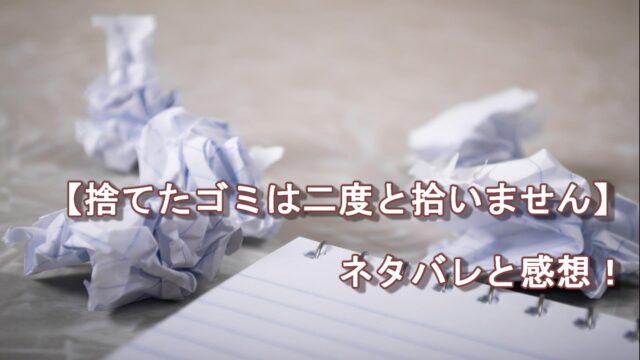こんにちは、ちゃむです。
「捨てたゴミは二度と拾いません」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

100話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 自覚⑥
新年祭まであと一週間というところで、王都には外国の使節団が続々と到着していた。
そのせいで目まぐるしく忙しくなった。
書類の処理も山積みだったが、それ以上に人々を相手にするのがひどく疲れる。
「なぜ皇帝陛下にお目通りできないのだ?」
「陛下は現在、別の公務で外出中でございます。」
「ならば、どこに行かれたのか言え。私が直接お訪ねしよう。」
「安全上の問題で、それについてお話しすることはできません。」
「それはどういうことだ? 私が陛下に何か害を及ぼすとでもいうのか?」
ウィントの侍従が怒りをあらわにして声を荒げたが、私は落ち着いて対応した。
「ウィントでは国王陛下の所在を他の者に公に話すのですか?」
それを聞いたウィントの侍従は口を固く閉ざした。
眉間に寄った皺が、彼の不満の深さを物語っていた。
「陛下が戻られたら、ウィントでお目にかかりたいとお伝えします。ですので、それまで宮殿でお待ちください。」
こうしてなんとか宥めて送り出したものの、今度は別の使者が訪れ、また騒ぎを起こした。
「陛下はどちらにおられますか?」
今度の訪問者は、ステラ王国の王女だった。
噂によれば、彼女はカリアンに一目惚れし、結婚するために訪れたという。
そのせいか、ステラ王女はカリアンの目に留まろうと必死に努力したが、すべて空振りに終わっていた。
カリアンは彼女に一瞥すらくれなかった。
道端の石ころよりも関心のない様子だ。
普通なら諦めるはずだったが、ステラ王女はしつこく足を運び続けた。
今日も同じで、カリアンが来るまで待つつもりだと言い、執務室にしばらく留まっていた。
ただ座っているだけなら無視して自分の仕事をすればいいのだが…。
「陛下が好きな食べ物は何ですか?好きな色は?あ、もしかして陛下の趣味や生活について知っていますか?」
彼女は私に矢継ぎ早に陛下に関する質問を投げかけた。
陛下の私的なことを軽々しく話すわけにはいかず、私は一貫して「知りません」と答えた。
「嘘よ!本当は全部知っているくせに!」
すると、ステラ王女が突然怒り出した。
「殿下も陛下のことが好きだから、私には教えたくないんでしょう?私を子供扱いしてるのね!」
とんでもない誤解だ。
「違います」と言っても、彼女は納得しそうにない。
ステラ王女は誤解を解く様子もなかった。
彼女をなんとか宥めて送り出し、再び書類に目を通そうとしたとき、またノックの音が響いた。
今度は誰だ。
確認する前から苛立ちがこみ上げてきた。
「はい。」
扉を開けて入ってきたのは、外宮の使用人だった。
「アステル卿、デロント卿が急ぎで法務大臣に書類を届けてほしいと依頼されました。」
これは歓迎すべき頼まれ事だ。
少なくとも、しばらくの間は外国の使節団相手に振り回されることはなさそうだ。
「どの書類のことを指しているのですか?」
単に書類を渡すだけなら、侍従や下僕に任せてもよかったが、重要な書類はそうはいかなかった。
途中で紛失するようなことがあれば大問題だから、自ら運ばなければならなかった。
私は下僕が言っていた書類を持って外宮へ向かった。
外宮へと続く長い回廊を歩いている途中だった。
「アステル殿下?」
回廊の反対側に、カリアンが貴族たちと一緒に現れた。
「陛下にお目にかかります。」
「どこへ行くところだ?」
「法務部長官に書類を届けに行く途中です。」
「そうか? 外宮の仕事は大半がデロント卿の担当のはずだが。」
「デロント卿が忙しそうだったので、私に頼んだのです。」
「ふむ。」
カリアンはしばし考え込んだ後、私の肩を軽く叩いた。
「もう少しの辛抱だ。新年祭が終わったら、補佐官をもう一人増やすつもりだ。」
これは聞きたかった言葉だった。
補佐官がもう一人いれば、私の負担も軽くなる。私は感謝の意を込めて頭を下げる。
「ありがとうございます。」
「感謝するにはまだ早い。本来なら、もっと早くやるべきだったのだから。」
カリアンは「お疲れ様」とだけ言い残し、静かに執務室を後にした。
私も再び法務部へと歩を進めた。
いくつもの省庁が集まっているため、外宮は普段から騒がしい方だった。
しかし、今日はそのざわめきが異常に激しく感じられた。
新年祭のせいだろうか?
そう考えるのも無理はなかったが、それにしても異様な雰囲気だった。
特に、元首府の官僚たちがひどくそわそわしていた。
ただの雑談なら気にも留めなかっただろう。
しかし、彼らが時折こちらをちらちらと気にしているのを感じ、無視することはできなかった。
一体、何が起こっているのだろうか?
不審に思った私は、耳をそばだてて彼らの会話を盗み聞きした。
「ウィリオット公爵閣下が……」
「まさか、本当に?」
……フィレンの話をしているのか。
そうなると、彼らが私を見てひそひそ話をしていた理由がわかる。
フィレンと私、そしてシスリーの間で起こった出来事は、今でも人々の間で絶えず話題になっているのだ。
元帥府の管理官たちが騒ぎ立てているのも妙だったが、元帥府長官であるフィレンが最も側近くで仕える人物だからだと思っていた。
しかし、それだけではなかった。
「レイラ。」
その噂の真相を知ったのは、法務部長官に頼まれた書類を渡し、宮殿の執務室へ戻る途中のことだった。
フィレンは回廊の柱にもたれかかって立っていた。
どうやら私が通るのを待っていたようだ。
「久しぶりだな、レイラ。」
本当に久しぶりだった。
あの日以来、初めて見る顔だ。
フィレンが首都に来ているという噂は耳にしていたが、まさかこうして対面することになるとは思ってもみなかった。
もしただ通り過ぎるだけなら無視することもできただろう。
しかし、彼が話しかけてきた以上、無視するわけにはいかなかった。
それに、周囲の視線もある。
ますます彼を無視することはできなかった。
個人的な感情よりも、身分が優先されるべき場面だった。
彼は公爵、私は男爵。
その間には歴然とした身分の違いがあった。
「……お久しぶりでございます、公爵閣下。」
そのため、私は仕方なくフィレンに挨拶をした。
彼はそんな私を、どこか哀しげな目で見つめていた。
彼の目つきも気になったが、それ以上に気になったのは、引き締まった彼の顔だ。
いや、「気になる」というよりも、「嫌悪感を抱く」という表現のほうが適切だった。
まるで周囲の人々に「私はこんなにも大変なんだ」とアピールしているようだった。
まるで、その原因が私であるかのように話して回っているかのようにも思えた。
「では、これで。」
とにかく、フィレンと長く話すのは気が進まなかった。
礼儀正しく挨拶を交わし、この場を去ろうとした。
しかし、フィレンは再び私の手首を掴んだ。
「最近、元気にしてた?」
そんなこと、なぜ聞くの?
今さら親しげに振る舞う理由は何?
まさか、フィレンは私たちの関係が戻るとでも思っているの?
もしそう思っているのなら、それは大きな誤解だった。
割れたガラスを元に戻せないように、粉々に砕けた私たちの関係も二度と戻ることはなかった。
「この間、君のことをよく考えていた……。」
「閣下。」
私はフィレンの言葉を遮り、まっすぐ彼を見つめた。
彼の瞳には妙な期待が浮かんでいた。
何を期待しているのかはわからなかったが、一つだけ確かなことは、少なくとも今の私は彼が望む言葉を口にするつもりはないということだ。
「私が閣下に誓った願いを、お忘れではないでしょうね。」
「……!」
やっぱり違う。
ウサギのように大きく見開かれた瞳は、血が滲むほど真っ赤だった。
深いダークサークルが目を引いたが、それだけだった。
彼を哀れむ気持ちも、気にかけるつもりも、少しもなかった。
「帝国の官僚である以上、攻撃的な出来事に巻き込まれるのは仕方がないことだと思います。ですが……。」
私は怒りの感情も込めず、ただ無機質な声で続けた。
「私的な理由で私を訪ねることは、もうないようにしてください。それが私の願いでもあります。」
どんなに頭が痛かろうと、ここまで言えば理解できるはず。
「では、これで。」
「レイラ。」
彼は私を引き止めないだろうと思っていたが、どうやら私はフィレンを過小評価していたようだ。
彼は考えている以上に愚かだった。
「愚か」という言葉では足りないほど。
「最後に一つだけ確認させてくれ。本当に俺のことを愛していないのか?俺に対して何の感情もないのか?」
はあ……、今それを質問するのか。
「ええ、ありません。」
私の答えに、私の腕を掴んでいたフィレンの手から力が抜けた。
私はその隙を逃さず、彼の手から腕を引き抜いた。
「空に向かって飛んでいく紙飛行機のように、もう私には未練もありません。だから、これ以上私を知っているふりはしないでください。」