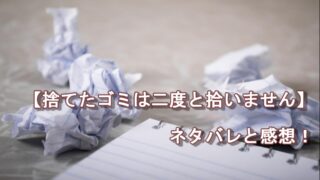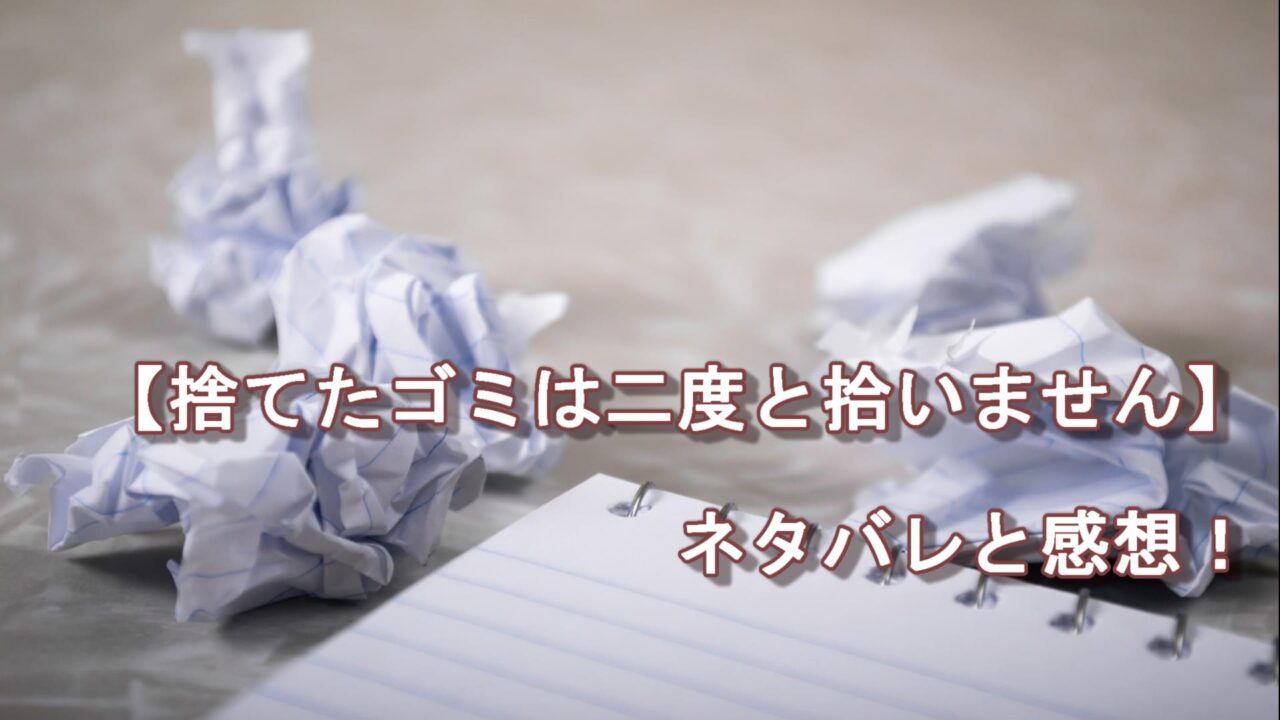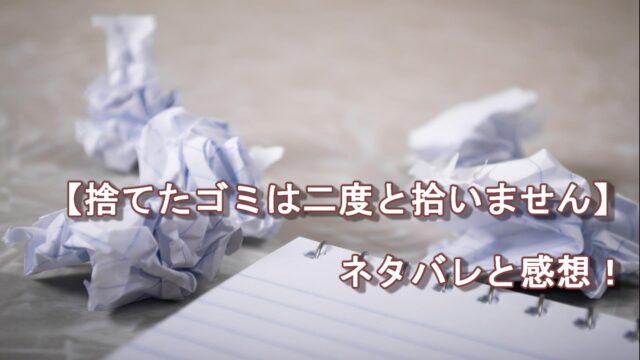こんにちは、ちゃむです。
「捨てたゴミは二度と拾いません」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

3話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- プロローグ③
「お嬢様、ご主人様がその女性に侍女をつけろとおっしゃいましたが、どの侍女をつければよろしいでしょうか?」
その女性を公爵夫人の部屋へ案内したミサの質問に、私は少し考えた後に答えた。
「ミサ、あなたが直接お世話をして。もし何か問題があればすぐに知らせて。その女性に少しでも奇妙な様子が見られたら、すぐに私に報告すること。」
「はい、お嬢様。」
ミサは非常に重要な任務を任されたことを神妙な顔つきで理解し、深々とお辞儀をして立ち去った。
午後になると、空が曇ってきた。
まもなく雨が降りそうな空模様で、空は灰色の雲に覆われていた。
開いていた窓から雨の匂いがかすかに感じられると、私はそっと窓を閉めた。
先代公爵夫妻が嵐の日に亡くなったせいで、雨が降る日には気分がどんよりと沈んでしまう。
雷が鳴り響く夜には、不安で眠れず、布団の中で小刻みに震えることもあった。
終いには子供のように泣き出すこともあった。
その事実を知っているのはミサだけだ。
使用人たちに見せるには恥ずかしいと思える姿だったのか、徹底的に隠していた。
ああ、フィレンも知っているのか。
まあ、今となっては忘れてしまっただろうが。
窓を閉めて席に戻った私は、フィレンがいない隙にこれまで目を通していなかった書類を確認し始めた。
公爵夫人の仕事だけでも一日が埋まってしまうのに、公爵の仕事まで代わりにこなしているため、本当に目が回るほど忙しかった。
そのため、有能な補佐官たちの助けがなければここまで無事にやり遂げることはできなかった。
私は書類を一つ一つ確認した後、ウィリオット公爵の印章を押した。
公爵の執務室にあるべきウィリオット公爵の印章が、私の執務室に入ってから早くも9年目だった。
最初のころは私が代わりに仕事をすることを良く思っていなかったが…。
人々も時間が経つにつれ当然のようにここに馴染んでいった。
そんな中で私が一度でも失敗すると、まるで期待していたかのような目で私を見つめ、非難してきた。
しかし、絶対に失敗は許されなかった。
全ての仕事が完璧に仕上がることはできないと分かっていても、最善を尽くさなければならなかった。
見落としがないように確認しながら印を押していくと、気づけば日は暮れ、夕食の時間となっていた。
午前中の出来事もあって、フィレンと顔を合わせて食事をする気にはなれなかったが、それを避けることもできなかった。
今日は特別な日で、彼が長い戦争を終え故郷に戻ってきた最初の日だったからだ。
昼食も一緒に取れなかったので、せめて夕食くらいは共にするべきだと思い、私は仕方なく使用人を呼びにいった。
・
・
・
「お呼びでしょうか、お嬢様。」
しばらくして侍女が入ってきて、腰をかがめて挨拶をした。
私は彼女を見ずに、机の上を整理しながら尋ねた。
「夕食の準備はどうなっているの?」
「それが……。」
私の質問に侍女はすぐに答えられず、口ごもり始めた。
そして最後には黙り込んでしまった。
明らかに気まずそうな彼女の態度に、私は手を止めて彼女を見つめた。
「どうしたの?」
「それが……主人様が、今日の夕食は食堂ではなくお部屋で召し上がるとおっしゃいまして。」
「食堂ではなく部屋で?」
「はい。疲れているので食堂には行きたくない、と……。」
タクッ——
器がテーブルに置かれる音が軽やかに響いた。
侍女はすぐに首を深く垂れて謝罪した。
「申し訳ありません。」
「君が謝ることではないよ。」
そう、これは侍女のミスではなかった。
ただ彼女はフィレンの言葉を私に伝えただけだったのだ。
特別な事情がなければ、遠出から帰ってきた初日には家族と一緒に食事をするのが習慣だった。
『そういえば私は、フィレンの家族に相応しい存在なのだろうか……。』
『いや、私ではない』という結論に至った。
私がウィリオット公爵家の後継者にふさわしい人物ではないと。
先代の公爵夫婦は私のことを実の娘のように思っていると語ったが、それはただの「思い」だった。
本当ではなかった。
ウィリオット公爵家に10年以上仕え、公爵のために働いているものの、私は依然として外部の人間だ。
だからと言って、フィレンに礼儀として一緒に食事をしようと提案することもできなかった。
もし彼が嫌だと言えば、それを受け入れるしかなかった。
それが少し腹立たしく感じられても。
『いや、不愉快になる理由はない。』
私もまた、彼の顔を見ながら食事をする気分にはなれなかった。
だからむしろ喜ぶべきことが正しいのに、心臓が動揺していた。
私は左胸に手を置いて驚いた。
「お嬢様、どこか具合が悪いのですか?」
「いいえ、大丈夫よ。」
夕食を一緒にしないなら、この服を脱いでもいいだろう。
窮屈な化粧も落として。
この事実が気分を少し和らげてくれた。
私は服を着替えるため、自分の部屋に向かった。
私の部屋はこの邸宅で3番目に広い部屋だった。
一番広い部屋はもちろん公爵の部屋。
その次に広いのは公爵夫人の部屋。
そして3番目に広いのが私の部屋だった。
どうせ公爵夫人になるのだから、そのまま使おうと思ったが、そうしなかった。
正式に公爵夫人になった後で入りたいと、ずっと拒んできたのに、まさかこんなことが起きるとは思わなかった。
一息ついて落ち着きを取り戻した。
「それをこちらに持ってきて!」
「えっ!これどうしよう?」
普段は静かだった北棟が、今日は騒がしかった。
全てはこの邸宅の主人であるフィレンが戻ってきたからだった。
「お嬢様、良い午後ですね。」
「こんにちは、お嬢様。」
忙しい最中でも使用人たちは、私が通りかかると作業を止め、深く腰を折って挨拶した。
特に彼らの邪魔をしたくなかった私は、足を速めて歩みを進めた。
「ちょっと待って。」
それでもどうしても足を止めた私は、食事のトレイを運んでいる侍女たちを呼び止めた。
「それは今どこに行くの?」
「主人様の部屋に運ぶ食事です、お嬢様。」
それは聞かずとも分かった。
この屋敷の使用人たちがこんなに豪華な食事を食べるわけがないのだから。
問題は準備された食器が一人分ではなく、二人分だったということだ。
食事も一人で食べるには多すぎる量だった。
どう考えてもフィレンが一人で食べようとしているのではなく、私を部屋に招待して一緒に夕食を取ろうとしているように思えた。
一緒に食事をするというのなら、まさか……。
「……フィレンの部屋にその女性も一緒にいるの?」
侍女は困惑した表情で顔を背けた。
「はあ。」
私は深いため息をつきながら髪をかき上げた。
部屋で食事をする理由が疲れているからと言っていたが、それだけではなく、その女性と一緒に食事をするためだったのだろう。
食堂で食べるなら、私も一緒に食べる必要があるし、そうなれば私と向き合うことになるから。
『フィレンが私と向き合う?』
そんな馬鹿げた話があるものか。
周囲の視線も気にせず、ひとまず立ち止まった。
大公夫妻と違い、気の利かない男だと呆れさせたフィレンだった。
少なくとも私がなぜ怒っているのか全く気づかなかった彼が、私のせいで部屋で食事を取るはずがなかった。
では、あの女性が私の目を気にして部屋で食事を取ろうとフィレンに言ったのだろうか。
気になったが、それを確かめる方法はない。
フィレンやその女性に直接尋ねることはもちろん、一緒にいた侍女たちにも聞くことはできなかったからだ。
公爵夫人の部屋を使うだけでも贅沢すぎるのに、フィレンと一緒に食事をするなんて。
何も知らない人が見れば、私ではなくその女性がフィレンの婚約者だと思うに違いない。
そのくらい彼女とフィレンの行動は親密だった。
だからこそ、その女性とフィレンの行動が気に入らず、食事トレイを運ぶ侍女を止めようとするほど苛立っていた。
そのとき、侍女がおずおずと慎重に言葉を口にした。
「そ、その……食事が冷める前に届けなければならないんです、お嬢様。」
「……そう。行きなさい。」
侍女たちは、私が再び妨害するのではないかと警戒しながら、料理トレイを急いで運び出した。
気持ちは彼女たちを追いかけ、「一体何をしているの?」と問い詰めたかったが、それができない自分の立場を思い出し、何をしても大きな違いがないという現実が、私をさらに悲しくさせた。
私は彼女たちの姿がほとんど見えなくなる屋敷の隅へと、足を無意識に動かした。
硬い床に沈む足音が心地よかった。
後ろからフィレンの話を伝えに来た侍女がついてきて、小さな声で尋ねた。
「お嬢様、今夜の夕食はどのようにされますか?」
「私は食べないわ。」
午前中の出来事と少し前の出来事が重なり合い、食欲が完全に消えてしまった。
何も食べたいと思えなかった。
「それより、君は私の世話をする子じゃなかったかしら?」
「ミサ様が、お嬢様のお世話をするようにと言われました。」
「そうなの?」
突然その女性の世話をするために精神を注いでいたはずなのに、その状況でも私の世話をするように指名していったのだろうか。
ミサがどれだけ私を気にかけているのかが伝わり、私は思わず微笑んだ。
すると、侍女が突然嬉しそうに手を叩いた。
「ずっと礼服を着ていらっしゃるので心配していましたが、無事で安心しました、お嬢様。」
「私がずっと礼服を着てた?」
「はい。ですが、礼服を着るような用事はなかったのに。本当にご主人様も困ったものです。どうしてお嬢様にそんなことをさせるなんて。」
唇を突き出してぶつぶつと文句を言う姿が可愛らしかった。
妹がいたらこんな気分になるのだろうか。
「あなたの名前は?」
「サラです、お嬢様。」
「そう、サラ。よろしくね。」
ミサがその女性の世話をしている間、彼女が私の世話をしてくれることになり、軽く挨拶を交わした。
すると、サラが恥ずかしそうに頬を赤らめてペコリと頭を下げ、控えめに言った。
「私もよろしくお願いします、お嬢様。」