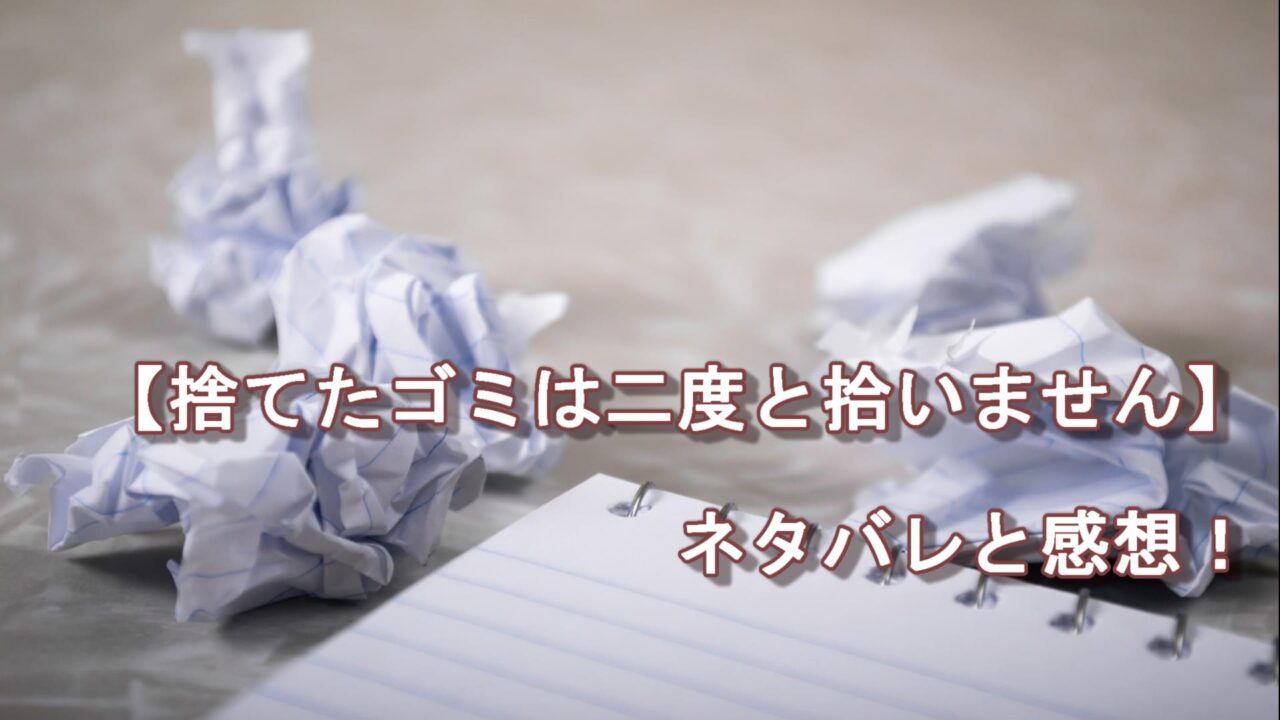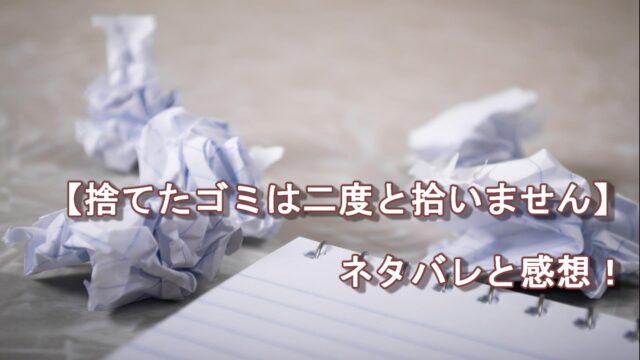こんにちは、ちゃむです。
「捨てたゴミは二度と拾いません」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

106話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 新年祭⑥
何かあったの?
もしかして外国の使節と帝国の貴族の間で問題でも起きたのか?
それとも陛下のスケジュールに支障が生じたのか。
「陛下、レイラ・アステルでございます。」
最悪の事態をいくつも想定しながら、皇族専用の休憩室に入る。
仮の休憩室とはいえ、皇族専用なだけあってとても豪華だ。
部屋に備え付けられた家具のどれ一つとして、安っぽいものはない。
「来たのか?」
急用があると聞いて来たのに、カリアンはあまりにも悠然とソファに座り、ワインを飲んでいた。
どう見ても、急ぎの用があるようには思えなかった。
「急ぎの用があると聞いたのですが。」
「…ああ、それ。」
カリアンが笑ってワイングラスを置いた。
「ウィリオット公爵のせいであなたが不快に感じているようだったから。」
ああ、それを見ていたんだ。
「お気を悪くされたのなら申し訳ありません。」
「なぜあなたが謝るの?願いをかなえてあげたのに、ねたんでいたウィリオット公爵が謝るべきでしょ。」
「それはそうなのですが……。」
「座って。」
カリアンは横に倒れていた空のワイングラスをまっすぐに立て直した。
「すぐ戻ったらあの人たちが不審に思うだろうから、少しだけいてから帰ろう。」
「でも、お客様たちが待っていると思いますが。」
帝国の貴族ならともかく、外国の貴賓たちを待たせるのは気が引けた。
「大丈夫だよ。」
カリアンは気軽にそう答え、空のワイングラスを満たした。
「彼らも私がいるより、自分たちだけで騒ぐほうが好きだろうさ。」
透明なグラスに赤いワインがきらめいた。
「じゃあ、一杯だけ飲んでから行くことにしよう。」
「陛下のお言葉とあらば……」
私はカリアンの向かい側に座った。
カリアンは私の前に半分ほど満たされたグラスを置いた。
「ワインは好きか?」
「好きでも嫌いでもありません。」
「じゃあ、シャンパンとか他のお酒は?」
「特に好きなお酒はありません。」
「なるほど。酒が好きじゃないってことは、まだ人生の苦味をちゃんと味わったことがないんだな。」
そうかもしれない。
私は十分苦い経験をしてきたつもりだけど。
これまでの出来事が頭をよぎって、私は苦笑しながらワインを口にした。
甘くはないが、少し渋みのある味が口の中で転がり、すっと消えた。
ちゃんと手間をかけて作られたワインらしい。
一杯で酔うつもりはなかったが、それでも用心しなければならない。
「ウィリオット公爵のこと、まだ気にしてるのか?」
もうこれ以上飲まない方がいいとグラスを置こうとした私に、カリアンが不意に尋ねた。
その質問への答えは、当然「はい」だ。
フィレンのことをできるだけ気にしないようにしているつもりだったが、言うほど簡単ではなかった。
それに最近になって、フィレンがやたらと目の前をうろつくせいで、さらに気になっていた。
さっきも私に近づいてきそうな気配を見せていたし。
いっそ、目に入らなければどれほど楽か。
そう切に願ってはいるものの、叶うことではないと分かっているので、それを口に出すことはしなかった。
フィレンを思い出すと胸が締めつけられた。
胸騒ぎがして、私はまたワインのグラスを取った。
酔いたくはなかったから、ただ一杯だけ飲むつもりだったのに、もっと飲みたくなった。
“お酒が恋しい”という言葉の意味が少しだけわかった気がする。
「ワイン、もう少し飲んでもいいですか?」
「もちろん。」
カリアンは迷いなく私のグラスに注いでくれた。
私はそのワインをもう一杯空けて、ようやくカリアンの質問に答えた。
「いいえ。嘘はつきません。」
「そうか。」
カリアンは淡々とそう答えてから、自分のワインを飲んだ。
私もまた、彼と同じようにグラスを口に運んだ。
もう一杯飲み干すと、少し酔いが回ってきた。
本当にこれ以上はやめておこう。
まだ飲みたい気はするけど、これ以上飲んだら本当に酔ってしまいそうで、グラスを置いた。
酔いが回ってくると、あれこれ考えが浮かんできた。
特にカリアンが新聖国からの縁談の申し出を受け入れるのかが気になった。
外交的に見れば受け入れるのが当然ではあるけど、それでも……。
酔いが回ったせいか、妄想も深まっていった。
ふと、カリアンの隣に若い少女が上品なウェディングドレスを着て立っている光景を想像し、我ながらぼんやりと見入ってしまった。
「新聖国からの縁談の申し出を……受け入れられるのですか?」
ワインのグラスを傾けていたカリアンの手が止まる。
私は驚くような青い瞳と目が合ってから、ようやく自分がうっかり口を滑らせてしまったことに気づき、慌てて言葉をつぐんだ。
「し、失礼しました、陛下。」
「いや。一緒に話を聞いたのだから、気になるのも当然だ。」
カリアンは再びワインのグラスを傾けた。
赤ワインが素早く消えていった。
「まだ考え中だけど。」
カリアンは少し間を置いてから続けた。
「たぶん、受け入れると思う。」
やはり受け入れるのか。
心臓が少し熱くなって、口の中が苦くなった。
ワインの甘みはもう残っていなかった。
甘さは消え、苦味だけがじんわりと残っている気がした。
「どうしてそんな顔してるの? 君は縁談を受けてほしくなかったの?」
「そういうわけではありませんが、あの縁談をするには新聖国の王女が少し幼すぎるような気がして……。」
「うん、それは俺もわかってるよ。だからまずは婚約から進めて、結婚式は少しずつ進めるつもりだ。」
「そ、そうですか……。」
そこまで考えているということは、縁談を受ける決意をしたということだと見て間違いなかった。
「君は?」
「え?」
「結婚するつもりはないのか?」
今日その質問、二度目だ。
「たぶん、しないと思います。」
“できない”の方が正確な表現だったが、そう言ってしまうとダイアンのようにカミングアウトしてしまうことになりかねないので、少しぼかして答えた。
「どうして?」
ぼかしても核心を突かれるのは同じこと。
「もしかして、ウィリオット公爵のせいか?」
図星なのか私は口をつぐんだ。
カリアンが深く息をつきながら髪をかき上げた。
「ウィリオット公爵に未練が残ってて、結婚しないだなんて……。」
「そ、そんな意味で申し上げたわけではありません、陛下。」
カリアンが何か勘違いしている気がして、私は慌てて言葉を付け加えた。
「私が結婚しないと言ったのは、私のことを好きになってくれる人なんていないだろうから……。」
「結婚しないんじゃなくて、できないってこと?」
しまった、焦って余計なことを言ってしまった。
「それに、あなたのことを好きな人がいないわけないじゃないか?」
訂正しようとしたけど、それよりも先にカリアンの言葉が飛び出した。
カリアンは今までで一番早口だった。
真剣な眼差しで私を見つめながら彼は言った。
「俺がいるじゃないか。」
・
・
・
こんなに衝撃的に言うつもりはなかったのに。“お酒は本音を引き出す”という誰かの言葉に、思わず深くうなずいてしまった。
彼女の前で酒を飲むんじゃなかった。
いや、そもそもこんな話をするタイミングではなかったのに。
カリアンが後悔している間、レイラは彼をじっと見つめていた。
突然の告白にも特に驚いた様子はなかった。
なぜあんなに堂々としてるの?
まさか私が彼のことを好きだって、気づいていたの?
「……もう知ってたの?」
動揺して迷いたくなかったカリアンは、率直に尋ねた。
レイラはゆっくりと視線を下げて答えた。
「はい、知っていました。私も陛下のことが好きなんです。」
「今……何て言ったの?」
口の中がカラカラに乾いた。
あまりにも緊張して、手と足に冷や汗がにじんだ。
「私のことが好きって?」
「はい。」
当惑したカリアンとは対照的に、レイラは平然と笑って答えた。
「陛下も、デロント男爵も、みんな好きです。」
つまり、それは恋愛的な意味ではなく、一人の人間として好ましいという意味か。
拍子抜けした。
カリアンは少し恥ずかしそうに手で顔を隠した。
でも、ベルンと自分を同じように好きだって?
それはちょっと気に入らない。
口を閉じていれば、酔った勢いの衝動的な失言を悔いることができたのに、理性の枠を超えた口が勝手に次の言葉を吐き出した。
「俺は君をベルンと同じ気持ちで好きじゃないよ。ベルンのことも好きだけど、君とは違う。異性として好きなんだ。」
「……え?」
レイラの目がぐらぐらと揺れた。
「今、なんとおっしゃいました……?」
「君のことを異性として好きだと言ったんだ。」
ワイングラスに付いた水滴が滑らかな表面を伝って、やわらかく流れ落ちた。
「人はこれを“愛している”って言うんだろう。」
少し潤んでいた琥珀色の瞳が、ぱっと輝いた。
「私は君を愛している。一人の女性として。」
彼女の顔はぴたりと固まり、唇は少し開いたまま、凍りついていた。
その姿さえも可愛い顔に、完全に心を奪われたようだ。
いや、レイラはもともと綺麗だった。
「すごく驚いたみたいだね。」
レイラは目を大きくぱちくりとさせて答えの代わりにした。
「自分なりにたくさん表現してきたのに、まったく気づかなかった?」
「わ……たし……。」
か細く出た声が少し震えていた。
「もともと優しい方だから、親切にしてくださっただけだと思っていました。」
「私が優しい、だって。」
カリアンの唇がかすかにゆがんだ。
「俺の剣で命を落とした者たちが聞いたら、あきれるだろうな。」
レイラは再び口を閉じた。
同じ場所をさまよう琥珀色の瞳が宙を漂ったあと、再びカリアンを見つめた。
「どうして……私を好きになったのですか?」
カリアンは空になったワイングラスにワインを注ぎながら答えた。
「誰かを好きになるのに、理由が必要か?」
「それは……そうですけど……。」
レイラは言葉の尻を濁しながらしばし考え、もう一度口を開いた。
「私、あなたより年上です。」
ああ、短い驚きの声とともに、ふっくらした唇が開かれた。
戸惑う様子も可愛い。カリアンはくすっと笑って腕を組んだ。
そろそろレイラがどんな言い訳をするのか気になってきた。
その言い訳をすべて聞けば、レイラが自分に心を開いてくれるのではと期待していた。
手をもじもじさせながらしばらく考えていたレイラが、再び口を開いた。
「それに……私には大きな欠点が……あります。」
「どんな欠点?」
レイラは「私、私生児なんです」と言いかけたが、カリアンも私生児だということを思い出し、別のことを口にした。
「婚約破棄しました。」
「離婚でもなく、ただ婚約を破棄しただけで何がそんなに後ろめたいっていうんだ?」
カリアンは気にしないとでも言うように笑いながら腕を組んだ。
「それが後ろめたいことなら、異母兄弟や継母たちを殺した俺なんかは、死んでもまともな人間とは言えないな。」
「そ、そんなはずないじゃないですか!」
レイラは蒼白な顔でカリアンを見つめた。
「私は決してそんな意味で申し上げたわけではありません。」
「わかってるよ。それで、他には何か理由が?」
カリアンは肘をついてレイラをじっと見つめた。
「もう言いたいことがないなら、僕の気持ちを受け入れてくれるって思ってもいいか?」
「えっ?」
今度はレイラの顔が真っ青になる。
誰かが見たら罪でも告白されたのかと思うくらいだ。
勢いで気持ちを告げたものの、レイラに自分の想いを強要するつもりはなかった。
そういう状況でもなかったし。
「冗談だよ。」
カリアンは笑いながら席を立った。
慌てて立ち上がったレイラは顔面蒼白になりながら、両手をぎゅっと握っていた。
カリアンをまともに見ることができず、うつむいた。
『完全にうろたえてるな。』
まさかこんなに動揺するとは思っていなかった。
カリアンは内心でため息をつきながら、レイラに言った。
「心配しないで。君に僕の気持ちを受け入れてくれと強要するつもりはないから。」
レイラの気持ちを和らげようと、カリアンはできるだけ優しく、穏やかに言葉を続けた。
「だから僕がこんなことを言ったからって、負担に感じる必要はない。もちろん、僕を好きにならなきゃいけない理由もないし。」
「……」
「でも、ベルンよりは少しでも僕を好きになってくれたら嬉しいな。」
レイラがあまりにも戸惑っていたので、カリアンは半分本気、半分冗談でそう言った。
冗談半分で言ったのに、レイラは少しも笑わなかった。
やはり自分は出過ぎたことをしたのだ。
どうせ叶わないことに、なぜ欲を出したのか。
カリアンは遅れてから後悔し、頭をかき乱した。
「僕は先に出るよ。」
レイラには今、自分の気持ちを整理する時間が必要だろう。
そう考えたカリアンは、彼女を残して部屋を出た。