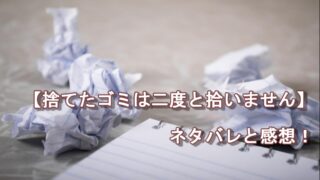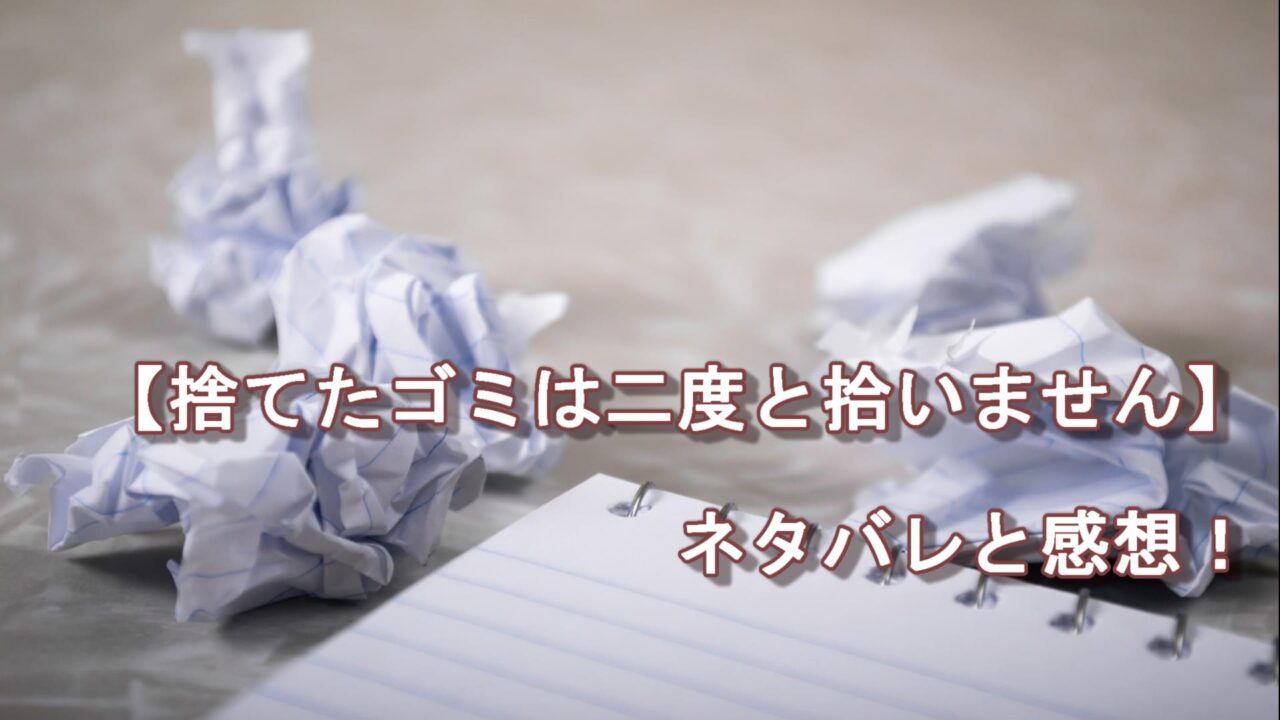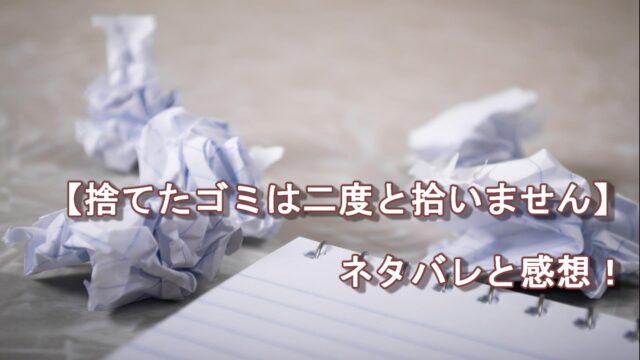こんにちは、ちゃむです。
「捨てたゴミは二度と拾いません」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

95話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 自覚
狂ってる。
どんなに時間が遅く、疲れていたとしても、皇帝の膝を枕にして眠るなんて。
カリアンは大丈夫だと言ったけれど、恥ずかしくて仕方がなかった。
これからあの顔をどう見ればいいのかと心配になり、家に帰ってベッドに横になっても、何度も寝返りを打ちながらなかなか眠れなかった。
そうして目を開けたまま夜を明かし、ついに耐えきれずに起き上がった私は、家を出た。
私が向かった先は朝早くから開いている唯一の花屋だった。
ミサの遺影の前に花が一輪もなく、がらんとしているのが気になり、花を買いに行った。
白い菊の花で作られた花籠を腕に抱え、再びアステル保育院を訪れた。
「いらっしゃいませ、院長先生。」
「おはようございます、院長先生。」
この時間にもかかわらず、働いている職員が多かった。
勤勉なことだ。
私は彼らに挨拶を交わした後、ミサの遺影がある部屋へと向かった。
すぐに出なければならないので、花籠だけ置いて行くつもりだったが、すでにミサの遺影の前には、白い菊の花籠が置かれていた。
誰が持ってきたのだろう?
まさか、アドリナ院長か?
「お嬢様、おいででしたか?」
ちょうどその時、アドリナが私を探しに来た。
私は菊の花を隠しながら、アドリナに尋ねた。
「この菊の花、院長が持ってきたものですか?」
「いいえ。私は存じ上げません。」
では誰だろう?
ほかの職員が持ってきたのか?
一度調べてみると言って出て行ったアドリナが戻ってきて、思いがけない事実を伝えた。
「すぐに警備に尋ねてみたところ、一時間ほど前に皇帝陛下がいらっしゃったそうです。」
「陛下がですか?」
「ええ。菊の花を一輪持って来られたそうですよ。」
ということは、この菊の花を置いていったのはカリアンだったということか。
1時間前なら、花屋はまだ開いていない時間だ。
どこで花籠を買ったんだろう?
私はカリアンが置いていった白い菊の花籠をじっくりと観察した。
丁寧に作られてはいたが、どう見ても専門家の手によるものではなかった。
それどころか、花びらには小さな傷までついていた。
花びらに傷があるということは、庭からすぐに摘んできたということか?
まさかカリアンが直接、皇室庭園から花を摘んで持ってきたのか?
・
・
・
「ミサの遺影の前に置かれた白い菊の花……まさか、手で摘んで持ってこられたんですか?」
もしかして、と思い、彼に会うなりすぐに聞いてみた。
するとカリアンは、少し動揺した表情で私を見つめた。
「それをどうやって……いや、それを見たということは、ぐっすり眠れと言ったのに眠らず、朝早くから保育園に行ったということか。」
「陛下も休まずに、朝早く保育園に行かれました。」
「俺はもともと眠れないんだ。」
「私も眠れないほうです。」
ただ事実を言っただけなのに、カリアンは気に入らない様子で目を細めた。
「口答えするところがだんだんベルに似てきたな。悪い影響を受けたものだ。」
「じゃあ、やめましょうか?」
「それもベルに似てるな。」
全然しっくりこない。
カリアンは独り言のように呟いた後、ギッペンにインクをつけた。
「君が菊の花がなくて寂しそうにしてたから持ってきたんだ。ただ、それまで君を見守っていたことへの礼儀のつもりでもある。」
「だからって、わざわざ手で摘んで持ってくる必要が……。」
「こういう時は、素直にありがとうって言えばいいんだよ。」
カリアンはそっけなく言い切った。
私は微笑みながら、静かに頭を下げた。
「ありがとうございます。」
「素直でいいな。」
カリアンは書類に署名した後、私に差し出した。
「これは法務部に持って行って、午後のスケジュールはどうなっている?」
「昼食の後は……」
私は書類を受け取りながら、午後のスケジュールを伝えた。
「昼食後の1時間ほどは空いているな。その時間に乗馬の練習をするように。」
「わかりまし……え?」
すでに馬を完璧に乗りこなせるカリアンが乗馬の練習をするはずがない。
つまり、これは私のことだと明らかだった。
私は戸惑いながら手を引っ込めた。
「私は大丈夫です。」
「新年祭で直接馬に乗りたいんだろう?新年祭まであと一か月もないんだから、しっかり練習しなきゃ。」
とはいえ、忙しいカリアンの時間を奪うことに少し気が引けた。
この時間は、彼にほんの少しでも休息のひとときを与えられればという気持ちで設けたものだった。
それに、以前に事故があったせいで、彼に乗馬を教えてもらうこと自体が申し訳なく思えてしまった。
「陛下の貴重なお時間を奪うわけにはいきません。」
本当の理由は言えなかったので、私はただ表向きの理由だけを伝えた。
「俺も体をほぐそうと思っているから、お前が俺の時間を奪うなんて考える必要はない。」
カリアンは笑いながら席を立った。
「だから、その時間に乗馬の練習をしろ。俺もお前が今回の新年祭で馬に乗って行進する姿を見たいんだ。」
「わかりました。」
そう言われたら断るわけにもいかず、私は仕方なく受け入れた。
・
・
・
「婚約破棄も見事にやってのけたのに、いまだに連絡がないとは。」
テベサ伯爵夫人は神経質に扇を軽く閉じた。
「まあ、昔も今も変わらず、扱いにくい子だこと。心に響く言葉を選ぼうと目を凝らしても、結局は見つけられないような子ね。」
向かいに座っていたアンダンテは、カップの向こうで微笑をかすかに浮かべた。
「あなたもそう思うのかしら、坊や?」
「そうですね。」
カップを再び置いたとき、優しい息子の顔には微笑が浮かんでいた。
「でも、たった一人の娘なのですから、母上の広い愛で理解してあげてください。」
「娘ですって?私はあの子を娘だと思ったことなんて、一度もないわ。」
テベサ伯爵夫人は鼻先で笑い、腕を組んだ。
「これまで育てたのも、それなりの理由があったからよ。女なんて結婚で商売できるんだから。」
伯爵家にとって、良い縁談が残るはずだと思っていたが、レイラはむしろウィリオット公爵家へと縁談を持ちかけた。
いや、縁談を持ちかけたのではなく、奪い取ったのだ。
婚約して結婚の準備まで整えていたのに、呆れたことにレイラがフィレンとの結婚が嫌だと言い出し、先に婚約破棄を宣言したのだった。
レイラが公爵夫人になるために、それをテベサ伯爵夫人は、まるで空から何かが落ちてくるのを待つかのように、その言葉を聞いて首の後ろを押さえながら崩れ落ちそうになった。
夫人は即座にレイラに駆け寄って何か言いたかったが、それをしなかったのは、フィレンのためだった。
「レイラは無条件で私と結婚します。だからご心配なさらないでください。」
その言葉を信じて待っていたが、結果は予想をはるかに超えて惨憺たるものだった。
レイラとフィレンは最終的に破談し、テベサ伯爵夫人は社交界の嘲笑の的となった。
もし計画通りに進んでいれば、彼女はウィリオット公爵夫人の義母という名声を得て、社交界で安定した地位を築いていただろう。
それなのに、こんな仕打ちを受けるとは。
「天の助けも得られない娘め!」
何度考えても怒りが収まらないテベサ伯爵夫人は、今にも気絶しそうな勢いで肩を震わせた。
「落ち着いてください、お母様。」
一方、アンダンテは余裕のある笑みを浮かべながら、テベサ伯爵夫人に言った。
「レイラはウィリオット公爵夫人にはなれなかったけれど、その代わりに皇帝の側室になったじゃないですか。」
「それは本当なの?」
テベサ伯爵夫人は目を細めた。
「デマだという話も聞いたけれど。記事にもなったし。」
「それは嘘です。」
アンダンテは優雅にお茶を飲みながら言った。
「皇帝がレイラを守るために、わざと偽の記事を出したんです。」
「本当?」
「もちろんです。私が母上に嘘をついたことがありますか?」
「ないわ。」
「だから、私の言うことを信じてください。」
アンダンテはテベサ伯爵夫人の隣にそっと座り、彼女の手を優しく握った。
「レイラが皇帝の側室になったのは明らかです。それでなければ、皇帝がレイラを補佐官として迎え入れる理由がないじゃないですか?」
「まあ、あの子が機転が利くのは確かだけど、管理職に就くほど頭がいいわけではないしね。」
今回、テベサ伯爵夫人はアンダンテの手を握った。
愛する息子を見つめるその目には、深い愛情が込められていた。
「管理職なら、むしろお前が適任だわ。私の息子が早く管理職に就くべきなのに。」
「僕はあまり管理職になりたいとは思いませんけど……。」
その言葉が口の中でつかえて消えた。
言ったところでテベサ伯爵夫人は聞く耳を持たないだろうと分かっていたので、アンダンテはしぶしぶ口を開き、話を続けた。
「あの娘がウィルリオット公爵夫人になれば、ウィリオット公爵家の家臣にしてくれと頼むつもりだったのに、それができなくなったのなら、帝国の管理職でもいいわ。」
「帝国の管理職ですか?」
「ええ。あの子が本当に皇帝の側室になったのなら、それくらいの地位を用意するのは簡単でしょう?」
テベサ伯爵夫人は明るく笑いながら、アンダンテの手を優しく撫でた。
「だから、彼女に会ってポストを用意するよう頼みましょう。あの子も恩義を感じていれば、それくらいはしてくれるはずよ。」