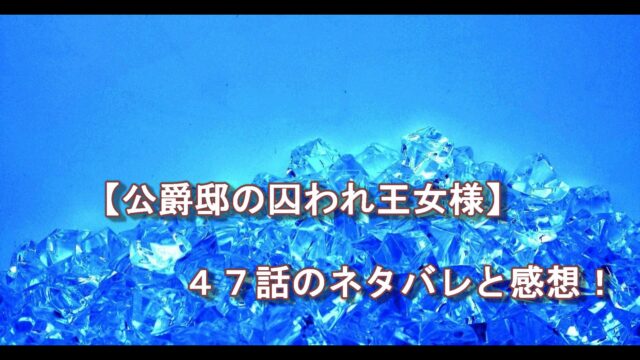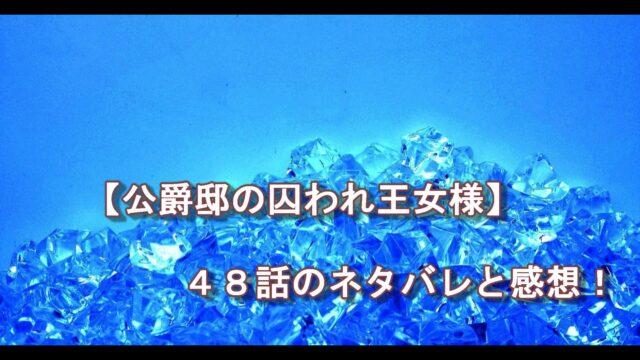こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

119話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 奇妙な要求
月末試験が終わり、ノアは魔法使いの城に行くと言って、一時的に首都院を離れた。
一体何の用事で行くのだろう?
クラリスが理由を尋ねたが、彼は「戻ったら説明する」という答えだけを返した。
もしかして公爵夫人の血縁検査に何か問題でもあったのではないかと心配したが、
どうやらそれではなかったようだ。
その原因についてはすでに調査が完了しており、公爵邸には正式に報告されていたからである。
それは誰かのミスによる不幸な事故だった。
クノー後継者の家では、昔から亡くなった後継者の血を大規模に提供してきた。
妻ではなく後継者の血を渡したのは、あくまで「直系の後継者」であることを明確にするためだった。
後継者は生前に何度か新しい血を抜き取って魔法使いの城に提供してきたが、問題は彼が亡くなった後に起きた。
新しい血を得ることができなくなった魔法使いたちは、彼が生前に残した血に保全魔法をかけて検査を繰り返していたが、誰かのミスでその血が他の物質と混ざる事故が発生したのだ。
魔法使いの城に残る記録にも、何度か同じような事故があったと記されていたため、アルステオは同様の事故が二度と起きないよう慎重を期すと約束してくれた。
クラリスはその慎重さに感心しながら――また、ノアが一体何を気にして魔法使いの城へ行ったのか、いつも気になっていた。
セリデン公爵の右腕であり、セリデンで最も几帳面な男。
クエンティン・センクレアはいつもこう言っていた。
「首都院は友達を作ったり恋愛をするための場所ではない。ただ学問だけを見つめ、情熱と青春を燃やす場所だ。」
さらに彼は、自分が恋愛できない第一の理由を「首都院」と挙げた。
「学問に夢中になって初恋さえ逃してしまったからさ。首都院なんて行かなければ、今ごろは妖精のような妻と一緒にパンを焼いて暮らしてただろうに……!」
もちろん、クラリスはこのような話をまったく信じたことはなかった。
ちょっと新聞を読めば、首都院出身のカップルの話が載るくらいなのだから。
最近はこれを基にした恋愛小説まで出版されたほどだ。(クエンティンは出版社に丁寧な抗議の手紙を送った。)
しかし、まさに「こんな」状況に直面したとき、クラリスはふとクエンティンの話が頭に浮かんだと言った。
ところが問題は、彼女が偶然それに出くわしてしまったことだった。
朝の運動時間まで約40分ほど余裕があったので、彼女はこの空いた時間を有意義に使いたいと思った。
つまり、早朝に勉強がしたくなったということだった。
彼女は勉強する本を手にして、勤勉に階段を下りていった。
今日はクラリスが1位じゃないかな?
そんなことを考えながらそっとドアを開けたとき――クラリスは目撃してしまった。
自習室の片隅で熱心にキスをしている恋人たちの姿を!
「……あ。」
思わず口から呆然とした感嘆の声が漏れた。
驚いたのはカップルたちも同じだったようだ。
口を半開きにしたままクラリスを見つめ、何の反応もできなかった。
『一体……どんな過程を経れば唇があんなふうになるの?』
クラリスは興味深そうに震える彼らの唇から視線を離せなかった。
この気まずい沈黙が続くと、クラリスは冷静さを取り戻し、お辞儀をした。
「す、すみません!」
とりあえず彼女は謝罪した。
そしてそのまま出て行ってくれればよかったのに。
慌てた拍子に「ただ学問だけを見つめ、情熱と青春を燃やす場所だ。」というクエンティンの話を思い出したクラリスは、意味のない言葉を口走ってしまった。
しかも、拳を握りしめたままで。
「ひ、火をつけてください!」
その瞬間の衝撃を何と表現すればいいのだろうか。
事態を収拾できないまま、彼女はそっと後ずさりしながらそっとドアを閉めた。
「………」
そのまま呆然と立ち尽くしていたクラリスは、しばらくして両手を顔に当てた。
「あ……」
顔が燃え上がるように熱くなった。
「……私はバカだ。」
彼女は少し前の自分を燃やしてしまいたい気分だった。
「クエンティンおじさん……どうして私にあんなことを言ったの……。」
思わず彼を恨めしそうに見上げたりもしたが、それは何の意味もないことだった。
クラリスは自分の部屋に駆け込み、ベッドの上で何度も枕を殴りながら苦しんだ。
午後になると幸いにも午前の衝撃はすっかり落ち着いた。
再び自習室に入って勉強できる程度にはなったということだ。
ただし「火」という単語を見つけるたびに、ビクッとして頭を振ってしまった。
「グレジェカイア・ヤン。」
しばらく集中していたところ、誰かがすぐ隣に座って話しかけてきた。
「どうしたんですか、ベルビルさん?」
受験生代表のエビントン・ベルビルだった。
しばらくの間、クラリスに友人として付きまとい、話しかけていたが、王妃が席を外して以来、彼は再び他人のような存在に戻っていた。
クラリスを見ると「フン」と鼻で笑いながら顔をそらしたり、ぶどうのように唇を噛みしめて味わっているかのように震えたりした。
「少し前に変な音を聞きました」
「え、変な……音ですか?」
クラリスは思わずびくっとして聞き返した。
今朝、彼女は妙な声を上げてしまったので。
まさかあの件がエビントンの耳にも入ったのだろうか?
いや、せめて彼には知られたくなかった。彼がクラリスのうろたえた反応をからかうのが目に浮かぶようで。
「わ、私にはわかりません。」
「まあ、そりゃそうでしょう。」
彼は何でもないというようにクラリスを見つめ、それから少し意地悪そうに軽く顎を上げた。
「師範たちが受験生代表の君だけに話した内容だからね。」
「あ……はい。」
クラリスはぎこちなく頷きながらも少しだけ安心した。
何にせよ、今朝の件がエビントンに知られてしまったのは間違いなかった。
「聞きたいですか?」
「いいえ。」
「……!」
いきなり拒否されるとは思わなかったのか、彼が戸惑った様子なのが一目でわかった。
「はあ、わかりましたよ。話してください。」
クラリスは、彼がこれ以上しつこくならないように、早めに答えを与えた。
「これは仕方ありませんね、グレジェカイア・ヤンがそこまで聞きたいのなら、言うしかありません。」
「……。」
「今週末に首都院で結婚式があります。」
「それはいいことですね。」
「はい、正確には首都院の主要な入学者のひとりである師範たちがとても気にする行事です。ですが、新郎新婦が首都院に奇妙な要求をしてきました。」
「奇妙な……要求ですか?」
「今首都園にいる受験生カップルが結婚式に出席して証人をしてほしいって話があったそうです」
それは確かに奇妙な依頼だった。
結婚式の証人というのは、首都園の住人か親しい人が務める名誉ある席であり、面識もない受験生を証人に立てるなんて。
「おかしいと思いませんか?」
「ええ、本当にそうですね。」
「受験生カップルだなんて、そんな変な組み合わせの話は聞いたこともありません。」
「……え?」
クラリスは驚いてエビントンの顔を見直した。
彼は真剣な顔で再び眼鏡を押し上げながらこう言った。
「首都園は友達を作ったり恋愛をしに来る場所ではありません。ただひたすら学問だけを見据えて、情熱と若さを燃やす場所です。」
「……!」
クラリスはなぜか開けたくなかった箱を開けてしまったような気分だった。
もしかして、クエンティンの受験生時代というのは、エビントンとかなり似ていたのではないだろうか?
「それで師範様は、私に受験生の中に結婚式に参加したいカップルがいるかどうか確認して知らせてほしいとおっしゃいました。」
「ああ…… えっと、よく探せばどこかにカップルのひとつやふたつはいるんじゃないでしょうか?」
「そんな馬鹿な話があるか!ここで恋愛が可能だというんですか?自習室でキスなんて、そんなことあると思います?」
熱く語っていた。
クラリスはそう返すしかなかった。慌てて片手で口をふさぎながら。
というのも、今日の午前にキスをしていたカップルは、普段は一緒にいるところを絶対に見せない関係だったからだ。
おそらく、皆の目を避けて秘密の交際をしていたに違いなかった。
今もその二人は自習室の対角線の席に座り、お互いをほとんど見つめ合っていなかった。
だからといってクラリスが勝手に出て行って、二人をカップルだと決めつける無礼を働くことはできなかった。
「じゃあ、正直に“いません”と言えばいいんじゃないですか?」
「本当にあなたは礼儀を知らないんですね、グレジェカイアさん。」
他の誰でもなく、エビントンから礼儀について指摘されるなんて。
クラリスは思わずプライドが傷ついた。
「わかりますか?結婚式は誰かの人生で本当に大切な瞬間です。受験生を呼ぶのはそれなりの理由と目的があるときだけです。」
それは確かに正論だった。
クラリスがそっと眼鏡を直すと、彼が手を差し出した。
なぜ急に握手を求めるのかはわからなかったが、「礼儀がないですね。」なんて言われたくなかったので、クラリスはとりあえずその手を握った。
「よかった。助かりました。」
手を振りながら、彼は安堵したように襟元を直した。
「いったい何の話ですか?」
「僕たちが証人になるんです。」
「正気ですか?!」
クラリスは掴まれていた彼の手を勢いよく振り払った。
「私とベルビルさんが恋人のふりをするって?どうしてですか?」
エビントンは振り払われた手をもじもじといじりながら眉をしかめた。
少し痛そうな様子だった。
「さっき話しませんでしたか?結婚式は重要なイベントなんです。」
「ええ。それで私が襟を直したのも、そのためだったんです。」
「その事実に共感したなら、当然私と一緒に出席しようという気になりませんか?」
なんでそんな話の流れになるの?
クラリスは、彼の思考が飛躍しすぎている点については、とりあえず突っ込むのをやめることにした。
「……なぜ私なんですか?ベルビルさんは私のこと嫌いじゃないですか。」
彼はため息をつき、しばらく眼鏡をいじっていた。
なんだかクラリスを気の毒に思っているようだった。
「嫌いだけど、あなたが一番適任だからです。」
「ベルビルさんの彼女役をですか?」
「正気ですか?私にも好みというものがあって、あなたみたいな暴力的な女性はその範囲に入りません。私は平和主義者ですから。」
ついさっきまで嘘をついてユジェニーを追い出そうとしていた人が、今度は平和を語るとは。
クラリスは彼の腕を一発殴りたくなったが、また「暴力的だ」と言われるのが嫌で必死に我慢した。
「じゃあ私は何に適任なんですか?」
「無駄なことに時間を使っても一番損が少ない人、という意味です。どうせあなたはこの試験で職を得るつもりもないんでしょう?」
クラリスは少しムッとはしたが、実のところそれは痛いほどの正論だった。
彼女がこの試験にどれだけ本気だったとしても、それは未来につながらないただの結果で終わることだった。
しかし他の受験生たちは事情が違った。これからの10年、20年後を見据えて時間を投資しているのだ。
だから、誰かが学習と無関係なことに時間を割かなければならないのなら、クラリスが一番適任だという意味らしい。
「とにかく……わかりました。でも、ベルビルさんはどうしてこの仕事を引き受けようとしているんですか?」
「それは当然じゃないですか。」
彼はメガネを直しながら、やや得意げな表情を浮かべた。
「私は受験生代表です。犠牲はリーダーの役目ですよ。後で自己紹介書に、今日の犠牲について書くつもりです。どこへ行っても、私のように優れた人格を持つ人材を知らないふりはできないでしょう。」
彼は明らかに「皆の勉強時間のために自分を犠牲にした。」という良い点だけを抜き出して自己PRに書くつもりのようだった。
「偽カップルを演じた。」という真実はしっかり隠したままで。