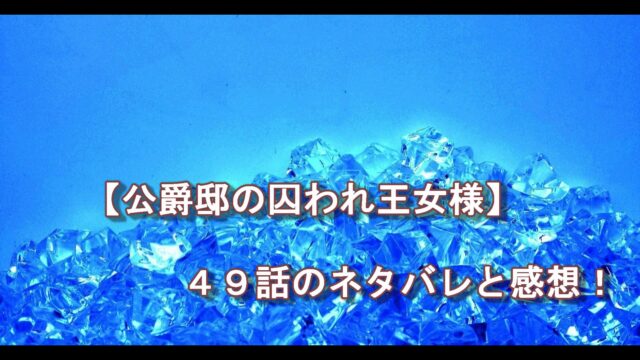こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

123話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 結婚の祝福
週末になり、受験生たちのほとんどが家に帰る中で、クラリスは首都に残っていた。
バレンタインは王都へ戻る馬車の中で、クラリスを思い浮かべて何度もにやにやと笑っていた。
彼女がエイビントンと恋人のふりをしなければならないという事実が、面白くてたまらなかったのだ。
「できるなら代わってあげたいけど、もし自分が恋人のふりをしたらニュースになっちゃうからな。」
彼はそう言ったものの、クラリスと恋人のような雰囲気を出すつもりは全くなさそうだった。
まあ、クラリスもそれを期待していたわけではないので、特にがっかりすることもなかった。
午後になり、彼女はきちんと身なりを整えて首都の礼拝堂へ向かった。
司祭様に用件を伝えると、待機室で案内を待つことができたが、まだベルビルは到着していないようだった。
「今日は儀式のお手伝いをしてくださってありがとうございます。これは新郎新婦の指輪ですので、後でこれを持って後ろに付いてきてください。」
案内をしてくれた司祭が、部屋の片隅にすでに準備されていた宝石の指輪を指し示した。
リボンがついた小さなクッションの上に、二つの指輪がきちんと置かれていた。
『これが結婚指輪なんだ。』
クラリスは興味深そうにそれを手に取って眺めた。
公爵夫妻も本当に素敵な結婚指輪をお持ちだったわ……。
彼らが指輪を分けてつけているという話は聞いたことがあったが、こうしてまだ誰の指にもはまっていない結婚指輪を見るのは初めてだった。
『ふたりが一生を誓い合う指輪……』
誰かに“一生”を渡す相手がいるというのは、一体どんな気持ちなのだろう?
クラリスは、愛や恋に心を向けたことがないせいか、今まで許されなかったことを思い描いてみた。
一生を誓い合うという甘い言葉とか、そしてその言葉を伝えたい――ただひとりの相手。
「……」
たとえ現実には存在し得ない人物でも、その男性の姿はまるで真っ黒なシルエットのようにしか描かれなかった。
でも今は、たとえ妄想であってもよかった。
どうせ想像の中でしかありえないことだから。
だんだんと空想に深く沈んでいくからだろうか?
彼女と向かい合って立っているその黒い男性の唇が、かすかに動くのが見えた――。
震える胸の上に両手を置いたまま、クラリスは彼をじっと見上げた。
男の唇が動いた。
「少女?」
え?
聞き覚えのある声にクラリスは目を見開いた。
いつの間にか彼女が想像していた男の姿は消えていた。
代わりに窓際に立つノアが彼女の前にいた。
心配そうな顔で彼女をじっと見ながら――
「ノ……ア?」
「なんだかぼーっとしてますよ?どこか具合が悪いんですか?」
「ううん、違うの。」
クラリスはまだ残る幻の気配に身震いしながらも、無理に明るく笑った。
「指輪がきれいで……ずっと見とれちゃってたの。」
「ん?」
ノアはようやく婚約指輪の存在に気づいたようだった。
「指輪についている宝石って、何か意味があるんですか?」
「いや、宝石は静かでね。語れない宝石だと思う。ただ……一生をただ一人の人に誓うっていうのが、とても素敵だと思って。ロマンチックだし。」
「もちろん、君もいずれはそうなれるさ。望めばの話だけど。」
あまりにも自然に未来の話をするノア。
クラリスは、そんなノアのところがとても気に入っていた。
他の誰も、こんなふうに答えてはくれないだろうから。
「そうだね、ノアもそうだし。それに、もう魔法使いの城から戻ってきたの?明日になるって言ってなかったっけ?」
「少し回り道をしたんだ。」
「冬だから道も危ないし、急ぐと危ないかもね。」
「……うん、そうしたかったんだ。」
彼は小さな声で「なんだか寂しくて……」とつぶやいた。
クラリスは「何が?」と聞きたかったが、彼の質問が先だった。
「この一週間、元気にしてた?」
「私?私はまあ……うん。」
どこかの扉の外から人の声が次第に大きく聞こえてきた。
窓の向こうには車が列を作って止まっているのも見えた。
結婚式に参列する人たちが少しずつ到着しているようだった。
「ベルビルさんに会ってない?」
「もちろん会ったさ。私をここまで案内してくれたのがまさに彼だったから。」
「え?ベルビルさんはここまで来たのに、まだ入ってきてないの?何してるの?」
クラリスは少し驚きながらも、ノアの言葉に肩をすくめて答えた。
「直接見るほうがいいって言ってた。」
ノアは親切にも扉を開けてくれて、礼拝堂の奥へと案内するように先を歩いた。
エイビントンは礼拝堂の一番後ろの席に座っていたが、見るからに恥ずかしいほど顔が真っ赤に染まっていた。
一体なぜそんなに傷ついているのか気になったが……。
「クエンティンおじさんじゃない?」
その隣にはどこか憂鬱そうに見えるクエンティンが座っていた。
彼にはサカマンのオーラがあふれていて、話しかけるには難しい雰囲気だったが、空気の読めないエイビントンはその隣を頑なに守っていた。
王妃の後ろ盾という絶対的な地位を失った今、試験生としての生活を成功させた先輩たちに良い印象を与えようとしているのだろうか?
ともかくクラリスは、自分もクエンティンに挨拶しに行くことにした。
エイビントンを引っ張り出すためにも。
……そうしようと思っていたのだが、すぐにノアによって衝撃的な話が聞こえてきた。
「彼は『急用』ができたから、代わりに私がその役目を果たしてほしいと言ってました。」
「えっ?!」
「大したことじゃないって聞きました。でも……私が一緒だとあなたが気まずくなったりすることはありませんか?」
なぜか彼はクラリスの表情を伺っているようで、彼女は慌てて両手を振った。
「違うの!そんなことじゃないわ。大変なことでもないし。いや、その、ね。」
要するに恋人のふりをしながら、新郎新婦の後ろをついて行くということだ。
これは嘘とはいえ、親しい友達に話せないほど悪いことではなかった。
実際、バレンタインに話すときも少し気まずかったものの、そこまで困ったことはなかったし。
けれどなぜかノアには簡単に言葉が出てこなかった。
『どうしよう……?』
クラリスは嘘をついてしまった。
試験生を代表して新郎新婦を祝福するためのことだと。
バレない自信はあった。
なぜなら、ノアとクラリスが手をつなぐのは九歳の頃からとても自然なことだったからだ。
新郎新婦に続いて歩くとき、ただ普段のように「私たちも手をつなごうか?」と声をかければ、ノアはそのまま手を差し出してくれるはずだった。
しかしクラリスの甘い計画は、入場してきた新郎新婦に会って完全に崩れてしまった。
「引き受けてくれてありがとうございます。突然こんなことをお願いして驚かれたでしょう?勉強の時間を奪って嫌ではなかったですか?」
白いドレスを着た華やかな新婦は、初めて会ったノアとクラリスにもとても親しげに話しかけてきた。
「時間は大丈夫ですが、こんな端っこの席なので誰かに迷惑をかけるかもしれません。」
「まあ、大丈夫です。かわいい仮面ですね。それに話し方がまるでうちの助手みたい……魔法使いはみんなこんなふうに話すんですか?」
「じょ、助手……!」
ノアが衝撃を受けている間に、クラリスが慌ててその二人の間に割って入った。
「私も大丈夫です!近くでお祝いできてうれしいだけです。」
「いい子ですね。私はジインが本当に嫌いだったんですけど。」
「えっ?」
「私たちが首都にいたときも同じお願いをしてきた夫婦がいたんですよ。私は絶対こういうことで時間を使いたくなかったのに、この人が……。」
彼女は隣に立つ夫の胸を手のひらで軽くたたいて笑った。
「絶対やるって言い張るものだから、来ることになったんです。あのセカマンの腹の中も知らずに。」
「セカマン……腹の中?」
クラリスは、穏やかでおとなしそうな新郎をじっと見つめた。
どう見ても、心に一点の曇りもなさそうな人だった。
「それが……」
彼女は白い手袋をはめた手で、ノアとクラリスの手を隠した。
「手をつながないといけないんでしょう?それが狙いだったんでしょう。」
「ふん!」
新郎は顔を赤らめて一瞬言葉を失った。
「手をつなぎたいなら、普段から自然につなげばいいじゃないですか?でもこうやってわざわざ口実を作るなんて、気まずくて仕方ないですよ、本当に。」
そして彼女はクラリスとノアの前に来て、とても興味津々といった顔で尋ねた。
「二人は手をつないだんですか?」
「あ、えっと、それは……。」
「付き合って長いんですか?」
クラリスは慌ててノアを見た。
もちろんそうしても、仮面があって彼の表情は分からなかった。
「い、いえ私たちは……。」
クラリスが必死に言葉を探しているとき、少し離れた場所にいた司祭が、もう礼拝堂に入らなければならないと彼らに声をかけた。
「……残念ですね。式が終わったら必ず話してくださいね。そして今日は私たちのために時間を作ってくれてありがとうございます。」
「いえ、本当に間近で結婚式を見られるなんて楽しみです。お二人が永遠に幸せでいられるように祈りますね。」
「そうですか?それなら私もお返しにお二人が永遠に幸せでいられるよう祈ってあげます。」
「あの、それは……。」
ダメなのに。
クラリスは彼女を止めようとしたが、言葉にならず、ただうろたえるばかりだった。
そして礼拝堂から演奏の音が聞こえてきた。
式が始まるという意味でもあった。
何も返せなかったクラリスの後ろで、新郎と新婦は先に礼拝堂へと向かった。
「……ご、ごめんね。」
しばらく二人きりになったクラリスは、すぐに両手を合わせて彼に謝った。
ノアは頭が良いから、おそらく今ごろはクラリスが何かを隠していたことにすっかり気づいたことだろう。
「すごく困ったでしょ?ベルビルさんが、こういうことを頼める受験生はいないって言ってたの。」
「別にそこまでじゃなかったよ。たしか以前にも似たようなこと、しなかった?」
彼はおそらく、クノー侯爵夫人の前で「求婚する騎士」の役をしたことを言っていたのだろう。
「それとは少し違うよ。気分が……悪くない?」
「ちょっとだけ。」
彼はどこかおもしろそうに微笑んでさえいた。
「むしろ幸いでしたね。少女がエイビントとそんなことをする場面を自分の目で見なくて済んだので。それは本当に気分が悪かったと思います。」
「私も気分が悪かったよ。だって、エイビントは私の手を離すなり、手のひらをハンカチでゴシゴシ拭いて……ノア?」
クラリスがエイビントとのエピソードを話しているだけなのに、ノアの手から赤い魔法が湧き上がり、指の間をぐるぐると流れていた。
「あ。」
彼はクラリスの視線を追って自分の手を見下ろし、ようやくそれに気づいた。
「癖なんでしょうね。」
彼は慌てて手を振り、魔法を消した。
ちょうどその時、遠くから司祭が彼らを見て合図を送った。
「私たちも行かないとね。」
「私が未熟で彼女に迷惑をかけないか心配です。」
「何言ってるの、ノアがそんなことするわけないじゃない。」
そのとき、二人の前にまた別の補佐官が現れ、ノアに灰色のケープを差し出した。
「お持ちしました、魔法使い補佐官殿。」
「わ、すみません。」
クラリスが代わりに謝った。
「ノアはローブを着ます。魔法使い団の規定なんです。」
「僕が持ってきてくれと補佐官に頼みました。聞いてくれてありがとうございます。」
「どうして着替えようと思ったの?そのままでも大丈夫なんじゃ?」
「理由があります。」
ノアの肩と腕に沿ってローブがすっと落ちた。
彼はその長く大きなローブをきちんと畳んで、補佐官のもう一方の手にそっと渡した。
「では、これもお願いします。」
「はい、承知しました。首都院の任務に協力いたします。」
「ありがとうございました。」
司祭は頭を下げて挨拶をし、ローブを翻して奥へと歩いていった。
ノアはケープをかけながらクラリスを見た。
すると彼女はびっくりして一歩後ろへ下がった。
何だか彼が少し違って見えた気がした。ただ衣装を変えただけなのに。
「ローブを脱いだのは失礼がないようにするためです。私がローブを着たまま出ていけば、主役よりも目立つでしょう?」
「そ、そうね……。」
クラリスはそっと襟元をつまんだ。
装飾用の刺繍糸を縫い込んでいる彼の手から目を離せなかった。
時おり青い糸や飾りの形がちらちら見えたり消えたりするのが、なぜか……好きだった。
そして丸い形で丁寧に手入れされた指先も。
『触りたい……。』
クラリスは自分でも気づかぬうちにそんなことを考えていたが、慌ててそっと視線を下げた。
彼の顔に手を伸ばしたそのとき、ある声が聞こえたのはついさっきのことだった。
でも顔に続いて手までそっと触れてしまえば、本当に不適切な行為として処罰されてしまうだろう。
『手をつながなきゃいけないじゃない?それを狙ったんでしょ。』
少し前に聞いた言葉が思い出された。
まるで一本の綱にすがる希望のように。
もちろんクラリスは、そんな気持ちをごまかすような言い訳は忘れずにつけ加えた。
「気まずくなんかないよ、本当に。」
『わ、私は……気まずいわけじゃないけど。』
クラリスは少しむくれた表情を浮かべて、ノアを見上げた。
ただ服を着替えただけなのに、ノアは普段とはまったく違う雰囲気を漂わせていた。
本当に「同じ受験生」だと言えるのだろうか?
――いや、ノアは受験生に分類されるような人ではなかった。
特有の雰囲気や白いローブのせいで、どうしても「先生」のような感じがあった。
それにぴったり合うくらい賢くて、クラリスが分からないことがあれば何でも明確に答えてくれた。
「そろそろ出発したほうがいいでしょう。何か注意することはありますか?」
「ううん、ない。ただそのままついて歩くだけでいいの。私、私と……手をつないで。」
クラリスはなぜかもじもじしながら恥ずかしそうに手を差し出した。
『これは何でもないことよ。』と自分に言い聞かせながら。
というのも、二人は小さい頃から今までずっと自然に手をつないできたのだから。
「ちょっと待ってください。」
でもノアはなぜか準備が必要なようで、ズボンのポケットを探り始めた。
「今日は忘れずに持ってきたのでありますよ。」
「持ってきた……何を?」
しばらく探っていた彼が取り出したのはハンカチだった。
手を拭くために使うのだろうか?
彼はハンカチをくるくる巻いてクラリスの手に渡した。
「持ってください。」
「……?」
言われるままにハンカチを掴むと、彼は手の外にはみ出た部分だけを軽く握って満足そうに口角を上げた。
「もう大丈夫です。」
……えっと、これっていったい……?
「遠くから見たらちゃんと手を繋いでるように見えると思いますよ。心配しないでください。」
「そ、そういうことじゃなくて。」
クラリスが何か言おうとする間もなく、ノアは一歩前に出て新郎新婦の後を歩き始めた。
『……なぜ。』
クラリスは前を歩いていくノアを見上げた。
しかし見えると言っても、仮面の下からちらっと見えるのは白い顎先だけだった。
だからこそ、どうして彼がクラリスの手をきちんと握ってくれないのか分からなかった。
いや、それよりも。
『……私はなんで寂しいんだろう。』
クラリスは自分の気持ちすら理解できなかった。