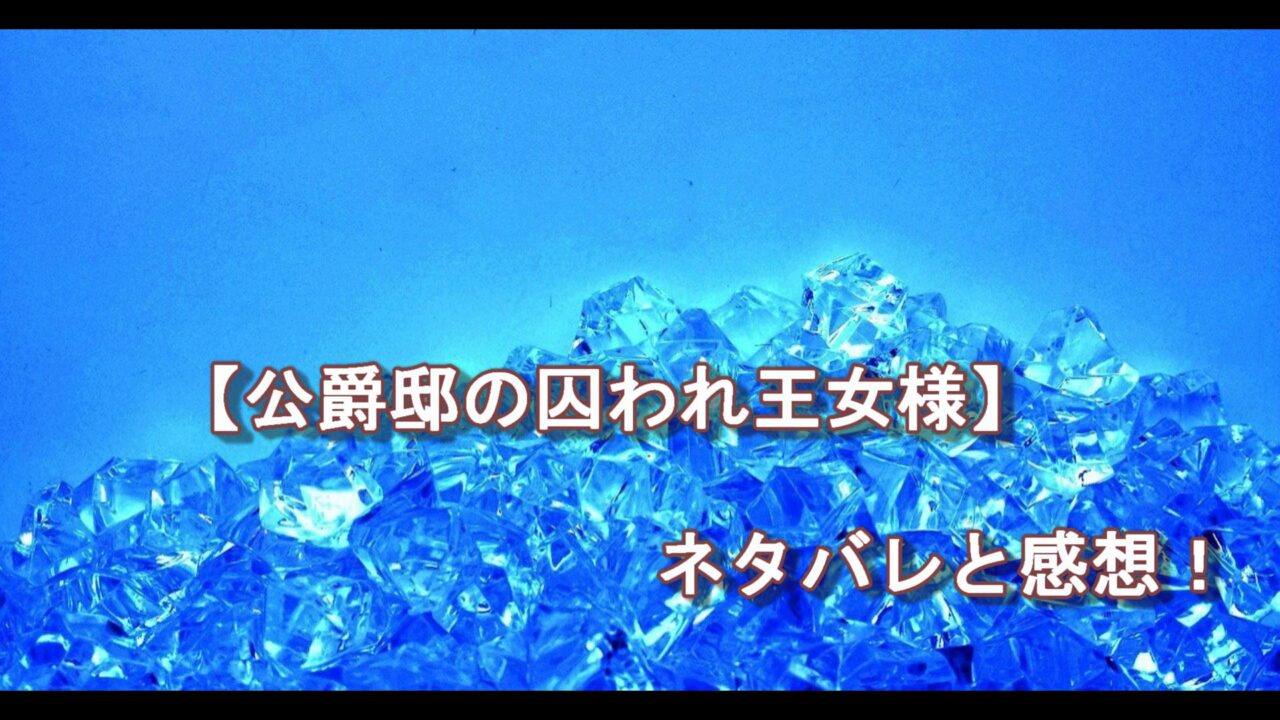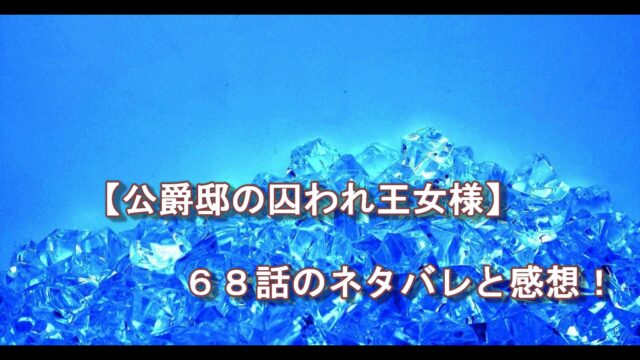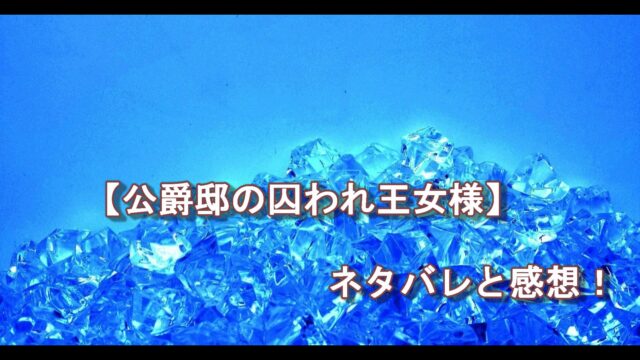こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

77話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 魔法使いの城③
(それでも、こんなにも時間が経つまで話せなくなるとは思わなかった・・・)
彼との深い友情を考えると、今すぐにでも話さなければならない。
「ねえ、聞いてノア!私、言いたいことがあるの!」
クラリスはなぜか震える手で彼のローブをしっかり掴み、訴えた。
「どうしたんですか?」
振り返るノアが仮面を外したせいで、クラリスは自分でも気づかないうちに言葉を止めたまま、彼をじっと見つめてしまった。
彼の顔は、相変わらずだ。
透き通るような肌の上に花びらのように散りばめられた赤いほくろが、ほのかに浮かび上がっている。
クラリスはその姿が本当に好きだった。
少し具体的に言うと、そのほくろから漂う雰囲気が好きだった。
気がつくと、彼女の手は無意識に彼の頬に触れそうになっていた。
「きれい・・・。」
「本当に、少女は!」
正直な感想に対して、ノアは慌てた声を出しながら顔を背ける。
「ひどいよ。」
クラリスは少しひんやりとした彼の頬を、ぎこちなく触れたまま、涙ぐむような表情を見せた。
「どうして僕が仮面を外すと、顔に触ろうとするんですか?」
「それは仕方がない!」
クラリスは一歩前に出て、彼の顎をそっと持ち上げた。
「だって私はノアの顔がすごく好きなんだもの!世界で一番好き!」
「・・・。」
「半年ぶりに見るってだけだよ。友達の顔が好きなのが何か悪いの?」
「顔を好きでいることに必ず触れるという行為が伴う必要はないでしょう?」
「それはそうだけど、私は触りたいって言ってるの。」
「それなら事前に許可を求めてください。もう子供でもないでしょう?」
ノアはクラリスも15歳を過ぎていることを考えれば、友達の顔をむやみに触れるのが普通ではないと分かっているようだった。
首都の貴族たちは15歳ともなれば、結婚相手を探すために宴会に出席したり、恋愛を楽しむような年齢でもあるのだから。
クラリスもそのことを意識し、15歳になってからは少し礼儀をわきまえるようにしていた。
しかし、ノアと一緒にいるときは、どうしてもそんな行動が取りづらかった。
ただ一緒にいるだけで、9歳の頃のクラリスに戻ってしまうような錯覚を覚えたのだ。
そうだ。
だから正直な気持ちでは「私はノアの顔に触れたいの。私の気持ちのままに。」と、子どもの頃のように無邪気に言いたかった。
「ふぅ。」
しかし、真剣なノアの表情を見て、そんなことを言ったらただ大きな反発を招くだけだと思い直した。
クラリスは身に染み付いた礼儀正しさを発揮し、彼に丁寧に挨拶をした後、お願いの言葉を口にする。
「親愛なるノア様、どうか私があなたのお顔を撫でることを許していただけませんか?」
「嫌です。」
クラリスは冷たく断られたが、両手をしっかりと組んだまま、真剣な顔つきで彼を見上げ続けた。
「嫌・・なの?」
「・・・。」
「私は・・・好きなのに。」
「・・・ダ、ダメです。」
そうか、やはり断られるのか。
それなら、もうこれ以上無理強いはしないでおこう。
クラリスはそう考えたものの、最後の未練を断ち切ることができず、泣きそうな顔で再び尋ねてしまった。
「本当に・・・ダメなの?」
しばらく迷っていた彼が、ようやく「分かりました」と言って、うなずいた。
「本当?!」
クラリスは冷えた両手をそっと持ち上げた。
「でも、まずは今しようとしていた話から続けたほうが良いと思います。私に言いたいこととは何ですか?」
「あ・・・」
クラリスはがっかりして、持ち上げた両手をそっと下ろした。
本当は彼に処刑に関する話をしようと思っていたのに・・・ノアの顔を見たら、それまで固めていた覚悟がすっかり消えてしまい、なぜか別の話題が口をついて出てしまったのだ。
「うん・・・私、さっきアルステア・アストさんに会ったの。」
ノアは少し疑わしげな目でクラリスを見つめる。
それが本当に彼女が話したい内容なのか、どうにも信じられない様子だった。
しかしクラリスは動じず、その話を続けた。
「とても良い方だったわ。私が失礼なことを言ってしまったのに笑って許してくれたの。」
「少女が失礼を?」
「まあ・・・あの方を団長様って呼んでしまったの。」
「魔法使いの中にはすでにそう呼ばれている方もいるらしいですから、大した無礼ではないですよ。」
「じゃあ本当に将来あの方が団長になるの?」
「魔法使いの宝石があの方を選ぶなら、そうでしょうね。」
「その話も聞いたわ。魔法使いの宝石って結局、何なの?」
「この絶壁の上の城を維持する魔法使いの宝石です。この城の主人となる者を選ぶのが、宝石の重要な任務なのです・・・少女。」
説明していたノアは突然目を大きく開き、クラリスをじっと見つめた。
「その表情の意味が説明できるなら、魔法使いの宝石に会わせてほしいと言おうとしているわけではないと願います。」
クラリスはぎこちなく笑い、少し動揺して体を揺らした。
宝石といっても、所詮は鉱物であり、そんな重大な役割を担う物質ならクラリスと会話できる可能性もあるだろうからだ。
「・・・いや、その。」
クラリスは急いで弁解した。
「宝石に聞けば、いつアルステア様が団長に選ばれるか分かるでしょう?」
「同時に少女の才能が大々的に宣伝されるかもしれません。」
「もし仮に聞いてみるなら・・・。」
ノアの表情がさらに険しくなったため、クラリスは言葉を飲み込んだ。
「私はただ・・・アルステア様が早く団長になってくれたら、それでいいの。」
ノアのために、という思いだった。
少し前に、無礼な灰色ローブの魔法使いが、ノアがここで暮らしているのはすべてアルステアのおかげだと言った。
だから、彼が正式に団長となって、さらに強い影響力を持つようになれば、他の魔法使いがノアを無下に扱えないように命令してくれるのではないか?
「私もそうなることを願っています。」
「うーん、あるいはノアが団長になっても格好いいだろうね。そう思わない?」
「やめてください、そんなこと言うのは。」
「・・・どうして?」
「魔法使いの団長は、この城を代表する存在です。統率力はもちろん、政治的な感覚も必要です。私のような至らない者には到底務まる役職ではありません。」
「ノアが至らない者と呼ばれるのも、私からすればおかしな話だけど。崩れた谷に行き、お母さんの石碑と語り合えば、方法が見つかるかもしれないし」
「それもあり得ますね。ただ、その前に魔法使いの評議会が少女を必要とするでしょう。」
クラリスは言葉を失った。
その言葉はまさに戦争を意味していた。
「少女、私は今が好きです。」
ノアは彼女の肩に垂れ下がった緩んだリボンをいじり始めた。
彼のローブの中に隠されていた同じリボンが現れると、両手首にしっかり結ばれているのが見えた。
「今のように穏やかに生きていけることを願うばかりです。」
「それでも、他の人々がノアを・・・あんな風に扱うのが腹立たしいの。もしかしたら私がその問題を解決できるかもしれないわ。」
「以前の私はこの状況を恐ろしく感じていただけでした。」
「・・・。」
「今もそういう部分はあるけれど、少しだけ・・・受け入れるようになりました。」
「・・・。」
「ここは荒廃した土地で、お互いを妬み、詐欺を働く者たちが集まっています。少女のような人が過ごせる場所ではありません。」
「それでもノアが一緒にいれば大丈夫な気がするけど。」
クラリスは無意識のうちにその考えを抱きながら、そっとノアの袖を掴んだ。
それは彼女の人生を支えてくれた恩人である工匠を裏切ることに等しい行為だった。
彼女はセリデンの保護の下にいなければならなかった。
3年後に迫る約束を守るためにも。
「わかった・・・うん。」
クラリスはほとんど聞こえないような声で返事をして、彼に向かって微笑んだ。
「それと。」
ちょうど彼に報告しなければならないことがあるのを思い出したのだった。
「今回の冬から首都院に行くことになったの。」
「それって勉強しに行くってこと?」
「うん、そうだよ。試験に慣れる機会だと思って。」
「せっかちな少女にぴったりの場所だね。」
「せっかちだなんて。」
「私の言葉、間違ってる?少女はいつも明日がない人みたいにせわしなくしてるけど。」
「それは・・・!」
「それは?」
「うん、まあ・・・私はせっかちなほうだよ。どっちみちそういう状況になったんだから、冬には手紙のやり取りが難しくなるかもしれない。」
首都院で過ごす間は連絡が制限される。郵便馬車が頻繁に来るわけでもないし、指定された保護者からの連絡以外では手紙を送ったり受け取ったりすることがほとんど許されていなかった。
すべては勉強に集中する環境を提供するためだ。
「週末には首都院を出て生活するけど、ハイデンの別宮で過ごすことになると思う。」
「ああ・・・」
ハイデンの別宮は首都院よりさらに手紙のやり取りが難しかった。
もしノアが普通の少年だったら分からないが、彼は魔法使いだ。
王室と魔法使い団の公式な関係がまだぎくしゃくしている以上、王宮内で魔法使いと手紙をやり取りするのは一般的に敬遠される傾向にある。
おそらくノアが魔法使い団に対して疑念を抱いていることを察してのことだろう。
「・・・そうなんだ。」
どうしても連絡を取りにくいという事実のためなのか、ノアは少し憂鬱そうな表情を浮かべた。
「首都院にはいつまでいるんですか?」
「夏前までいると思う。」
「怖くないんですか?」
「何が?」
「少女は誰かと一緒に過ごしたことがほとんどないでしょうから。」
「それはそうだけど・・・」
クラリスは微笑みながら答える。
「運が良ければ、バレンタイン王子が一緒に行くことにしてくれたの。」
「・・・!」
ノアは驚きを隠せない反応を示した。
一国の王子が首都院で勉強すること自体が非常に珍しいことなので、その反応は当然だろう。
「最初に私に、首都院で一緒に過ごしながら勉強するよう勧めてくれたのも王子だったの。驚きでしょ?」
「王宮にはまともな教師がいないの?」
「いるけど、王子も試験の雰囲気に慣れたいんですって。それ以上に。」
クラリスは、ノアの表情が少し曇っていることに気づかないまま、説明を続けた。
「王子には、他の人たちと一緒に過ごす経験も必要だと思うの。」
「私から見ると、王子はそういうことに興味がないように思えるけど。」
「ノアがそれをどうしてわかるの?私が何度紹介してあげるって言っても、いつも断るだけだったのに。」
「・・・それは。」
「二人はきっと相性が良いと思うのに。」
「申し訳ないけど、私は仲良くしたいとは思わないよ。友達なら君一人で十分だ。」
今回もやはり同じ返事が返ってきたため、クラリスは少し笑ってしまった。
本当に相性が良さそうなのに。
クラリスはどうすれば二人を会わせることができるか悩んだ。