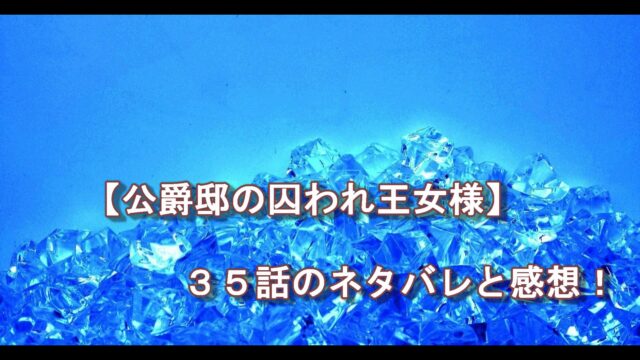こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

139話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 帰郷
ユジェニとも別れ、馬車の前に着くと、なぜかノアのほうから先に手を差し出していた。
馬車に乗り込むのを手助けするつもりなのだろう。
この好機を、そのまま見過ごすわけにはいかず、クラリスはすぐに彼の手に自分の手のひらを重ねる。
「……うん、すごくいい。」
胸の奥がふわりと浮き立つのを感じ、クラリスは思わずにこっと笑ってしまった。
ノアはぐっと力を入れて、クラリスを馬車の中へと引き上げた。
無事に座ったのを確かめると、名残惜しそうに手を離したものの――クラリスが離れていく彼の手を見つめていると、ノアは無言のまま、馬車の扉をきっぱりと閉めてしまった。
クラリスは窓に張りつき、ノアに向かって笑顔を向けた。
「ノア、本当に……魔法師の城へ戻って……あなた、本当に大丈夫?」
「ええ、もちろんです。ああ、森から持ち帰った石のことを心配しているのなら、ご安心ください。必ず魔法使いメイビスの墓のそばに供えておきますから」
「石のことが心配なわけじゃないの」
クラリスが案じているのは、ノアのことだ。
最近は何事も起きていないとはいえ、魔法使いアストがいかにも胡散臭い存在であるのは否定できない。
しかも、気立ての優しいノアは、今もなお彼を完全には疑いきれていないようにも思えて……。
「――少女」
その胸中を見透かしたかのように、ノアは窓辺に置かれたクラリスの手に、そっと自分の手を重ねた。
甲の上をなぞるように、彼の指先がかすかに触れ、クラリスは思わず息を呑み、ぱちりと大きく目を見開いて彼を見つめる。
「前にも言いましたが……どうか、私をあまりか弱く見ないでください」
「…………」
「私は、怪物の声を聞く者です。それは――」
言葉の続きは、静かな空気の中に溶け込み、これから語られる真実の重みだけが、そっと胸に残っていた。
「……いえ、別に外見の話をしているわけじゃありません。」
ノアは整った顔立ちをしていた。
横顔にのぞく白い耳でさえ、やけに目を引くほどに。
今しがた彼女を支えてくれた長い指も、言うことなしだ。
クラリスは言い返したい気持ちをぐっと飲み込み、本当に大切な点を口にした。
「でも前に、ノアは言ってたでしょう。私を害せるのは、たった一人だけだって。もしその人が悪意を持ったら、どうなるの?」
クラリスは、それがもしかすると魔法師アストなのではないかと、ひそかに考えたことがあった。
もしそうなら、事態はかなり深刻だ。
ところがノアは、くつくつと笑い出した。
「心配いりませんよ、少女。まさか私を殺すつもりでも?」
「ば、馬鹿なこと言わないで!」
「なら大丈夫です。今、あなた自身が言いましたよね。その“唯一の相手”は、私を殺さないって。」
「……え?」
動揺して問い返すと、彼はクラリスの手を取ったまま、わずかに力を込めた。
「それは……少女のことだ」
――ノアを殺せるのは、ただクラリスだけ。
あまりにも突飛で、現実味のない話だった。
そもそも、そんな発想をしたことすらなかったのだから。
「どうして、そんなことを言うの?」
「ただ……少女が不安にならないよう、はっきり伝えておこうと思って」
窓の向こうに滲む紫がかった視線が、わずかに濃さを増し、彼の言葉に込められた本心が、より深く伝わってきた。
「私の命は、少女の手の中にあります。今までも、そしてこれからも」
「…………」
「だから、どうか私のことを心配しすぎないでください」
最後に彼はそっと手を離し、指先でクラリスの髪をやさしく撫でると、一歩だけ距離を取った。
その仕草の余韻が、静かな空気の中に、いつまでも残っていた。
クラリスは言葉を失ったまま、彼の言葉について考え込んだ。
「後でセリデンに着いたら、手紙を書いてください。私は、少女からの便りを心待ちにしています。」
「私も……」
馬車が発つ前に答えなければと、クラリスは急いでそう返した。
手紙を待っている、と。
だが実際、彼女が本当に待っているものは、手紙だけではなかった。
――いいや、まったく別のものだった。
少し前なら、自分の本心を正直に打ち明けていいのか悩んだだろう。
けれど、今のクラリスは違った。
ユジェニの助言があったからだ。
クラリスがどれほど気持ちを言葉にしても、ノアは決して気づかない。
だからこそ、これからはただ率直に伝えることにしたのだ。
「ノアが迎えに来てくれるのを、指折り数えて待ってる。毎日、会いたいと思うから。」
「……あ。」
こんな答えが返ってくるとは思っていなかったのか、ノアは一瞬だけ言葉に詰まり、無意識に仮面の縁へと手を伸ばした。
「そ……それは、いずれにせよ行くつもりでしたよ!ほら、僕たちが一緒に調べている件もありますし。少女がきっと僕を呼ぶでしょう?そうですよね?」
ユジェニの助言は、見事に的を射ていた。
ノアは、クラリスの胸の内を、ほんの少しも察してはいなかったのだ。
そのことに、クラリスはなぜか肩の力が抜けるような気がして、むしろ、ほっとしてしまった自分に気づく。
――少なくとも、ノアにこの想いを悟られる心配はなさそうだ。
「うん。その理由もあるけど……正直に言うと、私はノアのことが好きだから。たくさん会いたいって、そう言ってるの」
胸の奥がすっと軽くなる。
クラリスの口元には、気づかぬうちに穏やかな笑みが浮かんでいた。
一方で、ノアはというと、わずかに身じろぎしたかと思うと、慌てた様子で馬車の側面を軽く叩く。
「あ、ええと……とにかく、早めに出発したほうが良さそうですね!このままだと日が落ちて道も暗くなりますし……」
彼の声は少しだけ上ずっていて、それが妙に可笑しくて、クラリスは小さく息を弾ませた。
「そうなると、危険が増すかもしれませんから。」
「まだ昼間だけど?」
「行きなさい。どうか、日がいちばん高いうちに。私があなたを心配して引き返す姿を、見たくないのでしたら!」
……あ、それはちょっと見てみたいけど。
そんなことを考えているうちに、クラリスを乗せた馬車は、ゆっくりと動き出した。
名残惜しさに振り返ると、ノアはいつの間にか地面にしゃがみ込み、深くうなだれていた。
その後ろで立っていたユジェニは、いたわるような眼差しで彼を見つめている。
「……ノアも、修道院を離れるのが、やっぱり寂しいのね。」
クラリスは小さくそう呟きながら、どこか満ち足りた気分で馬車の背もたれに身を預けた。
これから先、ノアにどれほど「好きだ」と伝えられるのだろう。
そう思うだけで、胸が弾んで仕方なかった。
――これからは、手紙のたびに「好きだ」と書いてあげよう。
あれほど真剣に想いを打ち明けたところで、どうせノアは気づかない。
そう思うと、むしろ清々しい気持ちにさえなった。
ハイデンに到着したクラリスは、まず公爵夫妻に挨拶を済ませ、改めて滞在の許しを得ると、次にバレンタインのもとを訪ねた。
表向きの理由は、修道院の仲間たちの近況を伝えるため――ということになっている。
だが、それはあくまで建前だった。
本当は、彼が無事に過ごしているのかが気がかりだったのだ。
何度か手紙を送ってはいたが、返事が届いたことは一度もない。
「……あの日以来、王子殿下はずいぶん変わられた気がする」
死刑囚と面会して戻ってきた彼は、クラリスをこのまま死なせるわけにはいかないと、珍しく感情をあらわにしていた。
言葉遣いは荒く、態度も強硬だったが、クラリスには、そのすべてが彼なりの必死さから来るものだと分かっていた。
その慎重な心遣いは、ありがたいと思えた。
――けれど、王子殿下がそのような考えを抱くのは、やはり危険だ。
かつてセパス王は、クラリスの処刑を妨げる者は、たとえ誰であろうと決して許さない、と公言したことがあった。
王の言葉は、硬い岩に深く刻まれた文字のように、時が流れても容易に消えることはない。
だからもし、バレンタインがクラリスを助けようとすれば、ライサンダーは彼を排除しに動くだろう。
同じ王族だからといって、情けをかけてもらえるなどという期待は、最初から抱かないほうがよかった。
幼い頃のクラリスもまた、兄に命を狙われながら、無事に成長できたわけではなかったのだから。
――それでも、今は少し時間が経った。
王子殿下も、当時のことを忘れているかもしれない。
そう考えているうちに、いつの間にか彼の別邸へと到着していた。
すると、クラリスの前にバレンタインの侍従が歩み寄ってきた。
「王子殿下は、ただいまご多忙です。お引き取りください。」
彼はぶっきらぼうにそう言いながらも、どこかクラリスの反応を窺うように、ちらりと視線を向けてきた。
前回、食事の代わりに差し入れをしてくれた件を、気にかけている様子でもあった。
「少しだけでもお会いできませんか?修道院の修練生たちから、王子殿下にお伝えしてほしい話があると頼まれていて……」
「それは無理だな」
「お元気かどうか、確認するだけでも……心配で。王子殿下にお伺いすることは、できませんか?」
「まったく、君は人を困らせるのが上手だな!」
彼はそう言って顔をしかめ、両手を大きく振った。
その仕草が、どうにも“どうしても行ってほしい”と懇願しているように見えて、クラリスはかえって申し訳なくなった。
「行け。な?聞いてみて、少しでもあの方の気が晴れそうなら、もう行ってきなさい……!あ、いや、違う」
「……はい?」
「何でもない!」
彼は語気を強めて言い切り、話を打ち切るようにそっぽを向いた。
侍従は、少し前の言葉を必死に取り繕おうとしているようだったが、無駄な努力だった。
クラリスは、はっきりと聞き取ってしまったのだから。
バレンタインは、心変わりするつもりはないのだ、と。
それはつまり――
「もしかして、王子殿下が……私には会わない、とおっしゃったのですか?」
「い、いえ!決してそのようなことは……!」
侍従は、震える唇で必死に否定した。
「……では、いったいなぜです?」
だが、顔色を失ったクラリスの様子を見て、もう隠し通せないと思ったのか、彼は大きく息をついた。
「私がこんな失態を犯すとは……情けない限りです。」
「…………」
「とにかく、あまり深く考えないでください。王子殿下は、いまは外での務めに専念なさっているだけなのですから。」
「外部活動、ですか?」
「そうだ。ときどきは、王妃陛下の名代として、社交の席に顔を出されることもあるほどだ」
ヴァレンタインが王室の一員として、その立場を確かなものにしていくのは、祝福すべき出来事だった。
実際、彼の振る舞いに注目する貴族も徐々に増えつつあり、これから先、状況はさらに変わっていくのだろう。
「……あ」
クラリスは、彼の言葉の裏にある意図をすぐに理解してしまった。
王室の一員となったヴァレンタインの隣に、クラリスのような“気安い友人”の居場所はない――そう告げられているのだ。
王族に求められるのは、親しみやすさではなく、揺るぎない威厳と敬意。
それを保つためには、身分の低い友人との親密な関係は、むしろ足枷でしかなかった。
「……そう、ですね」
当然の帰結だと、頭では理解していた。
だからこそ、その結論に胸を抉られることもなかった。
それは、明らかな嘘だった。
けれど、理解できないわけでもなかった。
――むしろ、バレンタインがここまで迷いなく、確かな道を選び取ったことを、喜ばしく思えるほどだ。
「王子殿下のご判断は正しいと思います。私の考えが浅はかでしたね。」
「い、いえ、それは……」
侍従は何か慰めの言葉を探そうとしたようだったが、やがて小さく首を振り、自分から口をつぐんだ。
「王子殿下に、私がいつも応援しているとお伝えください。それから……」
クラリスは一歩下がり、そっと髪を耳にかけた。
指先に触れた赤いリボンが、彼女に不思議な勇気を与えてくれたおかげで、クラリスは気負うことなく、まっすぐ立って穏やかに微笑むことができた。
「バレンタイン王子殿下も、きっと私を応援してくださっていますよね。」
侍従が、はっきりとした眼差しで見つめてくるのを、クラリスは一瞬だけ受け止めた。
そして、何事もなかったかのように礼儀正しく一礼すると、来た道を静かに引き返した。
春のやわらかな陽射しに導かれるように、クラリスと公爵夫妻は、懐かしきセリデンへと向かった。
帰路は急ぐ旅ではなく、まるで小旅行のようだった。
マクシミリアンが「何があってもブリエルに無理をさせてはならない」と強く念を押したため、彼らは通り過ぎる町ごとに足を止め、休息を挟みながらゆっくりと進んだのだ。
そのおかげで時間には余裕が生まれ、クラリスは夜ごとに机に向かい、勉学に励む時間をしっかりと確保することができた。
けれど、走り出した馬車の中では、どうにも勉強に集中できなかった。
その理由は――
「……本当に、これをセリデンまで付けて行くんですか?」
クラリスがノアと一緒に作ったモビールが、馬車の天井からぶら下がっていたからだ。
「恥ずかしいです。」
クラリスは何度も、あの拙いモビールを外してしまいたい衝動に駆られた。
けれど、ブリエルが揺れるモビールをそっとなでながら、こんなふうに言うものだから、もう強くは言えなかった。
「でも、このモビールを見ると、赤ちゃんは楽しくなるんですよ。」
「……うぅ。」
「ちゃんと、愛されているって伝わるんです。」
「赤ちゃんが生まれて、実際にこれを見たら、がっかりするかもしれません。私が作ったものなんて、すごく不格好ですし。」
「そんなことありません。私が見ても、思わず感嘆の声が漏れるほどですね」
「実は、それを作ったのはノアなんです」
「まあ。大理石だけでも立派なのに、この華やかさ……本当に見事ですわ!」
「……それも、ノアが手掛けたものなんです」
「まあ……」
夫人がさすがに言葉に詰まると、向かいで書類に目を通していた公爵が顔を上げた。
「私は、この壺が気に入った。表面の凹凸が実に生き生きとしている……」
そう語りかけたところで、彼の言葉はふと途切れた。
ブリエルが、慌てた様子で首を横に振ったからだ。
「……まさか、サツマイモですか?」
慎重に問いかけた公爵の一言に、ブリエルはついに声を上げて嘆いた。
「ああ……」
「いずれにせよ、根菜というのは優れた作物だ。長年セリデンを支えてきた栄養価の高い食材でもある。セリデン邸を飾る調度の一部としても、これ以上ないほど相応しいだろう」
その言葉に、場の空気はどこか和らぎ、ブリエルは力なく肩を落としながらも、小さく息をついた。
サツマイモであろうと、ジャガイモであろうと——それがノアの手によるものである限り、その価値は揺るがないのだから。
クラリスは、真っ赤になった顔で、彼が「サツマイモ」だと思い込んでいたモビールの正体を、そっと明かした。
「それ、ヒトデです。」
公爵の眉がぴくりと動いた。
「……ほう。呼び名を間違えたことは謝ろう。私は……一つだと思い込んでいたのだ。ヒトデとは、四つの腕が集まって一つになるものだろう?」
いつも厳格で真面目な公爵が、赤ん坊用のモビールを大切そうに撫でながら、真剣に言い訳をする姿は、あまりにも可愛らしかった。
必死に笑うのをこらえていたクラリスだったが、隣にいたブリエルが先に吹き出してしまう。
それにつられて、クラリスもとうとう笑ってしまった。
そしていつの間にか、その様子を見ていたマクシミリアンまでもが、穏やかに微笑んでいた。