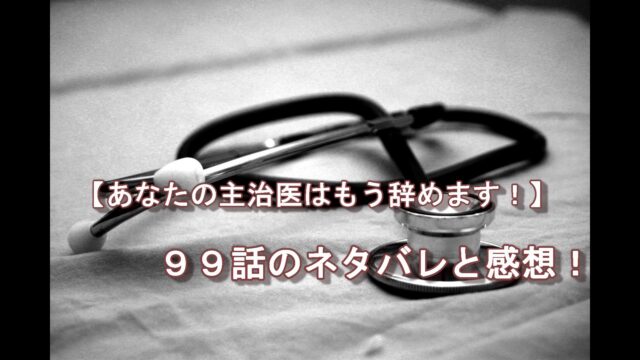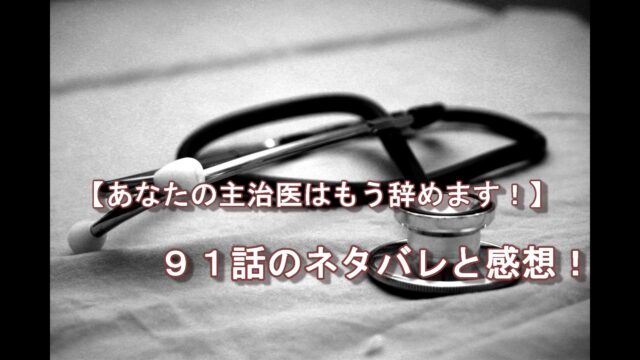こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

121話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 家族として⑥
お父さんは半信半疑ながらも、信頼が少しずつ湧いてくるような曖昧な表情を浮かべて尋ねた。
「・・・イシドール男爵はどうするおつもりですか。」
もちろん、イシドール男爵に一番恨みを抱いているのはイザベル様とエレアンだろう。
直接的に毒殺を試み、セルイヤーズ領地を奪おうとしたのだから。
しかし、彼が私たちを殺さなかったにしても、私を消そうとした上にお父さんに嘘をついたことは事実だ。
それでお父さんは公爵令から処分を任されたイシドール男爵をどうするつもりなのか尋ねたのだ。
「ああ。」
エルアンは命令をよく聞く獣のように素直な口調で、ぞっとするような言葉を吐き出した。
「ウェデリックの悲鳴が聞こえるほどの地下牢に閉じ込めて、鎖で縛りました。」
「それならウェデリックは、自分の父親と共に閉じ込められるとは思いもしなかったでしょう。」
「私の母は、幼い頃の私が痛みや苦しみで泣くたびに、胸が引き裂かれるようだと言いました。だから同じように、あの世をすべて味わわせるつもりです。」
エルアンは冷静な口調で『イシドール男爵は生涯、牢獄で息子の悲鳴を聞きながら苦しむことになるだろう』と続けた。
命を奪わないという約束を守ったことには違いなかった。
「でも、いつか誰かが彼を不憫に思って、ウェデリックの血に染まった布切れのようなものを投げてくれるかもしれませんね。」
恐ろしいほど残酷だったウェデリックを思うと、イシドール男爵は本当に苦しい毎日を過ごすほかないのだろう。
「それに、私たちのリチェを苦しめた人なら、なおさら放っておくわけにはいきません。任せていただければ、最善を尽くし、残酷な方法も考え出します。」
エルアンは真剣な表情で話を続けた。
しかし、私は苦笑しながら言った。
「ハエルドン皇子は自覚がないようですね。まあ、イセラ皇太妃が私にこっそりやって来て、妊娠しやすい薬を処方してくれと頼むくらい焦ってはいましたが。」
「そんな薬があるの? 処方したの?」
「まあ、役立つ薬を作ってあげはしましたが、可能性を少し上げるだけで、大した効果はないでしょう。」
「・・・そう? その事実、誰が知っているの?」
私は考え込んだ後、そう答えた。
「まずはジェイド皇太子様です。皇太妃がどうしても秘密にしてほしいと頼んできましたが、皇太子様の性格上、うまく秘密を守れるかどうか……。皇太子様がはっきりと一、二度は失敗しただろうと考えています。」
「私もそう思う。皇宮は情報が広まるのが早い場所だから、ほとんどが知っていると見た方がいいだろうな。」
「うん。」
エルアンと私の会話を聞いて、お父さんは気が重いという表情を浮かべていた。
調査官に真実を知らせたとしても、まだ終わったわけではないので、不安を感じているのは当然だ。
「リチェは異常なほど善良で優しいです。嘘もつけず、まったく普通すぎます。だからこそ隣に私のような少し妙な相棒がいれば、厳しい世の中をもっと上手く生き抜けるのではないでしょうか。」
エルアンにとって特に悪い記憶のない祖父と苦悩する彼の言葉には、反論の余地がなかった。
お父さんは腕を組んだまま、絶対に許さないという目つきだけを向けているだけだった。
「お父さん、公爵様も邸宅にしばらく滞在するのはどうですか? 換気が必要な時期ですし、症状も見守る必要があります。お父さんが公爵城に行くとしても、私たちから離れるのは同じじゃないですか。」
私の理にかなった言葉に、お父さんは深いため息をついた。
エルアンは私の手を優しく握ろうとしたが、お父さんの視線を見て少し躊躇い、優しい眼差しで丁寧に語りかけた。
「もし私が邸宅に滞在するとしても、家族と楽しい時間を過ごしてください。邪魔はしませんから、私のことは気にしないで。」
いつも私の前では従順な羊のようだった彼は、穏やかに話しながらも、まるで褒めてほしいかのように微笑んだ。
私が何も言い返す間もなく、お父さんが叫んだ。
「そんな風に笑うな! リチェの目が曇るだろう! 以前シオニーが私を見たあの顔を思い出すじゃないか!」
「あ……目が曇ってしまってごめんなさい。見るのも嫌なんですね。」
私の冷静な返答に、お父さんとエルアンが同時に言った。
「違う、娘よ。あいつが笑ったのが悪いんだ。」
「そうだ、リチェ。私が悪かったよ。お父様が嫌うなら、今後は顔にも気をつけるよ。」
一度決意すると振り返らないエルアンが、お父さんの前で断固とした態度を見せている。
その姿を見るのも少し気恥ずかしく、私はできれば今後、二人の間にいないほうが良いだろうと思った。
その時だった。
「当主様! 皇宮から人が来ました!」
突然、応接室の扉が勢いよく開き、使用人が一人飛び込んできた。
お父さんは微笑みながら立ち上がった。
「もうハエルドン皇子の尋問が始まったのか? 私を証人として呼びに来たのだろう?」
しかし、皇室近衛隊の制服を着た威圧的な表情の男が、正式な手続きを踏むことなく、応接室へずかずかと入ってきた。
使用人はおろおろしてどうすることもできなかった。
侵入にも似た無礼な態度に、お父さんが怒りを抑えつつ立ち上がった。
「皇室近衛隊所属、ベルロン・カイダーです。リチェ・エステルがここにいると聞きましたが、事実ですか?」
エルアンが私の前に立ってかばおうとしたが、ベルロンの目はすでに応接室で唯一の若い女性である私に向けられていた。
「イセラ皇太妃殿下に不適切な薬を処方した罪で、即時逮捕します。」
「何ですって?」
お父さんがベルロンの殺気に応じるかのように、前へ一歩踏み出した。
「今なんと言った? 逮捕だと?」
祖父も杖をつきながら立ち上がり、大声を上げた。
「なんて無礼者だ! 我がリチェを絶対に渡すことはできん!」
叔母はすでに剣を抜いており、私を守るように立っていたエルアンでさえ、「ついに独立戦争……」と呟きながら手を剣の方へ動かした。
私は急いで彼の腕を掴んで前へ出る。
皇室近衛隊の者たちは、ただ命令に従っているだけで、特に非があるわけではなかった。
誰かの指示で動いているだけで処刑されたことを知っている私は、彼らがエルアンの手にかかって命を落とす未来を見たくなかった。
私は本心からその状況を望んでいなかった。だから堂々と答えた。
「リチェ・エステルではなく、リチェ・シオニー・フェレルマンです。」
もしこれが平民だったら、即座に逮捕され、皇室近衛隊の手によって何の手続きもなく処刑されていたかもしれない。
しかし、貴族の女性ともなれば話が変わった。
ベルロンは困惑の色を隠せず、書類を取り出して読み上げた。
「しかし、ええと……爵位上はセルイヤーズ領地の平民だと……。」
「どうせその爵位を変更するために、お父さんが皇宮に行こうとしていたところなんですよ。」
冷静に言い返したが、実際は内心かなり動揺していた。
公式な処方ではなかっただけに、状況は不利だ。
国際ブースでの軽い診断で、正式な証拠もなかった。
証拠を捏造しようと思えば、いくらでも作れただろう。
これは私に対する完璧な悪意だ。
「一緒に行けばいいですね。でも、私が皇太妃殿下に薬を処方したという証拠はあるのですか?」
「皇室の全ての人々が服用する薬は、記録するのが原則です。皇室医療研究所が処方したものも含めてです。」
ひとまず時間を稼いで状況を見守ろうと考えた私は、気丈に最善の態度で堂々と話した。
「とにかく私が爵位を得た以上、正式な手続きを踏んでください。」
平民として長く生きてきたが、貴族のように振る舞う。
それは難しいことではなかった。
優雅な手つきで服のシワを整える私を見て、ベルロンはどうすればよいか分からずおろおろし始めた。
「しかし……うーん……皇室の安危に関わる事件で……。」
以前、聖殿の集会に出席した時、イザベル様があらゆる教師を招いて貴族たちに礼儀や話し方を教えたことが功を奏していた。
「私も行く。」
依然としてベルロンが困惑していると、エルアンが牙を剥きながら言った。
「まだ爵位がセルイヤーズ領の平民なら、私も関係者だろう。」
正直なところ、関係があるわけではなかったが、私についてこようとする姿はピンからキリまで予想通りだった。
「そしてフェレルマン領主は、私のお腹の中の婚約者でもあるのです。」
お父さんの目は怒りに燃えたが、ベルロンの口を塞ぐには十分だった。
いくら皇室近衛隊とはいえ、子爵家の女性を連行するだけでも気まずいのに、さらに大貴族である公爵家の婚約者を連れて行くことはできなかったからだ。
「どれ、皆で一緒に行かせてもらおう。私の婚約者を一人で行かせるわけにはいかない。」
エルアンまで同行しなければならないという事実を再確認したベルロンの顔には、疲れがにじみ始めた。
「私も、私も行くぞ! 我がリチェを守るために!」
「お父さんは家主でしょう? 今、襲撃されるかもしれないのに家を守ってください。お父さんこそ必要ですよ。もし邸宅を離れたら、ホアキン団長の騎士団は誰が守るんですか?」
祖父が杖を振り回しながら何か言いかけると、叔母がすぐに止めて後ろに下がった。
「代わりに私が行きます。」
叔母は剣を鞘に収めずにベルロンをじっと睨みつけた。
ベルロンは怯えた表情で力なく尋ねた。
「え? セイリン様はなぜ……。」
「リチェの後見人です。私が部屋を共にしながら、24時間付き添いますよ。」
ベルロンはため息をつき、エルアンまで少し不機嫌そうな顔を浮かべていた。