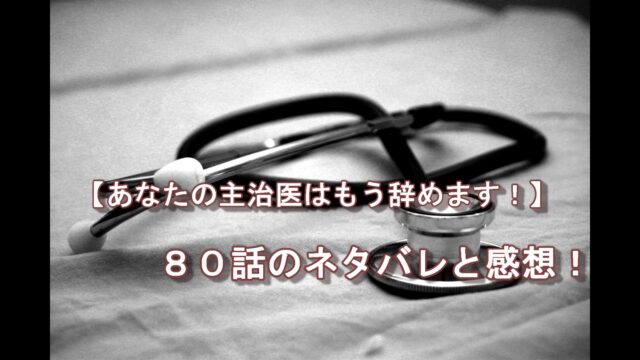こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

141話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 新しい人生を生きる最初の日
父はその日以降、忙しくなった。
新たに国立医療研究チームを構成するための仕事が次々と押し寄せたからだ。
そして、私に会いたいと言って、父は子爵邸から上がってきた。
子爵邸は公爵領とは違い、規模が小さく、数か月ほどなら無人のままでも問題ないと言われていた。
ホアキン団長のおかげで、ペレルマン子爵邸は反乱軍が押し寄せたときも、なんとか無事に乗り切ることができた。
「そんな、リチェ。」
首都の新しい子爵邸で、さらに歳を重ねた祖父は、ペレルマン子爵邸にいるときよりも、さらに健康になった。
「ひとつだけ譲ってくれないか?」
「ダメです。」
頭を使うのは知性だと言う叔母が山へ散歩に出かける午後の時間、私は祖父といつもチェスを指していた。
「シオニーには一回ずつ譲ったのに。チェスの実力はシオニーにそっくりなのに、どうして性格は似ていないんだ?」
「性格は父に似ていますから。」
「ああ。」
甘いチェリーケーキを食べながら祖父とチェスをすると、いつも私が勝ってしまうので、正直あまり面白くはない。
でも、ささやかな幸せが広がっていった。
父は毎晩帰宅すると、医療研究チームについての話をしていた。
どうせ私が働く場所なのだからと、決意を固めることも忘れなかった。
チェスを終え、ふとカレンダーを見ると、今日は私が帰還した日。
心が痛くなるほど良い秋の日に、地下の監獄に閉じ込められ、ただひとり理不尽に死を待っていたあの日。
「おじいちゃん。」
私は微笑みながら言った。
「もし私が無実の罪で監獄に閉じ込められたら、どうしますか?」
「監獄に入れられるまで黙ってはいない。何があっても、その前に助け出す。」
祖父は、奇妙なことを聞くものだと言わんばかりに笑った。
私は「それでも監禁されて死刑宣告を受けたら、迎えに来てくれますよね?」と聞こうとして、やめた。
あまりにも明白な答えが返ってくるのが分かっていたからだ。
皇室近衛隊のベルロンが私を逮捕しようとしたとき、武器を持って私の前に立ちはだかった家族のことを思い出すと、本当に愚問だった。
チェス盤を片付けながら窓の外を見ると、叔母が黄色い帽子を持って嬉しそうに歩いてくるのが見えた。
叔母があんな花の飾りがついた可愛い帽子をかぶるはずがないので、明らかに私へのプレゼントだろう。
叔母は時々こんなふうに都を歩き回って、思いもよらないプレゼントを買ってきては、夕食の時間にそっと渡してくるのだ。
今日は私にとって平凡な一日だったが、それゆえに心が高鳴る日だった。
明日からは、本当の意味でただ一度きりの人生を生きることになるのだから。
「リチェ、どこに行くんだ?」
「公爵様のところへ行きます。」
「一時間後に行くって言ってなかったか?もう一局やってもいいんじゃないか。」
「ただ、なんとなくです。また夕食を食べてからもう一局やりましょう。」
ただ急に会いたくなったとは言わず、私は衝動的にエルアンが横たわっている部屋へ向かった。
・
・
・
エルアンはまるで絵のように横たわっていた。
「公爵様。」
私は静かに彼の手を握り、いつものように魔力の流れを確認しながら、じっと凍りついたように立っていた。
「実は、今日は私にとって本当に大切な日なんです。すべてが変わり、新しい人生を生きる最初の日なんですよ。」
父と祖父、叔母と一緒に過ごす人生。
そして、愛する私の恋人がいることで、もう私は一人ではない人生。
「だから、早く起きてください。今日が終わる前に、どうしても伝えたい気持ちがあるんです。」
『私が一人で愛してもかまわない。結局、与えることだけでも十分に幸せだから。』
『一方的に愛しているわけじゃないのに。』
エルアンをじっと見つめていると、かつて気にもしなかったことが一つ、また一つと思い出された。
今まで一度も「愛している」と口にしたことがなかったこと。
そして、今まで彼のためにしてあげたことといえば、せいぜい500ゴールドもするシャツを贈ったことくらいだ。
裁判の前日、彼とディエルが交わした会話が何度も頭をよぎり、私はひどく後悔した。
「つらくないですか?愛の確信もない、手が届きそうで届かない相手のために、絶えず欲望を抑え、懸命にすがり続けなければならないことが。」
ディエルの目にも、私は愛の確信を持てない曖昧な存在に映っていたのだろう。
ただ、家族を見つけた後、もっと大切なことに気を取られていただけなのに。
私は、言葉にすることすら怠っていた。
少し近づくだけで、エルアンがすべてを満たしてくれると信じていたからだ。
「このままだと、どれだけそばにいても孤独を感じると思います。愛というものは、当然のように見返りを求める感情じゃないですか。」
エルアンは、その言葉をはっきりと否定しなかった。
「ごめんなさい。あなたに確信を持たせられなくて、それで孤独を感じさせてしまって。私があまりにも遅かった。実は、あなたに応える気持ちはずっと私の中にあったのに。でも、私はこういう面で本当に未熟でした。言葉にしない愛は伝わらないことに、気づいていませんでした。」
私は深く息を吐きながら、彼の髪を撫でた。
「家族と楽しい時間をたくさん過ごしたかったけど、エルアン様とも、これから素敵な時間をたくさん過ごすつもりです。だから、起きてください。」
もう一度、私は慎重に魔力を注ぎ込んだ。
これは毎日行っている治療の一つ。
いつもよりも切実に、長い時間彼の手を握りしめ、魔力を送り込んだあと、その大きな手にそっと唇を寄せた。
すると、唇の先から感じられるかすかな魔力の流れに驚き、私は思わず跳ねるように立ち上がった。
「…あ。」
そして、背後を振り返り、ディエルに頼んで持ってきてもらった小さな箱を慎重に開けた。
やはり彼を長く待たせることはないという考えに、涙が込み上げてきた。
今日はどうしても目を覚ましてほしいと思っていたのに、まるで私の言葉を聞いていたかのように、彼はゆっくりと目を開けた。
彼のそばに座り、鼓動が高鳴るのを抑えながら、再び手を握ったまま待っていると、予想していた通り、彼がゆっくりと目を開いた。
「……リチェ?」
彼が最初に口にした言葉は、私の名前。
何度確認しても、彼の全身の状態は正常だった。
彼は意識を失っていたときの記憶が曖昧なまま、ぼんやりとした瞳で私を見つめていた。
視線が絡み合い、一瞬、感情が揺れ動いた。
「約束したじゃないですか。」
私は涙を浮かべながらも、そっと笑みを浮かべ、彼の黒い瞳を見つめる。
彼が目を開けたときに伝えようと、何度も心の中で準備していた言葉だった。
「必ず治療すると。私は嘘をついたことがありません。」
幼い頃から、私はこういう言葉をよく口にしていた。
「……そうだな。君の言うことは、いつも正しい。」
彼の返事は、昔からいつも同じ。
エルアンはまるで少しの間眠っていたかのように、爽やかに笑った。
私たちは時間が止まったかのように、しばらくの間、手に伝わる互いの体温だけを感じていた。