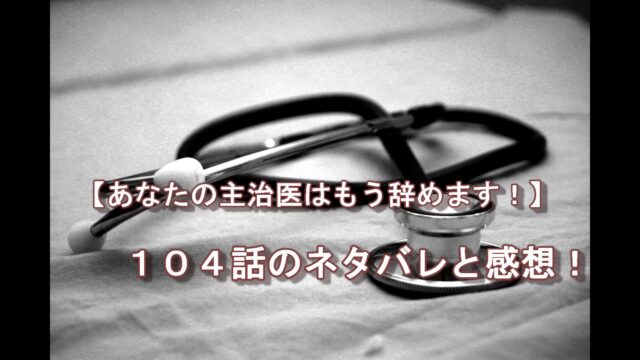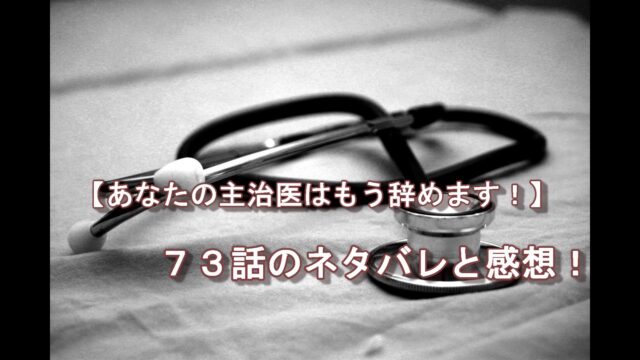こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

161話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- ユリアの宴会
こんにちは、はじめまして。
まずは自己紹介をしますね。私はユリア・イレン・セレイオスといいます。
薄い茶色の髪は父に似て、緑色の瞳は母に似ました。
お兄ちゃんとそっくりです。
嫌いなものはほうれん草と牛乳で、好きなものはディエルとブドウです。
少しずつ人生が大変になり始める年齢、六歳になります。
「お兄ちゃん、遊ぼう。」
「さっき遊んだばかりじゃないか、ユリア。」
最近、とても退屈なんです。
一つ年上の兄、セドリアンが文字を覚えてから、だんだん私と遊んでくれなくなったんですよ。
お兄ちゃんは毎日のようにただ一冊の本を読むことに夢中なんです。
「僕、これを全部読まなきゃいけないんだ。」
「それ、何?」
「『薬物学概論』。」
「どうしてそんなつまらない本を読むの?ねえ?」
絵本なら一緒に楽しく見られるけど、字ばかりぎっしりの『薬物学概論』なんて、一緒に遊ぶ余裕がないじゃないですか。
「その通りだ。」
お兄ちゃんは本から目を離さずに答えました。
「私が天才なのはね、ママに似たからだよ。」
それは耳にタコができるほど聞かされた言葉でした。
お兄ちゃんはママとおじいちゃんに似て天才なんだそうです。
まあ、私たちのママ、リチェ・シオニー・セレイオスは本当に天才なんです。
ここでちょっとだけママ自慢をしてもいいですか?
ママは先月、王宮で模範表彰を受けました。
詳しくは分からないけど、何かの伝染病予防で大きな功績を立てたそうです。
不思議なことに、ママは「表彰状にはあまりいい思い出がないけど……今回ぐらいは受けてもいいか」と一人ごちていました。
でもやっぱり、とても名誉なことだったそうです。
普段はあまり来客を迎えないセレイオス領地で、大規模な宴を開くことになったくらいです。
全ての帝国に向けて「リチェ・シオニー・セレイオス侯爵夫人」の名が広がったんですよ。
〈実模範表彰記念宴会〉が盛大に開かれるというのは、噂になるくらいでした。
その宴会が明日なんです。
人がたくさん来たら楽しいはずなのに、実感があまり湧きません。
でもディエルが「宴会ではクッキーの種類がたくさん並ぶんだ」って言っていたので、ちょっと楽しみにしています。
お母さんは歯の健康とか栄養のバランスとか言って、私にあまりクッキーをくれませんから。
「お兄ちゃん、退屈すぎてお腹が痛い。」
「退屈で腹痛が起こることはない。」
私がぐずっても、お兄ちゃんは優しいけれど冷静に切り捨ててしまいます。
「お腹が痛いなら、他の理由があるはずだ。確かな症状は何だ?」
「そ、それはただ痛いだけで……」
「脈の乱れを見る限り嘘みたいだな。ただ痛いだけなんてあるか。詳しく言ってみろ。熱はないが。」
私は結局、兄の部屋を飛び出してしまいました。
こんなことになるなら、兄に文字を教えたりしなければよかったと本気で思いました。
以前は一日に二十回もお医者さんごっこをしなければならず少し疲れてはいたけれど、今よりはずっとマシでした。
兄の部屋を出たあと、少し悩んだ私は足を別の場所へ向けました。
――ふん、セドリアン。あなただけが遊び相手じゃないんだから。
「おや?ユリアお嬢様。」
私がウサギのぬいぐるみを抱えて姿を現すと、研究室にいたディエルが明るく笑いながら私を抱き上げました。
お兄ちゃんも私も幼いころから乳母よりもずっと頼りにしていた人が、まさにディエルだったのです。
「またセドリアン様は遊んでくださらなかったんですか?」
「うん、本を読んでた。」
「まあ、セドリアン様は最近私とも遊んでくださらないんです。」
「ディエル、私も文字を習える?」
私はディエルの膝に座って、甘えるように揺さぶりました。
「そしたらセドリアンみたいに『薬草学概論』なんて読んで楽しめるの?」
「うーん……」
ディエルは少し考えるような表情を浮かべてから答えました。
「本来なら曖昧に答えることもできるけれど、あなたは特別だから正直にお話ししますね。」
「私が特別って、何が特別なの?」
「これは多くの人が忘れている事実ですが、実はお嬢様は……」
ディエルは誰もいない周囲を一度見回してから、重大な事実を語るかのように声を落としました。
私もドキドキしながら、抱えていたウサギのぬいぐるみをぎゅっと抱きしめました。
「……私の友人の娘さんなのです。」
なんということ!
私は驚いて目をぱちくりさせながら、ディエルをじっと見つめました。
「つまり、私はリチェ様のお友達だったということですか?」
「そう、それも確かに認められている友達だ。」
「わあ……」
「今でもリチェ様は私をとても信頼してくださいます。大事なことはいつも私に任せてくださるのです。」
その時のディエルはとても偉大に見えました。
私は感動して胸がいっぱいになりました。
「でもここにいられるなんて、本当にすごいわ。お父様やお母様にとって大事な人を二人も救ったなんて……」
「私自身もすごいと思います。」
ディエルは誇らしげに言いました。
「ですが、その分私はお二人から多くの愛をいただきました。いろんな意味で誠実な友人です。多少は物質的な見返りもあったとはいえ。」
「ねえ、ディエル。」
私はくすくす笑いながら尋ねました。
「ディエルは恋をしないの?どうして結婚しないの?もう年なんだから。」
「お嬢様の基準では多いかもしれませんが、それほど多い年ではありませんよ。」
ディエルは真面目に答えました。
「それに、私は恋をしています。前から少し好意を持っていたのですが、遅れてようやく本気の想いに気づかせてくれた相手がいるんです。」
「えっ、本当?誰なの?」
「お金です。もともと好きでしたが、増えるにつれてもっと好きになりました。」
「……。」
「私に真実の愛を気づかせてくださったセレイアス公爵様に感謝するばかりです。」
私は理解できないという目でディエルを見つめました。
お金遊びもできず、話をすることもできないのに、なぜお金がいいのでしょう?
しかも不格好な人形たちよりも見た目が悪いのです。
でも母はいつも「多様性を尊重しなければならない」と教えていたので、特に変だとは思いませんでした。
「少し話が逸れてしまいましたが、とにかく本題に戻りましょう。」
「うん。」
「お嬢様は年齢に比べて非常に聡明ではありますが、特に医学的な書籍を好むようには見えません。」
「どうして?」
「セドリアン様は、いろいろと違いますから。セドリアン様が六歳のころには、まだ字も読めないのに、すでにあらゆる薬草の名前を暗記していました。」
それは本当のことです。
兄は、私が覚えている限りずっと、星の草の名前を一つ残らず暗唱していました。
もちろんそのたびに、皆が口を揃えて『セドリアンはリチェに似た天才だ!』と言っていました。
特に外祖父は、「ペレルマンの血が濃く流れている、まさに研究所長の三代目だ……」などと。
「でも、お嬢様は違うでしょう?」
私は否定できず、ため息をつきました。
私には草はただの草に見えて、とても覚えたいとは思えなかったからです。
「私は……やっぱり母様には似てないんだね。」
私はしょんぼりして口ごもってしまいました。
帝国の民であれば「伝染病から帝国を救ったリチェ・シオニー・セレイオス」という名を誰もが知っています。
そして私の知る限り、皆が母を愛しています。
祖母は毎日のように母のドレスや装飾品を注文するのに忙しく、外祖父は母の名前が出るだけで誇らしげな表情を隠せません。
その中でも一番の信奉者は父で、父は本当に……はぁ……。
とにかく、だからこそ兄とは違い、私が母に似なかったのはとても悲しいことでした。
「すべての人が医学の天才である必要はありませんよ、お嬢様。正直なところ、一世代に一人いれば十分です。」
ディエルは優しく私の頭を撫でながら言いました。
「それに、お嬢様のご家族はリチェ様だけではありませんよ。誰に似ていてもきっと素晴らしい方になります。本当ですよ。」
私は思わず瞬きをしながらディエルを見上げ、その膝から勢いよく飛び降りました。
ディエルの言う通りなら、私が似ている誰かが必ずいるはずですよね?
「わかった。」
私はぎゅっと拳を握りしめました。
「私に似ている他の家族を探してみるわ。そうしてお兄様に教えてあげるんだから!」
ディエルは微笑みながら、困ったようにため息をつきました。
こうして私は「お兄ちゃんはお母様に似ているけど、私は誰に似ているの!?」と叫びたくなる時に、その「誰か」を探しに行くことにしたのです。
再び廊下に出て、私は一階上にある一番大きな部屋へ向かいました。
そう、そこは祖母イザベルの部屋です。
「ユリア!」
ノックをして入ると、カタログを見ていた祖母がぱっと立ち上がり、私をぎゅっと抱きしめてくれました。
祖母は背がすらりと高く、目つきも鋭いので、多くの人が一目見ただけで怖いと口にするほどでした。
「ユリア、一緒にケーキを食べましょうか?ね?」
でも、私は一度も祖母を怖いと思ったことはありませんでした。
いつも美味しいものをたくさんくれて、やさしく抱きしめてくれたからです。
「ちょうど呼ぼうと思っていたんだよ。」
おばあさまは私をぎゅっと抱きしめながら囁きました。
「どうしてかっていうと…… いくら考えてみても……」
急に胸騒ぎのような予感が押し寄せてきました。
「君には大きなリボンは似合わないような気がするんだ。」
まさか……。
私は不安な目でテーブルの上を見つめました。
おばあさまが見ていたカタログは、子ども用ドレスに関するものでした。
「えっ、おばあさま?」
「もちろん明日の集まりだから新しく作ることはできないけれど……飾りだけでも組み直してみようかね。」
明日の宴会で着るドレスは、祖母が一か月も前に直接選んでくださったものでした。
そのとき、私はほとんど一日中その服を着て過ごしたのです。
宴会が明日だなんて、うっかりしていて、こんなふうになるとは思ってもみませんでした。
「どうせならリチェと似た感じで着るのが可愛いだろう?リチェと何か揃えてみるのもいいんじゃないか。」
結局、私は祖母と一緒に長い時間をかけて装飾を選んだあとでやっと、ケーキをひとつもらうことができました。
温かく温められたミルクを飲みながら、私は祖母をじっと見つめていました。
おばあさまはカタログを見つめながら思案にふけっていました。
「どうにも……リチェの靴も気に入らないのよ。宝石をもっとつけるべきかしら。」
「おばあさま。」
私は思い切って尋ねました。
「おばあさまは今日、一日中ずっとカタログだけをご覧になっていたんですか?」
「いいえ。」
おばあさまはにっこり笑って答えました。
「朝はベッドでごろごろして、昼食を食べた後は少し昼寝をしたの。今ようやく始めたところよ。」
「じゃあ、私が行ったらこれから何をなさるんですか?」
「新しいカタログをいくつか見て、それから社交界に出る準備をするのさ。」
「……」
「私はこれまでずっと一生懸命生きてきた。これからはゴミみたいに生きるつもりだよ。残りの人生はただ消費だけしながら過ごすんだ。」
「えっ、おばあさま?」
「今夜だって『私は今日も生産的なことは何もしていない』とつぶやきながら、ぐっすり眠るつもりさ。」
生産とか消費とか、ただ漠然とした概念としてしか知らなかったけれど、一つだけ確かなことがあった。
私は、これまで必死に生きてきた祖母の姿を知らない。
だからこそ、いつもああしてぐったりしている姿しか見ていないのだ。
兄に向かって「お兄ちゃんは天才の母に似ているけど、私はぐるぐると無為に過ごすおばあさまに似ている」なんて絶対に言いたくなかった。
確かに人生は少しずつしんどくなってきてはいるけれど、私はまだ夢を抱えた六歳の子どもで、無駄に生きたくはなかったから。
私の不満げな顔に気づいたおばあさまは、眉をひそめて慌てたように言った。
「でもね、ユリア。私は昔は本当に情熱的に生きていたのよ。本当よ。お前のお父さんほどではないけれど、領地経営も上手くやっていたの。」
おばあさまは目を細め、昔を懐かしむように続けた。
「だから領地で問題を起こした悪党どもは、最後まで追い詰めて首を全部はね飛ばして…いやいや、こんなことをお前に話すなんて教育上よくないわね。」
お父さんが子どもの頃、領地経営を任されていた――と、幼い私は聞かされて育った。
花が咲いたような表情をしていたので、それはあの頃の話だったのでしょう。
けれど、私がその時代の話を聞きたくないとすぐに察した祖母は、さっと話題を変えました。
「そうだね。私がまだ若くて恋に夢中だった頃……お前のおじいさんに一目惚れしたんだよ。」
「え?」
「一日二十四時間でも足りないくらい、飽きることなく一緒にいたくて仕方なかった。きっとエルアンもそうだったんじゃないかしら。」
父の名前が出た途端、私はもうこれ以上聞く必要はないと思った。
そして、ますます「おばあちゃんに似ている」と言われたくなくなった。
いや、むしろ将来好きな男の子ができたときに、おばあさまやお父さまのようになってしまうのではないかと、少し心配になったのです。
だから結局、私はぶすっとした顔でおばあさまの部屋を出てきてしまいました。
次にどこへ行こうか考えながら、ぼんやりしていた私は、やがてトトトトと階段を降り始めました。
――「お前のお父さんほどではないが、領地経営もうまくやっていたのよ。」
母は誰もが認める天才だったけれど、父は誰もが認める優れた領主だったと聞いています。
兄が母に似た天才医師になり、私が父に似た立派な領主になれたなら、それで十分なのです。
それもまた悪くはないと思いました。
だから私は父に会いに行くことにしたのです。
使用人の何人かに尋ねると、父は宴会の準備のために宴会場に行っているとのことでした。
宴会場の下見でもしているのだろうか、と考えると気になって、私は足早に向かいました。