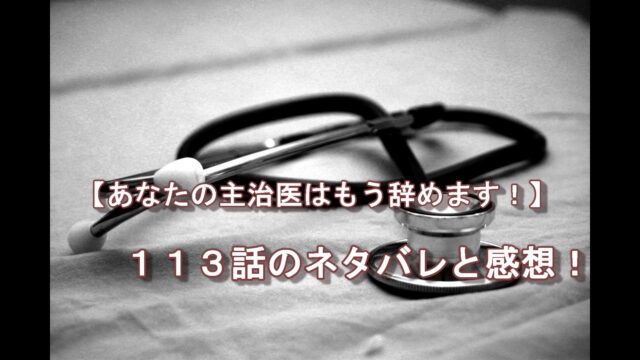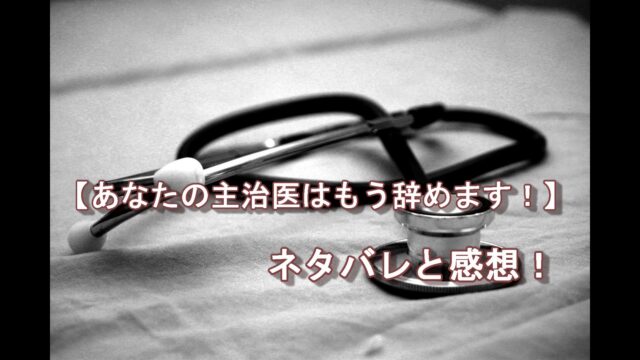こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

147話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- エピローグ⑤
「港から行きたいです。」
イシドール男爵領に到着し、宿舎に荷物を降ろした後、私はすぐに再び馬車に乗り込み、御者に港へ向かうよう指示した。
母の故郷であるラベリ島へ行くには、必ず立ち寄らなければならないのが、イシドール男爵領の港だった。
『もうこれ以上、イシドール男爵領に留まる理由はないけれど……。』
「天候があまり良くないようですが、大丈夫でしょうか?確認したところ、港は10月から閉鎖されているそうです。」
「はい、少し様子を見るだけです。」
「はあ……。まだ冬の初めだというのに、まるで真冬のような寒さですね。海もすっかり冬の装いです。」
「そんなに北の方でもないんだ。」
御者の中途半端な返答に答えたのは、道を尋ねていた旅人の一人だった。
「シブリ海を見てそう思ったんです。」
「シブリ海?ラベリ島を囲む海のことですか?」
私が興味を持った様子で問いかけると、彼はその言葉に乗った。
「ラベリ島の美しさを妬んだ神が、1年の半分を冷たい海風の中に閉じ込めたんです。ラベリ島の島民たちは、その美しさを容易に自慢できないようにしたという話ですよ。」
「とても嫉妬深い神ですね。」
「え?」
「まあ、以前に調べてはいたんですがね。ともかく、ありがとうございます。」
港へ行きたかったのは、ラベリ島を遠くからでも見てみたかったからだ。
祖父母はすでに亡くなり、領地を継いだ母の弟も数年前に跡継ぎを残さず亡くなったと聞いた。
今は母の叔父が領主となっているので、ラベリ島にはもはや私の直系の親族はいないも同然だ。
私を探しに奔走する前は、父は母の家族と良好な関係を築いていたと聞いていたが……。
それでも、一度は母の故郷を訪れてみたかった。
もしかして、突然訪ねても大丈夫だろうか?
そんな迷いがよぎった。
送ってくれた手紙には、冬の季節には暴風のせいで来るのが難しいから、後で必ず来るという返事があった。
領主様もシオニーの可愛がられていた幼い頃を覚えていて、だからこの全ての話に本当に嬉しくて、今では本当に私に会いたいという内容だった。
ラベリ島は大陸とは違い、植物が豊かで景色が美しいので、必ず訪れて楽しんでほしいという神託まであった。
しかし、御者の言葉は明白だった。
港に到着した途端、激しい風が吹くのは難しくない。
視界は曇っていたが、どうにかラベリ島の痕跡だけでも見たいと思い、傘をさしたまま外に出た私は、むしろバサッと傘を閉じてしまった。
「……来年の春に行けるとしても、せめて遠くからでも見たかったのに。」
「そう?」
エルアンは目を細め、灰色がかった空を見上げた。
彼は、私が望むことは何でも叶えてやりたいと思っているのだろう。
しかし、風を止めることはできなかった。
「おやおや、風がどんどん強くなってきましたね。これは!」
帽子が飛ばされ、馬たちが驚いて足をばたつかせた。
「あ……私が無理に港へ行こうなんて言ったせいで……。」
「何を言っているんだ。お前のせいじゃない。これは天気のせいさ。」
エルアンは簡単に手綱を操ると、左手の小道を指さして言った。
「あちらへ行けば、イシドール男爵領の近くまで出られる。出発しよう。」
外部の領地に幼い頃一度訪れたことがあると言いながら、エルアンがイシドール男爵領自体が招待した御者に行き方を教えてくれた。
「イシドール男爵領?なぜですか?」
元々一時的に立ち寄っただけで、再び首都に早く戻るつもりだったので、イシドール男爵地に行く考えは少しもしていなかった。
私が疑わしげに見ていると、エルアンは私の髪の毛の水分をぎゅっと絞りながら言った。
「こんなにバサッと濡らしておいて、どうやって長時間また馬車に乗るの?それに御者や馬たちも少し休ませなきゃ。」
その言葉は確かに事実だったので、私はひとまず魚を焼くのをやめた。
「空いていますよね?」
「管理状態はひどいものだけど、とりあえず一息ついていくくらいはできるだろう。」
エルアンの言葉通り、そう遠くない場所にイシドール男爵邸が見えてきた。
貴族の邸宅としてはごく普通の造りだったが、庭の芝が伸び放題になっているのを見る限り、長い間手入れされていないようだった。
幸い、馬小屋の状態はそれなりに良かったので、私は安堵のため息をついた。
エルアンとともに邸宅の中へ足を踏み入れると、割れたガラス瓶や落ちた額縁が散らばり、かつての装飾品らしきものは一つも見当たらなかった。
室内は薄暗く、エルアンが持っていたランプを灯して進んだが、二人で廃墟のような屋敷の中を歩くのは、なんとも言えない気持ちだった。
荒れ果てたイイシドール男爵邸は、まるで持ち主のいない時間に取り残されたように、寂しさを漂わせていた。
エルアンは手慣れた様子で、雑然としていても比較的清潔で高級感のある部屋へ私を案内した。
「お母さんが結婚する前に使っていた部屋だって。」
やはり、使用人たちが家を出る際に色々なものを持ち出したせいで、部屋は混乱していた。
しかし、持ち運びが難しい大きなベッドと数枚のシーツはそのまま残されていた。
クローゼットを開けてみると、ドレスは一着もなかったが、価値はなくても古びた数着の室内服と、いくつかのタオルやバス用品が奇跡的に残っていた。
「あちらが浴室だから、まずはシャワーを浴びて。暖かいお湯がちゃんと出るかは分からないけど……うん?」
突然、上の階から「ドンドン」と音が聞こえ、エルアンは一瞬言葉を止めた。
私は少し驚いて眉をひそめた。
「もしかして……誰かいるんじゃないでしょうね?」
「まさか。この古びた海沿いの邸宅に誰かがいるはずないだろう。気のせいだ。」
「……。」
とりあえず、ずぶ濡れになって少しずつ体温が奪われていたので、不安な気持ちを振り払うようにして、エルアンが案内してくれた浴室へ向かった。
エルアンの心配とは裏腹に、温かい湯が勢いよく流れてきた。
上水道は魔法使いたちが管理しており、どうやら契約がまだ残っていたようだ。
温かい湯でゆっくりと体を洗い、母がかつて着ていたような室内着を羽織ると、すでに別の浴室で体を洗っていたエルアンが部屋まできれいに掃除していた。
その室内着は見たことがないものだったが、明らかに小さく見えることから、他の部屋から持ってきたもののようだった。
「え?エルアン、掃除もできるの?普通、下僕がするものじゃない?」
「だから、僕がやってるんだよ。」
彼は淡々と答えた。
「リチェの下僕は僕だから。」
何か言おうとした瞬間、またもや上の階から正体不明の「ドンドン」という音が聞こえ、私は口を閉じた。
「……」
「……」
私とエルアンはしばらくお互いを見つめ合い、さらに音がしなくなったのを確認して、ようやく不安そうに笑みを浮かべた。
彼はため息をつきながら言った。
「風邪ひいたらどうするんだ、リチェ。一冬の寒さの中で髪も乾かさずに出てきて。」
私は適当にタオルで髪を拭いただけの状態だった。
「別に真冬じゃないよ。」
「でも、気温は冬みたいに寒い。」
「孤児院育ちだから、適当にしておくのが慣れてるんです。乾かすのも面倒で。」
「そんなこと言って、少しでも体調崩したら俺が心配で仕方ないんだぞ。」
エルアンはシーツをきれいに整えたベッドに座っていたが、ふと立ち上がり、私の髪に手を伸ばして優しく撫でるように拭いた。
「面倒なら、俺がやってあげる。」
この殺風景な邸宅に、女性用の香油なんてあるはずがない。
彼はポケットから、小さな瓶に入った香油を取り出し、私の髪に丁寧に塗り始めた。
「こんなものまで持ち歩いてるんですか?」
「君が俺の匂いが好きだって言った日につけてた香水さ。いつでも塗れるように、こうして香油の形で持ち歩いてる。」
彼の手つきがあまりに優しくて、妙に気が緩んでしまった。
髪に彼の香りが染み込み、耳の後ろを撫でる指先が、執拗に残り続けた。
「他に面倒くさいこと、ないのか?」
「え?」
「俺が全部やってあげる。君が面倒くさがること、全部。」
彼が私の耳元でそう囁いたので、息が詰まりそうになった。
「まさか…洗うのは面倒じゃないの?」
「なんだって?」
私はびくっとして後ろを振り返った。
彼の親指が私の首筋をなぞりながら、優しくうなじの髪を撫でた。
肩をすくめた瞬間、彼と目が合った。
彼はつい最近、イルビアから戻ってきたばかりで、以前のように私をからかうような笑みを浮かべていた。
少し開いたシャツの隙間から、鍛えられた彼の体が見えた。
「なんで、変なこと考えた?」
「……それって、深読みしろってことですよね。でも、そんな変なことは考えませんでしたよ。」
「からかうのは本気でやるよ。意地悪しない程度に。」
彼は滑らかな手のひらで、私の耳元をなぞり始めた。
「君は、ずっとずっと俺を待たせてたんだから……。」
彼の声はだんだん低くなり、ゆっくりとした調子になった。
熱を帯びた息が、私の喉元を優しくかすめる。
「俺、無理強いしないよ。……でも、すごくたくさん想像してた。」
「……え?」
「ここ、俺たち二人きりだろ?そうじゃない?」
「本当に!」
少し前まで一生懸命掃除していた姿が、彼の声にあっけなくもみ消された。
私は無表情のまま手を上げて、ため息をついた。
「胸を叩くと、君の手が痛くなるよ。ここを叩いて。」
しかし、エルアンが素早くほうきを持って行ってしまい、私は軽くでも叩くことができなかった。
「少しでも、絶対に痛い思いをしてはいけない、リチェ……。あんな経験は一度だけで十分なんだ。」
「あんな経験?」
「世界が崩れ落ちるような経験のことだよ。」
再び彼は優しく私をしっかりと抱きしめてくれた。
「正直、君が雨に濡れたとき、また風邪でも引くんじゃないかって、どれだけ心配したことか。」
「最近まで弱ってたのはエルアンのほうでしょ。」
今はとても元気で、風に吹かれても平気そうだけど、少し走っただけで数時間もぐったり横になっていたエルアンを思い出すと、やっぱり胸が痛んだ。
そのときの気持ちを思い返すと、もう二度とエルアンが病気になるのは見たくなかった。
「俺は後悔してないよ。君の家族を守ったし、どうせならデートの許可くらいもらってやる。結婚の許可を得るには、あと何回か転がらなきゃいけないだろうけど。」
「もう二度と”転がる”なんて言わないでくださいよ。本当にゾッとします。」
「うーん……俺のほうがゾッとしたけど。」
エルアンは伏し目がちに眉をひそめ、動きを止めた。
「君が僕の代わりに蛇に噛まれて倒れていたあの時。」
それはとても昔の話だった。
「その時、わかったんだ。君がすでに僕の世界になっていたってことを……。」
「とてもとても昔の話じゃないですか?」
「僕が持っている持病が、その時ほど嫌だったことはなかったよ……。君が目を覚ますまで、僕は正気ではなかったんだ。」
意識が戻ったとき、私に必死にしがみついていた幼いエルアンが浮かび、僕は軽く唇を震わせてしまった。
いつの間にか、私たちが過ごしてきた時間が、お互いで満ちているような気がした。
だから、私はまず先に優しく彼の首に腕を回し、近づこうとした。
カンッ!
天井から響く音に、私はまた驚いて目を丸くした。
これはネズミが出せるような音じゃない。
「……この部屋は、ウェデリックの部屋だ。」
彼は低い声でささやいた。
「俺は君が目の前にいれば、上の階で何かがタップダンスを踊っていようと気にしない。でも……君が集中できないなら話は別だ。」
二人の時間を邪魔されたことだけで、普段は優しい彼の瞳に殺気が宿り始めた。
「行ってくる。待ってろ。あれが獣だろうが人間だろうが――どんな幽霊だろうと、もうこれ以上音を立てられないようにして戻ってくるから。」
「行かないで、一緒に行きましょう!」
私は彼の手首を慌てて掴んだ。
「一人でいるのは怖いです。」
外では風雨が吹き荒れ、火の消えた暖炉だけがあるこのがらんとした屋敷で、一人でエルアンを待つことを考えると、ひどく怖くなった。
「じゃあ、そうしよう。」
エルアンはとても優しい笑顔を見せながら、私の手を握りしめ、歯を食いしばりながら上の階へと登り始めた。
ぎしぎしと軋む階段を一階上がると、静かに広がる北の廊下から、かすかな物音が聞こえた。
部屋の隙間から漏れる灯りが見えた。
「そこがウェデリックの部屋ですか?」
「うん。」
誰もいないはずのこの屋敷で、しかもセルイヤーズ公爵の監獄に幽閉されているはずの令息の部屋に灯りがともっているというのか?
エルアンが躊躇なく歩を進め、私を背後に庇いながら扉を勢いよく開けた。
「……あ……?」
エルアンの戸惑いを含んだ声に、私はかえって驚かされた。
「どうしました?誰がいるんですか?」
「名前は……たしか……そいつは……」
彼の大きな背中に隠れて、部屋の中はまだ見えなかった。
私は彼の脇にしっかりと身を寄せた。
床に倒れていた人形の形を確認したと同時に、エルアンは茫然と動きを止めた。
「盗んで食べる家ですか?」