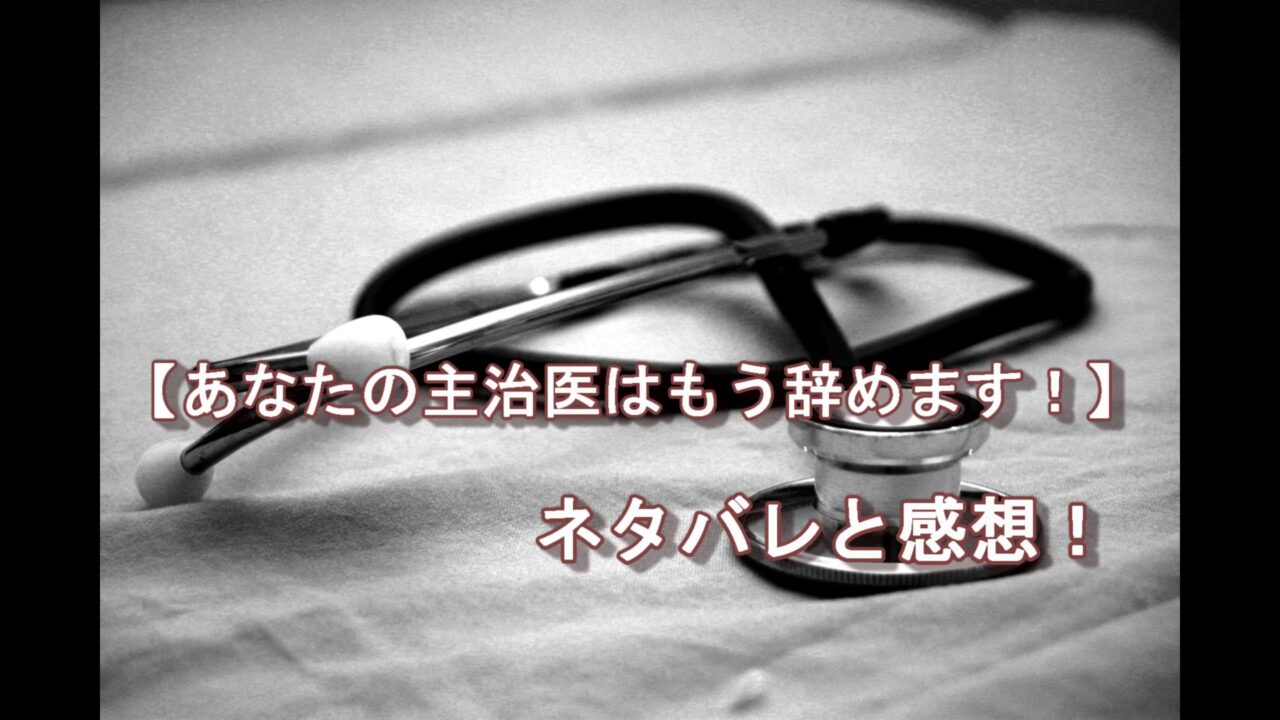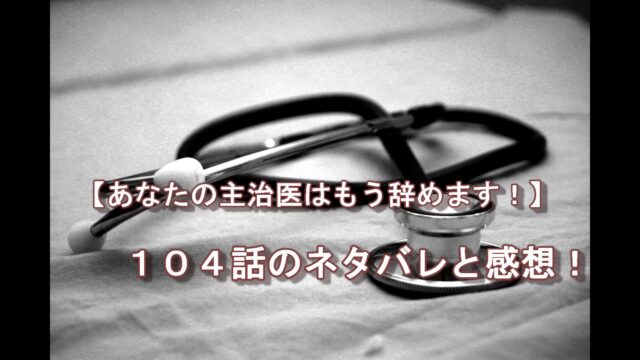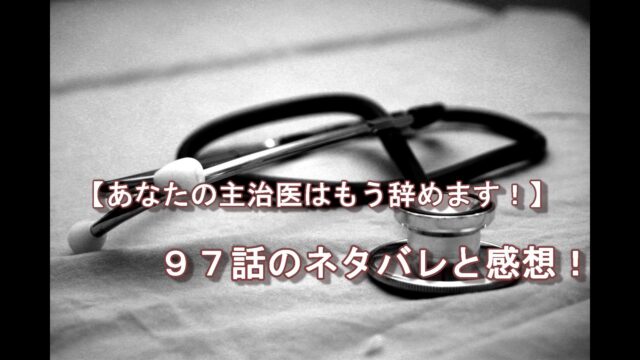こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

152話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- ハッピーエンド
「蛍の夜」の行事は、アルカには非常に退屈なものだった。
もちろん、夜になれば一斉に飛び交うというメイリス公国の蛍を眺めることにも、まったく期待は持てなかった。
「シオニー、次回メイリス公国に来なさい。”蛍の夜” に招待するよ。一度その光景を見てみるといい。半月の光がどれだけ美しいか知らないんだ。」
「それ、見たら蛾みたいじゃないですか?」
「うーん……、まあ、それでも……。若い男女のカップルがその光景を見れば、恋が成就するんだって。」
「メイリス公国の出生率を見ると、根拠のない伝説みたいですね。帰国されたら、国民の科学的な思考と教養のために、そのような噂話を控えるように心がけてください。」
その時も作り話だと思って気分が悪かったのに、その息子シリオンの話を聞くと、さらに気分が悪くなった。
「一緒に半月の光を見に行こう」という話がロマンチックな意味を持つなんて…。
息子シリオンがリチェに執着するたびに思い出すあいつが憎らしくてたまらなかった。
名前も同じだし、顔つきまでそっくりだなんて。
あいつを見ると父の面影が浮かび、リチェを見ればシオニーが重なって見える。
だったら、いつも表情管理ができず、後ろでじっとしているエルアンは……。
「……馬鹿だな。こんなこと考えるのはやめよう。」
アルカは苛立たしげに腕を組んだ。
少なくともシオニーは執拗に絡んできたあいつをあっさり突き放していたのに、リチェはジェンシー公妃との関係を言い訳にして、微妙に距離を保とうとしている。
「さっさと吹き飛ばされるかと思ったら、リチェの前では随分と大人しいんだな。」
彼は再びエルアンをちらりと見て、深く息を吐いた。
彼らは公式な挨拶をすべて終え、今や「半月の光」を見に、わいわいと賑やかな人々の中で待機していた。
外交的な理由でリチェの隣の席を占めているのは、シリオンであり、エルアンはその後ろに立っている様子だ。
男性たちに人気のあったシオニーの後ろに立っていた、自身の若い頃を思い出し、アルガは再び顔をしかめた。
『あの頃、私は小さな地位しか持っていなかったし、シオニーとはただ目を合わせるだけの関係だった。それなのに、あの男は公爵の地位があり、リチェと恋人関係だというのに、なぜあんなことをしているんだ?』
彼は内心で三人を睨みつけながら、考えをぐっと抑えていた。
「楽しみにしていてください。一度に舞い降りてくる半月の光が、どれほど美しいか。」
「伯爵がそうおっしゃるなら、期待していますよ。」
「綺麗だからって虫が寄ってくるわけじゃないぞ!」
不満げなアルカは、せっせとリチェのもとへ向かった。
「リチェ、お前の顔になんか付いてるぞ。鏡で確認してこい。」
「そうですか?」
シリオンが微笑みながら割り込んできた。
「どこです?私には美しさしか見えませんが……。」
「……すぐ見てきます。」
その言葉には到底肯定できないのか、リチェは身震いしながら、小刻みに歩いて、全ての荷物を持ってディエルを探して姿を消した。
アルガは腕を組んだまま、じっと立ち位置を守っていたが、シリオンがエルアンに話しかける声が聞こえた。
「公爵様、これはプレゼントです。」
「え?」
「半月の光を捕まえて持ち帰れるガラス瓶です。あの森の中に行けば、簡単に捕まえられるでしょう。」
「私は蛍を捕まえることに興味はありません。」
「そうですか。」
シリオンはエルアンの手に無理やりガラス瓶を握らせ、ほのかに笑った。
「分からないですよ。いつか誰かが、半月の光を見たくなるかもしれませんし。患者の中には精神的なケアが必要な人もいるかもしれませんよね?リチェ様が患者を支えるなら、彼らの心のケアも考えるべきではないでしょうか?」
「……。」
エルアンは黙ったまま、ガラス瓶を握りしめた。
アルガは思わず心の中で叫んだ。
『行くな!あいつはリチェと二人きりで蛍を見て、甘い言葉で騙すつもりだ!貴族どもにとって、蛍は恋愛の道具なんだぞ!』
誰の父親にしても、その息子も同じ考えなのか。
シオニーの誕生日に自分を遠ざけたのと同じ手口だ。
シオニーは以前、アルガの元へ先に駆け寄ってきたことがあった。
しかし、今の状況では、リチェが動揺するなら、エルアンの方へ向かうのではないかと思えた。
アルガはエルアンの方を見つめた。
彼の内的葛藤を見守りながら、心が爆発しそうだった。
蛍が一斉に飛び立つのは壮観かもしれないが、特に大きな期待はしていなかった。
それでもここまで来たのに見ずに帰るのも変なので、私は庭だけを一巡りしてすぐに戻ろうと考えていた。
ディエルに会って様子を見て、何も聞いてこないことを確認した後、私はそのままディエルを連れて元の場所に戻る途中だった。
「確かにお父さんは、エルアンよりもシリオンを嫌っているみたい。君、それをわざと利用してるの?でもさ……なぜ初対面の人をこんなにも嫌うんだろう? 確かに父は人を嫌いがちだけど、ここまでではなかったのに。」
「……まあ、何か事情があるんじゃないかな……。」
ディエルと一緒に歩いていた私は、目の前で起こった光景に驚いた。
エルアンがどこかへ行こうとすると、父が彼の手首をがっしりと掴んだのだ。
私とディエルは、その場に釘付けになったように立ち止まった。
父は苛立ったように声を荒げた。
「お前、馬鹿か?馬鹿なのか?」
エルアンに向かって「お前」と言い、さらにタメ口まで使うのを見て、冷静さを失っていることが明らかだ。
このような状況はとても頻繁に起こっていたので、エルアンや私、ディエルさえも特に驚きはしなかった。
しかし、その後に続いた言葉は、私たちを十分に驚かせるものだった。
「なぜ私がリチェの婚約者だ。お前はリチェに執着する権利はない。そうはっきり言えないのか?」
その言葉にエルアンも驚いたのか、口を少し開けた。
「一体何が足りなくて、あんな奴の目に映るんだ?私たちは結婚を前提とした恋人同士だ。お前が入り込む余地はない。なぜはっきり言えないんだ!私に向かって堂々と挑発していた時の半分でも、なぜ言えないんだ!」
「あ、お父さん?」
私はあ然として固まった。
父が神経質に叫び、しばらく震えている間、最初に冷静さを取り戻したのはエルアンだった。
「ありがとうございます、公爵閣下。今、私たちの関係を認めてくださったんですよね?」
「そうだ!認めた!認めたから、あいつがしつこくするのを止めさせろ!」
「お父さん!」
私が怒って駆け寄ると、父は私を睨みつけ、鋭い声で言った。
「お前も同じだ。はっきりと意思疎通している相手が目の前にいるのに、ほかの男がくだらないちょっかいを出すのを許すのか?シオニーですらそんな曖昧な態度は取らなかったぞ! 一体誰に似たんだ?」
私はその場で立ち止まり、一瞬目をつぶった。
「あ、お父さん……今エルアンをかばって私に怒ったんですか?」
「……あ?」
慎重に尋ねる私の質問に、お父さんはようやく我に返ったように目をぱちくりとさせた。
しかし、すでに放った言葉は取り消せない後だった。
エルアンは素早くお父さんの前に立ち、機転を利かせた。
「ついに私たちの関係を正式に認めてくださるんですね。本当に感謝いたします。ご配慮いただきありがとうございます。ですが、私はリチェのために準備された人材であり、今後の計画について改めてご説明させていただきます。」
エルアンはこの機会を逃さないとばかりに、呆然と立っているシリオンを押しのけ、お父さんの前に立って、まるで用意していたかのように言葉を繰り出した。
「現在、セルイヤーズ公爵領と首都を結ぶ道路が完成すれば、馬車で1時間以内に往復可能になります。リチェが結婚すれば、セルイヤーズ公爵邸から通勤するのも十分可能です。」
「そ、それは今……。」
「リチェが公爵閣下と共にしっかりと能力を発揮できるよう、私が公爵邸で一生懸命補助します。リチェの健康管理もしっかり続け、子供の世話も私がすべて担当します。」
父は一瞬息をのみ、荒い息を吐いた。
まるで父の口から今、私たちの結婚が既成事実であるかのように認められたかのようで、否定の言葉をすぐに出すことができない様子だった。
「では、私はこれで失礼します。改めて私たちの関係を認めてくださり、ありがとうございます。必ずうまくやります。」
「えっ、どこに行くんですか?」
私が驚いて尋ねると、彼はにこやかに笑いながらガラス瓶を持ち上げた。
「ホタルを捕まえに。」
「え?」
「ルシに見せてあげるんだ。君がずっと気にしてたじゃないか。ルシが少しでも気分が良くなればいいなって。ずっと気を使ってたけど、この子が良い方法を教えてくれたんだ。」
「あ……。」
「僕は君が少しでも望むことは何でも聞いてあげたいんだ。それが僕にとって一番大事なことなんだよ。」
メイルリス公国でも一年に一度しか見られない絶景だというのに、今、彼は私の気持ちだけを優先してくれている。
幼い患者のために自ら蛍を捕まえて戻ると言っていた。
自分の患者でもないのに、ただ単にその子の機嫌の良い姿を見たいという理由だけで。
「はぁ。」
父は髪をかき乱した。
「わかった、わかった。俺の負けだ。」
「……え?」
「あんな氷のような男を俺がどうして止められるんだ!ただ一つ言っておくが、すぐに結婚しろという意味じゃない。ただ認める、それだけだ。わかったな?」
父が「わかったな?」と問いかけると、青ざめたシリオンが焦点を合わせようとしていた
しかし、エルアンと私は興奮して夢中で肉を噛みしめた。
「はい、お父さん!」
「はい、ありがとうございます!」
そっと横目で見たディエルが、怪しい表情でゾッとした。
私はこのすべての出来事の原因をしっかりと調べなければならないと心に決め、父にしがみついた。
「記念日としよう。」
エルアンが囁くように私の耳に話しかけた。
「ついに許可をもらえた日だよ。これで僕はいつでも結婚できるように、早速準備を始めるつもりだ。そして……」
もっと遅くなる前に、ルシのためにホタルを捕まえなければいけないと言って、エルアンは急いで話を続けた。
「ディエルに内緒で給料を上げてやってくれ。セルイヤーズで十分働くことになるから。」
最後に残った唯一の関門もどうにか解決し、これで堂々と恋愛し、祝福を受けながら結婚するだけとなった。
明らかに反対することもできたはずなのに、ただ諦めたようにふてくされている父を見て、もしかしたら父もいつまでも反対できるわけではないと気づいていて、この機会を待っていたのかもしれないと思った。
まだ蛍が舞い上がることはなかったが、最高の夜だった。
シリオンを除いて、ディエルを含めたすべての人々にとって、これはハッピーエンドだった。