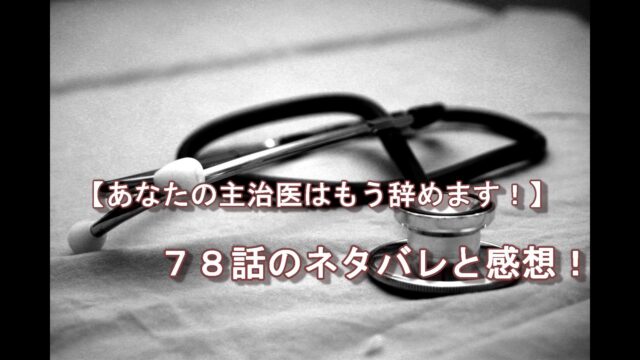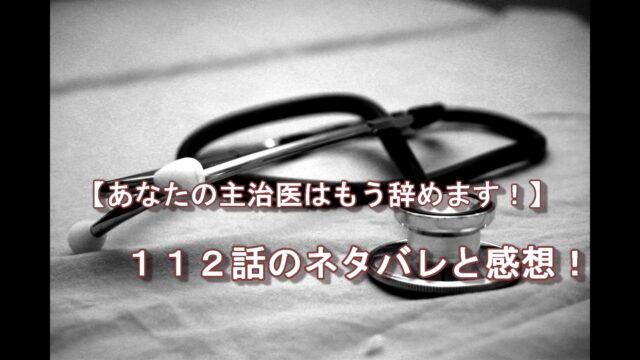こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

156話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 主治医が苦しければ②
エルアンは茫然自失の中で意識を失ったリチェを抱き上げた。
リチェが何度も予告し、行動指示まで明確にしていたが、いざその瞬間が来ると頭が真っ白になるのは避けられなかった。
「こんにちは、公爵様。」
エルアンが港に降り立つと同時に、待機していた医師がすぐに駆け寄ってきた。
「ご連絡をいただいております。公爵夫人がご不調とのことですね。」
実はエルアンは、ジケルに命じてすでに西からヘリコプターを飛ばしていた。
幸いなことに船には非常用のヘリコプターが1機あったためだった。
そのヘリコプターを送ったのは、イルビアの王宮だ。
公爵夫人病患。4月28日正午到着予定。
短いメッセージだったが、王宮でこのメモを受け取ったセルリアナはすぐに意図を理解した。
時間に合わせて王宮医を送れという意味だった。
したがって、彼らはイルビアの地に到着するや否や、イルビア王宮医に会うことができた。
リチェは「イルビアに到着したら貴族の主治医を呼ぶだろう」と予想していたが、それは違っていた。
エルアンは船の中からすでに王宮医を待機させていたのだ。
「これを見せてくれと言われていたんです。」
エルアンは、リチェが渡していたメモを王宮医に手渡した。
王宮医はメモを見て感嘆した。
「これは……本当に体系的にうまくまとめられていますね。」
彼は安心したようにエルアンを見て微笑んだ。
「症状に応じた魔力投与量まで、見た医師が気を悪くしない程度に配慮して添えられています。もしかして、公爵夫人は医師でいらっしゃいますか?」
「……とても素晴らしい医者だ。」
「そんなにご心配なさらないでください。カルカラスの花の葉は副作用ですが、南部では長い航海をするときに前もって摂取する薬草でもあります。船酔いするくらいなら、むしろ気を失っていた方が楽だという人もかなり多いんですよ。」
エルアンは不安な気持ちを押し殺しながら、静かに毛布を引き上げた。
そして新婚旅行中に元々宿泊予定だった木造の家に到着するとすぐに使用人に言った。
「S級のハチドリを10羽連れてきて。首都へ送るんだ。」
「10羽……ですか?それにS級のハチドリは本当に高価ですよ。基本的な訓練だけでも訓練費がすごくかかりますし……。」
S級のハチドリなら1羽使うだけでも費用がかなりのものだった。
イルビアの王族でさえ簡単には使えないほどだ。
「予算の制限はない。」
そして彼は、リチェから受け取ってすでに切り離していたメモをそのままアルガに送った。
リチェが「これくらいなら構わない」と許可していたからだ。
リチェが新婚旅行に出てしばらくして、アルガはフェレルマンの別荘地でビドルギ(伝書鳥)を10羽受け取った。
エルアンが送ったもので、内容を読んでみると、リチェが蕁麻疹を起こし、過剰な薬草摂取によって軽いショック症状を起こしたようだ。
10機には、それぞれリチェがこれまでに摂取した薬草の量が正確に記録されていた。
中にはS級のものもあり、急ぎのようだった。
「ふむ、リチェが整理しておいたのか。」
アルガはそのドローンのうち2機にメモを添えて送った。
<大したことではありません。すぐに正気を取り戻すはずです。>
<それでも万が一ということもあるので、観察日誌があれば送っていただきたい。>
実のところ、医者が見たわけではないので観察日誌があるとは思っていなかった。
けれども些細な軽い症状とはいえ、娘のことが心配だったので「万が一」を考えて送ったメモだった。
その後、エルアンの元に届いたビドルギ(伝書鳥)は一羽だった。
<観察日誌をすべてお送りすべきでしょうか?>
アルガはくすっと笑いながらつぶやいた。
「観察日誌を書いていたとは……昔のリチェが書いていたんだな。使っているのを見たことがあるのか……それとも、船の医師がそばにいたのか?」
その後……アルガは退勤途中に空を横切るドローンの群れを目にした。
「なんだ?ドローンたちがなんで急に全部飛んでいくんだ?」
その瞬間、不安な予感にとらわれた。
そして、そのドローンの群れがワラワラとペレルマン邸の窓に入っていくのを見て、口を開けたまま固まった。
「まさか……まさかこのバカな奴が……」
アルガは気が狂ったように自分の部屋へ駆け込んだ。
ビドルギ(伝書鳥)が運んできたメモは、一枚ずつ机、本棚、ベッド、椅子に貼り付けられていた。
「……これは一体……」
アルガはいくつかのメモを手に取り、呆然とした。
「就寝時間と起床時間、水を飲んだ量……それに排便の回数まで……なんでこんなのまで書いてあるんだ?」
アルガはそのメモを一つ一つ開いて見ながら、思わず笑ってしまった。
エルアンは医者ではなかったため、医学的な条件を反映していない「観察日誌」をそのまま一言一句書き綴って送っていたのだ。
「これほど書かれているなら……ちゃんと眠れてるのか……」
これはまるで、24時間ずっとリチェを観察していたかのようだった。
アルガは特に問題がないと分かっていながらも、エルアンのメモをすべて広げて、順番に一つずつ照らし合わせてみた。
「大丈夫だと分かっていても不安になるな。自分の子どもだからか……」
かつて彼に「お願いだからセルイヤーズの指導で残ってほしい」と懇願したイサベルの心情が、今になってようやく理解できた。
「まあ……」
彼はドローンの一機に「特に異常なし」というメモをくくりつけて送り出しながら、深く感情に浸っていた。
「本当にリチェを愛して大切にしているのは確かだね。すでに知ってはいたけど。」
そして、部屋中にぎっしり詰まっていたS級ビドルギ(伝書鳥)たちを見て叫んだ。
「行け、もう!みんな行け!」
エルアンは庭でビドルギを受け取り、「特に異常なし」と書かれたメモを読んで、ようやく安心して大きく息をついた。
すでに帝国まで王服(王室の使いの装い)を三度も着て運んでくれたS級ビドルギは、切なそうな目でエルアンを見つめた。
疲れてエルアンの部屋まで行けず、庭で泣き続けていたせいで、そこまで来たのだった。
リチェが倒れてからすでにしばらく経っていた。
彼はS級ドローンの足に金貨を一枚握らせ、庭でのんびりしていたS級ドローンは金貨を受け取ると、やる気が出たように必死に飛び立った。
「……まあ、よかった。」
エルアンは青ざめた顔で再びリチェがいる部屋へ向かった。
そして空のベッドを確認して驚きで目を見開いた。
「公爵様。」
その時、トレーを引いてきた一人の侍女が穏やかに言った。
「公爵夫人が起きられました。今、身支度中です。私に食事の準備を頼まれて、厨房に行って戻ってくるところです。」
「え、起きたって?」
「はい、公爵様がビドルギ(伝書鳥)を見つけて降りた瞬間に目を開けられました。」
エルアンが一時ビドルギを見て庭に出ている間に、リチェが目を覚ましたのだ。
その瞬間、ビドルギを下人に持ってこさせるべきだったと後悔した。
侍女の一人が彼の青ざめた表情を見て言った。
「公爵様がいらっしゃったら、奥様から伝えるようにと言われていた言葉があります。」
「何?」
エルアンの声はすでにかすれていた。
「とても正常なので、ご心配なさらないでください。それから……」
彼女はにっこり笑って言った。
「……洗っているときは入ってこないでっておっしゃいました。」
それでエルアンはすぐに浴室に入りたい気持ちを必死に抑えた。
そして静かにリチェのベッドの端に座って気持ちを落ち着けながら待った。
あまりに心配している様子を見せれば、リチェがまた困ると思って表情まで気をつけながら、というわけだ。
リチェは体を洗って出てきて、そんなエルアンの姿を見て、一人で思わず笑みをこぼした。
これまでずっと落ち着かなかったのに、ぐっと我慢して待っていたことが、愛おしかったのだ。
「エルアン、私がどうって言いましたか。大丈夫だって言ったじゃないですか。」
リチェはエルアンに抱きつきながら背中を軽く叩いた。
リチェより体格がずっと大きいエルアンだったが、彼はリチェを抱きしめたまましばらく何も言わなかった。
そして静かで穏やかな声でゆっくりとつぶやいた。
「僕は……ほんとに……少しだけ心配した……君が言ったとおりに……うまくやった……うぅ。」
エルアンはついに涙がぽろぽろとこぼれて言葉を続けられなかった。
リチェは彼の背中を撫でながら「もう大丈夫よ」と何度も優しく言った。
そして数日後、リチェはとても丁寧に書かれた観察日誌の存在を知ることになる。
「観察日誌……こんなものをどうして……書き方も習ってないのに……」
「君も書いてたじゃないか。もしかして少しでも役に立つかと思ってさ。万が一に備えて全部記録したの。何を記録して何を記録しなくていいのかわからなかったから。」
その観察日誌の内容が明らかになり、イルビアのすべてのS級伝書バトが過労であったことまでわかった。
その伝書バトたちは十分な対価をもらってかなり満足していたとも記されていた。
「ちょっと……あきれるよ。ただ捨てて。」
エルアンは観察日誌を見て少し気まずそうに顔をしかめたが、リチェはそれを抱えてバッグの奥深くにしっかりとしまった。
そして帰る際に、リチェはひどい船酔いに悩まされるイルビア人たちがあらかじめカルカラスの花の葉を食べて正気を失ったまま航海するのではないかと真剣に悩んだ。
しかし、すべて杞憂に過ぎなかった。
「うーん……エルアン、これ何ですか?」
「王国に要請したんだ。軍艦だよ。船はかなり大きいから、三半規管が弱い人でなければ船酔いしないらしい。」
「え……こんなもの、私たちが使ってもいいんですか?」
「十分な対価を払ったから心配しないで。」
こうしてリチェは人生で初めて軍艦に乗った。
そして一瞬、侯爵夫人ではなく主治医の立場に戻り、「この費用はエルアンの精神的安定のためなら十分に価値がある」と考え、何も言わなかった。
「エルアン。」
幸いにもリチェは軍艦の上では船酔いしなかった。
彼女はエルアンの髪を撫でながら、侯爵家の予算のためにも絶対にもう病気にならないでと心に誓った。
「でも、その“十分な対価”って何だったの? 軍艦を借りるのにとんでもない金額がかかったでしょう?」
「そうだね。」
「あっ。」
エルアンはふっと笑って言った。
「誰がいないか見えない?」
リチェはようやく、出発のときとは違って誰かがいないことに気づいた。
「ジ、ジケルを……お姫様のところに置いてきたんですか?」
「置いてきたんじゃなくて、強制的に休暇を取らせたんだ。嫌がってたけど、一日中うろうろしてるだけだったし。」
エルアンは寂しそうに笑って言った。
「もうジケルは手放してあげる時が来たと思う。実はもっと前に手放すべきだったのかもしれないけどね。」