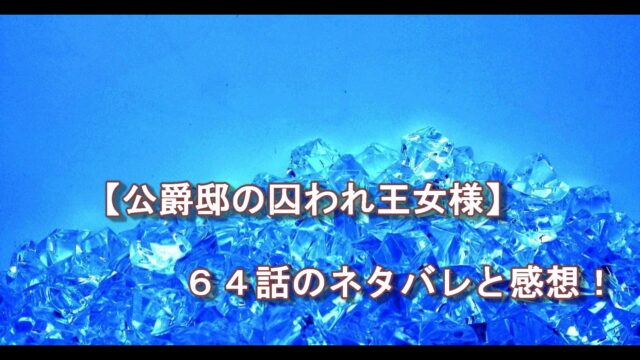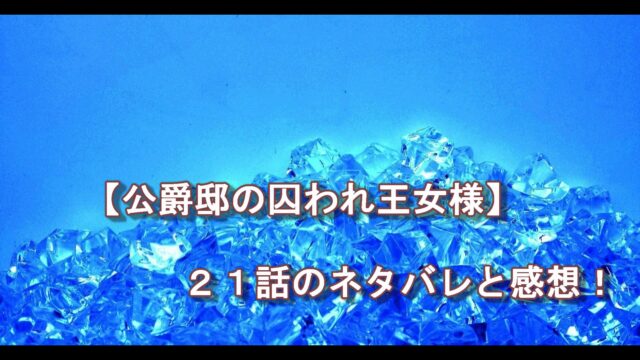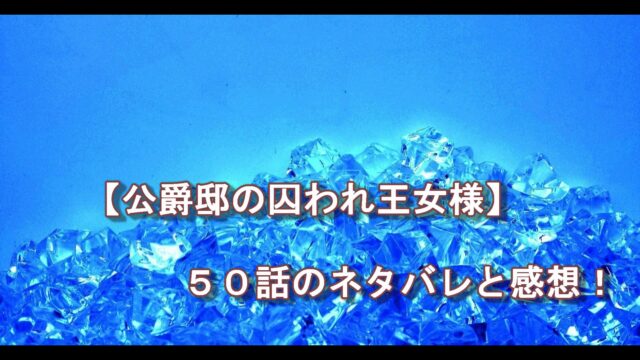こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

140話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 未来へ向かって
三人は、夜ごとに貴族たちの別邸や町の宿屋などに宿を取った。
どこへ行っても彼らの到着を迎える人々がいたことを思えば、マクシミリアンが毎晩きちんと寝所を手配していたのは、疑いようもない事実だった。
クラリスは床に就く前、必ず夫婦の部屋を訪れ、ほんのひとときでも挨拶を交わすようにしていた。
ある伯爵家の別邸に世話になった日のこと。
その夜もまた、クラリスはいつものように、ためらいなく夫妻の部屋の扉を叩いた。
マクシミリアンはどこへ行ったのか、ブリエルは一人で座っていた。
彼女は移動中、何度も出し入れしていたカバー付きの本を読んでいる。
ここ数日、クラリスは彼女の読書を邪魔したくなくて、あえてどんな本なのか尋ねなかった。
けれど、何日も同じ本を手にしている様子を見るうちに、さすがに気になってきた。
(もしかして、育児書かしら?)
そうだとしたら、クラリスも借りて一緒に読んでみたいと思った。
生まれてくる子どもに、きちんと向き合ってあげたかったからだ。
「そんなに楽しそうに、何を読んでいるんですか?」
「あら、クラリス。」
声をかけると、ブリエルは少し驚いたように身をすくめながら答えた。
クラリスが興味を示したのが、嬉しそうにも見える。
「これは、ブロカ大陸語の文法をまとめた本です。」
「ブロカ大陸……!?船で半年もかかる場所じゃないですか?」
クラリスは、思わず目を見開いて問い返した。
公務試験でも、ブロカ大陸については概略的に触れられる程度で、特徴を把握するくらいの知識しか持っていなかったのだ。
蒸し暑い気候、豊富な資源、そして肌の色が異なる人々が暮らしている――教本には、その程度の情報が記されていただけだった。
「ええ。王都で暮らしていると、ブロカ大陸からもたらされる品々が、年々増えていることに気づくようになりますから」
「それで、奥様も勉強なさっているのですか?」
「はい。いつかセリデンが、ブロカ大陸と交易を行う日が来るかもしれませんし」
もっとも、海を隔てたセリデンに、果たしてそのような機会が巡ってくるのか――クラリスは、内心では懐疑的だった。
その思いを察したのだろう。
ブリエルは、間を置かずに言葉を継いだ。
「もしかしたら……ブロカ大陸へ赴く機会が生まれるかもしれませんよ」
「……私が、ですか?」
「はい、母が話してくれたんです。あ、つまり……クノーの母の話なんですけど!母方の遠い親戚の中に、ブロカ大陸に住んでいる方がいるそうで。」
「ああ……」
クラリスは、どう返事をすればいいのかわからず、気の抜けた相槌を打った。
――クノー夫人の母方の一族。
それはつまり、グレジェカイアの貴族ということになる。
となれば、王家と何かしらの縁があっても不思議ではない……。
クラリスの戸惑いに気づいていないのか、ブリエルは明るい声で話を続けた。
「クノーの母方の親戚なら、私にとっても家族みたいなものですし。いつか会いに行くこともできますよね?」
「……ええ、そうですね。」
「そうなんです。でも、独学だとやっぱり難しくて……なかなか思うように進まないんです。」
そう言って、彼女は文法書を閉じたまま、深くため息をついた。
「実は、きちんと外国語の授業を受けた経験って、ほとんどなくて……」
「それなら、公爵様にお願いしてみてはいかがですか?」
クラリスの提案に、ブリエルは控えめに首を振った。
「公爵様はお忙しい方ですもの。私のために、これ以上お時間を割いてほしいとは思えません。誰かが……勉強のやり方を教えてくれながら、一緒に学んでくれたら、とても心強いのですが」
クラリスは深くうなずいた。
彼女自身、修道院で仲間たちと過ごすうちに身につけた勉強法が、大いに役立っていたのだから。
(奥様にも、学びを支えてくれる人がいればいいのに)
そんなことを考えた、その瞬間。
ふと気づけば、ブリエルの視線がまっすぐ自分に向けられていた。
それは迷いのない、そして――はっきりとした願いを宿した眼差しだった。
彼女の胸が、かすかに高鳴った。
「……わ、私が、ですか?」
「うーん、クラリスが不都合だというなら、無理には……」
「い、いえ!不都合だなんて、そんなことありません!」
「だって試験範囲に入っている勉強でもないでしょう?邪魔になるようなら、私が悪いですし……」
「気にしないでください。」
クラリスは一瞬、かぼちゃ色の瞳をくるりと動かしてから、きっぱりと言った。
「ノアが言っていました。何かを学べば学ぶほど、学習に向いた考え方が身につくって。だから私が新しい言語を学ぶことは、きっと官吏試験の勉強にも役立つはずです!」
「それなら……クラリスが、私を手伝ってくれますか?」
「もちろんです!実は私も、新しい言語を学んでみたいと思っていたんです。」
「まあ、よかった。」
夫人はぱっと手を打つと、鞄の中から別の文法書を取り出し、クラリスに差し出した。
まるで、こうなる未来をあらかじめ知っていて、準備していたかのように。
「それじゃあ、時間があるときはいつでも、クラリスが勉強したことを私に教えてくださいね。いいでしょう?まずは……ここに並んでいる、くねくねした文字の書き方から。一緒にやってみましょう」
クラリスは、彼女から手渡された本をぱらぱらとめくった。
生まれて初めて目にする不思議な模様――それが「文字」だと記されている。
これを覚えなければ、ブロカ大陸語の勉強を始めることすらできないのだろう。
「丸暗記するしかなさそうですね。毎日小テストをすれば、すぐに身につくと思います」
「まあ、素敵な考えですわ!」
ブリエルは両手を胸の前で重ね、感激したように何度も頷いた。
「どうやって、この複雑な文字を覚えればいいのかしらって、ずっと悩んでいましたの」
「私に任せてください、奥様。毎日一緒に小テストを――」
そこまで言いかけたクラリスの声は、柔らかな期待を帯びた空気の中に溶けていった。
「慣れてしまえば、こういうのはすぐ覚えられると思いますよ。」
クラリスは拳で胸をとんとんと叩き、誇らしげに顎を上げた。
「せっかくですから、自由にお話しできるくらいのレベルまで仲良くなれたら嬉しいです。
もし困っていることがあるのに、言えずに一人で我慢していたら……それは、とても悲しいですから。」
ブリエルが慎重に口にした願いは、正直なところ簡単に叶うものではなかった。
独学で外国語を学ぶのは難しい。
それでも、目標は大きく持った方がいい。そう考え、クラリスは彼女と一緒に頷いた。
「一生懸命やれば、きっとそうなれますよ!」
クラリスが部屋に戻ってから、あまり時間を置かずにマクシミリアンも部屋へ戻ってきた。
ソファに静かに腰掛け、文法書を撫でていたブリエルは、ゆっくりと立ち上がり、少し前の出来事を思い返していた。
「クラリスが……ブロカ大陸語に興味を持っているように……見えたの」
少し前まで、「勉強を手伝ってくれる」という言葉に、ぱっと顔を輝かせていた彼女の姿は、もうどこにもなかった。
「自分から、勉強すると言ってくれたんです」
前へ出たマクシミリアンが、そっと彼女の両頬に手を添えた。
ブリエルの顔は青ざめていた。
深い罪悪感と、不安がないまぜになった色だった。
「……ごめんなさい。嫌な役目を押しつけてしまって」
「ううん。私が出しゃばっただけです」
彼女は、自分の顔を包み込む大きな手に、そっと身を委ねた。
「賢い子ですね。どうやって勉強したらいいか、すぐに思いついたみたい」
「ええ……そうでしょうね。いろいろなところが、あなたに似ていますから」
静かな声でそう告げると、部屋にはしばし、穏やかな沈黙が落ちた。
それは本心だった。
マクシミリアンは、ブリエルが正式な貴族教育を受けられない立場でありながら、セリデンの女主人という役割を見事に果たしていることを、心から高く評価していた。
それはおそらく、彼女が伯爵家の庶子であった頃から、屋敷という場所の仕組みや秩序を正しく理解し、身につけてきたからだろう。
クノー侯爵家が代々優秀な後継を輩出してきたことを思えば、彼女の才覚が際立っているのも当然のことだった。
「とんでもない。クラリスがあれほど懐いているのは、公爵様が最初に心を向けてくださったからです。」
「いいえ、それはすべて、あなたの人柄です。」
マクシミリアンは気づいていた。
クラリスの愛らしさには、どこかブリエルと似た輪郭があるということに。
血のつながりがなくとも、同じように深く誰かを思いやる心を持っていれば、自然と似通った部分が生まれるのだろう。
そんなふうに、確かに二人は似ていた。
「…………」
そして、重苦しい沈黙が続いた。
不思議なことだった。
愛する子の長所を語る場面なら、本来はもっと柔らかな笑みが浮かんでいてもいいはずなのに。
けれど、二人の表情はどうしても和らがなかった。
きっとそれは、クラリスを欺いているという罪悪感のせいだろう。
「……そのうち」
長い沈黙ののち、ブリエルがようやく、誰かに聞かれるのを恐れるような小さな声で口を開いた。
「クラリスが……外国語を学ばせた理由を知ったら……」
そのとき思い浮かぶ光景は、ひとつしかなかった。
クラリスは、きっとたくさん泣く。
すでに“死”を受け入れて生きているあの子に、さらなる混乱を与えてしまうことになるのだから。
「……傷つきますよね?」
その言葉は、祈りにも似た震えを帯びて、静かに部屋の空気に溶けていった。
マクシミリアンは、ゆっくりと頷いた。
「はい。」
最悪の場合、クラリスはすべての計画を捨て、王室へ自らの首を差し出しに駆け込む可能性すらあった。
なぜそこまでの覚悟をするのかといえば――それは、マクシミリアンならそうする人間だからだった。
もし彼が一国の王子であり、最後の王族であるならば。
与えられた死を正面から受け入れ、国家の終焉を名誉ある形で締めくくっただろう。
「……その処刑式は、クラリスが王族として執り行える、最初であり、そして最後の任務になります。」
「そんなの、あり得ません。」
ブリエルには、死に深い意味を見出す王族や貴族の価値観が、どうしても理解できなかった。
「――あの子は、生まれながらの王女なのです」
生得的に備わった誇りと気高さは、どのような環境に置かれようとも、完全に踏みにじられることはなかった。
家族からの寵愛と冷遇、その両極端な扱いを受ける中にあっても、あの子は自らが持つ“光”を失わなかった。
もし平凡な王家の子であったなら、それは祝福すべき資質と呼ばれていたことだろう。
けれど――クラリスは……滅びゆく国の王女だった。
「クラリスは、自分の死が、そのまま一国の終焉を意味することを理解しています。ですから、恐怖に駆られて醜く逃げ惑うような真似は、決してしないはずです」
むしろ、恥や羞恥という概念を知らぬ子であったなら、ここまで事態は難しくならなかったに違いない。
「あるいは……セファス王室の意思を翻すことよりも、あの子自身の考えを変える方が、よほど困難なのかもしれません」
その言葉は静かだったが、重く、深く胸に沈んだ。
誇り高き王女の覚悟が、否応なくその場の空気を支配していた。
「無理に生かしたとしたら、その子は……私たちを恨むでしょうか?」
「そもそも大陸を離れるという計画に、簡単に頷くような子ではありません。いずれ、クラリスと私たちの間には、避けられない対立が生じるでしょう。」
ブリエルは唇を噛みしめた。
子どもに憎まれること自体がつらいわけではなかった。
その過程で、心優しいクラリスが味わうであろう混乱が、あまりにも痛ましかった。
「あの子は……私たちを完全に恨むことすら、できないかもしれません……」
それならいっそ、王女の名誉を汚そうとする人間たちであれば、指一本でも動かしてくれたほうがよかったのに。
「今となっては……」
彼は、少しずつ涙を滲ませているブリエルの手を引き、そっと自分の胸元へと抱き寄せた。
体温が、じわりと深く伝わってくる。
「準備をして、待つしかありません。」
「……待つ……のですか?」
「ええ。どうせ王室の兵がセリデンに滞在している間は、クラリスをどこかへ逃がすことなどできません。その隙に……誰かが」
マクシミリアンは、温もりのある夫人の身体を抱き寄せ、柔らかな髪に顔を埋めた。
「だからこそ、願うのです……。どこかの、心優しい誰かが、あの子を変えてくれることを。ほんの少しでいい。生に、そして未来に、欲を持てるように」
「……それは、本当に可能なのでしょうか?」
ブリエルがかすれた声で投げかけた問いに、マクシミリアンは迷いなく、力強く頷いた。
「もちろんです」
それだけは、確信をもって言えた。
彼自身、過酷な人生を歩んできた身でありながら、すでに“そういう存在”が現れていることを知っていたからだ。
ブリエルと、クラリス。
その二人の少女は、この世に未練などないと思い込んでいた彼の価値観を、根こそぎ覆してしまった。
なかでもクラリスは、誰よりも正直で、真っ直ぐに――そして驚くほど健やかに成長していた。
この世に神という存在がいるのなら、あの子のために、特別な縁を用意していないはずがなかった。
――いや、もしかすると、すでに出会っていたのかもしれない。
彼は、クラリスをそれぞれ違った眼差しで見つめていた二人の少年――いや、青年たちの姿を思い浮かべた。
今となっては、誰であっても構わなかった。
どうか、クラリスが未来へ向かってその手を伸ばすことができますように。
マクシミリアンは、切実に祈った。
淡い桃色の花が咲き、風に揺れて美しく散り始めるころ、ノアはクラリスからの手紙を受け取った。
セリデンへ無事に到着したこと、そして彼女がいなくなったあと、壁の向こうで起きたセリデンの新しい出来事が綴られていた。
ブロカ大陸の言葉を学び始めたという知らせも。
そして――会いたい、という言葉と、好きだという言葉も一緒だった。
その丸みを帯びた文字があまりにも愛らしくて、ノアは胸の奥がきゅっと締めつけられるような気持ちになった。
やっぱり、ユジェニの言った通りだ。
クラリスは、きっと永遠にノアの本心には気づかない。
だからこそ――友人同士の「好き」と、そこに滲む「恋しさ」を、こんなにも素直に語ることができるのだ。
ノアは、言いようのない寂しさを覚えながらも、不思議と後悔はしていなかった。
どうせ彼は、気軽に「好きだ」なんて言える立場じゃない。
クラリスはそれを、すべて「友情」として受け取ってしまうのだから。
ノアはすぐに返事を書いた。
自分もクラリスのことが大好きで、いつも大切に思っていること。
ずっと一緒にいたいと願っていること。
――どこからどう見ても、まるで恋文のような内容だったけれど。
それでも、決して恋文ではなかった。
少なくとも、彼自身の中では。
そしてほどなくして、クラリスからの次の返事が届いたのは――散った花びらが乾いて、かさりとかすかな音を立てる――夏の始まりを告げる頃だった。
クラリスは、いつの間にかブロカ大陸の言葉と文字に慣れ、拙くも丁寧な筆跡で、「ノア、好き。」と書いて送っていた。
やけに唇を打ち鳴らす音の多いブロカの言語で綴られたその告白が、彼の胸にどれほど鮮烈に響いたのか――それを、クラリスが知ることは、きっと永遠にない。
ノアもまた、かつて少しだけ覚えたブロカ大陸の言葉で、「私はクラリスが恋しい。」と書いて返事を送った。
クラリスの名前は、ブロカ大陸の文字で書いても愛らしかった。
語尾がすっと伸びる形が、なぜか彼女の長い髪を思わせる。
「……ああ、本当に。」
ノアは机に突っ伏した。
クラリスに会いたかった。
彼女と別れて、まだ四か月も経っていないというのに、今すぐにでも会いに行きたい衝動を、どうしても抑えきれずにいた。
小さな体を腕に抱きしめたかった。
長い髪から漂う香りを、胸いっぱいに吸い込みたかった。
そして何より――その笑顔を、朝から晩まで見つめていたかった。
それはつまり、クラリスが幸せでいてくれるということだから。
もし今すぐそれが叶うのなら、世界中のどんな宝でも差し出せる気がした。
――そのときだった。
控えめなノック音が響いたのは。
『魔法使いアスト様がお呼びです』
黒いローブに身を包んだ若い魔法使いの伝言に、ノアは反射的に仮面を整え、すぐさま部屋を出た。
春に魔法使いの塔へ戻ってからというもの、ノアは何度もアルステアのもとを訪ねている。
正直、何を話せばいいのか整理できていたわけじゃない。
それでも――今すぐ、あの顔を見なければ胸の奥が落ち着かなかった。
だが、アルステアはまるでこちらの事情などお構いなしに、淡々と自分の予定を優先するような態度でノアは、アルステアに会いに行かなかった。
自分がそんな態度を取っている理由は、もしかすると本当に――魔法師メイを殺したのが彼だったのではないか、そう疑っているからではないのか。
ノアはそう考え、同時に自分自身に少し驚いた。
そんな思考がごく自然に浮かんだということは、ノアの心の奥底では、今なおアルステアを「疑っているだけ」なのだという証でもあった。
確信ではなく、疑い。
――だから、なのか。
アルステアの部屋の前で立ち止まったノアは、無意識に仮面の位置を直した。
『自分は、まだ彼を信じたいと思っているのではないか』
二人による明確な証言が存在しているにもかかわらず、なお疑念を完全に捨てきれないということは、それはすなわち、クラリスの力を疑っているのと同じことに他ならなかった。
クラリスとアルステア。
その二人のうち、どちらがより大切かなど、考えるまでもない事実だった。
――それでも。
ノアの胸には、どうしても消えない引っかかりが残っていた。
ノアは、その扉をノックすることすらできず、ただ立ち尽くしたまま見つめていた。
「……俺は」
気配を察したのだろう。
ほどなくして扉が開き、以前と何一つ変わらないアルステアが、満面の笑みを浮かべて両腕を広げた。
「我が弟よ!」
「……」
ノアが言葉もなく彼を見返すと、アルステアは両腕を広げたまま、ぴたりと動きを止めた。
「ま、まさか……!今度こそ、俺が抱きしめてもいいってことか?これまで一度も許してくれなかったのに……!」
感極まった様子で、わなわなと肩を震わせる兄の姿に、ノアの胸に奇妙な感覚が芽生えた。
――不思議な話だ。この男を、本当の兄だと思ったことなど一度もなかったのに。
「許した覚えはない」
ノアは静かにそう告げると、片手を上げて、はっきりと拒絶の意思を示した。
すると彼は、再び薄ら笑いを浮かべた。
「そうだろう?グレジェカイア王を抱いたその夢が、他の男に汚されるなんて、嫌に決まってる……しかも、こんな三十七にもなったおっさんにな」
「へ、変なこと言わないでください!」
ノアが怒鳴ると、彼は両手をぎゅっと握りしめたまま、顔をぐっと近づけてきた。
「本当に抱かなかった?」
「……」
「はは、どうせぎゅうぎゅうに抱きしめたんだろ?」
「……」
「香りだって、ほら。な?そうだろ?」
「……」
「やーい魔法使い!俺の弟がすっかり普通の男になって帰ってきたぞ!誰か来い!今夜は盛大なパーティーだ!」
彼が廊下の向こうへ向かって大声で叫び始めたので、ノアは慌てて彼を部屋の中へ押し込み、バタンと勢いよく扉を閉めた。
「くだらないこと言わないでください!」
「冷たいなあ!魔法使いなんだから、もう少し大きく構えてくれてもいいだろ?」
そう言って、アルステアは改めてノアを見下ろし、どこか感慨深そうに目を細めた。
かつては腰ほどの高さだった少年が、いつの間にかこうして見上げる存在になっている。
それだけで、奇妙な感慨が湧くのも無理はなかった。
「それにしても……もうすぐ成人か?」
彼は鼻で笑い、くるりと背を向けると、散らかり放題の部屋を横切って窓を開けた。
最近は実験続きで忙しく、ノアに会えないと言っていたが――どうやら、それもまったくの嘘ではなかったらしい。
分解された木製の人形が部屋のあちこちに転がっている。
床には、起動しかけて途中で潰れたのだろう、淡く光を失った魔法陣の痕跡が残っていた。
「転移魔法を研究していてね」
「術者じゃなくて、対象そのものを移動させるってこと?」
ノアの問いに、アルステアは素直に頷いた。
「そう。でも、これがなかなか厄介でさ。どうしても――腕や脚が一本、足りなくなる」
「……」
「まあ、見た目がみすぼらしいし、少し片づけるか?」
彼は散らかった部屋が気になるのか、遅ればせながら人形の部品をあちこちへ移動させ始めたが、正直なところ、あまり意味はなかった。
「片づける必要はありません。魔法使いアストがきれい好きだなんて、最初から期待したことはありませんから」
「それもそうだな」
彼は中途半端な片づけを諦め、窓枠にもたれて体を預けた。
背後から差し込む陽光が、彼の輪郭をやさしく包み込む。
逆光のせいで、鼻筋がぼんやりと浮かび上がるアルステアを静かに見つめているうちに、ノアはふと、別の人物を思い出していた。
師匠、ヨナ・アスト。
いつも周囲に人が集まり、
ノアに愛情を教えてくれた、ありがたい大人。
最後まで彼の味方でいてくれ、気にかけてくれた――ノアとアルステアは、驚くほどよく似ていた。
本物の親子ではないというのに、仕草や生活の癖まで似通っているのだから、不思議なものだ。
「父親は片付けが本当に苦手な人でね。だから、いつの間にか幼いお前が、代わりに部屋を整理するようになってた。面倒だっただろ?」
「……いいえ」
ノアは、迷いなく首を横に振った。
それは片付けではなく、学びだった。
部屋に散らばる不思議な文書や道具、生き物について、ノアは何度も質問した。
師は一つとして疎ましがることなく、丁寧に答えてくれた。
さらに、答えを与えるだけでなく、ノア自身が考えられる時間をきちんと残してくれた。
すべてが遊びであり、同時に、かけがえのない教えだった。
ノアはその時間を、今でも心から愛している。
「ノア」
呼びかけられた声に、ノアは顔を上げた。
気づけば、声の調子まで、あの人に似てきている。
それを指摘されるのが、少しだけ怖くて――それでも、どこか誇らしくもあった。
「……魔法使いアスト」
ノアは、思わず心が揺らいでしまった。
彼に気をつけろと言っていたクラリスの可愛らしい声さえ、もうはっきり思い出せないほどに。
「いずれにせよ、お前にとって大切な人ができたようで、うれしいよ」
「……」
「修道院で共に過ごす時間も長くなった。今ではもう、自分の命よりも大切に思っているんじゃないか?」
「変なことを言わないでください」
ノアは苛立ったように答えながらも、それを否定することはできなかった。
自分の命より、クラリスの存在のほうが大切だというのは、あまりにも当然のことだ。
たとえ修道院で、そういった出来事が特別あったわけではなくても、だ。
抱きしめたり、額に口づけをしたりしたことも――確かにあったけれど。
「なんで指先まで赤くなってるんだ?何を考えてたんだい?」
「な、何でもない!」
ノアは慌てて両手を背中に隠し、わざとらしく声を張り上げた。
「どんな理由で呼び出したのか、ちゃんと説明してください。戻ってきてから、ずっと知らないふりをしてたじゃないですか」
「やっぱり気づいてたか」
アルステアはノアの前まで歩み寄り、苦笑した。
「悪い。少し立て込んでてね。……今も仕事中だって知ったら、また不機嫌になるかな?」
「子ども扱いしないでください」
「客が来る」
ふざけた調子だった彼の表情と口調が、すっと引き締まった。
「……客?大事な人ですか?」
彼は顎に指を当て、ほんの一瞬、言葉を選んだ。
ノアはその沈黙の意味を、直感的に悟ってしまった。
「……少し、意外な相手でして」
「誰なんだ?」
「王室です」
「……セファス王室のことですか?」
アルステアは、即座にうなずいた。
「お前も知っているだろうが、ゴーレムが崩壊して以来、王室が我々と直接話をするのは、これが初めてだ」
――初めて?
それなら、メイビスが持ち去ったという手紙は何だったのか。
ノアはそこを指摘しかけて、やめた。
「その話を……なぜ私に?」
「正直に言えば、私が少し立て込んでいてな」
アルステアは両手をきちんと揃え、頼みごとをするような姿勢を取った。
「代わりに、お前が対応してくれないかと思っている」
……怪物相手の来客対応、ということか。
いつもなら、そう言って即座に断っていただろうが、ノアはそれ以上、反論しなかった。
もし今の権限移譲が、アルステアの描く大きな計画の一部であるなら、ここは素直に従っておくのが賢明だと判断したのだ。
「……ひとまず、わかった」
「おや?反論しないんだ。てっきり『怪しい客の相手なんてするものか』って噛みつくと思ってたけど?」
ノアは少しむっとしながらも、知らないふりをして肩をすくめた。
「そんなこと言ったら、どうせクラリスの評判を盾に説教されるじゃないですか」
「よくわかってるね」
「王室の人間をもてなす礼儀がなってないと、将来、公爵家への縁談にまで影響する、とか言うんでしょう?」
「……そこまで言うつもりはなかったけど」
「ほら!」
とうとう堪えきれなくなったノアは、彼の胸元をぐいっと叩いた。
「少しは静かにしてください!本気で心配してるんですから!」
「いてっ、ちょ、叩くなって」
「もちろん!二人の結婚は心から祝福しますから!……だからって、何度も殴らせないでください!」
彼は苦笑しながらノアの手首を軽く押さえた。
「わかった、わかった。悪かったよ」
そう言って、アルステアは一歩下がり、いつもの余裕ある笑みを取り戻した。
「じゃあ、準備をしよう。客はもうすぐ来る」
ノアは小さく息を吐き、気持ちを切り替えるように背筋を伸ばした。
「……どんな人なんですか」
「さてね」
意味ありげに笑うその横顔を見て、ノアは嫌な予感を拭えずにいた。
「そもそも、魔法使いアストがどんな立場で私の結婚を許可するんですか!」
「ん?ああ、それ?」
彼は向かい越しにノアと目を合わせ、やわらかく微笑んだ。
「当然だろ。弟を愛している兄としての資格、かな?」
「…………」
ノアは、彼から視線を逸らすことができなかった。
アルステアは確かに悪ふざけが過ぎるところはあるが、結局はいつも、こうして穏やかに笑ってくれる人だった。
まさに“兄”という言葉が似合う――
……本当に、この人だったのだろうか。
自らの手で、罪なき魔法使いメイビスを殺したのは。
ノアは、どうしても頷けなかった。
たとえそれが事実だったとしても、そこには何か事情があったのではないか、そう思えてならなかった。
アルステアは、魔法使いの城を平穏に統治する実質的な権力者だった。
もしかすると、魔法使いメイビスが取り返しのつかない過ちを犯した際、混乱を最小限に抑えるため、静かに処理する道を選んだのかもしれない。
目の前のセリデン公爵だけを見ても、それは明らかだった。
彼もまた、平和のために罪人を殺めた人物だった。
その行いが正しいとは言い難いが、大義の前ではやむを得なかったのだろう。
――本当に、そういうことではなかったのだろうか。
「とにかく、よろしく頼む。どんな依頼になるかは分からないが、お前なら賢明な判断を下せるはずだ」
「俺に判断まで丸投げする気ですか?」
「おいおい。お前が全身真っ白なローブを着てる、なんて思ってないぞ?」
「……」
「魔法師シネットとして下した決断なら、俺は何であれ支持する。好きにやれ」
その言葉は、静かでありながら、揺るぎない信頼を含んでいた。
あの揺るぎない信頼の言葉は、本当に心からのものだったのだろうか。
ノアは、結論を出せずにいた。