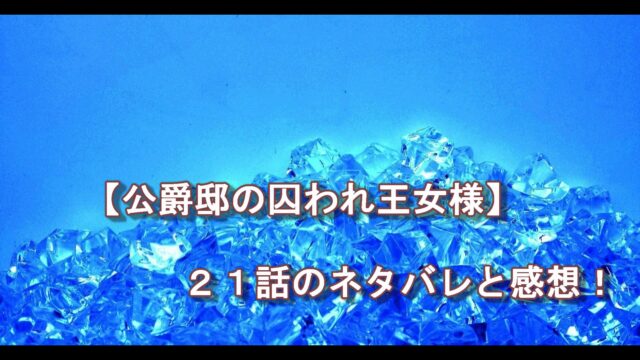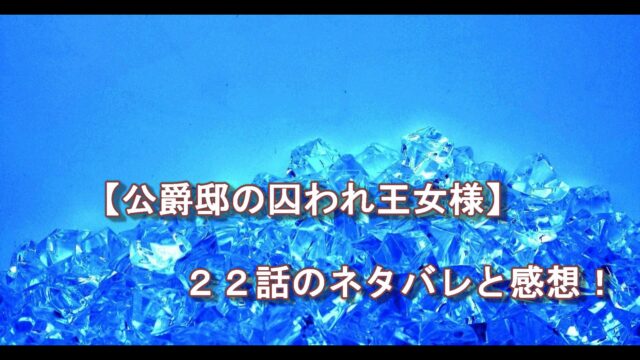こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

138話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 別れの言葉
寒さに固く閉ざされていた大地のあいだから、緑の芽が慎重に顔を出した。
太陽が空を巡る時間が変わり、成長を促す風が吹き始める頃――。
王室では、一部の貴族を対象に、秘密裏に新たな事実が発表された。
長いあいだセリデンに眠っていた遺物、崩れ落ちたゴーレムを本格的に掘り起こす調査を開始する、というものだ。
実のところ、これまで王室は崩壊したゴーレムに対して、消極的な姿勢を取り続けてきた。
その中に先王の遺骸が眠っていると考えれば、やや異様にも思える話ではある。
しかし、新王の即位に伴う国内の混乱、さらにはグレジェカイアとの戦争といった外的要因を踏まえれば、避けられない事情だったとも言える。
何より、魔法使いたちですら満足な成果を上げられなかった問題を、ただの人間が解決できるはずがない。
そうした理由から、崩壊したゴーレムは長らく王室の関心から外れた存在となっていた。
だが――今は違う。
長きにわたり、王国には平穏が保たれていた。
王室では、今こそが長年先送りにしてきた難題に取り組むべき時だと判断したのだ。
こうして王室直属の騎士と兵士たちが、自ら武具を整え、あの堅牢なゴーレムの周辺を調査することになった。
そして、マクシミリアンはその知らせを耳にした場所で、静かに息をのんだ。
それは、春を迎えて主要領地の領主たちが一堂に会した政務会議の場であった。
「ふむ。我らの愛する父を、いつまでもあの冷たい大地に眠らせておくわけにはいかないだろう?私の兵を送って、中を開いてみようと思うが」
ライサンダーは指先をくるくると回しながら、軽い調子でそう告げた。
その瞬間、会議場の視線が一斉にマクシミリアンへと集まる。
それはすなわち、まもなく王の直轄軍がセリデンへ派遣される、という意味を持つ。
彼らが地域に直接害を及ぼすことはないだろう。
だがその中に、王の目や手となる者が紛れ込んでいる可能性は否定できない。
王室の威光は心強い一方で、歓迎しがたい――それが地方領主たちに共通する本音だった。
こんな事態になる前に、王は兄に何らかの配慮を示していただろうか。
王室の兄弟関係が、噂どおり本当に良好であるなら、きっとそうしていたはずなのだが。
「もちろん、セリデンとしては特に反対はない、という理解でいいな?」
ライサンダーの問いかけに、マクシミリアンは表情一つ変えず、静かに答えた。
「はい、陛下」
どうやら兄弟の間ではすでに話が通っていたらしく、貴族たちはマクシミリアンへ向けていた探るような視線を引っ込めた。
その唐突な発表が、彼の胸中をどれほどかき乱しているのか――それを見抜けた者は、誰一人としていなかった。
季節が温みを帯び始めたということは、クラリスにとって、修道院での生活を整理する時期が来たことを意味していた。
おそらくこれが最後になるであろう朝の鐘の音を聞きながら、クラリスはいつもと変わらぬ動作で、静かにベッドを抜け出す。
本当は“最後の日”という名残惜しさに、鐘が鳴るよりも前に目が覚めていたのだが、なぜか今朝は、胸に去来する感情をうまく掴めないまま――彼女はただ、淡々と朝の支度を整え始めた。
前日と変わらぬ時刻に目を覚ましたいがために、彼女は毛布の中で待っていた。
「おはよう、モチ。」
そばに置いてあった石に口づけると、ゴーレムの姿をしたモチがぴょんと跳ね起きた。
「コオ。」
「どうしてこんなに早く起きるの?修道院にいる友だちに挨拶しなくていいの?」
「モチ!」
マランは「友だちじゃないもん!」と言わんばかりに、窓辺で両足をどんどん踏み鳴らした。
ここで過ごしているあいだに知り合った石たちへ挨拶をして、戻ってくるつもりなのだろう。
クラリスは服を着替え、髪をまとめてから部屋を出た。
以前は毎朝、ノアがクラリスの世話を焼くために訪ねてきたものだが、最近はそんなこともなかった。
いや、朝だけではない。
彼は、クラリスの部屋そのものを、まるで無視しているかのようだった。
話の流れで部屋へ行こうなどと言い出しただけで、両手を激しく振って全力で否定されるほどなのだから。
――もしかして、私……迷惑なのかな?
いや、それは違う。
そこだけは、はっきりしていた。
それを除けば、ノアはいつだって変わらず優しかったから。
どうせ悩んだところで、答えが出るような問題でもない。
クラリスはそう割り切って、いつも通り素直に考えることにした。
――私はノアが好き。できることなら、もっとたくさん会いたい。
ならば、答えは簡単だ。
クラリスのほうから、会いに行けばいい。
階段を下りかけていた彼女は、くるりと踵を返し、ノアの部屋へと向かう。
――最後の日なんだから、「一緒に行こう」って言ってもいいよね。
それくらいなら、友人として十分に許されるはずだ。
……でも。
――それで、もし私が……ノアの手を取っても、いいのかな?
胸の奥に生まれたその小さな問いを、クラリスはまだ言葉にできないまま、そっと抱きしめていた。
十五歳にもなって、友だちと手をつないで歩くというのは、さすがに少し……変な気がした。
もっとも、セリデンにいた頃は同年代の友人もおらず、そのことを特に意識することもなかった。
だが、ここで数か月を過ごすうちに、クラリスは気づいてしまった。
一般的な友人関係には、彼女が思っていた以上の「距離」があるということに。
――その決まりを破ってしまえば、ノアのことを好きだという事実が、誰かに知られてしまうかもしれない。
それだけは、どうしても避けたかった。
「……少女?」
部屋を出たところで、ちょうどノアと鉢合わせし、クラリスは驚いてその場に立ち尽くした。
目の前には、仮面をつけたノアが立っていた。
その隣には、ほかの男性修道生たちの姿もある。
「あ、……おはよう、ノア。」
「部屋に何か置き忘れたの?」
――違う。本当は、ノアと一緒に行こうと思っていただけなのに……。
でも、そう口にしたら、ノアが友人たちと過ごす時間を邪魔してしまう気がした。
「あ、う、うん!そ、それを取りに戻るだけ。そう!」
クラリスは慌てて話を合わせ、大きく一歩、進む方向を変えた。
「また後でね、ノア。約束だよ?」
ノアは少し不思議そうな目でクラリスを見たものの、やがて小さくうなずき、他の修練生たちと一緒に階段を下りていった。
「……やっぱり、うまくいかないな」
自室へ戻るふりをして歩き出したクラリスは、途中で立ち止まり、そっと息を吐いた。
誰かを好きになること自体は、後悔するほど難しいことじゃないと思っていたのに。
――気持ちを悟られないようにしなきゃ。
そう自分に言い聞かせた途端、かえって胸の奥がぎゅっと苦しくなる。
「このままじゃ……ノアのこと、思う存分好きになることすらできないかも」
小さくこぼした本音は、廊下の静けさに溶けて消えていった。
不安を覚えたクラリスがもじもじしていると、少し離れた場所からユジェニがこちらへ向かってくるのが見えた。
クラリスが片手を上げて挨拶すると、ユジェニは足早に近づき、ぐっと顔を寄せてきた。
「ユ……ジェニ……?」
「ごきげんよう。」
彼女は急にきっぱりとした態度になり、腕を組んで腰をそらした。
「顔に“悩みあり”って大きく書いてありますよ。」
「な、なに言ってるの!」
クラリスは両手で冷えた自分の頬をつねってみた。
もちろん、そうしたからといって何かが分かるわけではないのだが。
「今日が最後だから、もう先延ばしにはできないと思って言ってるんですけど。」
「……え?」
ユジェニは「うーん、さすがに早すぎる助言かな」と一瞬迷ったあと、もう仕方ないといった様子で口を開いた。
「魔法使いさまは、気づきませんよ」
「……え?」
「クラリスが何をしても、きっとわからないでしょう。致命的なくらい、鈍感ですから」
「そ、そんな……」
クラリスは思わず「どういう意味ですか?」と問い返しかけたが、バレンタインに似たユジェニアの鋭い眼差しに射抜かれ、反射的に口をつぐんだ。
よく考えてみれば、以前ノアとキスする夢を見ただけで動揺していたのだから、感の鋭いユジェニアが彼女の想いに気づいていたとしても、不思議ではない。
「ですから、肩の力を抜いて、きちんと表に出しても構いませんよ。それは、壁に向かって叫ぶのと、そう大差のない行為です」
「……そ、そう……ですよね。だって、ノアは絶対に気づかない……ですよね?」
「ええ」
「ありがとう。なんだか、すごく気が楽になりました」
胸に溜まっていたものが、すっと溶けていくのを感じながら、クラリスは小さく、安堵の息を吐いた。
「特に何も……」
「あ、そうなんだ。」
クラリスはユジェニと並んで階段を下りた。
「王子殿下に、個別に伝える言葉や手紙はないの?二人、とても仲が良さそうだったのに。」
バレンタインは、あの一件以降、修道院へ戻ってきていなかった。
直接来られなくても、長年親しくしてきた修道生たちに手紙くらいは送るものだと思っていたが、そうしたこともなかった。
クラリスは、ほかの修道生たちが誤解しないようにと、顔を合わせるたびにバレンタインへ伝言はないかと尋ねていた。
すると修道生たちは、「よろしく伝えてくださいね」と冗談めかして言ったり、「試験の日に会いましょう」と温かな挨拶を託したりした。
ユジェニも王子殿下とはかなり親しかったはずで、何か言づてがあるのでは……と思ったのだが。
「ありません。」
「……え、ないの?」
ユジェニアは、どう見ても“良心が欠片ほどもない”としか思えない不愉快そうな表情のまま、こくりと頷いた。
「二度と顔を合わせたくない相手ですね。生理的に受け付けません」
もっとも、二人とも容姿は整っているから、並んで立っているだけなら目の保養にはなっただろうが。
「……あ」
階段をしばらく下り、玄関を出かけたところで、ユジェニアはふと思い出したように足を止めた。
「そんなふうに険しい顔ばかりしていると、性格の悪さが滲み出て、皺まで深く刻まれますよ。気をつけるよう、伝えておきましょうか?」
「…………」
「その言葉を聞いた王子殿下の表情が、ほんの一瞬でも歪みますように」
そう言って、ユジェニアは心底楽しそうに――滅多に見せない、実に愉快そうな笑みをこぼしていた。
朝の運動を終えると、前回の試験結果の発表があった。
いつもと変わらない席順に戻ったエイビントは、クラリスの名前を見て思わず顔をしかめた。
結果を確認したあと、クラリスは部屋に戻って荷物をまとめ、玄関近くまで降りてきた。
ちょうど、公爵家の馬車が到着する時間だ。
出発前に最後にユジェニと玄関で会う約束をしていたため、クラリスは階段の上から彼女が来るのを待っていた。
「グレジェカイア嬢!」
――だが、駆け寄ってきたのはエイビントだった。
クラリスは思わず身を引き、後ずさった。
修道院で過ごす最後の日まで、彼が起こす騒ぎに巻き込まれたいとは思わなかったからだ。
「これ、受け取ってください。」
しかし彼は、なぜかきちんと包まれた贈り物を差し出してきた。
分厚な箱には、淡い桃色のリボンまで丁寧に結ばれている。
「……?」
クラリスは相手と贈り物を交互に見比べ、戸惑いを隠せない表情のまま、それを受け取った。
「……あ、ありがとう……」
「別れに際して贈り物を渡すのは、当然の礼儀でしょう?ご存じですか。私がこれほど礼儀正しい人間だと、公爵さまと聖職長さまに、きちんと伝えておいてください」
箱を開けると、中には一枚のノートが収められていた。
どうやらエヴィントが他の修練生たちに頼み、クラリスへ伝える言葉を一つずつ集めたものらしい。
「……あ……」
そこに綴られた温かな言葉を目にした瞬間、クラリスの胸がきゅっと締めつけられた。
思わず目頭が熱くなり、エヴィントに謝りの言葉を伝えたくなる。
こんなにも心のこもった贈り物を用意してくれた相手を、勝手な先入観だけで見ていた自分が、ひどく恥ずかしく思えた。
胸の奥に、じんわりとした後悔と感謝が、同時に広がっていった。
そして、ノートのいちばん最後のページ。
[公爵様の推薦状を送ってくださるようお願いする手紙は、こちらです。お分かりですよね?もし私が出立できなければ、グレジェカイア嬢が推薦状を受け取れなかったせいです。一生恨みますからね!]
「…………」
クラリスの胸に芽生えた感動が、すうっと冷めていくあいだに、エイビントは今度は荷物を抱えて降りてきたノアにも、青いリボンのついた贈り物を手渡した。
どうやらそれも、修道生たちの寄せ書きが書かれたノートらしい。
クラリスは、彼のノートの最後のページに何が書かれているのかが気になって仕方なく、思わず近づいて一緒に中をのぞき込んだ。
そのとき、ようやく到着したユジェニに向かって、エイビントがにやりと笑った。
「照れるなよ、ユジェニ。どうせ勉強ばっかりしてたくせに、別れの贈り物だけはやけに気合い入れて準備してるんだから。負けたと思わない?」
「負けた」
「え?」
「完全に負けた。しかも、ものすごくいい負け方だ」
「なに、それ。私が用意したものより、よっぽど立派だって言いたいの?」
ユジェニアは、頭がぶつかりそうなほど距離を詰め、
ノートを覗き込むクラリスとノアの顔を、交互に見やった。
ここ最近、妙に距離を取っていた二人の間隔は、いつの間にか元通りになっている。
きっと――少し前、廊下でノアにかけた、あの言葉のせいだ。
『魔法使いさまが何をしても、クラリスは絶対に気づきません。致命的なほど鈍感なのですから。ですから、気負わずに表に出して構いませんよ。それは、壁に向かって叫ぶのと、大差ない行為です』
ああして双方に同じことを吹き込んでおけば、二人とも余計な遠慮をしなくなる。
そうなれば――いつか必ず、何かが動く。
ユジェニアは、そんな未来を思い描きながら、意味深な笑みを、そっと唇の端に浮かべていた。
これほどまでに大げさに言われてしまえば、さすがに気づかないわけがないだろう。
ユジェニはその面白い場面をしっかり目に焼きつけるように、楽しげにうなずいた。
「ええ。」
「ま、まさか……あなたも公爵様と魔法師団の推薦状を受け取るつもり……!?」
「あ。」
エイビントの言葉で、ユジェニはようやく腑に落ちた様子で、手のひらで拳を軽く打った。
「それも……悪くないわね。」
「やめろ!同じ推薦状をもらったら、俺が面目丸つぶれだろ!」
「廊下で大声を出さないで。」
ユジェニは騒ぐエイビントをあしらい、クラリスとノアのもとへ歩み寄った。
「公爵家の馬車が到着したようです。」
「もう?約束より少し早いですね……」
クラリスは懐中時計を確認し、少し驚きながらも大きなかばんを持ち上げた。
もともと重かった鞄は、ここに来てから数か月の間に、さらにずしりと重みを増していた。
「持とうか?」
その瞬間、ノアがさっと手を伸ばした。
「だ、大丈夫!そんなに重くないから……」
クラリスは、好きな人に負担をかけたくなくて、慌てて鞄を背中側へ隠した。
「嘘はだめ。肩がぴくぴくしてる」
そう言うが早いか、ノアはぐっと距離を詰め、クラリスの腰の後ろへ腕を回して鞄をつかんだ。
「……っ」
不意に視界いっぱいに彼の胸元が迫り、クラリスは思わず息を呑む。
そのまま抵抗することもできず、素直に鞄を手放してしまった。
鞄を奪い取ったノアは、なぜかとても楽しそうな足取りで、玄関の外へ向かう。
「もう、本当に……私が持つつもりだったのに!」
後ろ姿に向かってそう抗議しながらも、クラリスの胸は、先ほどの距離の近さを思い出して、静かに高鳴っていた。
クラリスは名残惜しそうにノアの後ろ姿を目で追っていたが、やがてユジェニの腕をつかんだ。
「正直に言うと……さっきのは本当に心臓に悪かったです。あんなふうに急に来られたら、誰だって……ああ、本当に!」
小さな声でこぼした言葉に、ユジェニは思わずくすっと笑った。
「それから、もし以前お話しした件で、私にできることがあれば、いつでも連絡してください。たいしたことはできないかもしれませんけど……それでも。」
クラリスは、周囲に聞こえないよう声をひそめて続けた。
「ありがとうございます。たとえそうでなくても、一度は現地を自分の目で見に行こうかとも考えていました。」
それは、北の城壁まで足を運ぶつもりだ、という意味だろう。
「そのときは、必ず連絡してくださいね。いいですね? 約束ですよ?」
「もちろん、お約束します。」
「……あ、あの……でも……あまり遅くなると、私……少し困ってしまうので……わかりますよね?」
「え?」
クラリスは、十八歳を過ぎたらもう助けられない――そんな話をどう切り出せばいいのかわからず、思わず言葉に詰まった。
「そ、その……ユジェニアに、早く会いたくて……」
とっさに作った言い訳は、あまりにもぎこちなかった。
けれど、ユジェニアはそれを咎めることなく、ただ微笑んだ。
「承知しました。クラリスは、少しせっかちなところがありますものね」
「ええ……まあ、そうかもしれません」
外へ出る頃には、ノアはすでに公爵家の馬車にクラリスの荷を積み終えていた。
「では、お気をつけて。クラリス。あなたと出会えて、本当に嬉しかったです」
そう言って、ユジェニアは手を差し出し、握手を求める。
「私も……友だちになれて、嬉しかったです。お手紙、送ってもいいですか?」
「送ってくださらなければ、寂しくなってしまいます。どうか、その後も――」
別れを惜しむ言葉が、やわらかな風に溶けていった。
「……その話、気になります?」
そう言いながら、彼女がちらりとノアに視線を送ったのを見て、クラリスは慌ててその手をつかみ、勢いよく握手した。
「ぜ、絶対にお手紙書きます!私の話ばっかりになると思いますけど!」
そこへ、二人の後を追ってきたエイビントが口を挟んだ。
「返信するの面倒でしょう。俺には手紙なんて書かなくていいですから。」
クラリスはユジェニの手を握ったまま、振り返って彼を見た。
「私がベルベルさんに手紙を書くと思ってるんですか!?」
「書くでしょう。どうせ試験で優秀な成績を取って新聞に載って、私みたいな有名人と知り合いだってことを自慢するためでしょうから。」
そう言いながら、彼は想像しただけで疲れたと言わんばかりに肩をすくめ、さらに余計な一言を付け足した。
「一度でも俺の手を握ったことがあるって、どこへ行っても自慢するに決まってますよ。……正直に言って、困ります。わかっていますよね?私は、あなたのような乱暴な女性と同類に見られるのは御免なんです」
「…………」
「ですが、推薦状だけは所定の修道院へ必ず送ってください。あなたが“恩人”だと名乗るなら、そのくらいは当然でしょう?」
そこまで言い切ると、エヴィントは言葉を打ち切り、何か急ぎの用でもあるかのように、足早に修道院の奥へと戻っていった。
「……はぁ、ほんとに」
クラリスは小さく首を振り、苦笑いを浮かべながらユジェニを見やる。
「ベルベルさんが、ユジェニを困らせないといいんだけど……」
「私は、誰かに虐げられて生きるような性分ではありませんよ」
そう答えながら、彼女は軽く肩をすくめ、先ほどまで握っていた手を、そっと解いた。
「気をつけて行ってください」
「うん。じゃあ……また、いつか会おうね?」
春の風に背中を押されるように、別れの言葉はやわらかく空へ溶けていった。