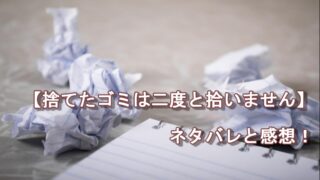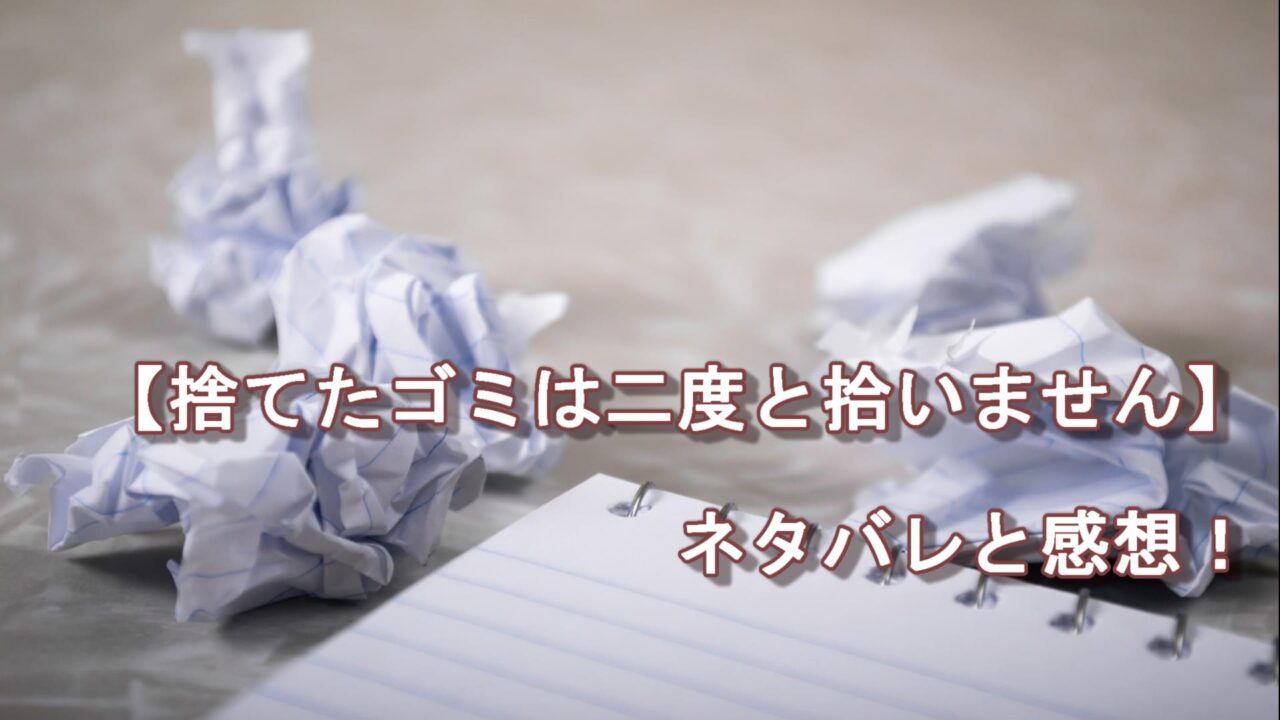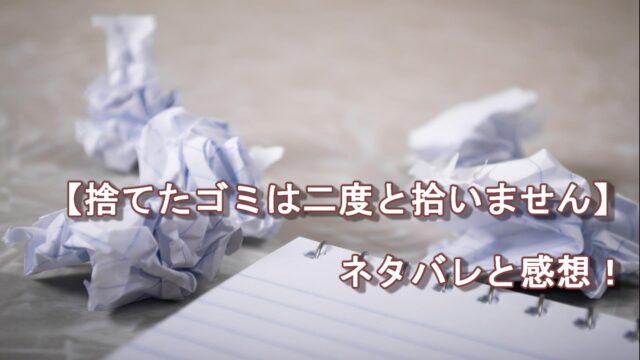こんにちは、ちゃむです。
「捨てたゴミは二度と拾いません」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

103話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 新年祭③
新年祭の記念パーティーは全3日間行われた。
初日に開かれるパーティーには、外国の使節団と皇族、そして侯爵以上の高位貴族たちのみが参加できる。
2日目に開かれるパーティーからは、招待状を受け取った貴族であれば誰でも参加できた。
つまり、私が参加するパーティーはたったの2つしかないということ。
ところがカリアンは、なんとドレスを4着も送ってきた。
まさか次の新年祭でも着てほしいという意味だろうか?
流行に敏感なタイプではないから、そうとも思えないが、やはり少し戸惑ってしまった。
「どれを選べばいいのかしら?」
「ほんと、4着ともすごく素敵だよ。」
一方、サラとネスは興奮した様子で顔を輝かせながらドレスを眺めていた。
「男爵様が男爵になってから初めて参加するパーティーなんだから、目立つように派手に着こなすべきよ!」
ネスの言葉に、サラが口をとがらせた。
「何もわかってないわね。男爵様は普通の貴族の恋人じゃなくて、なんと男爵様よ!だからこれくらいきちんとした装いをしなきゃ!」
「でも、華やかなのもいいと思いますけど。男爵様はどう思われますか?」
「私はサラの意見に賛成だよ。」
私の返事にサラの顔がパッと花のように明るくなり、ネスは黙り込んだ。
「じゃあ、このドレスが良さそうですね。」
サラが選んだのは、4着のドレスの中で最も派手に見えるドレスだった。
あの中ではそれだけが控えめとはいえ、そのドレスにも宝石とフリルがふんだんにあしらわれていて、パーティードレスとしては申し分なかった。
ボリュームのあるフリルドレスの上にショールタイプのコートを羽織ることで保温性も高められ、ドレスのシルエットもより引き立っていた。
ネスとサラの助けを借りてドレスを着たあと、髪は高く束ねてピンでしっかりと固定する。
「ドレスが上品だから、アクセサリーは華やかにしてみてはどうでしょう、男爵様?」
「でも、アクセサリーがあまりにも派手だとバランスが悪くなるかも。」
「そうなんですね。」
ネスは少し気まずそうにして言葉を引っ込めた。
「それでも、アクセサリー1つぐらいはいいでしょう。」
「そうですよね?」
いつの間にか機嫌が直った様子のネスが明るく笑いながら、冷蔵アクセサリーボックスを持ってきた。
「イヤリングもいいですが、私はネックレスが一番似合うと思います。オフショルダーのドレスなので、ネックレスがよく映えると思いますし。」
「ごめんね、ネックレスはもう決めてあるの。」
「どんなものですか?」
私はドレッサーの引き出しを開けて、以前カリアンから誕生日プレゼントとしてもらったネックレスを取り出した。
かなり前にもらったものの、ドレスを着る機会がなかったので、それまで一度も着けたことがなかった。
普段着に合わせるにはあまりに豪華すぎたのだ。
「わあ、素敵なネックレスですね。プレゼントでもらったんですか?」
「うん。皇帝陛下が誕生日プレゼントにくださったの。」
「まあ、皇帝陛下が男爵様に誕生日プレゼントを?」
ネスの目が細くなった。サラも口元をきゅっと引き結んで、笑いをこらえていた。
みんな、なんでそんな反応するの?
「どうしたの?」
「なんでもありません。そうよね、サラ?」
「そうね、なんでもないわ。」
なんだか、何かある気がするけど……。
「わっ、もうこんな時間なんですね。パーティーに遅れるといけませんから、早く仕上げてくださいね、男爵様。」
急いで支度を済ませた後、レティコルと扇子を手に取り、皇宮へ向かう馬車に乗り込んだ。
皇宮の入り口には多くの馬車が並んでいた。
すべてパーティーに参加する貴族たちの馬車だった。
「アステル男爵様ですか?」
馬車を降りた途端、誰かが近づいてきた。
仕事中に何度か見かけたことのある男性だった。
ええと、名前は……。
「ミレノ公爵。」
出納部の管理官、エルペン・ミレノだった。
「今年もブルードラゴンの加護が男爵様にありますように。」
「公子にもブルードラゴンの加護が共にありますように。」
新年に初めて会ったときに交わす儀礼的な挨拶だった。
「新年祭のパーティーに参加されるようですね。」
「はい、公子もパーティーに参加されるようですね。」
「そのとおりです。」
エルフェン・ミレノは私の目の色を伺いながら微笑んだ。
「何か言いたいことがあればおっしゃってください。」
「実は、今日のパーティーに私一人で出席することになってしまって……だから……その……」
しばらく口ごもっていたエルペン・ミレノは、ついに目をぎゅっとつぶって叫んだ。
「わ、私と一緒にパーティーに参加していただけませんか?」
「それはできません。」
答えたのは私ではなく、別の人物だった。
エルペン・ミレノはびっくりして振り返った。
その場にふさわしくない視線でこちらを見ていたのは、デロント男爵だった。
デロント男爵はエルペン・ミレノのすぐ後ろまで近づき、こう言った。
「アステル男爵は私と一緒にパーティーに参加する予定です。」
「そ、そうでしたか。」
エルフェン・ミレノは目に見えて落胆しながら身を引いた。
デロント男爵が腕を組みながら鼻で笑った。
「見る目はあるんで。」
「男爵?」
私が呼ぶと、デロント男爵が微笑みながらこちらを見た。
「道が少し混んでいました。長くお待たせしましたか?」
「私も今来たところです。」
「よかったです。ところで、アステレ男爵。どうしてそんなに素敵に着飾っていらっしゃるんですか?あまりにも輝いていて、目がくらんでちゃんと見られませんよ。」
気恥ずかしくなるような言葉に、思わず顔が赤くなった。
「驚かせないでください。」
「驚くなんて、とても本気なんですけど。」
デロント男爵は明るく笑いながら、片方の手を胸に当て、もう一方の手を私に差し出した。
「アステル男爵、私にあなたをエスコートする栄誉をいただけますか?」
私は微笑みながら、デロント男爵の手の上にそっと自分の手を重ねた。
「こちらこそ光栄です。」
・
・
・
会場はにぎやかだった。
片側には食欲をそそるフィンガーフードがあり、もう一方には疲れた人のための小さな休憩スペースが設けられていた。
ホールの中央ではオーケストラが美しい曲を演奏しており、その周囲ではカップルたちがダンスを踊っていた。
「シャンデリアがすごく明るいですね。」
舞踏会場をぐるっと見渡したデロント男爵が小さくつぶやいた。
「フィンガーフードの種類も思ったより少ないし、シャンパンにはどうして取っ手がついてるんでしょう?これじゃ酔っ払う人が出たらどうするんですか。」
不満をぶつぶつ言っていたデロント男爵が、ふいに感嘆の声を上げながら私に手を差し出した。
「申し訳ありません、アステル男爵。つい職業病が出てしまいました。」
「大丈夫です。私も同じことを考えていましたから。」
「それは嬉しいですね。」
同じ仕事をしているからか、デロント男爵とは話が尽きなかった。
彼が気さくに話しかけてくれたおかげで、彼との会話が楽しかった。
彼と笑いながら話していると、背後から視線を感じた。
振り返ると、じっとこちらを見つめているフィレンの姿が目に入った。
私はフィレンと目が合った瞬間、そっと視線を逸らした。
フィレンが怖かったわけでも、怖気づいたわけでもない。
私は、ほんの些細なことであっても彼と関わりたくなかったからだ。
フィレンを避けたかったけれど、あまりに堂々とした態度に気後れしてしまった。
周囲の人々も私とフィレンをちらちら見ながらひそひそ話していた。
「ウィリアム公爵閣下、さっきからアステル男爵しか見ていませんね。」
「私はかつて婚約者でしたから。それに聞いたところによると、まだアステル男爵に想いを寄せていらっしゃるようですよ?」
「まあ、本当ですか?見た目よりもウィリアム公爵閣下は一途なんですね。」
フィレンが一途だなんて。
私の知らない間に「一途」の意味が変わったのかしら。
フィレンが何をしたのか分かっているのに、ああも堂々とした態度を取ることに唖然とした。
しかも、フィレンと関係があるように見えるのも腹立たしかった。
背中に突き刺さる彼の視線も不快だった。
こんなときは席を外すのが賢明だが、カリアンがまだ来ていない以上、ホールを出るわけにもいかない。
そして、フィレンのせいで席を外すというのもプライドが傷つく。
――だから耐えよう。
どれだけひそひそ言われても、フィレンがじっと見てきても無視して耐えよう。
そう決意したものの、それは簡単なことではなかった。
噂話なら聞き流せばいいが、問題はフィレンの執着した視線だ。