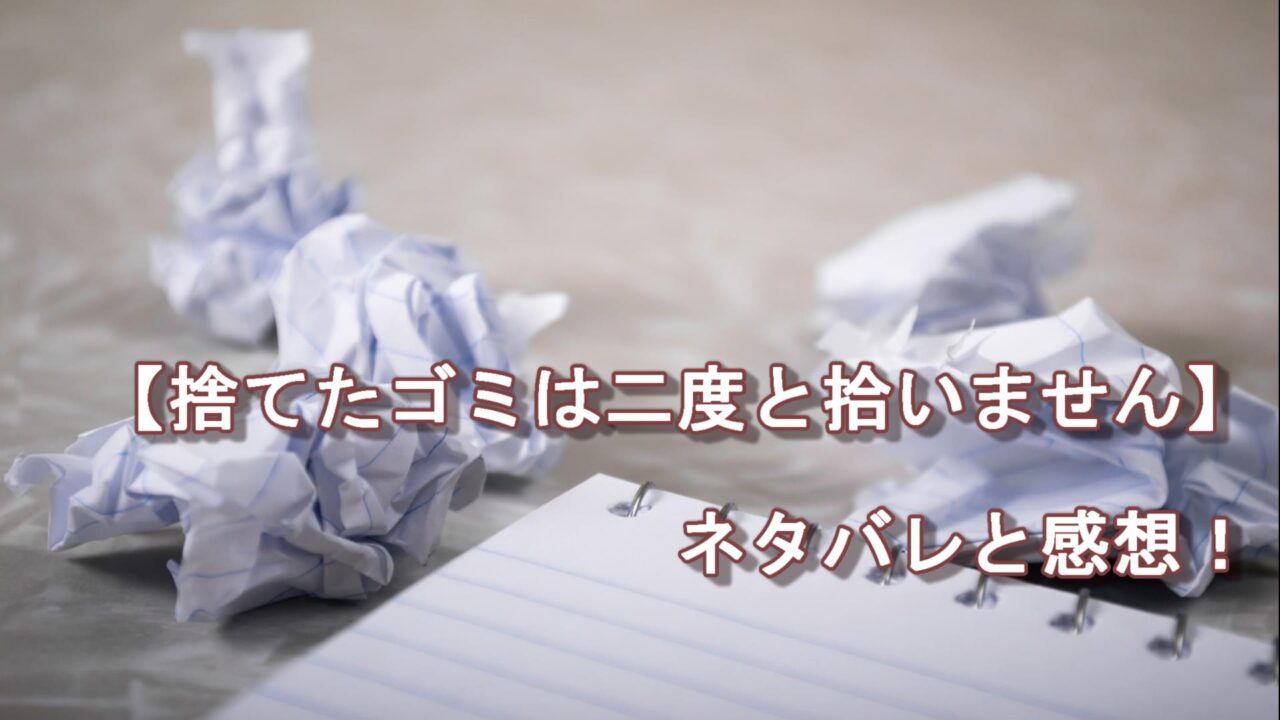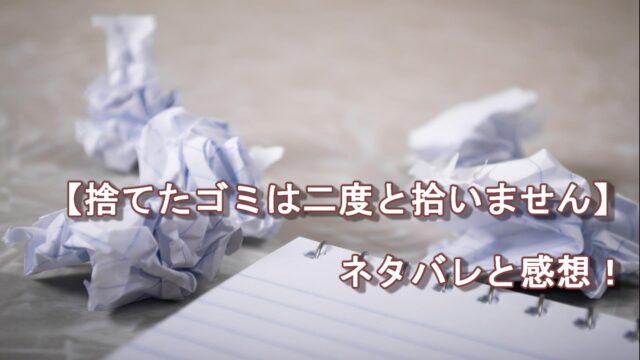こんにちは、ちゃむです。
「捨てたゴミは二度と拾いません」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

107話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 新年祭⑦
カリアンは「気にしなくていい」とは言ったが、それでも心を楽にするわけにはいかない。
体が重く感じられた。
心の中に重い石を乗せられたような気分だった。
まさか、陛下が私のことを好きだなんて——。
まったく予想していなかったことなので動揺してしまい、どうすればよいのかわからなかった。
以前のようにカリアンに接することができなかった。
彼の顔を見るたびに心臓がドキドキして、逃げ出したくなる思いだけが募っていく。
『新年祭の期間でよかった。』
もしそうでなければ、一日に少なくとも二回はカリアンに会わなければならなかったはず。
私は新年祭の期間中、本来皇后が行うべき仕事をクラウド公爵夫人の代理として引き受けていた。
それは今日も同じだった。
「アステル男爵、これを外宮の出納部に届けてくれますか?」
「はい、わかりました。」
「それから、戻ってくるとき……」
私はクラウド公爵夫人の依頼を丁寧に聞いて、彼女が差し出した書類を受け取った。
「すぐに実行いたします。」
「お願いね。ああ、それともう一つ。あとひとつだけ済ませたら、あとは退勤してもいいわ。」
「でも、まだやるべきことが……」
「大丈夫よ。ほとんど終わったから。だから、戻ってこなくていいから、すぐ退勤してちょうだい。私もこれだけ終わったら邸宅に戻るつもりなの。」
「かしこまりました。」
私は公爵夫人に挨拶をしてすぐに外宮へ向かった。
外国の使節団の到着や新年祭など、さまざまな理由で最近外宮はずっと騒がしかったが、今日は静かだ。
新年祭の儀式や祭礼に出席するなど、各部署が業務のため席を外していたからだ。
カリアンとデロント男爵もブルードラゴンとの儀式に出席するため席を空けていた。
私は最初に出納部に入った。
役人たちの多くは儀式に参加していて席を外していたが、一人だけ残っていた。
「クラウド公爵夫人から預かった書類です。」
「ここに置いていってくだされば大丈夫です。」
「それと……」
私は出納員と宮廷事務部などの部署を回ってクラウド公爵夫人に頼まれたことをすべて終えた。
これでまた宮中に戻って荷物をまとめて退勤しなければ。
軽い気持ちで長い回廊を歩いていたその時だった。
トン、トン、トン、トン──
噴水から黄金色にきらめくボールが飛び出してきた。
私は無意識のうちに、目の前に転がってきたボールをつかんだ。
「誰が投げたんだろう?」
ボールの持ち主を探そうとあたりを見回していると、バシャッと噴水がもう一度揺れた。
ボールが転がってきた方向とは反対側だ。
噴水から出てきたのは、クラウド公爵夫人のように明るい青色の髪のカールを持った少年だった。
つまり、その特徴からして皇族ということだ。
カリアンとクラウド公爵夫人を除いて他の皇族は一人しかいなかったため、私はその相手が誰なのかすぐにわかった。
「ヘス・ド・チェフェル・ユスベルディア殿下に謁見いたします。」
私はお辞儀をして丁重に挨拶した。
ようやく私に気づいたのか、少年は一瞬止まった後、微笑んだ。
「私のことがわかるのか?」
「もちろんです。」
「私は君を知らないけど。」
「私の名前はレイラ・アステルです。」
「レイラ・アステル?」
何度か私の名前をつぶやいていたヘス皇子が、突然手を叩きながら明るく笑った。
「おお、君が兄上が大切にしているというあの補佐官なんだね。」
皇帝陛下がそんなことをおっしゃったのか。
恥ずかしさを感じながらも、一方ではヘス皇子がカリアンと親しいことに驚いた。
それもそのはずだ。
カリアンは自らが皇位継承に関係ある者たちを粛清し、生まれたばかりの赤ん坊に至るまで皇子をすべて殺した。
だが、先代皇后の息子であるヘス皇子は、彼の立場から見れば最も“関係ある”存在のはずだったのに、生き延びたのだ。
なぜこの皇子だけを生かしておいたのか?自然と気になってくる。
きっと特別な理由があったのだろう。
思ったよりは気楽に過ごせるかと思ったが、なぜかぎこちない空気が残った。
玉を手にしたヘス皇太子が私をじっと見つめた。
好奇心に満ちた瞳だ。
「君の名前はアステル男爵だと言ったか?」
「はい、皇太子殿下。」
「今どこへ行くところだった?」
「内宮へ戻るところでした。荷物をまとめて退勤しようと。」
私の答えにヘス皇太子の目が輝いた。
「退勤するということは、今日やるべきことはすべて終わったという意味か?」
「はい、そうです。」
「それじゃ、君の時間を少し借りてもいいかな?」
「わ、私の……時間ですか?」
領門の帽子の縁から顔を出したヘス皇子が、明るく笑ってボールを差し出した。
「僕とキャッチボールしよう。」
・
・
・
木々が生い茂った森に囲まれた広大な池。
その水面に降り注ぐ日差しがまぶしかった。
ここはまさに帝国を守る“ブルードラゴン”が眠る池。
『本当に眠っているのかどうかは誰にもわからない。』
実際に見た人はいないのだから。
あとで機会があれば、湖に潜って確認してみようか。
そんな馬鹿げたことを考えながら、カリアンは静かな湖面を見つめていた。
ここは神聖な領域で、ブルードラゴンの祝福を受けた皇族しか入ることができないため、カリアンは一人だった。
外では、彼が湖の水をくんでくるのを待ちながら、ブルードラゴンに捧げる儀式の準備を熱心にしているはずだった。
外国の使臣たちは、その様子を興味深く眺めていることだろう。
「本当に無意味な儀式だ。」
ブルードラゴンへの祭祀は年に二回行われる。
新年祭と秋の感謝祭である。
新年祭は「今年も一年よろしくお願いします」という意味で、秋祭りは今年も農業がうまくいったことに感謝する意味で祭礼を行った。
それ以外に切実な願いを祈ることもあった。
「あなたにお願いしてみても、あなたは何もしてくれない。」
冷たい冬の風にうなだれた木の枝がサラサラと揺れた。
「もしあなたが望むことを叶えてくれていたら、あんなことは起きなかったでしょう。」
カリアンは小さくつぶやきながら、片膝をついて池に瓶を沈めた。
「私もまた、そんな罪を犯さなかったでしょう。」
すると瓶を中心に小さな波紋が起こった。
その様子はまるで静かに眠るブルードラゴンがカリアンの言葉に答えるかのようだった。
「もしあなたが本当に存在していて、だからこそ私たちの言葉を聞いているのなら。」
瓶に水がいっぱいになると、カリアンは席を立った。
「どうかあの子を守ってやってください。」
カリアンはもう一度静かな湖に背を向け、言葉を続けた。
「私とは違って、あなたの血を色濃く受け継いだあの子を。」