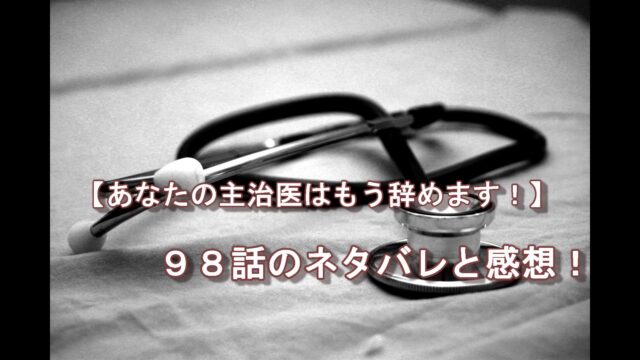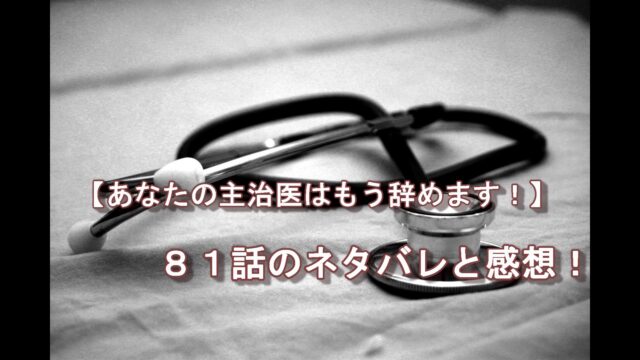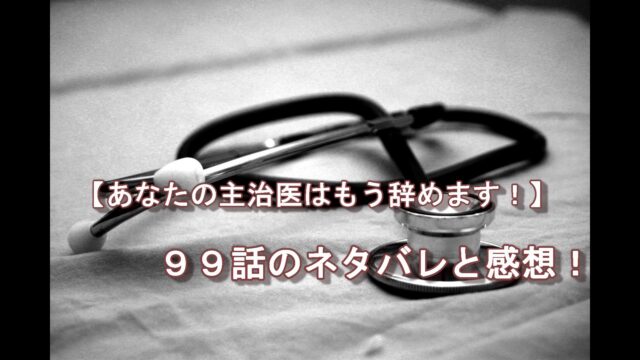こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

153話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- プロポーズ
「リチェ、本当に久しぶりだね。」
「え……一週間ぶりなんですけど。」
「それでもすごく長く感じるよ。毎日一緒にいたときもあったのに。」
お母様はため息をつきながら、私の髪を優しく梳かしてくれた。
私は少し休みを取って、セルイヤーズ公爵城に来ていた。
首都とセルイヤーズ公爵領を結ぶ道路が完成して、今では馬車を急いで走らせれば1時間ちょっとで到着するようになった。
もちろん、エルアンはまるで狂ったように黒馬を駆って全速力で走れば、はるかに速く行き来することができた。
しかし、私は特にそんな必要性を感じなかったので、いつも馬車に乗って楽に移動している。
「それで、エルアンが今いないけど……連絡もせずに来たの?」
「はい、わざと連絡せずに来ました。」
私は3日前からエルアンが城の騎士団と共に辺境の視察に行っていることをすでに知っていた。
予定通りなら今日の午後には戻ってくるはずだ。
「渡すものがあって……でも、ちょっとかっこよく渡したかったんです。」
母は私の計画を聞いて驚いたようだった。
「そうね、リチェ。やりたいことは何でもやりなさい。そして……」
「そしてですか?」
「私はこれから本格的に勉強を始めるわ。ああ、忙しくなるわね。」
「勉強ですか?」
お母様が何を勉強するのか聞いて、私は目をパチパチさせて、ぎこちなく笑うしかなかった。
「じゃあ、お母様……エルアンが来たら、お願いできますか?」
「はあ……」
お母様はハンカチをぎゅっと握りしめ、悲しそうに中腰になった。
「本当にあなたはエルアンにとても甘いわね。」
「知っていますよ。」
私は笑いながら答えた。
「それなら、とても愛しいですね。」
エルアンは午後の日差しが暖かく庭園に降り注ぐ頃、公爵邸に到着した。
さっぱりとした服に着替えた後、イザベルに簡単な挨拶をしに行ったところ、イザベルは普段よりもはるかに多くのカタログを横に積んでいた。
「お母様、ただいま戻りました。」
「それで?」
彼がちらりと視線を投げると、イサベルは慌てて山積みのカタログをすべてテーブルの下に放り投げた。
エルアンは唯一目の前のカタログに記載された年度が2年前のものであることを確認するしかなかった。
「特に問題はなかった?」
「はい、ではお休みください。」
「ちょっと待って。私は何か用があったんだ。」
イサベルはエルアンに小さなメモを手渡した。
「部屋を出たらすぐに開けて見なさい。」
エルアンは戸惑いながらも、小さなメモを受け取り、イサベルの部屋を出た。
部屋を出てすぐ、イサベルの指示通りにメモを開いて見たエルアンの目が大きく見開かれた。
「私たちが初めて出会った場所へ来てください。」
リチェの足跡を彼が気づかないはずがない。
エルアンは鳥のように駆け抜け、欄干を飛び越えた。
初めてウェデリクの前で草のようにしおれていた彼に、ためらうことなく近づいてきた短い金髪の少女を思い出し、彼の心臓がドキドキと高鳴った。
走りながら、当時庭園の一角にあった子供用ブランコが静かに置かれているのを目にした。
エルアンはボールとその上に置かれた丁寧に折りたたまれたメモを見つけた。
メモの内容(手書きのメモ):
「今は相手にしてもらえないかもしれませんが、 それでもボール遊びをしたいときは いつでも一緒にして差し上げます。」
エルアンはほとんど呼吸困難になりそうなほど驚愕した。
「こんなにかわいいことをされたら、どうすればいいんだ……。」
メモの裏側には、さらに別のメッセージが書かれていた。
「エルアンと私が一緒にイチゴを分け合って食べた場所へ来てください。」
彼は再び長い足で駆け出し、あっという間に美しい木々が生い茂る丘の上へとたどり着いた。
そこにはイチゴが二つ入った小さな容器が置かれ、その横にはやはり手紙がしっかりと挟まれていた。
「幼い頃、食べさせてほしいとせがんでいたのを覚えていますか?」
「人目がない時なら、たまには食べさせてあげますね。」
追伸:今なら指でつまんで食べさせるのも許可します!
エルアンは、成人してからは自分が先に「好きだ」と言うことができず、ずっと婉曲的な表現で誘惑していたその時を思い出し、密かに笑った。
「もう指先くらいは許されてもいい頃だと思うけど。」
手書きのメモの内容:「エルアンが告白した場所に来てください。」
メモの裏側には、さらに彼が行くべき場所が記載されていた。
エルアンは頭がズキズキするのを感じながら、リチェの研究室へ向かった。
彼女が彼を待っている場所へ…。
彼が突然姿を消した後、主を失い、まるで時間が止まったかのようなあの研究室に、彼が時折こっそり訪れて夜を明かしていたことを知っていただろうか。
彼が破り捨てた婚約証書を見つけて捨てたあの書類の束の中に、小さな箱が一つ置かれていた。
箱を開けると中は空っぽで、ただ一枚の手紙だけが大切に入っていた。
「もう破り捨てた婚約証書ではなく、新しい書類で私たちの関係を正式に決める時が来たのではないでしょうか?」
「はぁ……」
手書きのメモの内容:「いつも一緒に眠っていた場所に、私が一番好きなものをかわいく飾って来てください。」
メモの指示を読んだ彼は、急いで自分の部屋へ向かった。
リチェが一番好きなものといえば、自分の顔だった。
彼は髪をもう一度整え、服装に乱れがないか確認し、顔に何かついていないか慎重にチェックした。
まるで雲の上を歩いているような気分で彼が部屋に入ったとき、リチェはにっこり笑い、彼のベッドの上に座っていた。
「ちょっと待ってください!」
彼女を見た瞬間、抱きしめようとした彼を素早く制しながら、彼女は彼の手を引いて落ち着いた様子で隣に座った。
彼女は小さな手で彼の両頬を包み込み、にっこりと微笑んだ。
「きれいに準備して来たのね。」
「もっときれいにできたんだけど……急いでたから。」
「そうだと思った。」
彼としばらく視線を交わしていた彼女は、ゆっくりと彼の左手を取り、引き寄せた。
そして、彼の薬指に光る指輪をそっとはめた。
エルアンは研究室にあった空の箱にもともと収められていたものが、この指輪だったことに気がついた。
「私の指輪、あまりに高価なものを買ったそうですね。値段を合わせるために、給料を貯めるのに時間がかかったんです。」
リチェは以前、医療研究員としての給料を貯めて指輪を買ってあげるとエルアンに言ったことがあった。
それ以降、何も言わなかったので、エルアンは彼女がその約束を忘れたのだと思って少し寂しく感じていたが、負担になるかもしれないと考え、何も言わずにいた。
「いや……本当に何でも買ってくれればいいのに……」
「ダメですよ。一生身に着けるものですから。」
彼が指輪を見て信じられないような顔をしていると、リチェが穏やかに続けて言った。
「私や私の家族のせいで遠慮して、一生プロポーズできないんじゃないかと思って、だから私がするんです。」
エルアンは心の中で、自分の鈍さを改めて嘆いた。
すべてを知っているリチェが、指輪の約束を忘れるはずがないのに。
「今すぐは無理だけど、ちょうど1年後の今日、結婚するのはどう?今までずっと待っていたの、知ってるよ。」
「僕は……僕は、なんでもいい……。」
彼はしどろもどろに答えながら、言葉を詰まらせて黙り込んでしまった。
「どうしよう。君に告白したとき、僕は急ぎすぎて、こんなに素敵にできなかったのに。」
「そうね。心の準備がまったくできていない人に、いきなり指輪を押しつけるだけだなんて。」
「君が成人になるのを待つのがあまりにも待ち遠しくて、我慢できなかったんだ。本当に我慢するのが大変だったよ。」
「そんなことを我慢したって死にませんよ。どうせ急ぐこともないので、ゆっくり準備しました。当然受け入れてもらえるかわからないので、緊張もしていませんでしたし。それに、心の中で悩んでしまった分、入る空白も似たようなものですよ。」
しっかりとしたリチェの言葉に、エルアンは結局また笑ってしまった。
「もちろん、お母さんも手伝ってくれましたよ。」
「あ、そうなんだ……。」
「はい?」
「さっき、お母さんが3年前のカタログを集めていたと言っていたから。」
「はい……ウェディングドレスの研究をされていたそうです。3年前からじっくり見て、流行を知ることができると。」
ウェディングドレスを着たリチェを想像するだけでとても嬉しくなり、エルアンは全身が震えるような気分だった。
「これは、最後のメッセージ。」
リチェは、慎重に小さな紙片を直接手渡した。
「これからたくさんの夜を一緒に過ごしましょう。そうすれば、夜よりも怖いものからお互いを守れると思いませんか?」
幼い頃から今まで、この工場で一緒に過ごした日々が頭の中を駆け巡り始めた。
この広くて寂しい部屋でも、リチェの小さな手を握っているだけで、すべてが大丈夫だったあの時と、今が本質的に違うのかどうか分からなかった。
依然としてこの女性がエルアンにとっては世界そのものだったからだ。
「明日連れて行くよ。」
彼はリチェの薄茶色の髪を撫でながら、静かに言った。
「今夜もそばにいて。」
「幼い頃のように?」
「ああ、ダメだ。」
彼女の額に唇をそっと押し当て、彼は笑った。
「もう、手をつなぐだけでは寝られません。」
一生待てると言っていたけれど、残された1年はとても長く、もどかしかった。
エルアンはリチェが息苦しくてもがくまで、決して彼女を離さなかった。
暗闇の中でお互いの肌の温もりを感じながら、囁くような会話が続いた。
「新婚旅行はどこへ行こうか?」
「メイリス公国以外なら、どこでも。」
「結婚式の準備は面倒じゃない?正直、そんなことに気を使うほど暇じゃないし。」
「お母様がきっと全部手配してくれるわ。」
「そうだね。実は、誕生日パーティーの時も最高だった。ものすごく幸せになれそうだ。想像もできないよ。その日、君を見て嬉しすぎて気絶したらどうしよう?」
「私がしっかり応急処置してあげますよ。結婚初日から夫を失うわけにはいきませんからね。気絶する時は頭だけは気をつけてください。」
1年後のことだけれど、その未来を語り合うだけで一晩中起きていられそうな気がした。
甘い未来を夢見る二人の会話は途切れることなく続いていった。
「朝起きたら、すぐここで食事ができるようにするね。君は朝が弱いし、朝食もそんなに食べないし。」
「あぁ、いいですね。」
「それから、毎日遅れずに首都まで送っていくよ。もちろん、仕事が終わったら迎えにも行く。どんなに遅く帰ってきても、外泊はダメだよ。私、眠れなくなっちゃうから。」
「お父さんは少し寂しくなるかもしれませんけど、でも平日はずっと一緒に働いているから、きっと良い息子さんですよ。」
「そうだな。俺も涙をこらえて、20時間の拘束を覚悟したんだ。」
エレアンはそっと息をついた。
「そうだね……人生は思い通りにならないことも多いけど。」
「それでも、幸せな人生じゃないですか?私がいるんですから。」
「もちろんだよ。」
優しく、温かい手が再び腰を抱きしめた。
「そして、これからはもっと幸せな日々だけが残るはずだよ。」