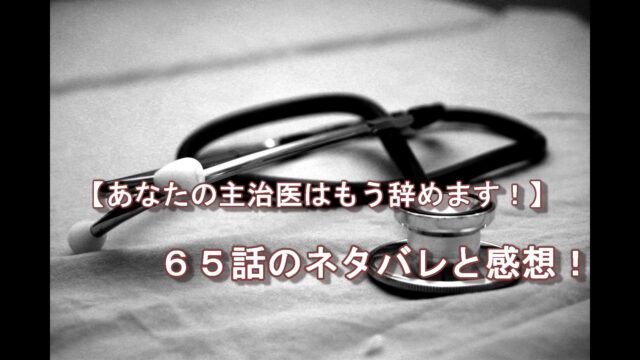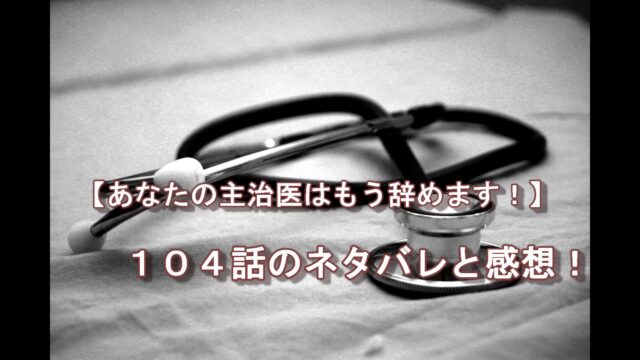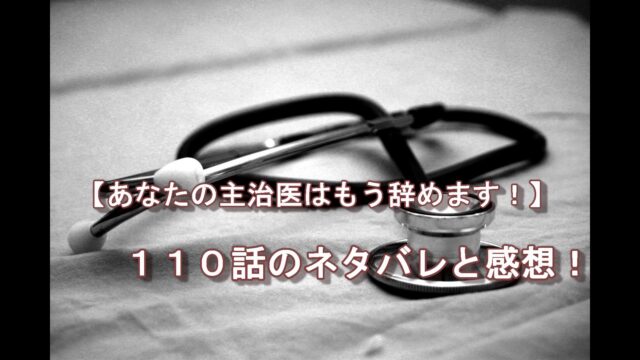こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

162話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- ユリアの宴会②
宴会場に入った瞬間、私は目を見張りました。
普段のだだっ広い空間ではなく、きらびやかな装飾があちこちに施されていて、まるで絵本に出てくる妖精の森のようだったのです。
使用人たちが忙しく立ち働く中、私を見つけた父が瞬く間に駆け寄ってきました。
「ユリア!」
一瞬で視線が高くなりました。
「先に来ていたのか。明日、完成した姿を見ながら、大好きな顔を見たかったのに。」
父の低く落ち着いた声を聞くのが好きで、私はにこにこと笑いながらしがみつきました。
父は私を抱いたまま仕事を始めました。
宴会場にいても人々が次々とやって来て、父に話しかけます。
「イレピス子爵の件は、前に言ったとおりに処理して、騎士団の配置は三案に変えておけ。」
ともかくセレイオス領地は広く、父は上に立って隅々まできっちり管理する性格なので、いつも忙しそうでした。
あの執事もそうでした。
けれど父は、私が会いに行くたびに一度も面倒くさそうな顔を見せたことはありません。
「密輸団は馬車の中から出てくる手筈だ、計画を立てろ。」
先ほど私を抱き上げてくれたときの優しさとは正反対に、部下たちへ指示を下す父の声は低く冷ややかでした。
「ネズミのような密輸どもは、今回は私が直々に処断する。入念に準備しろ。」
私は父に抱かれたまま、うっとりと笑いました。
実際には何の話か理解できなかったのですが……雰囲気というものがありますよね。
落ち着きと威厳に満ちた口調、明確な命令、ただそこにいるだけで感じる圧倒的な威圧感。
――やはり、父に似ていると言われるのも悪くないと思いました。
受け継がれないとは思えませんでした。
特に兄が母の後を継ぐなら、この領地は私が受け継ぐ可能性が高いのですから!
だから黒い髪以外にも、自分が父に似た部分を探してみようと思いました。
「お父さま。」
私は父にしがみつきながら言いました。
「お父さまは、六歳のときどんな子どもでしたか?」
「うーん、よく病気をしていて、毎日ベッドに横になっていた気がするな。」
今の父は、ここにいる誰よりもたくましいので、その姿はなかなか想像できませんでした。
「まあ、よく覚えてもいないし、覚えたいとも思わない子ども時代だな。」
私もまたとても丈夫だから、六歳のときの父と似ているのでしょう。
似ている点はない、と言わざるを得ませんでした。
父は柔らかく笑みを浮かべ、言葉を続けました。
「だから、記憶がはっきりしているのは十一歳からなんだ。」
「十一歳の時にはもう治ったのですか?」
「いや。」
父は大きな手で私の髪を撫でました。
「そのときに君の母さんに出会ったんだ。」
ああ……やはり母を思い出しているから、あの表情になってしまったのですね。
「……こうして話していたら、急に会いたくなったな。退勤まであとどれくらいだ?」
父は急に真剣な顔になり、そばに立っていたジケルに鋭く言いました。
「ジケル、セレイオスで一番速い競走馬をリチェの馬車に繋ぐのはどう思う?」
「競走馬を馬車に繋げば、乗る人の体がとんでもなく揺れるかと存じますが。」
「ではセレイオスのすべての工房に投資しよう。競走馬を繋いでも揺れのない馬車を開発するように。」
母の出退勤時間を短縮できる、という考えにすっかり夢中になった父は、そのときばかりは誰よりも熱心に言葉を次々と吐き出しました。
「もちろん馬車の内装はもっと柔らかくしなければならないし……馬車の内装デザイナーも探さねば。競走馬を操れる御者も雇う必要があるな。もちろん長期プロジェクトになるだろうから、少しずつ始めないといけない。ああ、子どもの頃から育ててみるか?」
「かなりの長期プロジェクトになると思いますけど……」
「リチェの出退勤時間が10分でも短くなるなら、10年かかっても構わない。」
「……」
父の切実そうな表情を見て、私は心に決めました。
もし誰かに「お父さんにそっくりだね」と言われたら、きっとあまりいい気分ではなかっただろう、と。
仕事がどんなにできて外見が立派でも、母の名前が出るだけで我を忘れる姿は、誰の目にも明らかでした。
私は父のような男性を夫にするのは良くても、父のような妻には絶対なりたくありませんでした。
そういえば、おばあさまも恋愛には一生懸命だったって言っていた気がする……。
お父さまはおばあさまに似たのだろうか?
「降ろして、パパ。」
「ん?もう?」
私は気まずくなって、お父さまの腕から降りた。
お父さまはあんなにもお母さまを愛しているのだから、私よりもずっとお兄さまを可愛がるに違いない。
なぜなら、お兄さまはお母さまにそっくりだから。
その夜、私はひどく悲しくて、お母さまが帰ってきた後も眠ったふりをして部屋から出なかった。
お母さまとお父さまが、眠っているふりをしている私の髪を撫でたり、頬にキスをしてくれても、気づかないふりをしていたのだ。
ソンは翌日にある母の表彰式の祝賀宴のために夜遅くまで忙しくしていたが、宴会そのものにはあまり期待していませんでした。
誰もが兄を見ては「やっぱりリチェ様に似た天才だ!」と叫ぶばかりなのです。
私はおばあさまにも似たくないし、お父さまにも似たくない……。
やはり、いつまでも幸せな子どもでいられるはずはありませんでした。
私は世界一不幸な六歳児となり、大きくため息をつきながら眠りについたのです。
あらゆる馬車が侯爵邸に集まり始めました。
公爵城でこんなにも多くの客人を迎えるのは初めてで、私と兄は城壁にしがみついて見物するのに夢中になっていた。
「ふむ、あの人の歩き方はずいぶんおかしいな。オスモ症候群かカリカス病の後遺症みたいだ。」
もちろん兄は一人ひとりを見ながら、あらゆる病名を口にするのに忙しかった。
「それって、遠くから見ただけでわかるの?」
「うん。」
兄は私の頭を撫でながらにっこり笑った。
「僕は天才だからね。」
「……。」
そこに混ざれず、悔しくて死にそうでした。
けれども、公爵邸に来た客の中には同年代の子供たちも多く、すぐに楽しくなりました。
お兄さまは相変わらず本を抱えて部屋に引きこもってしまい、他の子供たちの顔すら見ませんでしたが。
私は新しく出会った子供たちと庭園を駆け回り、かくれんぼや鬼ごっこをして久しぶりに心から楽しむことができました。
「セレイアス公女様、今度ぜひ私たちの屋敷にも遊びにいらしてください。」
なんと、かなり可愛らしいバラス公爵家の令息が私を招待してくれたのです。
「公女様のお好きなケーキをたくさん用意しておきますね。」
もちろん、私はそんな状況にすっかり舞い上がってしまいました。
宴会の日取りが決まってから、父は私に厳しく教育を施しました。
――「ユリア、もし宴会の時にまた男の子が君に親切にしてきたら、こう答えるんだ。」
「どう親切にするのが“親切”なんですか?」
――「うーん……君を招待するとか、美味しいものをくれるとか、可愛いだの綺麗だのと褒めながら隣にぴったりくっついているとか。とにかく、そういうやつが現れたら……」
バラス公爵の嫡子は、父が挙げた三つの条件すべてに当てはまる男の子でした。
だから私は、父に教わったとおりに答えたのです。
「でも、私がセレイアス公爵邸を出るその瞬間から、父がずっと隣にいることになりますけど……それでも大丈夫ですか?」
その言葉に、バラス公爵令息の表情がわずかに引きつりました。
まあ、私の父の顔立ちは少しきついですからね。
格好良いことに違いはありませんが、母や私以外の人を見るときに眉間に皺を寄せると、ものすごく怖く見えるのです。
「特に、令息方からの招待には必ず同行することになりますよ。」
父が淡々と告げると、バラス公爵令息は体をびくりと震わせたような表情を見せました。
私は最後に付け加えました。
「それに、私は顔が整っている人なら好きなんです。身分とかは関係なく。」
バラス公爵家の嫡子のあの顔を見てしまったので、私はもうそれ以上言葉を交わす必要はありませんでした。
午後になると、身支度を整えるため乳母に連れられて部屋へ戻ったのです。
――「確かにイザベル様は首元が美しいですね。リボンを外すと、ずっと映えますよ。」
周囲の人たちは、私があまりにも可愛いと感嘆の声を上げましたが、私はどうにも気分が良くありませんでした。
華やかな服はただ窮屈なだけで、むしろさっきやりかけた鬼ごっこを続けたかったのです。
その時でした。私の部屋の扉が、ノックもなく勢いよく開いたのです。
――「ユリア!」
――「おばあさま!」
そこに現れたのは、セイリン外祖母だったのです!
外祖母はいつものように立派な家族の集まりにふさわしい、整った身なりをしていました。
「今日もとても可愛らしいわね。ユリアのためにお土産を一つ買ってきたのよ!」
「……」
「どうしてそんな期待できないという顔をするの?みんな、どうしたの?」
私を含め、女の子たちは皆、気のない表情で外祖母を見つめました。
なぜなら、外祖母は母や私にいろいろと贈り物をしてくれるのですが、そのほとんどが微妙だったからです。
フリルがやたら多いワンピースとか、やけにリアルすぎるドラゴンの人形とか。
特にファッションに敏感な母は「一体どこでこんな趣味の悪いものを買ってくるの?」とよく言っていました。
外祖母は深く息を吐きました。
「ユリアのために特別に買ってきたミンダルペンギンのフィギュアセットよ!とっても可愛いでしょう。」
「わぁ、ありがとうございます。」
侍女たちまでが、今や哀れむように私を見つめていました。
外祖母はふっと笑みを浮かべると、こう続けました。
「ところでユリア。お前のお兄さんのために買ってきた贈り物なんだけど、受け取ってみる?」
「え?なんですか?」
「子供用の剣だよ。七歳以上に推奨されているものなんだけどね。本当は来年お前に渡そうと思っていたのに……」
外祖母はそう言いながら、私に剣を差し出しました。
「さっきセドリアンの部屋に入ったら、あの子が薬草学の本を読んでいるのを見て、そのまま出てきちゃったわ。」
外祖母の表情には嫌悪感が浮かびました。
「アルガが幼い頃を思い出すわね。」
「えっ?」
「アルガも小さい頃から医学書ばかり読みふけって、つまらないことばかり言っていたのよ。まるでセドリアンみたいに。」
「うーん……お母さんもそうだったんじゃないですか?」
「見たわけじゃないけれど、あなたたちのお母さんは、それでも可愛らしかったはずよ。でもセドリアンは……妙な子ね……」
外祖母は咳払いをして、深いため息をつきました。
「リチェよりはアルガがあの男に似ているみたいだね。私がその不愉快な状況を避けるために名前に『セ』の字まで入れたっていうのに。」
「ねえ、外祖母。」
「なに?」
「外祖母はどうして外祖父を嫌っているのですか?」
「嫌っているんじゃなくて、ただ顔を合わせたくないだけよ。普通の嫁姑の関係ってやつさ。」
外祖母はにっこり笑いながら言いました。
「それでも血縁だからって、ぐちぐち言ったり、だらしない姿を見ると腹が立つのよ。悪口を言うのも私じゃなきゃいけない。まあ、そういうこと。あんたとセドリアンみたいなものさ。仲はいいんでしょう?」
「最近、お兄ちゃんが変なんです。」
妙なことでした。
お母さんやお父さん、そしておばあちゃんには言えない胸の内がこぼれ出し始めたのです。
たぶん、お兄ちゃんに親しい人ができたからだと思いました。
「前は私にすごく優しかったのに、文字を覚えてからは本ばかり読んでいるんです。いざ一緒に遊んでも、患者の話ばかりしてつまらないんです。」
「なるほど。」
外祖母が険しく眉間にしわを寄せました。
「そのまま抑えられなければ、アルガみたいになってしまうね。大変なことだわ。下手すれば使命感に取り憑かれることになる……結局、恨みを抱えたまま生きれば、一生損をする人生になるのさ。」
「外祖母は医学が嫌いなんですか?」
「私が好きなのは人を傷つけることだよ。傷を治すことじゃない。」
私の質問に外祖母はためらいもなく答えました。
「私は草むらを見ると虫が嫌いでね。剣で全部なぎ払って消し去りたくなるんだよ。」
私は思わず、外祖母がくれた子供用の剣をぎゅっと握りしめました。
どうやら私は、やっと自分の似ている人を見つけた気がしたのです。
「ねえ、外祖母。」
「なに?」
「私に剣を教えてください!」
「今?」
外祖母の目が大きく見開かれました。
「演会は二時間以内に始まるはずでしょう?」
やっぱり駄目かなと思って肩を落としかけた時、外祖母がクスクス笑い始めました。
「とてもいいじゃない!絶好のタイミングよ!さあ、早く!」
侍女たちは私たちを止められませんでした。
私はドレスの裾を持ち上げて、外祖母のあとをちょこちょこと追って行きました。
「ユリア!ここで何をしているの?」
演会が始まる直前、お母様が私を迎えに来られたのです。
祖母は庭園までいらっしゃいました。
私はちょうど外祖母から剣を習っている最中でした。
「リチェ、すまない。」
外祖母は心から母に申し訳なさそうな表情を浮かべて謝りました。
「どうやら、これからはお前が私の愛情を受ける第一位から外れてしまう気がする。」
「え?それはどういう意味で……?」
「これからの第一位はユリアだ。ごめんね。」
母は傷ついたというよりも、あまりに突拍子もない言葉に驚き、私たち二人をじっと見つめました。
「こんなに大切に育ててみたいと思えるのは、エリザベスを育てていた頃以来初めてだよ。」
「エリザベスって誰ですか?」
「私が十歳の時に育てた長寿風筝よ。」
一瞬、外祖母が隠していた娘なのかと思ったけれど、そうではなかったのです。
お母様は私の剣を見つめながら、ゆっくりと言いました。
「……まさか?ユリアに剣を教えたのですか?ユリアはまだ幼いのに……」
「私は幼くありません。」
お母様が万が一にも私から剣を取り上げてしまうのではないかと心配で、私は剣をぎゅっと抱きしめて、きっぱりと言い切りました。
「六歳ですから。」
「ふむ。」
お母様は私の瞳をじっと見つめながら、わずかに眉をひそめました。
「六歳なら、まだ過度に筋肉を使う運動は成長に良くないわ。学ぶのは構わないけれど、無理をしないように気をつけるのよ。」
「お兄ちゃんには無理するなって言わないくせに。」
私はつい拗ねたように、足で地面をトントンと鳴らしました。
「お母さんは、お母さんに似たお兄ちゃんだけを可愛がってるんでしょ?」
実際にそんな風に感じたことはなかったけれど、そのときの寂しさがふっと込み上げてきたのです。
外祖母は目を大きく見開き、呆れたように言いました。
「リチェ、もしかして拗ねてるの?でも、あなたがそんな子じゃないはずよ。」
母もまた驚いたように私を抱き上げました。
母のきれいなドレスにシミがついてしまったけれど、母はまったく気にせず言いました。
「絶対にそんなことはないわ、ユリア。お母さんはセドリアンもユリアも同じくらい愛しているのよ。はあ……とにかく……」
母は眉をひそめながら、今にも泣き出しそうな顔をしていました。
「子どもたちと過ごす時間を増やさなければ。私は仕事にばかり熱中しすぎたみたい。エルアンに育児を任せきりにしてはいけなかったのに……」
母ともっと一緒にいたいという気持ちは本当でしたが、私は同時に、多くの人々が母を必要としていることも理解していました。
お父様もいつもそう言っていたのです。
お父様も本当は母とずっと一緒にいたいけれど、母は本当に大切な仕事をしているのだから、我慢して待たなければならないの。
お母さんのおかげで多くの人が助かり、それで表彰まで受けるんだから。
だから私は、こらえて大人のように言いました。
「違うよ、お母さん。お母さんは私と過ごす時間の合間に、一生懸命研究して表彰される立派なお医者さまだよ。」
「……やっぱり。」
お母さんは深くため息をつきました。
「私が受ける表彰には、いつも代償があるのよ……」
「大丈夫。お父さんがいつも一緒にいてくれるから。でも……」
私は母の胸に抱かれながらぐずりました。
「……私はお兄ちゃんみたいにお母さんに似た医学の天才じゃないから悲しいです。みんなお母さんを好きなのに。」
「みんながお母さんを好きなのは本当だけれど、ユリア。」
母は私の髪を撫でながら、そっと囁きました。
「みんながお母さんを好きなのは、お母さんが医者だからじゃないわ。可愛くて優しくて、それで賢いからなの。」
「そうだ。可愛くない医者なんて、うまくやれると思うか?」
外祖母がきっぱりと言い、母は私の頬にキスをしながら続けました。
「だから医学の天才じゃないからといって、悲しむ必要はないんだ。」
「そうだ、アールを見てみなさい。医学の天才ではないけれど、あんなに可愛くて気立てもよく、みんなから好かれているじゃないか?」
私は外祖父に申し訳なくて、何も答えませんでした。
でも、私の顔を見たお母さんがにっこり笑って頬を撫でました。
「うちのユリア、もう気が晴れたのね。悩みがあったらいつでもお母さんに言ってね。お母さんがちゃんと聞いてあげるから。」
「……はい。」
「さあ、それじゃ一緒に行きましょうか?おばあさまが特別に、お母さんとユリアをお揃いのセットにって、サファイアのブローチまでそろえてくださったのよ。」
私は嬉しくて母と外祖母の手を握り、軽やかな足取りで宴会場へ向かいました。