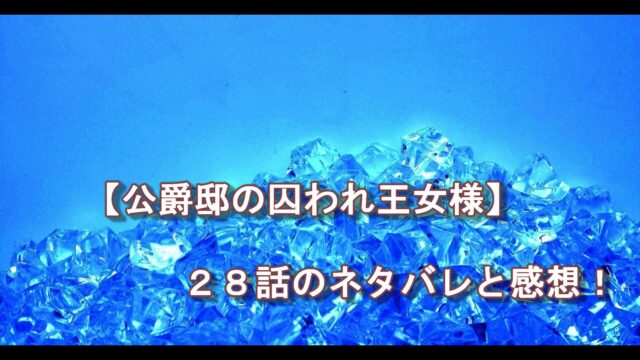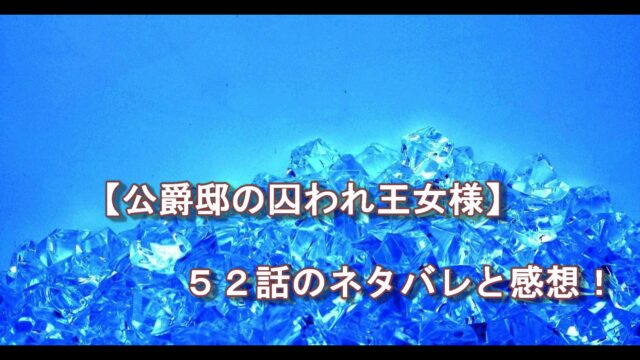こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

129話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 裏切り者②
修道院からしばらく走って戻ってきた書庫だったが、馬車を使えばほんの数分で着く距離だった。
幸いにも、修道院の正門が完全に閉じられる前に戻れたおかげで、クラリスとノアは無断外出を疑われることはなかった。
「魔法使いアストに会えて、結果的にはよかったわね?」
階段を上りながらクラリスがかけた言葉に、ノアは相変わらず不機嫌そうに鼻を鳴らすだけだった。
「全然よくない。胡散臭い男だから、絶対に近づかないで」
「でも……」
クラリスはノアの髪をそっと撫でながら、先ほどの手つきを思い出していた。
過剰なほどに自然で、ためらいのない、どこまでも優しい手。
――あの人は、間違いなく“慣れている”。
そう思った瞬間、胸の奥に小さな違和感が残った。
「……何?」
視線に気づいたノアが、ちらりと睨み返す。
「ううん、なんでもない」
クラリスは慌てて首を振り、視線を逸らした。
ノアはしばらく黙っていたが、やがて小さく息を吐く。
「……ルカのこと、放っておくつもりはないから」
その声音は低く、揺るぎがなかった。
「うん」
短く返しながら、クラリスはポケット越しにモチの存在を意識する。
――動かない。けれど、確かに“いる”。
それだけで、なぜか少しだけ心強かった。
石造りの廊下に二人の足音が静かに響き、夜の修道院は何事もなかったかのように、深い静寂を取り戻していった。
「私は、あの人が好き」
「……!」
「ノアを大切にしてくれるでしょう。はっきり言って、家族のように思っているはずよ」
「そんな家族、私はいらない」
二人は、すでにクラリスの部屋の前に着いていた。
「さあ、戻って体を温めなさい。足がすっかり冷えているでしょう」
「足の感覚が、少し鈍いだけ」
「具合が悪くなったら、必ず呼びなさい。それから今日のことは……いや、後日改めて話す方がよさそうですね」
それにはクラリスも同意だった。
事態が切迫しているのは分かっていたが、凍えるほど冷えきった靴下を、今すぐ脱ぎ捨てたかったのだ。
「分かった。すぐ洗って、ノアの部屋に行くね」
「何だって!?」
クラリスはノアの返事を最後まで聞かず、部屋へ駆け込むと靴を脱ぎ捨てた。
「……あ、やっぱり。足の裏、少し腫れてる」
床に座り込み、指でそっと押す。
「コオ?(大丈夫?)」
モチが心配そうに鳴きながら、ポケットから飛び出して机の上へ着地した。
「うん、平気よ。セリデンでもね、こっそり革靴を脱いで遊んでたら、こうなったことがあって……」
言いかけて、クラリスはふと口を閉じた。
モチが――見知らぬ小さな砂利を、頭の上にちょこんと乗せていたからだ。
「……そ、それ……!」
「コオ?(探してたやつ?)」
モチは一声鳴くと、砂利を机の上に落とした。
それきり役目を終えたと言わんばかりに、体をゆるめて砂粒へと戻っていく。
「……本当に、あったのね」
クラリスはしばらくその場から動けなかった。
落ち着こうとして深呼吸を一つし、初めて見る砂利に顔を近づける。
ひび割れた白。
ごく微かに、魔力の残滓が感じられた。
「……はじめまして」
まるで相手が“聞いている”かのように、クラリスは小さく頭を下げた。
「あなたが……ルカの、痕跡なのね」
砂利は当然、何も答えない。
けれど、その沈黙が、かえって確信を強めていた。
――あの森で感じた“異物感”。
――時間から切り離された、違和感。
「ノア」
背後から呼びかける声に、クラリスは振り返る。
「……本当に、戻ってきてよかったわ」
そう言って微笑むと、クラリスは机の引き出しを開け、布切れを一枚取り出した。
「これ、保管する。ちゃんと」
モチが小さく「コオ」と鳴く。
その声は、まるで――**“それでいい”**と認める合図のようだった。
夜の修道院は静かだった。
だが、その静けさの底で、確実に何かが動き始めている。
クラリスは、まだそれを言葉にできずにいただけだった。
「こんにちは。わざわざここまで連れてきてくれてありがとう。それでね、あなたに聞きたいことがあるのだけれど……もし私が魔力に触れても、平気?」
像から返事はなかったため、クラリスはひとまず慎重に、凍った表面に唇の先をそっと触れさせた。
[……あ、あ?!]
驚いた声と同時に、像の返答が聞こえてきた。
[ひどい人。]
「ごめん。あとで首都へ戻るとき、必ず森を通る道で連れて行ってあげるから。ね?」
クラリスがなだめても、像の態度は変わらないようだった。
[ひどい人。]
「私はね、あなたが見たかもしれない、ある出来事について知りたいだけなの。どんなことでもいいから、話してくれない?」
[ひどい人!]
とげとげしく返ってきたその言葉を最後に、像からはもう返事がなかった。
「……みんなでやらなきゃ。だから、もっと大きな器を」
そう言い終える前に、モチはすでに机の縁まで駆け寄り、両腕を高く掲げていた。
「コオ!コオ!」(はやく! はやく!)
「わかった、わかったよ。」
クラリスは笑いをこらえながら、戸棚からいちばん大きなたらいを取り出した。
水差しからほどよく温かい水を注ぐと、うっすらと湯気が立ちのぼる。
「今度は順番だからね。」
「コオ。」(やくそく。)
モチはおとなしく頷いた。
さっきまでの大騒ぎが嘘のように、慎重に水際へ腰を下ろす。
クラリスは引き出しから小さな布袋を取り出した。
昨夜、大切に保管しておいた――あの白い小石が入っている。
「これも……少しだけ。」
そっと小石を水に沈めると、水面がごく微かに揺れた。
音も、光もない。
それなのにモチは目を丸くして、息をひそめる。
「コオ……」(いる……)
「うん。感じるよ。」
クラリスはたらいの縁に手を置き、しばらく目を閉じた。
水のぬくもり、石の冷たさ、そしてその間のどこかに残る気配。
時間から切り離された残響。
魔法使いの痕跡。
「ルカ。」
その名を呼ぶと、水面がもう一度、静かに波紋を広げた。
モチはじっとその様子を見つめたあと、そっと水の中に入り、小石の隣に身を沈める。
「コオ。」(いっしょ。)
クラリスは何も言わず、静かに頷いた。
部屋に残るのは、水の音だけ。
窓の外では、低く鐘の音が鳴り響いている。
ありふれた朝。
けれど確かに、昨日とは違う今日だった。
クラリスは、その事実を――もう否定しなかった。
「連れてきてくれたでしょう?」
「コオ。(今ではクラリスは、私のことを少しも特別扱いしてくれない)」
「そんなこと、絶対にないわ」
クラリスはモチの頭を指先で軽くトントンと叩き、笑った。
「どの石も、あなたの居場所を奪うことなんてできない」
「……コオ」
「それからね」
クラリスは最後に、昨日拾った石を取り出し、水鉢の中にそっと沈めてやった。
「水、少し冷めちゃったわね。そうでしょう?」
そのあと、前もって用意しておいた熱いお湯を、少しだけ注ぎ足した。
水の流れに合わせて、小石同士がぶつかり合い、まるで楽器のような音を立てた。
再びちょうどいい温度になったのを確かめると、クラリスは頬杖をつき、色とりどりの小石たちが水の中で体を浸している様子を、じっと眺めた。
「かわいい」
石たちは、どうしてこんなにも愛らしいのだろう。
こうして眺めているだけで、思わず笑みがこぼれてしまうほどだった。
「コオ。」
「出るの?ちょっと待って。」
クラリスは、ふわふわのタオルを何枚か持ってきた。
水気を丁寧に拭いてやると、気分がよくなったモチは窓辺へ行き、陽の光を浴びた。
「君たちも出してあげるね。」
クラリスは、幼い頃にノアからもらった赤い石を、まず取り出した。
[ありがとう、少女。]
「ううん、いいの。」
[少女がいつも丁寧に手入れしてくれるから、うれしい。]
「私も好きでやってるんだよ。日向に置いてあげようか?」
赤い石がそれでいいと言ったので、クラリスはそれをモチの隣に並べて置いた。
そのあとは、セリデンの庭やハイデンで拾ってきた石たちを、ひとつずつ拭いて、窓辺やクッションの上、引き出しの中など、それぞれが望む場所に置いてやった。
みんな、クラリスと過ごす“入浴”の時間に、心から満足しているようだ。
たった一つの石を除いて。
[……悪い人。]
その変わらない返事に、クラリスは答えず、引き出しから鑢(やすり)を一本取り出した。
長い間、外で過ごしてきた石には、細かな砂粒が隙間なく入り込んでいるからだ。
クラリスは経験から、こうしたものを丁寧に取り除いてきれいにしてやると、石たちがとても喜ぶことを知っていた。
[わ、私……悪い……]
さらさら。
柔らかな鑢で表面を整えると、石は非難するのをやめた。
クラリスは、石の気分が少し落ち着くのを待ってから、慎重に声をかけた。
「……あるでしょう?」
[悪い!]
さらさら。
[……]
「どうして私をそんなふうに思うのか、聞いてみたかったの。ここへ連れてきたこと以外にも、もし何か悪いことをしていたなら、きちんと謝らなきゃって思って」
[わ、私は……悪い……人と、友だちだから]
「悪い人?」
クラリスは、今度はやわらかな布で、押し出されてきた砂を一粒一粒、丁寧に拭っていった。
[……うん]
クラリスの友だちなら……ノアの話だろうか。
けれど、ノアは少しも悪い人には思えなかった。
[悪い人を好きになると、悪い人になる]
「ごめん。何の話をしているのか、分からなくて……」
クラリスはルーペを持ち出し、石の表面をじっくりと覗き込んだ。
そして、ほんのわずかな隙間に残っていた最後の砂粒まで、そっと拭い去った。
「誤解を解きたいの。もしよかったら、もう少し詳しく話してもらえる?」
[本当に、悪い人じゃないの?]
石が投げかけたその問いは、クラリスに向けた言葉ではないように思えた。
窓辺で、クッションの上で、そして引き出しの中で、ほかの石たちがクラリスをかばうような気配があった。
[でも……]
クラリスはそれ以上は何も言わず、静かに、石が語ってくれる話を待った。
[本当だよ!わ、私は一つも取りこぼさず、全部見たんだ!]
森の石は、長い年月のあいだ、同じ場所に留まり続けていた。
満月が来ると意識がはっきりし、やがて魔力が尽きれば、半分眠ったような状態になる。
ときおり動物が近づくことはあっても、硬い石そのものに関心を示すことはなかった。
だからこそ――初めてだった。
誰かの手に、こうして触れ続けられるということは――
『どうすれば……どうすれば……ああ、もう……』
昨夜、突然姿を現した若い男は、崩れた道の下に身を潜めたまま、指先で突き出した石の表面をそっと撫でていた。
ときおり、遠くから聞こえてくる人の気配に、びくりと体を強張らせ、そのたびに石をぎゅっと握りしめる。
初めて触れた生き物の温もりは……真冬だというのに、まるで夏が訪れたかのようにあたたかく、石はいつの間にかその男を好きになっていた。
たとえ彼がゴーレムマスターではなく、石の声を聞くことはできなかったとしても。
『どうか……早く来てください。お願いします』
男は何度も、そんな祈りを捧げた。
疑わしい願いだったのかもしれない。
石は、彼が何を待ち望んでいるのかも分からないまま、それでも彼の願いが叶うことを、共に願っていた。
『……!』
そして、撫で続けていたその手がすべてが止まった。
きっと彼は、何かを感じ取ったのだろう。
ほどなく男は、石を握ったまま、その場から立ち上がった。
石は「まさか、僕を連れて行ってくれるのかな?」と期待した。
こんなふうに優しく撫でてくれる人なら、一度くらいはついて行ってみたいと思ったからだ。
男は、脇道の坂を一気に駆け上がっていった。
その指の隙間から、石は誰かが近づいてくるのを感じ取った。
沈みゆく赤い夕陽の中では、相手の顔ははっきりとは見えなかったが。
「……あ……あ……」
安堵したような男が、よろめきながら、相手に向かって一歩ずつ歩み寄った。
石が白い雪の上に落ちたのは、ちょうどそのときだった。
おそらく彼は、石を握っていたという自覚すら失っていたのだろう。
石は、雪の上にぽつんと残されたままだった。
相手に向かって、一歩、また一歩と近づいていった。
「それで……どうなったの?」
クラリスが尋ねると、しばし沈黙していた石が、ぽつりと答えた。
[……あの悪い人は、男の人を抱きしめたまま、背中を刃物で何度も突き刺したの。]
「…………」
[わ、わたし……一緒には行けなくても、あの人が幸せでいてくれたらって……そう願ってたの。撫でてくれたから……]
嗚咽まじりに語る石があまりに痛ましくて、いつの間にか近くに来ていたモチが、その表面をとん、とん、と優しく撫でた。
「そ、その人って……まさか……」
クラリスは強張った表情のまま、恐る恐る問いかけた。
というのも、石の話を聞いているうちに、ある人物の姿が頭に浮かんでしまい、どうしても嫌な予感を拭えなかったからだ。
彼を悪い人だと思うことは、もうできなかった。
[あなたはあの男を「魔法使いアスト」と呼んだのよ、クラリス。]
不安で震えていた心臓が、その瞬間、きゅっと締めつけられた。
アルステアは、第二城壁の地下にある牢獄へと、ゆっくりと降りていった。
彼の肩には白いローブではなく、粗い毛織物で仕立てられた、重く長いコートが掛けられていた。
階段を一段下りるたび、そのコートの裾は、まるで魔法使いのローブのように揺れた。
「すぐに身なりを整えてください。」
階段をすべて下りきると、王室侍従が彼の服装を指摘した。
「あ、すみません。」
アルステアは肩をすくめたが、コートをきちんと着直すことはなかった。
「癖なんです。撫でていないと、落ち着かなくて」
「通せ」
すぐに、牢の奥から低くくぐもった声が響いた。
シジョンは相変わらず、アステオを値踏みするような目で見てはいたが、それ以上は何も言えず、黙って頭を下げた。
彼は――重要な客だったからだ。
「どうぞ、お入りください」
「いつもありがとうございます」
アステオはシジョンの結界を抜け、長い牢獄の廊下へと足を踏み入れた。
震えるような異臭が立ち込めるその空気に、これまで数多の修羅場をくぐり抜けてきた彼でさえ、思わず眉をひそめる。
だが――彼を待っていた人物は、その忌まわしい臭気などまるで感じていないかのようだった。
否、むしろその周囲には、ほのかに薔薇の香りが漂っていると錯覚するほど、気高く静謐な雰囲気が満ちていた。
「大王妃殿下に、謁見いたします」
貴族の礼儀作法に弱いほかの魔法使いたちとは違い、彼はこうしたことにすっかり慣れていた。
彼女が白い手袋をはめた手を差し出すと、アルステアはその甲に軽く口づけた。
「この程度の演出では、陛下の美しさには到底かなわないようですね。」
半ば本心の言葉ではあったが、叱責が返ってくる可能性も十分にあった。
だがアメルダは、眉一つ動かすことなく、まず用件から切り出した。
「魔法使いは?」
「私が直接処理しました。派遣された騎士たちが一緒に死亡を確認していますので、彼らに再確認させていただいても構いません。」
「遺体は?」
「魔法使いの塔に葬る予定です。通常どおりに。」
しばし考え込んだアメルダは、ゆっくりとうなずいた。
「今回の件で、あなたの功績があったことは覚えておきましょう。」
「もちろん、見逃すわけにはいきませんから」
彼は薄く微笑み、ためらいもなく彼女と視線を交わした。
「私が……望むのは――」
「無礼だ、目を伏せろ!」
シジョンが即座に怒声を上げたが、アメルダは手を挙げてそれを制し、周囲の者たちをすべて下がらせた。
「もし、そこまで大仰に要求する男でなかったなら、貴方の首はとっくに落ちていたでしょう」
「いえ」
アステオは、あどけなさすら感じさせる笑みを浮かべた。
「殿下でしたら、そのようなことはなさらない。そもそも――私と完全に利害が一致する相手など、他にいないはずですから」
「…………」
「崩れたゴーレム」
アステオは、アメルダの足先に触れそうなほどの距離まで歩み寄った。
「我々は、その歪んだ事実を正しく聞き届ける必要があります」
「私は、まだ同意していないわ」
静かな拒絶が、重く空気に落ちた。
「陛下のような完璧主義のお方は、『どんな可能性』であっても後回しにはなさらないでしょう。」
柔らかな微笑みを浮かべて放たれたその言葉に、彼女は首を縦に振ることができなかった。
その親切そうな口調が、実のところ脅し以外の何ものでもないことが、あまりにも明確に伝わってきたからだ。
「ゴーレム・マスター……その肩書きだけでも、これほど厄介なものだとはね。」
「陛下。」
アルステアは静かに頭を下げた。
「そのようなものは存在しない、という事実をお受け入れいただくべきです。彼らは石と意思疎通ができますから。」
一瞬の間を置いて、彼は続けた。
「石の箱を開けなくとも、その中に宿るすべての真実を知ることができるのです。」
アメルダの眉がわずかに動いた。
だがすぐに、彼女は平然とした口調で答えた。
「……今は冬。大地は凍りついているわ。それに北側の城壁となれば、なおさら得られるものは少ないでしょうね。」
「そういうことでしたら、お待ちしましょう。陽射しの長い夏が終わるまで。少々退屈な時間が続くことになるでしょうが……ふむ?」
アステオは言葉を切ると、すぐ隣にある空の牢へと視線を向けた。
足音を立てぬよう歩み寄り、きしむ扉をそっと押し開く。
アメルダは、彼の唐突な行動をただ黙って見守っていた。
彼が調べている場所――それは、つい先ほどまであの魔法使いが囚われていた檻だった。
アメルダのもとへ、アステオの手紙を運んできた、まさにその魔法使いである。
「彼は……何かを残したのか?」
「これは、なかなか興味深いですね」
床に転がっていた小さな器を、彼は迷いなくひっくり返した。
普通の人間なら、「中身は空だ」と言うだろう。だが、彼にははっきりと“感じ取れた”。
「私の……弟が、ここを知っていたようです」
立ち上がった彼の表情には、濃く入り混じった感情の色が浮かんでいた。
彼は含みのある微笑を浮かべていた。
アメルダは、ようやくこの魔法使いを心から信頼してもいいのではないか、と思えるようになった。
人望と実力を兼ね備えた魔法使い団の臨時代表が、何を求めてこの王宮まで足を運び、尻尾を振るような真似をしているのか――彼女はいつもそれが気にかかっていた。
もしかすると、その内には王室に対する負の感情があるのではないかと疑ったことも、正直に言えばあった。
だが「弟だ」と口にする彼の表情を見た瞬間、アメルダははっきりと理解した。
それは彼女が「マクシミリアン」の名を語るときに浮かべる表情と、まったく同じだったからだ。
だから、あれは――
決して殺すことのできない誰かを、どうしても殺してしまいたくて、正気を失ってしまった人間の顔だった。
「……だ、だから、ノアが絶対に信じないってことは分かってる!分かってるけど……それでも、魔法使いアスト様が……」
クラリスはノアに向かって「話がある」と切り出してから、部屋を訪れてすでに一時間が経って、ようやくここまで話を進めることができた。
残された言葉は、ただ一つ。
――魔法使いメイビスを殺した。
しかし、その事実だけは、どうしても口に出すことができなかった。
ノアにとって、魔法使いアストがどれほど大きな存在であるかを思うと、なおさらだった。
どれほど深く傷つくことになるのか、想像すらできなかったからだ。
「……魔法使いメイビスを、殺しました」
けれど、その答えは不意に――机の上に腰かけていたノアの方から、先に返ってきた。
「……?!」
向かいの椅子に座っていたクラリスは、驚いてぱっと顔を上げた。
「え、どうして……」
「……うん」
彼は少し身を引き、視線を別の方向へと逸らした。
「なんだか……引っかかるんだ」
「引っかかるって、どんなふうに?」
「彼が私に言った言葉」
クラリスは、森で彼と交わした会話を一つひとつ思い返してみたが、はっきりとこれだと思えるものは浮かばなかった。
「ごめん、私……うまく……」
「少女が気づけないのは当然だよ」
ノアは長く垂れた髪を肩の後ろに流し、少しだけ笑った。
クラリスには、それがどこか無理に作った笑顔のように聞こえた。
「僕が保存魔法を使ったあとに、彼が到着したのを覚えてる?」
「うん」
「それから彼は僕にこう言った。『保存を使うなら、早いほどいい。せいぜい十分の差しかないけどね』って」
ノアは、その優しい口調までそっくりそのまま真似て言った。
「どんな魔法使いでも、魔法がいつ発動したのかを正確に把握することはできないものだ。ましてや一日二日どころか、分単位となればなおさらだ」
「……その時から、何かおかしいって思ってた?」
「すぐに見抜いたわけじゃない。胸の奥に小さな違和感が残っていて、それをゆっくり辿っていただけだ。もしかしたら、と思って」
「…………」
「少女がそう証言したことも、現場を見ていたドールの証言も、すべて僕の推測と一致している。彼は……僕たちが到着する前から、すべてを見ていたんだ」
「……ノア」
「もしかすると、僕たちが現れるとは思っていなかったのかもしれない。翌日には捜索隊がメイビスの遺体を発見するだろうと考えて、森に放置したんだろう」
ノアは一度仮面に手をやり、整えるようにしてから、静かに語り続けた。
「魔法使いアストを誰よりも信じ、慕っていた人物だ。それなのに、なぜ殺したのか……疑問が尽きない」
そして、なぜか……彼の言葉は次第に早口になっていった。
「これまで上級魔法使いが殺されることは何度もあったけれど、か弱い下級魔法使いに手を出す者はいなかった。ローブの色だけで屈服させられる相手を殺して、いったい何の得がある……」
「ノア」
立ち上がったクラリスは、許可も求めず彼の襟元をつかみ、強く引き寄せた。
両腕に力を込めたことで、ようやく彼の話は止まった。
「……一人で抱え込まないで」
切実な頼みにもかかわらず、彼が不規則な呼吸を無理やり飲み込む音は続いていた。
クラリスは、ノアが森から戻ってきてから、ずっと心の奥に押し込めてきた苦しみがあるのではないかと思った。
そして彼女のその言葉は、彼の心に、さらに確かな傷を残したに違いなかった。
「……ごめん……」
「……その……少女の……せいじゃ、ない。これは……」
そう言い残すと、彼は嗚咽を必死に押し殺しながら、クラリスの肩に顔を埋め、肩を小さく震わせた。
クラリスは静かに彼の背に手を回し、ゆっくりと撫で、時折とん、とん、と優しく叩いてやった。
それは、彼女が泣くたびにノアがしてくれた仕草と、まったく同じだった。
この瞬間、ここ数日彼女を苦しめていた、ノアに向けられた複雑で混乱した感情は、ひとつも浮かんでこなかった。
今となっては、そんなことは何ひとつ重要ではなかった。
ただ――大切な友が、少しでも楽になってくれれば、それでいい。
「……ノアが、決して一人でこの重荷を背負うことがないようにするわ」
そう、決意を込めて告げると、彼はようやく顔を上げ、真正面から彼女を見つめ返した。
仮面の奥にのぞく紫色の瞳には、すでに涙がにじんでいた。
「それはできない。これは……」
「セリデン公爵家の問題でもあるの。私があの場所をどれほど大切に思っているか、ノアも知っているでしょう」
「……」
「魔法使いメイビスは、レノクス侯爵家の使用人を装って手紙を届け、その後、魔法使いアストに殺された」
ここにルカがアルステアの追従者である点を考え合わせると、その手紙の差出人はアルステアである可能性が高かった。
「単純に考えれば、魔法使いアストは何かを企んでいる。ノア」
「レノクス侯爵家と……いや、もしかすると王家と手を組んでいるのかもしれない」
厳重な手続きが求められる第二城壁を越えるために身分を偽ること。
罪の裁きもないまま、誰かを牢に押し込むこと。
それはすべて、権力を持つ者でなければ成し得ないことだった。
「目的は……」
公爵夫人誘拐事件。
メイビス殺害事件。
一見、無関係に見える二つの事件を一本の線で結ぶものは何なのか。
たとえ、メイビスが公爵夫人の正体を記した手紙を届けようとして殺されたのだとしても、それは真実に辿り着くための“過程”にすぎない。
すべては、ある目的のために実行されたはずだった。
今のところ、明らかになっている情報だけでは、その全貌はまだ見えないが――。
「今は……見守り続けるしか、ないよね」
小さく頷くノアの横顔を見つめながら、クラリスは本当は口にしたい言葉があることを、自覚していた。
――もしかしたら、目的はあなた自身なのかもしれない。
だが、それはどこまでもクラリス自身の推測に過ぎなかった。
その一線を越えてはいなかったため、これ以上話すことはできなかった。
いや、それよりも。
ノアは、ここでこれ以上傷つくことを望んでいなかった。