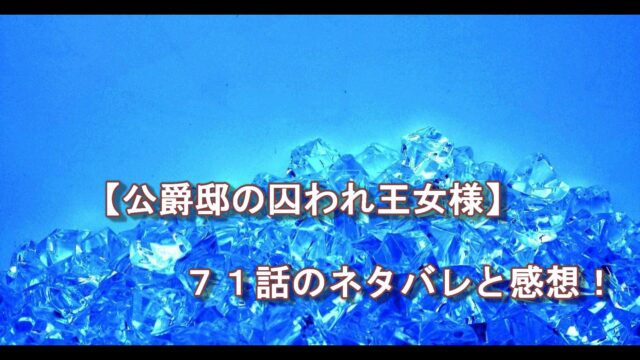こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

128話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 裏切り者
「……はぁ、はぁ……」
鬱蒼とした森の奥、獣道のような細い道を抜けた先で、灰色のローブを纏った魔法使いルカは、ようやく身を隠せる場所を見つけた。
斜面に沿って傾きながら伸びた大木の根元。
そこには、洞穴のように自然と抉れた空間があった。
彼は幹と根を掴み、慎重に下へ降りる。
自然が用意した即席の隠れ家に身を滑り込ませて、ようやく長い息を吐いた。
「……はぁ……」
見上げた西の空では、いつの間にか太陽が沈みかけている。
魔法使いとして、森で夜を越すこと自体は慣れていた。
だが今夜は――誰かに追われているという事実のせいか、迫り来る闇が、いつもよりずっと重く感じられた。
胸の奥に、嫌な予感が静かに広がっていくのを、彼は無視することができなかった。
来ることだけが、ただただ恐ろしかった。
『魔法使いシネットは、まだなのか?』
周囲に神経を尖らせてみたが、返ってくる音はなかった。
数時間前、牢から出されたルカは、そのまま騎士たちが用意した馬車に乗せられた。
どこへ向かうのかと問うても、誰一人として答えはしなかった。
だが、このときばかりは、ルカはそれほど恐れてはいなかった。
魔法使いアストが、きっと自分を救ってくれると信じていたからだ。
何よりも、彼はアストが最も目をかけていた魔法使い。
王都へ密書を届けるような極秘の任務を任されるほどに。
彼の予想どおり、馬車は修道院の城壁を一つ、また一つと越えて外へ向かっていった。
ただし、一つ目の城壁を過ぎて間もなく、馬車はその場でぴたりと止まった。
何事かと、向かいに座る兵士たちの顔を交互に見やったが、彼らは何も答えなかった。
ただルカを、外へ放り出すように突き飛ばしただけだった。
頭から地面に叩きつけられる衝撃に、彼は一切の抵抗もできない。
その隙に、彼を運んできた馬車は、来た道をそのまま高速で引き返していった。
――まさか、こんな形で解放されるとは。
「ふざけやがって……!」
地面に転がったまま、悪態をついた、その瞬間。
背後から、肌を刺すような禍々しい気配が押し寄せてきた。
間違いない。明確な殺意だ。
おそるおそる振り返ると、武器を構えた数人の男たちが、包囲するように距離を詰めてきている。
「う、うわあっ!」
よろめきながら立ち上がった彼の掌から、反射的に魔力が溢れ出した。
だが、それがどんな魔法なのか、自分でも把握できていない。
――死ぬ。
その恐怖だけが、脳裏を支配する。
詠唱も理論もなく、ただ思いつくまま。
生き延びたい一心で、彼は無我夢中に魔法を放ち続けた。
それでも、運よく効果はあったようだ。
正気を失ったかのように森の中へ駆けていく彼の後を、あの恐ろしい男たちはすぐには追ってこられなかった。
わずかに冷静さを取り戻したとき、思い浮かんだのは、牢獄で見た魔法使いシネットの光。
彼がここから遠くない場所にいるという事実を思い出した瞬間、それがたとえ命綱であっても見つけられたようで嬉しかった。
決して仲が良いとは言えないが、彼は白いローブの魔法使いなのだから。
当然、ルカを守る義務があった。
そうして彼は、ノアに追跡の光を送ることになったのだ。
だが、木の根元で完全に落ち着きを取り戻してみると、少し軽率だったのではないかという考えも浮かんだ。
『あの怪物に光を付けておくのは、ちょっと気が引けるな』
あのずる賢い猫は、仮面を直しながら、さも自分がとても有能であるかのように振る舞った。
――気分の悪い連中だ。
そう思った、その時。
少し離れた場所から、人の気配がした。
「……あの人、魔法使いは一撃で首を落とせって言ってたよな」
「いや、俺は“お前がやれ”って言われたと思ったけど?」
「仕方ないだろ。あの方が直々に出るって言い出したんだから。どうなろうと結果は同じさ。俺たちは命令通り、死体を確認すればいいだけだ」
――“あの方”。
ルカは息を殺したまま、男たちの会話に耳を澄ませた。
わずかな手がかりでも掴めないかという、ほとんど祈りに近い期待を抱いて。
「そこにいるか?見えるか?」
次の瞬間、その声が――真上から降ってきた。
心臓が跳ね上がる。
どうやら、自分が身を隠している木のすぐ近くまで来ているらしい。
「……いや、いないな」
「ちっ、あんな腰抜け、どこへ消えたんだ?」
男たちが舌打ちしながら、その場を離れていく。
足音が遠ざかったのを確認してから、ルカは、今まで必死に堪えていた呼吸を――一気に吐き出した。
肺の奥まで空気が流れ込み、ようやく、生きているという実感が戻ってくる。
――助かった……?
そう思ったのも、束の間だった。
背筋を、氷の指でなぞられたような感覚。
この森には、まだ何かが残っている。
ルカは歯を食いしばり、再び身を固めた。
本当の追跡は――これから始まる。
『助かった』
しかし、いったい「その人」とは誰なのだろうか。
まさか、魔法使いを害そうとする刃があるという意味だろうか?
『ともあれ、魔法使いシネットさえ来てくれれば……いや』
彼は考えを切り替えた。
必ずしも、シネットを待つ必要はないのではないか?
今の彼は、牢獄ではなく王都近くの森にいる。
貴族たちの権力が、この木の根元まで及ぶことはないだろう。
ならば、魔法使いアストの助けを得られるはずだ。
男たちの気配が完全に消えるのを待ちながら、
ルカはもう一つ、別の光を放った。
今度こそ、魔法使いアストに会えることを願って。
ノアとクラリスは修道院を抜け出し、冬枯れの畑を横切るようにして走った。
道を行く馬車があれば、無理を承知で同乗を頼むこともできただろう。
だが今日は、祈りのために修道院を訪れる者もなく、夕闇に沈みかけた道はひどく静まり返っていた。
畑を抜けると、王都へ続く街道の脇に、樫の木が密集した森が姿を現す。
ルカの灯した淡い光は、歩きやすく整えられた大路を外れ、二人を黒々とした木立の奥へと導いた。
人も馬車も通らない獣道。
常に影の落ちる場所には、脛まで埋まるほど雪が積もっている。
ノアもクラリスも革靴の中まで雪解け水が染み込み、足先の感覚が失われていくのをはっきりと感じていた。
それでも、歩みが緩むことはなかった。
――嫌な予感が、拭えなかったからだ。
街道を外れ、この混み合った森へと足を踏み入れた瞬間に覚えた、背筋を撫でるようなざわめき。
まるで森そのものが、二人に背を向けろと告げているかのような――そんな風さえ、吹いていた。
それでも彼らは、立ち止まらなかった。
「コオ。(気をつけて、クラリス)」
何かを感じ取ったのか、モチが静かに警告した。
そして同時に、彼らを導いていた小さな光が一瞬、揺らいだ。
「……まったく」
ノアが残念そうに息を吐いた。
「もしかすると、到着する前に魔力がすべて尽きるかもしれないな。急いだほうがよさそうだ」
彼は振り返りながら手を差し出した。
いや、正確には――クラリスが彼の手を取るのを待てず、彼のほうから一歩踏み出して、彼女の手をつかんだのだ。
それほど、状況は切迫していた。
クラリスは彼に引かれるまま懸命について行きながら、どうしても、彼に握られた自分の手から目を離せなかった。
『これは……ごく自然なことだったはずなのに』
ノアとクラリスが互いの手を握ったまま眠った夜が、何度もあったほどなのだから。
クラリスは顔を上げ、半歩先を行くノアを見上げた。
白い耳の後ろから長く垂れた空色の髪が、歩調に合わせて揺れ、すれ違いざまに彼女の頬をかすめていく。
クラリスは無意識のうちに思った。
――この人は、本当にきれいだ。
今はその顔に刻まれていた微かな疲労の影も、まるで嘘のように消えているというのに。
そして、彼の背を追ってもう一歩踏み出した、その瞬間だった。
森の正面から、突き刺すような強風が吹きつけてきた。
思わず足を止め、顔を背けなければならないほどの、圧のある風だった。
「……っ!」
荒れ狂う空気の流れが、二人の間を完全に通り過ぎたあと。
ノアとクラリスは、同時に、目を見開いて互いを見た。
「……今」
クラリスが低く呟くと、ノアも同じ感覚を抱いたのだろう、小さく頷いた。
二人とも、はっきりと“何か”を感じ取っていた。
彼らは再び、風が吹いてきた方向へと走り出した。
いつの間にか、彼らを導いていた光は消えていたが、進む道に迷いはなかった。
なぜなら、彼らをかすめた風の中に、あまりにもはっきりと血の匂いが混じっていたからだ。
決して、遠くから流れてきたものではない。
その予感は外れず、再び息を荒らす間もなく、彼らは足を止めた。
似たような獣道の向こうに、ちょうど太陽が沈みかけているのが見えた。
そしてその手前――根を張った巨大な木の下に、血まみれの男が一人、崩れるように座り込んでいた。
「……魔法使いメイビス?」
ノアは慎重に声をかけながら、彼に近づいた。
深い闇のせいで、その姿ははっきりとは見えなかった。
「…………」
返事はなかった。
ノアは、もう一歩だけ前へ出た。
いつの間にか濃くなった闇が視界に滲み、彼の輪郭が少しずつ曖昧になっていく。
前屈みになり、頭を垂れたその背は、力を失ったかのように張りを欠いていた。
まだ乾ききらない濃い血が、肩口から伝い、雪の上へとぽたり、ぽたりと落ちていく。
「……っ!」
次の瞬間、ノアは反射的にクラリスを背後へ引き寄せた。
同じものを見たのだろう。
彼女の指が、彼のローブをきつく掴み、引き留める力がはっきりと伝わってくる。
「……これ以上は、見ない方がいい」
低く抑えた声だった。
幼い頃のクラリスが“戦争”の中で、あまりにも多くの残酷を目にしてきたことを、ノアはよく知っていた。
けれど――。
クラリスは、ゆっくりと首を振った。
視界の端に映ったその姿に、本能的な恐怖が走り、手も足も震えているのは確かだった。
それでも、彼女は目を逸らさなかった。
逃げないと、そう決めたように。
しかし、この死から目を背けたいとは思わなかった。
なぜか、そうしてはいけない気がした。
なぜなら、その遺体を見た瞬間――
「ノア……殺そうとしていた魔法使い……どうなっ……た……え?」
そんなノアの独り言が、なぜか脳裏をかすめたからだ。
クラリスはぎゅっと目に力を込め、ノアの隣に並んで立った。
「背中を刺されてる。もしこの人が魔法を使っていたなら、ノアなら痕跡で分かるって言ってたよね?」
隠すつもりはないという意志が伝わったのか、ノアは一瞬心配そうに遺体を見下ろしたあと、何かを感じ取ったように答えた。
「魔力が残っていれば分かる。でも残念だけど、ここにはそういうものは少しも残っていないみたいだ。」
「魔法を使っていないってこと?」
「それなら、かなり不自然だね。」
「魔法を使う余裕がなかったとか?魔法を扱うには集中力が必要だって言ってたじゃない。」
「……それは、そうだけど」
ノアは慎重な足取りで、崩れ落ちるように地に伏したルカへと近づいた。
「命の危険を感じた瞬間、人は自分でも気づかないうちに魔法を溢れさせるものだ。それは……君が恐怖を覚えるたび、無意識に“石”を引き寄せてしまうのと、同じだよ」
「……そうだとしたら」
クラリスは懐からモチを取り出し、口元に運んだ。
「モチ。周囲を見て、誰か様子をうかがっている存在がいないか、確認してくれない?」
「コオ」
「ついこの前が満月だったでしょう。だったら、誰かが起きていても不思議じゃない」
「コオ」
「雪が深くて、視界はきっと悪いだろうけど……それでも、念のため」
「コオ」
「……ありがとう」
モチは小さく鳴くと、白い雪原へと溶けるように飛び立っていった。
モチは雪の吹きだまりに半分ほど埋もれてはいたが、その短い脚で雪道をきちんと歩き回っていた。
その間、ノアはルカの体に直接触れることなく、魔法を使って彼の亡骸を静かに木へともたれさせた。
「……あ」
ようやくあらわになったルカの顔。
そこには、死が彼に残していった感情が、あまりにもはっきりと刻まれていた。
大きく見開かれた目、開いたままの唇。
いったい何が、彼をここまで驚かせたのだろう。
本能に近い魔法すら使えなくなるほどに。
「失礼します」
ノアは遺体に一言断りを入れ、彼のポケットを探った。
しかし、犯人たちがすべて持ち去ったのか、中には何も残されていなかった。
「……僕が、遅すぎた」
ノアは生気を失ったその瞳を見つめながら深く頭を下げ、心からの謝罪を口にした。
「私は白のローブをまとう魔法使い、ルカ・メイビス。本来なら、あなたを守る責務がありました。……それを果たせなかったこと、謝罪します」
そう告げると、ノアは白い雪の上に落ちた赤い血溜まりへ、静かに両手をかざした。
ルカを中心に、淡く透けるような球体がふわりと広がり、周囲を包み込む。
「……何の魔法?」
「保存魔法です」
その球は、ルカの身体を完全に覆い、外界から隔てるように保たれていた。
立ち上がったノアは、クラリスの方を見て、静かに説明を続ける。
「魔法使いの塔に保管されている血液に施される魔法と、同系統のものです。この魔法に守られている存在は、時間の影響を受けません」
「だから……どれだけ時間が経っても、採取された時点の状態を保つことができる」
一瞬の沈黙のあと、ノアは続けた。
「もしこの魔法がなければ……そもそも、血を採ること自体が不可能だったでしょう」
死者を集めて蘇らせるなどという行為は、もはや不可能だった。
「魔法使いは、仲間や友の死に疑問を抱いたとき、必ずこの魔法を使って現場を保存してきたんだ」
彼は沈んだ表情でルカを振り返った。
「もっとも僕は、彼を仲間や友だとは思っていなかったけれど……」
クラリスが彼の前へと歩み出た。
「責任を……感じているの?」
「僕には、機会があった。せめて、彼が捕らえられたときに引き止めることくらいはできたはずだ。いや、最低でも牢獄まで探しに行こうとするくらいは……」
「そんなに単純な話じゃなかったんでしょう。クエンティンおじさまも、そう言っていたじゃない」
クラリスは、彼から聞いていたルカの表向きの立場を、改めて思い返した。
「この事件の裏には、レノクス侯爵家が関与した痕跡があった」
その一族は、単に「有力な貴族」という言葉で片づけられる存在ではなかった。
大王妃アメルダの双子――オラヴィン・レノクス侯爵。
彼が「王の外戚」という立場をことさらに強調し、王室の長老として振る舞っている――そんな噂は、確かに耳にしていた。
「それほどの家門が、理由もなく名を汚されるとは考えにくい。……間違いなく、理由があったはずだ。あの連中が、魔法使いメイビスを殺さなければならなかった理由がな」
「その手紙の内容、とか?」
「あるいは……その手紙が“存在した”という事実そのもの、かもしれない」
「……そう、なると」
ノアはしばし黙り込み、困ったようにこめかみを指でなぞった。
「いずれにせよ、ここはもう引くべきだろう」
「引く、って?」
魔法使いの亡骸を、この凍てつく場所に置き去りにすることに、クラリスはどうにも割り切れない思いを抱いた。
「魔法師団に連絡を入れる。座標はすぐ割り出せるはずだ。魔法使いメイビスは……いずれ、魔法使いたちの土地へ戻されることになる」
そう言って、ノアは穏やかに視線を向ける。
「だから――少女が無理に背負う必要はない」
静かな言葉だったが、不思議と強い説得力があった。
「でも、こんなに寒いのに、一人で……」
死んだ人間に寒さや孤独は関係ないと分かっていても、クラリスはどうしても心配になってしまった。
「ここで今すぐ、私たちにできることも……ないし……」
そこまで話していたノアが、ふと顔を上げ、クラリスの肩越しに視線を向けた。
少し離れた場所から、ガタガタと馬車の音が聞こえてきたのだ。
ノアは音のする方へ、一歩前に出た。
最初はやや緊張した様子だったが、ほどなくして彼は安堵の息をついた。
森の道から姿を現した人物は、彼らにとって見慣れた存在だった。
「魔法使いアスト!」
深い森の闇の中でもクラリスが彼だと分かったのは、彼の前にも、ノアを導いていたのと同じ光が揺らめいていたからだった。
光は矢のように走り、ノアの結界をかすめると、そのまま虚空に溶けて消えた。
ほんの一瞬、ノアは小さな声でつぶやく。
「……魔法使いメイビスの魔法だね」
ほどなくして、彼らの前に姿を現したアルステアは、周囲を照らす魔法で状況を確認し、ようやく地に伏したルカの姿を見つけたようだった。
その表情に、蒼白な衝撃が走る。
「ルカの魔法を辿って来たが……どうやら、間に合わなかったらしい。保存魔法まで施してあるとはな……」
「アスト様が来ると分かっていたら、待っていたわ」
ノアの言葉に、アルステアはゆっくりと首を横に振った。
「保存は、早いに越したことはない。たとえ、ほんの僅かな差であってもだ」
「……魔法使いアスト」
クラリスは一歩前に出て、彼をまっすぐに見据えた。
その瞳には、恐れよりも、確かな意思の光が宿っていた。
「グレジェカイア嬢、こんな場所でお会いするとは、実に奇遇ですね」
「クラリスは、ただ私についてきただけです。魔法師団の件を軽々しく言いふらすような人では、決してありません」
クラリスはこのときになってようやく、こんな状況でアルステアに会えたことを、自分が内心では少し嬉しく思っていたのだと気づき、それが恥ずかしくなった。
魔法師団としては、この件について静かに調査を進めたいはずだ。
「も、もちろんです。私は絶対に話しません。誓います」
「ええ、承知しています。私はグレジェカイア嬢を信頼しています。あなたは、お顔立ちがセリレン公爵様に似ていますから」
彼は再びノアへと視線を向けた。
「じきに捜索隊がこちらへ来るでしょう。心配せず、戻られた方がよさそうですね」
「魔法使いアスト」
ノアは彼の顔をじっと見つめた。
何かを深く考え込んでいる様子だった。
「……心配しなくていい」
そう言って、アルステアは柔らかく微笑み、ノアの頭をくしゃりと撫でた。
「ルカは、私が目をかけていた魔法使いだ。この死がどこから来たものか――必ず突き止める」
「……子ども扱いしないで」
ノアは彼の手を軽く叩き落としたが、その動きに本気の拒絶はなかった。
「ああ、そうだったな。すまない……女性の友人の前で、これは失礼だった」
「だ・か・ら!そういう余計な一言を、いつまで言うつもりなんですか!」
耳まで真っ赤にしたノアが声を荒らげ、勢いよくクラリスの腕を掴むと、そのままアルステアの結界を抜けて歩き出した。
「もう戻る。今後の話は、魔法使いの城でする方がいいでしょう」
「馬車を呼ぼうか?」
「いらない!」
即答だった。
「……とはいえ、グレイジェカイア嬢は、少し疲れているようだが?」
アルステアの視線が向けられ、クラリスは一瞬だけ言葉に詰まった。
だが、ノアは歩みを緩めることなく言い切る。
「この子は大丈夫だよ。私がついてる」
その声には、はっきりとした覚悟が滲んでいた。
アルステアはそれ以上は何も言わず、ただ静かに二人の背を見送った。
雪を踏みしめる足音が遠ざかっていく。
――そして、森に残されたのは、結界の消えかけた光と、横たわる一人の魔法使いだけだった。
アルステアはルカを見下ろし、低く息を吐く。
「……安心して眠れ、ルカ。これは、私の責任だ」
冷たい風が吹き抜け、森の闇が再び深さを取り戻していった。
「……です」
その言葉で、ようやくノアははっとしてクラリスを振り返り、彼女はすぐに首を横に振った。
「私は大丈夫、ノア」
「それでも、こんな夜更けに森を歩くのは感心できません。グレジェカイア嬢」
彼は軽く手を払うようにして、少し離れた場所に控えている馬車へ合図を送った。
「捜索隊が来るまで、私はルカのそばを離れられません。ですから、必ず馬車に乗ってお戻りください。妹の恋人に、これくらいするのは当然でしょう」
ノアがまた泣き出しそうになったため、クラリスは慌てて一歩前に出て、代わりに答えた。
「そ、そうですね!魔法使いアストのご配慮に感謝します」
「グレジェカイア嬢にとっては当然のことです。いずれ家族になる間柄なのですから」
「……とにかく、急いだ方がよさそうですね」
彼女の手を握ったノアが急かし、クラリスは彼について、馬車のある場所へと戻ることになった。
その前に、木の陰に隠れていたモチを、手のひらにそっと乗せ、素早くポケットへ滑り込ませたことも、彼女は忘れていなかった。