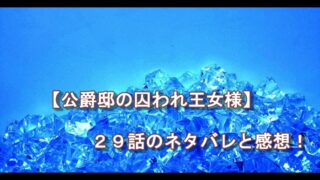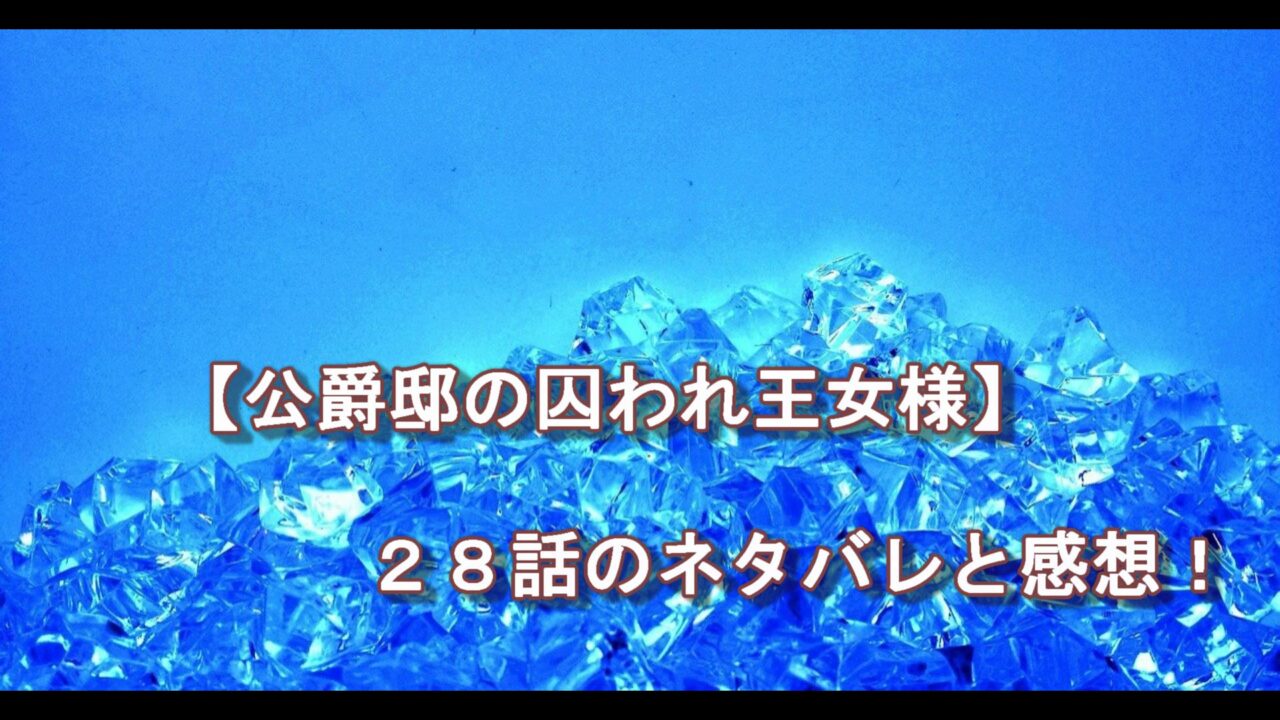こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
今回は28話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

28話 ネタバレ
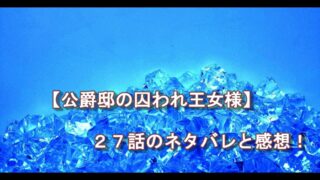
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 本当の気持ち③
アセラはブリエルをシェリデンに送り、外国で自由を満喫しながら生きてきた。
小言を言う母親もおらず、彼女の毎日はパーティーと娯楽の連続だった。
さらに、公爵との結婚により、伯爵家には定期的に品位維持費も支給された。
娘を大切にしている伯爵は毎月そのお金の半分以上をアセラに送ってきた。
美貌と財力まで備えた彼女に対して、ハンサムな男たちが数え切れないほど飛びつくのが当然のこと。
アセラは特に相手を選ばずに、恋人のような楽しい関係を維持した。
楽しい生活が終わったのは先日。
妊娠の事実を知った瞬間からだった。
父にこのような事実を告白することはできなかった。
いくら娘を大事にしている父親とはいえ、浮気をした男性の子供がいることを知れば、すぐに支援金が切れるのはもちろんのこと、どこかの修道院に自分を送ってしまうから。
そうなると、豪華な生活とは永遠に別れることになる。
唯一の解決策は、結婚。
ただ、外国の男性と結婚することはできなかった。
貴族は王の許可なしに外国人と結婚するできなかったし、もしそうなれば爵位継承資格を剥奪されることになる。
後になって当然伯爵になると思っていたアセラは、直ちに外国生活を整理した。
お腹が大きくなる前に、サッパーズ王国の男を一人捕まえて結婚しなければならなかった。
しかし、故国で「アセラ」という名前はすでに公爵夫人になっている。
だから彼女に残された選択肢は一つだけ。
「今からでも私がマクシミリアン公爵と本当に結婚して寝床を持つしかない・・・」
シェリデンはとても寒く、邸宅は古くてすぐに幽霊でも出てきそうで本当に嫌だったが、今は方法がこれしかない。
修道院に行くよりはましだろうから。
(だから不愉快でもここを我慢してくれていたのに!)
アセラはブリエルを鋭い目でにらみつけた。
「・・・卑賤の女中が恩知らずに主人を噛むなんて?」
「主人・・・」
ブリエルはがっかりして笑った。
しばらくの間、アセラの境遇を残念に思い、心配していた自分が本当にバカだと思って。
廊下に戻ってきたベンソン卿が、この事態を知りながら近寄らなかったのは、ブリエルが彼を阻んだためだ。
ここでアセラの秘密がさらに広がるのを防ぐために。
単に彼女のためではなかった。
少なくともこの世に新しく生まれる子供に最小限の道理をしようとするのだった。
「伯爵家に戻りなさい、お嬢様。快適な馬車をお出ししますから」
「はあ、今誰に命令するの?」
「ここはお嬢様には寒すぎます。何より、これからは安全な環境にいらっしゃらなければなりません」
「どうかしてる!?父が知ったら・・・」
「伯爵様は状況を知らないんですか!?」
ブリエルは驚いて叫んだ。
正直に言うと使用人たちからアセラの妊娠疑惑を聞いた時から、伯爵と一緒に組んでここに来たと思っていたから。
「いったい何を考えているんですか?いや、そもそも父親は・・・」
「し一、うるさい!」
アセラは顔を真っ赤にして叫んだ。
すると、廊下の遠いところから飛んでくる視線が感じられた。
ブリエルの命令で近づくことはなかったが、廊下の遠いところに立った使用人たちはこちらを非常に鋭い目で眺めている。
アセラはなぜか肩をすくめた。
「お嬢様」
ブリエルは軽く腕をつかんだ。
驚くほど柔らかい手つきだった。
まるでアセラのことを心から心配しているかのように。
「・・・何よ」
しかし、ブリエルのそのような態度は、アセラの怒りを呼び起こした。
「あなたなんかが私のことを心配して!あえて!」
結局、彼女は我慢できず再びかっと叫んでしまった。
ブリエルは子供の頃から卑しく、アセラは特別だった。
この世がいくら逆にひっくり返ったとしても、あえてブリエルなどがアセラを心配することは起きなかった。
これでは・・・ブリエルが自分より優位に立ったようではないだろうか。
「それでもお前の偽のお母さんが命でも持ち堪えることができると思う?私がお父さんに連絡して、あなたのお母さんなんか今すぐ殺してしまえと言うよ!分かった?」
アセラはさっと身をかわした。
こうなった以上、残った方法は一つだけ。
ブリエルを永遠に地獄に落とすのだった。
「お嬢様!」
ブリエルは彼女の腕をつかんだが、アセラはもがいてやっと彼女を引き離した。
「離せ!私が公爵様に全部言ってしまうから。あなただけ威勢よく生きるようにすると思う!?」
「ちょっと待ってください、お嬢様!お嬢様!」
ブリエルが急いで呼ぶ言葉に、アセラはにっこりと微笑んだ。
「なんで?まだもっと騙していたいの?」
「そうじゃなくて・・・」
「お前は女中の娘・・・いや、それでも実の娘じゃないじゃないか!?森に捨てられたくせに! この事実を知っていながらも公爵があなたをこの場に置くと思う?」
彼女は私の怒りに打ち勝つことができず、片手を高く持ち上げた。
瞬間、目をぎゅっと閉じたブリエルの前に誰かが遮られた感じがした。
「・・・」
ブリエルが目を開けると、マクシミリアンが立っていた。
「公・・・爵様」
ブリエルは震える声で彼を呼んだ。
しかし、すぐに自分があえて彼を呼ぶことができる境遇になるかと思い、両目をぎゅっと閉じて首をかしげた。
「そこまでだ」
彼の低いため息が聞こえてくる。
当然のことだが、ひどく腹が立ったのだろう。
「公爵様!今まで知らなかったと思いますが、あの女は・・・!」
彼の後ろで,アセラは興奮した声で言い出した。
ブリエルは唇をかんだ。
(少なくとも、こんな風に知らせたくはなかったのに)
他人の口を借りて、それもこんなに派手にふるまうアセラを通じて真実を知らせることに
なるなんて。
恥ずかしさが押し寄せてきて、ブリエルはさらに頭を深く下げた。
「知っています」
「そうですよ、知らなかったでしょう・・・何ですって?」
「私の奥さんが『アセラ・ダーリントン』ではないということは、すでに知っていました」
「はい・・・?」
慌てたのはアセラだけではなかった。
ブリエルもしばらく頭の中が真っ白になった。
「知ってたって、いったい・・・いつから?どうやって?」
「最初から」
そう答えながら、マクシミリアンはアセラの方に立る。
「初めて見た瞬間から分かりました」
「嘘!それならどうして・・・!?」
なぜ結婚を強行したのかという質問に彼は答えなかった。
その代わり、すぐそばに近づいてきたベンソンを振り返り、命令を下すだけだった。
「罪人を連れて行くように。公爵夫人を脅迫した者だ」
「はい」
ベンソンはすぐにアセラの腕をつかみ、彼女は当惑した顔でマクシミリアンに懇願する。
「ああ、公爵様!詐欺師はあの女です!私があなたの本当の奥さんです!私にこんなことをしてはいけません!」
その緊迫した言葉にもマクシミリアンは依然として落ち着いた口調で答えた。
「先ほどおっしゃった『殺してやる』という言葉は、脅迫罪で処罰することができます」
「いや、それは・・・あの女を殺すというのではなく・・・」
「母を誰よりも愛する人です。十分に脅迫罪が成立します。もう連れて行くように」
アセラはベンソンに連れ去られながらも大声で叫び続けた。
あの女は詐欺師だと。
みんな騙されているだけで、実は一介の女中なんだって。
私が本当に公爵夫人だって。
しかし、誰もこれに反応しなかった。
ブリエルはアセラが引きずられる姿を見て、静かに首を回してマクシミリアンの後ろ姿を眺める。
彼は微動だにせず立っていた。
ブリエルは自分が馬鹿だと思った。
少し前の事件が起こり、彼女がマクシミリアンに言わなければならないことはいくらでもある。
謝罪と感謝はもちろん、これまで隠してきた真実まで全て話さなければならなかった。
ところが、彼女がやっと口にした言葉は。
「妊婦は罪人だとしても、ストーブのある部屋を保証される権利があります」
アセラの子供のことを心配しているだけだった。
それは当然言うべきことだと思ったが、それでもこれよりはもう少しまともな言葉があったのではないか。
「・・・そうなんですね」
マクシミリアンの少しゆがんだ顔を見ただけで彼女の言葉が気に入らなかった。
「妊婦じゃなかったら・・・」
「はい?」
「いいえ。正当な待遇をします。法律にのっとって」
なぜ彼が残念がっているように見えるのだろうか?
多分ブリエルの勘違いだと思うけど。
「それから」
彼女は手を心臓の近くに置き、震える息をした。
「お詫び申し上げます、公爵様」
ブリエルは深く腰を下ろす。
「お嬢様の言うことは少しも間違っていませんでした。私は今まで欺隔行為でこの場を占めて多くの権利を享受しました」
「・・・」
「私は・・・」
ブリエルはしばらく自分の唇をかんだ。
好きな男にこんなことを言わなければならないのがあまりにも恥ずかしいせいで。
「・・・詐欺師です」
「お聞きになっていませんか?」
「え?」
ブリエルは彼の質問にやっと頭を上げる。
「私は騙されていませんでした」
「で、でも・・・」
「最初から知っていました」
「そんなはずないでしょう」
「私がたった一度でもあなたのことを『アセラ』と呼んだことがありましたか?」
「・・・」
なかった。
しかし、それは彼らの関係があまりにも疎遠で名前を呼ばないと思ったのに・・・。
「それでも、王が主管した結婚で私が偽物なら、問題になります」
ブリエルはなんとか自分の罪を証明しようとした。
「王様もご存じです」
「え!?」
「王室はそう簡単に騙せる場所ではありません」
「それならどうして・・・?」
「私が進行すると言いました」
「なぜ・・・ですか?」
彼はしばらく悩みながら視線をそらした。
ブリエルは待ちわびていたが、久しぶりに返ってきた答えは・・・。
「・・・よくわかりません」
彼自身も少し困っている曖昧な言葉ばかりだ。
「同情しましたか?」
「それは違います」
「それとも、誰でもいいのですか?」
ブリエルはマクシミリアンの婚約者が王妃になるために国王であるライサンダーと婚姻した事実を知っていた。
もしかして、婚約者の裏切りで傷が深かったのではないだろうか。
誰とでも結婚するほど。
「誰でも良かったのは・・・決してなかったです」
しかし、マクシミリアンはすぐにこれを否定した。
「あなたは詐欺師ではありません」
「・・・」
「そもそも騙されたことはないから。むしろ私があなたを翡したことに対して許しを請いたいです」
ブリエルは彼の顔をじっと見つめ、やっと口を開いた。
「・・・とんでもないです、これは」
声がぶるぶる震えた。
ブリエルは自分があえて「安堵」しているという事実に深い良心の呵責を感じた。
恩も知らない心臓が勝手に暴れ、マクシミリアンに対する期待を膨らませた。
もしかするといくらかは彼のそばを許してもらえるかもしれないとか・・・。
(だめだよ、私なんかが・・・)
マクシミリアンは王子様だ。
例えではなく、本当に、王族の男だった。
こんな高貴な男が女中なんかを妻としてそばに置くなんて。
ブリエルの存在は彼の汚点になるはず。
(・・・それでも)
騙されたわけでもなく、誰でも良いわけではなかったという彼の言葉で、ブリエルは妙な期待を抱く自分があまりにも憎かった。
「泣いてはいけません」
ブリエルは彼の静かな言葉を聞いて目の周りに涙が浮かんでいることに気づいた。
「すみません。私があえて・・・」
ブリエルはすぐに袖で涙を拭う。
「同情を買おうとしているのではありませんでした。そんな意味は少しも・・・」
ブリエルは彼が涙の意味を誤解するのではないかとすぐに説明を付け加えた。
本当にそうではなかった。
むしろブリエルは彼にいつものように厳しくしてほしかった。
「そんな誤解はしません。私はただ・・・」
ブリエルのぼやけた視界の向こうに彼はなんだか困っているようだった。
「あなたのことを何と呼んでなだめたらいいのか分からなくて困っていただけです」
「・・・はい?」
マクシミリアンは取り出したハンカチを押し出した。
「あなたの名前を聞きたいです」
そして、彼は他のところに視線を落とした。
「ずっと・・・そうでした」
マクシミリアンがカッコいいです!
最初から全てを知っていたとは・・・。
ここからの二人の関係が楽しみですね。