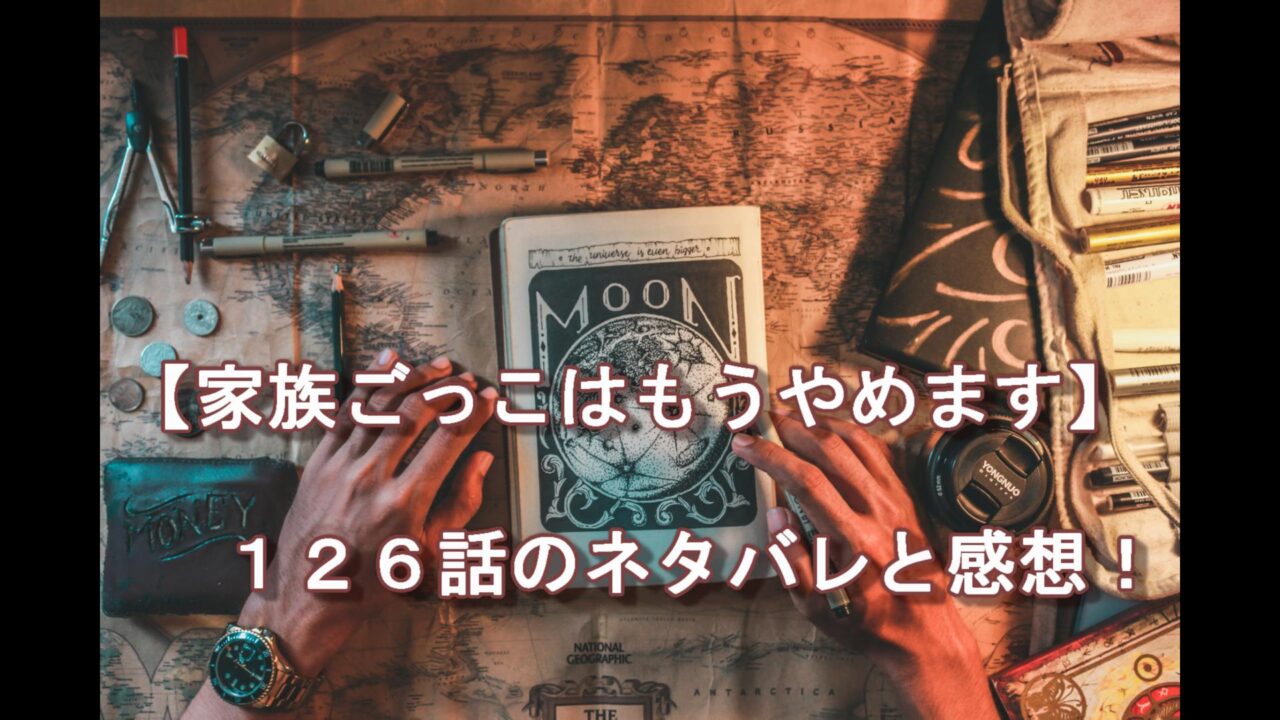こんにちは、ちゃむです。
「家族ごっこはもうやめます」を紹介させていただきます。
今回は126話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

126話 ネタバレ
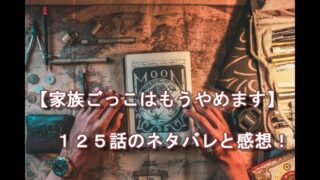
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 唇を求めて
クリードの目はウサギのように丸くなる。
彼は間違いなく自分が聞き間違えたと思った。
姉が急に自分にキスしてくれとせがむなんて、気の狂った妄想に違いない。
正直、休憩室に来ようと言った時、変な何かを思い浮かばなかったわけではないけど・・・。
ところで、その苦い風が急に現実になるなんて?
(・・・これは本物なのかな?)
クリードは頭の中が複雑になるのを感じ、できるだけ落ち着いて話し始めた。
「・・・うん?」
それが彼ができる最も理性的な反応だった。
「キスね。あなたと私が唇を重ねて・・・」
「ちょっとお姉さん」
彼は悟った。
これは自分の切実な妄想が作り出した幻聴のようなものではなかった。
ナビアは今彼が応じさえすればすぐに飛びかかるかのように目を大きく見開いている。
乾いた唾が自然にごくりと音を立てた。
ナビアは少しいらいらした表情で説明した。
「皇帝の安危に問題が生じたなら、私の力で治癒することができるって知ってるでしょ?」
ところで、それがどうしてキスしようということになるの?
クリードがそのような疑問をちょうど思い出した時、ナビアが明確な答えを出した。
「黒月は接触水位が高いほど魔力をより早く吸収する。私が皇帝に近づくためには、姿が見えないように透明化魔法を使わなければならないじゃない」
実際にはクリードが彼女に賭けてくれたかもしれない。
(生きていて、父が初めて私を助けてくれる瞬間だね)
クリードは皇帝といえば、震えるほど嫌だった。
母親を殺した張本人であり、甚だしくは自分も放置したくせに役に立つと思うと、すぐ息子と呼ぶ嫌な利己主義者。
事実、戦場に出ることになったのは魔力制御のために仕方ないことでもあったが、皇帝が参戦を勧めたこともあった。
息子が参戦してこそ士気が上がるのではないかとし、あなたはそのためにそのような強大な力を持って生まれたと話した。
皇子の義務を果たせ。
見掛け倒しのうわさだった。
そんな人間の血が自分に流れているという事実に時々酷い自己嫌悪がこみ上げるほどだ。
「本当に・・・でも大丈夫?」
キスするのは自分の望み通りだったが、一抹の罪悪感がしばらくためらった。
「頼む人があなたしかいないの」
ナビアは魔法使いではなく、今まで透明化魔法に対してはラルクが使うのを見たのが全てだった。
彼女は透明化の魔法が他人にも使えることを知らない。
それで一番理想的な方法として思い出したのがキスだった。
(口を合わせることくらいなら、人工呼吸も同じよね)
確かにこれはただの人工呼吸のようなものだと思いながらも、心臓は口から飛び出るように狂ったように動いていた。
(いや、これは絶対に性的な意味のものじゃないよ)
ナビアは自分が非常に理性的で鋭く冷静に判断していると信じていた。
しかし、心は焦っている。
「それとも透明化魔法を使える他の魔法使いを探してキスしなければならない・・・」
「やるよ」
ナビアが他の人とキスするなんて、想像だけでも殺意が沸き立った。
クリードはすぐにドアに手を突っ込み、上半身をくるりと下げる。
彼の影が一瞬にしてナビアを飲み込んだ。
お互いの顔が近づくと、これが魔力を共有してもらうための行為だということを知りながらも、さらに提案した方が自分であるにもかかわらず、どうしていいか分からない気持ちになった。
(本当にこれが最善かな?)
何度悩んでも答えは一つだ。
これが最善だった。
必ずしも透明化魔法でなくても、いざという時にナビアが武力を使えるということだけを見ても、10回も100回も口を合わせるのが得だった。
唇がぶつかる直前、クリードの顔がぐっと近づくと驚いて瞬きするナビアにクリードが静かにささやいた。
「ずっと私を見るの?」
「・・・」
その時になってようやくナビアは目をぎゅっと閉じる。
ナビアの羽のようなまつげがぶるぶる震えているのが目の前で見えた。
クリードは彼女が緊張していることを感じながら舌で唇をぬぐう。
理由は何かいずれにせよ、彼らのファーストキスだ。
彼女にこのキスがただ必要による行為であっても、クリードは違う。
彼はもう片方の手で後頭部を包み、ナビアの腰をしっかりと上げた。
ナビアは突然両足が宙に浮くと、素早く彼の首を両腕で強く抱きしめる。
実際、その必要もなく、まるでどこかにしっかり固定されたかのように安定的だった。
クリードは、隙間一つ許せないかのように、互いの体を重ねながら首をひねった。
すぐに二人の唇がかみ合った。
まず、唇の表面だけを見るように軽く含み、後ろに退く。
二つの唇の間に微細な隙間ができ、再び重なった。
ふっくらと膨らんだ唇をぎゅっと押したまま、柔らかく広げると、ナビアが喜んでそれに,応じる。
クリードは頭をさらに深く下げて口の中に潜り込んだ。
熱い息が交じってお互いを抱いた手がもっと強くなった。
その時になって、ナビアは「これは絶対に人工呼吸のような行為にはなれない」という事実に気づく。
全身が興奮でしびれ、思わず彼の頭を私の方にさらに引き寄せていた。
クリードはその手に着実に応じる。
焦るナビアをなだめるように、より深くキスをしながらゆっくりと足を踏み入れた。
歩くごとに体が優しく揺れ、いつの間にか休憩室に設けられた広いソファに体を重ねて横になった。
手を握って抱擁する程度ではびくともしなかった魔力が激しく流れてきた。
ここが皇居なのか森の真ん中なのか混乱するほと清涼で悦惚とした香りが全身を包み込んだ。
クリードのにおいがする。
まるで世界とかけ離れて彼らだけの森に閉じこめられ、お互いを欲しがっているような気がした。
(それでも足りない)
ナビアは体の中に魔力がぎっしりと積もっているにもかかわらず、より多くの魔力を望んだ。
(もっと、もっともっと・・・)
自分が望むのが果たして魔力なのか、それともクリードそのものなのか分からなかった。
とにかくナビアが考えるほどの魔力がまだ満たされていないのは事実。
ナビアは突然喉が渇いた。
理性の半分が飛んだ状態で、ナビアは新たな決断を下した。
魔力をもっと早く吸収したいから、ほんの少しだけ水位を上げようと。
ナビアはクリードが着ていた服を乱暴に脱ぎ始める。
クリードは気が狂っていたので、シャツのボタンを喜んで外す。
魔力がもっと早く流れてくるのが感じられた。
その感覚はクリードも一緒に感じていた。
クリードはいつも自分を苦しめていた魔力が早く安定化する驚くべき感覚を感じながらも、むしろこれがもっと苦しいと思った。
魔力が自分を苦しめない代わりに、もう性欲が苦しめられないように苦しめていたからだ。
夢中で重ねていた唇が一瞬落ちると、ナビアが焦げた声でむずむずした。
「だめだよ、もっと・・・」
少しも離れている時間がない。
そのため、クリードを自分の方に引き寄せて、彼女が先に唇を重ねて口の中を見回した。
クリードは本当に気が狂いそうだった。
それでも我慢した。
我慢しなければならなかった。
ここで犬のように発情することはできないから。
「・・・もういいの?」
クリードはまず唇を落としながら尋ねた。
その一方で、熱気が抑えられず、何度も唇の上を音がするほど吸い上げた。
ナビアはぽかんとした表情であえぎながらうなずいた。
「うん、いいよ」
「よかった」
クリードは低い笑みを浮かべながら彼女の鼻筋を見るように唇を当て、髪の毛が乱れて現れた額にキスをする。
到底愛さずにはいられない恋人に向けたわがままのように、頬と目元にキスを浴びせた。
彼は優しく上半身を起こして、ナビアの後頭部と背中を包んだ。
「もういいんだって・・・」
ナビアは困ったように言いながらも大きいクリードを押し出さなかった。
それができなかったというのがもっと正確だ。
今がどんな状況なのかも忘れるほど甘くて、このままもう少し夢に浸っていたかった。
そう思いながらも、まじめな性格に従った彼女の手は、クリードの広がったシャツを収拾してくれていた。
どうして人の体がこんなことができるのだろうと思う筋肉が白いシャツに徐々に隠され、適当に収拾されていく。
ナビアの身なりもまともではなかったので、クリードは早くから脱いで、まともな自分のジャケットを彼女に着せた。
「私がドレスをくしゃくしゃにしすぎて。気をつけるべきだったのに、ごめんね」
彼は許しを請い,再びナビアのこめかみにキスをする。
その間ナビアはどこかかすかな記憶にかくれた目で彼を見ていた。
(またジャケットだね)
8回目で自分にジャケットをくれたクリードが思い浮かんだ。
彼は前世でも今世でもこんなに優しかった。
その事実になんとなく気が引き締まる。
これ以上自分を隠すことができなかった。
騙すこともできなかった。
すでにキスまでしたところだったし、それ以上のことも思い出した。
それがすべて可能だった。
クリードなら、何でもできた。
それが意味することは明確だった。
魔力供給のためにキスをする二人。
ナビアも自分の気持ちを自覚したようです。