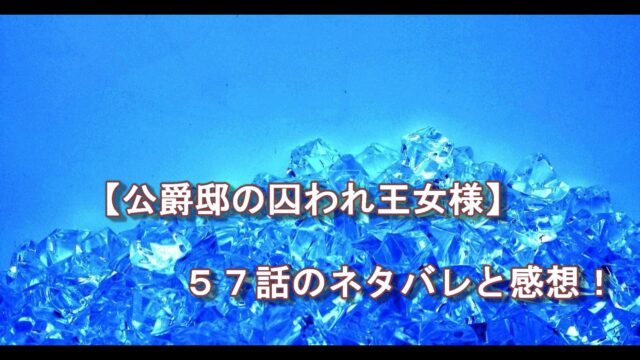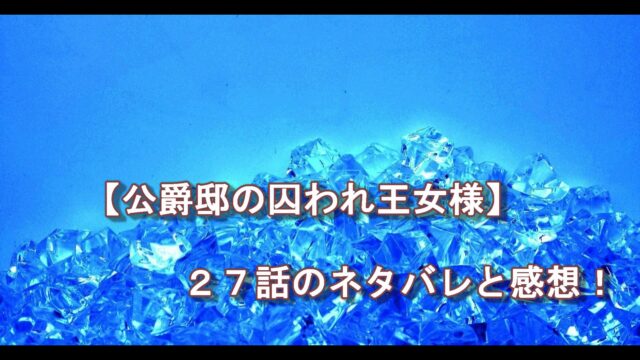こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

112話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 強襲③
一方ロザリーは抵抗をやめることなく暴れていた。
弱々しい腕をひたすら振り回しながら、鋭い罵声を浴びせた。
「セリデン公爵が来るぞ!この地獄の火に焼かれる奴らめ!あのお方が黙って見ているとでも思っているのか!」
「はあ……うるさいな。」
顔をしかめた男がロザリーの首筋に力強く手を振り下ろした。
ひたすら抵抗していた頑固な体がピクピクと震えるのも束の間、すぐに彼女は完全に力を失ったかのようにぐったりした。
「ロ……ロザ……」
まだ馬車の床にしゃがみこんでいたブリエルは両手で口を押さえたまま、ぐったりしたロザリーの体を見つめていた。
恐怖に突っ張ったままの自分の手は、もう感覚すらなかった。
まるで、あの冷酷なセリデンの冷気に凍りついてしまったように。
『セリデンの……冷気。』
彼女は無意識に口をついて出た言葉をつぶやいた。
「セリデン。」
北方の氷海に接した最初の地、勇敢な者だけが生き残れるというあの過酷な冬で有名な場所。
ブリエルは、その地で「奥様」と呼ばれる人物だった。
彼女は無理やり拳を握りしめた。
肉が裂けて赤く血が滲むと、少しずつ意識が戻ってくるようだった。
「……目的は何なの?」
瞬間、目を細めて問いかけたその言葉に、ロザリーを抱えていた男が驚いたように見えた。
「よくも私とあの娘をさらった目的を言わずにいられるな!」
その変化に、ほかの男たちも戸惑ったのか、しばらく互いに顔を見合わせた。
ブリエルは少し勇気が湧いてきた。
「要求があるなら聞こう。ただし、あの子は無事に返してもらう。」
マキシミリアンなら、おそらくこう言っただろう。
彼は自分の人たちを「家族」のように大切にしていた。
どんな状況でも彼らをまず心配していたのだ。
そう考えると、かすかに残っていた恐怖すらすっと消えていくようだった。
「罪のない夫人には礼を尽くせ。お前たちの目的はここ、私にあるはずよ。」
ブリエルはロザリーを抱える男をじっと見つめた。
雨音が一層強くなった。
お互いに視線だけを交わしたまま、誰も口を開かなかったのはそのせいかもしれない。
やがてその男が馬車に向かって歩を進め、ロザリーを放そうとしていた。
ブリエルの心に小さな安堵が芽生えた。
だが――
「お前たちは下がれ!」
男たちの背後から誰かが声を張り上げた。
ブリエルはびくりと驚いて首を上げた。
セカマン家の外套を頭まですっぽり被った人物が現れると、男たちはすぐさま両側に分かれた。
濃い雨と雲が作った影が深く、顔は見えなかった。
ブリエルは目を細め、じっとしたまま相手を注視した。
そして、ゆっくりと歩み寄ってきたその人物は、フードをゆっくりと脱いだ。
「……!」
暗いフードを脱いだその人物が少し近づいたとき、ブリエルは相手の顔を見ていなかったが、いくつかの事実は分かった。
相手が女性であること。
そして非常に身分の高い貴族であること。
ここに来た理由は、その人の歩き方がきっかけだった。
雨が降る舗道の森道でさえも優雅に踏みしめるその足取りは、明らかに長い年月鍛錬を重ねてきた成果であろう。
ついに、近づいた相手がゆっくりとフードを下ろし──暗がりの中でも、あの特徴的なワインレッドの髪がはっきりと見えた。
「……殿下。」
なんとデビナ・セイファースだった。
この王国で2番目に高貴な女性だ。
ブリエルは自分の見間違いではないかと疑った。
たとえ彼女が自分を殺そうとしているにしても、わざわざその場に現れることはないだろう。
少なくともブリエルが知る限り、貴族たちは皆そうだった。
計画を立てるのは自分たちでも、汚い仕事は必ず金で雇った者に任せ、自らは決して手を汚さなかった。
「すみませんね、セリデン公爵夫人。」
デビナが軽く笑いながら馬車のすぐそばまで来た。
その声はまるで久しぶりに再会した知人にかけるような落ち着いたものだった。
「ご覧の通り、私の可愛い手下たちがちょっと騒ぎを起こしたみたいですね。そうでしょう?」
彼女は馬車の中に手を差し伸べた。
ブリエルが床から立ち上がって椅子に座れるように手を貸そうとしているようだった。
『どう……すればいいの。』
ブリエルは自分に近づいてきた白い手を警戒するように見つめた。
一体、王妃の本心とは何だろうか?
王室の高貴な王妃様が、平民出身のブリエルに何か恨みでもあるのか、こんなところへ……。
『……公爵様のせい?』
一瞬そんな考えが浮かぶこともあった。
ブリエルは、彼女がマクシミリアンの元婚約者であるという事実が気にかかっていた。
たとえマクシミリアンがその婚約に心を動かしたことがないと知っていても、なおさらだ。
いずれにせよ、彼にとっては最初の婚約者だった。
それだけでも意味が深いのだと彼女は思った。
『もしかして王妃殿下も……?』
しかしやはり、違和感が拭えなかった。
たとえ彼女がマクシミリアンに未練があったとしても、この状況で得られるものは何もない。
「夫人、私の手を恥ずかしくさせるおつもりですか?」
鋭い声でそう言ったデビナは、ブリエルの手首を無理やり掴み引き寄せた。
「……っ!」
ブリエルは振り払おうとしたが、瞬間的に強く引かれて馬車の外へと引きずり出されてしまった。
冷たい雨粒が全身にぶつかり、次々と落ちてきた。
すぐに肩から崩れるようにして地面に倒れ込む。
そんな中でも、ブリエルは無意識に両腕で自分の腹をかばった。
一切の迷いもなかった、本能的な行動だった。
雨音に混じって、デビナがくすくすと笑い声を漏らすのが聞こえた。
「……詐欺師のくせに。」
それは……。
ずっと昔にブリエルが自分をそう呼んでいた言葉だった。
今はマクシミリアンとすべての真実を共有する関係になり、しばらく忘れていたが、というわけだ。
「やっぱり、何の返答もできませんね。それ、マクスの子じゃないんでしょ?」
「……えっ?!」
想像もしていなかった言葉に、ブリエルはあまりに驚いて思わず口を押さえてデビナを見上げた。
「どうして分かったのかって顔ですね。」
「いや、私は。」
「私は……わかるんです、なぜなら。」
デビナは膝を折ってブリエルと近い距離で目を合わせた。
「私でもそうしたと思うから。欲望の権利を守るためなら……誰の子でも。」
「違います!絶対にそんな……!」
「主人の子供だと言い張れば簡単な話でしょう?まさか公爵夫人の貞操を疑う人なんていないでしょうし。そうじゃありません?」
ブリエルの服を掴んだデビナが、悲しそうに微笑んだ。
「心配しないで。マクスは永遠に気付かないわ。マクスは……」
怒りに満ちていた彼女の声が、マクシミリアンのことを語る時だけは驚くほど柔らかく甘かった。
そのわずかな変化だけで、ブリエルは自分の予想が全く外れていなかったことを悟った。
「……シシィの裏切りを知れば耐えられない。」
視線を外しながら、小さくつぶやいた話にブリエルは反応した。
「シシィ……?」
「ええ、マクシミリアンの……本当の婚約者。」
一体何を言っているのか。
本当の婚約者だなんて、ブリエルは目を見開いたまま、デビナをただ見つめるしかなかった。
「死んだと思ってたのに。みんなそう思ってたのに……本当に運がいいですね。そうじゃないですか?」
ブリエルを見つめる彼女の緑の瞳の光が妖しく変わった。
少しずつ理性が消えていくようだった。
「な、何をおっしゃって……」
「何って言えばいいか。」
いつの間にかデビナの手には短剣が握られていた。
その鋭い先端がブリエルの喉元へと向けられた。
「私は、誰も信じない。」
震える手で握ったその剣の先もまた、止まることなく揺れていた。
白い喉元に、その不器用な刃先で赤い糸のような跡が残っていた。
「誰にも任せない、必ず自分の手で、二度と……!」
彼女の声は徐々に震え始めた。
「二度とあなたが私を止められないようにしてやるわ!」
そしてデビナは片腕を高く振り上げた――
きっと一瞬の出来事だったのだろうが、ブリエルの目にはやけにゆっくりと映った。
それだけではなかった。
いつの間にか顔を打っていた雨も感じられなくなった。
寒さと恐怖でガタガタ震えていた体も驚くほど落ち着いてきた。
剣先がだんだん近づいてくる。
その距離だけ首筋を残して、ブリエルは現実から数歩離れているような感覚に陥った。
この違和感は一体何なのか。
「私の手であなたを……」
デビナが再び口を開いた。
これまでとは違って、ほとんど声にならないささやきに近い言葉だった。
「必ず殺してみせる。」
ブリエルはその唇の動きが……なぜか見覚えがあると感じた。
『見覚え……があるって?』
彼があのような残酷な言葉をささやいていたのを聞いたのは、事実だった。
伯爵家の一人娘として暮らしていた頃のことだ。
だが、こんなに惨めな暮らしではなかった。
『これは……伯爵家にいた時の記憶じゃない。』
もっとずっと昔のこと。
普段は「知らない」として片づけていた、あの暗い領域が頭の中で再びざわめいた。
「この手でお前を……必ず殺してやる。」
黒マントをまとった男がそう言った。
冬であり、森だった。
ブリエルは外套もなく寝間着姿で、不満げに腕を抱きながら彼を見つめていた。
「殺す」と言われたが、なぜか怖くはなかった。
それは……男の足に深い傷があったからだ。
裂けた服の間から覗いたその傷の深さに心配になり、ブリエルは顔をしかめた。
「……おじさま、痛い?」
男は騎士ではなかった。
だが、それは大人になった今だからわかることにすぎない。
幼い子どもにとって、武器を持った大人はみんな「おじさま」と呼ぶのが自然だった。
「……!」
思いがけない言葉に、男は思わず驚いた。
「痛いのは嫌なのに……」
ブリエルは唇を噛んでいた手を離し、彼の痛む脚をそっと抱きしめた。
「ねえ、うちのパパは、ナデナデしてあげると痛くないんだって。」
そして破れた服のすき間から見上げる子どもの顔の上に、男はゆっくりと剣先を下ろした。
しかし、それも長くは続かなかった。
すっとその手から剣が離れ、音もなくその白い目の上にストンと落ちていった。
「お前……」
男は自分の足にしがみついていた子どもを乱暴に引き剥がし、その子の両肩を掴んだ。
『生きたい……?』
あまりに当然すぎる問いだったので、ブリエル……いや、シシィは喉を詰まらせた。
その呆然とした姿のせいか、男はしばし言葉を失ったように笑った。
『乞うのか、俺もそうだ。』
彼は落ちていた剣を手に取り、子どもの長い髪を切り落とした。
彼の手に残った血混じりの銀髪は、たちまち証拠品になった。
『……よく聞け、お嬢ちゃん。』
男は子どもの体を引き寄せ、目の前へと引っ張った。
『ここは猛獣の狩場だ。少しでも血の匂いがしたら、飢えた獣どもがお嬢ちゃんを追ってくるぞ。』
彼の吐く冷たい息が、シシィの顔に容赦なくかかった。
子どもは何も答えなかった。
「わかった?お願いだから、俺の手を汚さなくても、子どもは絶対ここでは生き残れない!お前はどうせ死ぬんだ!」
それは、なぜか彼自身を納得させるための言葉のように聞こえた。
シシィは遅れてこみ上げる恐怖に、小さく喉を鳴らした。
男はしばらく視線を落とした。
そして静寂が訪れた。
空から雪が落ちる音がはっきりと聞こえるほど、あまりにも静かだった。
「……それでも。」
しばし沈黙の後、男はシシィを握る手に少し力を込めた。
「もし、万が一、お前が生きて……」
「……」
「誰かに会ったら。」
男が視線を上げた。
再び見つめ合ったその目は、あまりにも切実だった。
本当に、何かを願っているように見えた。
「お願いだから君を助けてくれって言って。そして……何も知らないって言うんだ。」
「……きょ、恐縮です。」
「自分の名前も、親も……知らないってことにして。」
シシィは喉を鳴らした。
彼女は自分の名前と家門を忘れることはできなかった。
だから「知らない」と言うのは嘘になってしまう。
「はあ、でも……嘘は悪いことって言われたよ。叱られる。」
「そうしないと君が……死ぬ。」
男は短くなったシシィの髪を撫でながら、再び言った。
「俺が先に死ぬさ。」
「……!」
「だから、お嬢ちゃん。」
「も、もうしゃべりません!」
小さな手で口を少し覆った子どもが、震えながら答えた。
自分を殺そうとしていた男を安心させるために。
「私、何も知りません。おじさまを殺さないでください!」
そう叫んだとき、すぐ近くの草むらで何かが動く気配があった。
なぜか体中に音が響くような……。
「思ったよりしぶとかったみたいね。血の匂いを嗅ぎつけたのか。」
そうつぶやいた男が、再び剣を構えてシシィの前に立ちはだかった。
「……おじさま。」
「お嬢ちゃん、約束したよね?」
彼が振り返って言った。
「君も僕を助けるって。」
子どもはそっと喉を鳴らし、彼は剣先で森の反対側を示した。
「そっちに走るんだ。」
「……」
少し離れた茂みで鳥が驚いて飛び立ち、巨大な何かが動くのが見えた。
本能が「とても恐ろしい獣だ」と警告していた。
シシィが不安そうに見上げたのも束の間だった。
「行け!」
男が子どもの小さな肩をぽんと押した。
倒れそうになったが、すぐに体勢を整えて、シシィは彼が教えてくれた方向へ夢中で走り出した。
バシャッ!
少しして背後から聞こえてきた鋭い音に、シシィは後ろを振り返った。
男の剣が獣を切り裂くと、羽毛の血が彼の頭上に降りかかっていた。
彼はその血を浴びたまま、子どもを振り返って見た。
目が合ったのか?それはわからなかった。
気がつくとシシィはまた走っていた。
体を包んでいたぬくもりある毛布もどこかへ落としてしまったまま。
そして、その道の果てで出会ったある夫人にこう言った—「お願いです、助けてください!」と。
驚いた婦人は凍りついた手をほどき、子どもの体を抱き寄せながら尋ねた。
「まあ、坊や。ご両親はどこにいらっしゃるの?」
子どもはごくりとつばを飲んだ。
そして答えた。
「わ、わかりません……。」
その答えを口にしたとき、子どもは深い安堵を感じた。
恐ろしい猛獣を防いでくれた優しい人との約束を守れた、そんな純粋な喜びも混じっていた。