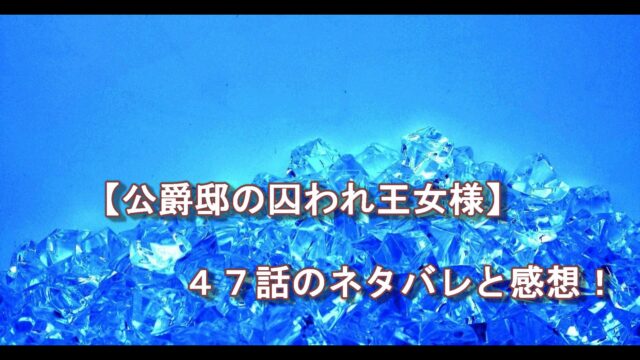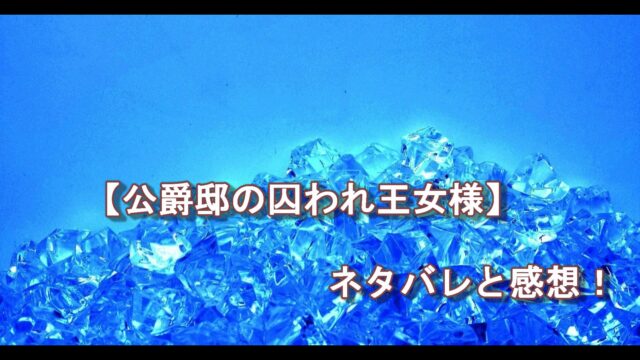こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

122話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 王子の悩み②
バレンタインが悪いのは事実なので、彼もそれ以上は問い詰めなかった。
「はぁ……とにかく、一度帰って洗顔でもして来ようかな。」
「むしろ部屋で少し寝てきたら?」
「だめです。そうしたら夜にまた眠れなくなりますから。」
「昨日寝られなかったの?」
「はい、眠れなかったので、そのまま朝まで……本を読んでました。」
「じゃあ、自習室にでも来ればよかったのに?僕も結構遅くまでいたんだけど。」
「う……」
クラリスは少し困ったように目をそらしながら視線をさまよわせ、ぎこちなく笑って襟元を直した。
「しばらく自習室には昼間しか行かないことにしてます。」
「えっ、お前も見たの?」
クラリスがビクッと反応した。
「自習室の闇の幽霊。」
「え?」
「ここで有名でしょ、深夜に自習室の隅でうめき声がするっていう、あの噂の幽霊。」
もちろんバレンタインはそんな陰気な幽霊なんて全く怖くなかった。
根性がないと死ぬまで勉強する鬼教師なんじゃないのか。
でもクラリスはなぜか本気で怖がっている様子だった。
顔色が青ざめて毛布をきゅっと握りしめているのを見ればわかる。
「もう、バカなこと言わないでくださいよ。首都に幽霊なんているわけないじゃないですか。」
「首都だから多いんだよ。朝、登校する時に道沿いにお地蔵さんがずらっと並んでるの見たことない?」
「……っ!」
見るとクラリスはすっかり目が覚めてしまったようだ。
怖がる姿がなぜか面白くて、バレンタインはくすっと笑った。
「幽霊が多いってわかったなら、もう夜更かしせずにぐっすり寝ろよ。」
「……冗談ですよね? そんなのウソでしょ?」
「後でマクルドに聞いてみてよ。もし本当だったら、ゾッとするよ。」
「マクルドさんが、そんな非現実的な存在を信じるわけないでしょう。」
「まぁ、好きに考えなよ。ところで今日はまだ勉強、たくさん残ってる?」
バレンタインは自然にクラリスの前に置かれたスケジュール帳に手を伸ばした。
二人は互いのスケジュールを共有しているようなものだったので、特に距離感を感じさせる行為ではなかった。
少なくとも……今までは。
彼がスケジュール帳を開いた瞬間、何かを察したクラリスは慌てて彼の手からそれを奪い取った。
「み、勝手に見ないでください!」
「……?」
一瞬でスケジュール帳を取られたバレンタインは顔をしかめながら、クラリスを再び見つめた。
「先週も私のノート勝手に見たでしょ?」
「そ、それは……ごめんなさい。もうしません。」
いや、彼はそのことを謝ってほしかったわけじゃなかった。
クラリスと彼は予定を共有するような間柄でもなかったのだから。
だから彼が言いたかったのは、なぜ急に秘密があるかのように振る舞うのかということだった。
今もノートをぎゅっと持ったまま、彼の目をうかがっているじゃないか。
「君、何か隠してるんじゃないの?」
「絶対にありません。」
ある。間違いなくある。
バレンタインはクラリスが握るノートをもう少しのぞき込んだ。
さっきチラッと見えた今回の予定が、ひとつひとつ思い出される。
「わ、私、これから部屋で一人で勉強します!」
慌てて席を立ったクラリスは机の上に置いてあった本とノートを素早く片付けて、かばんの中にササっとしまった。
「お昼の時間にまた会いましょう、王子様!」
バレンタインはあっという間に姿を消したクラリスをぼんやりと見つめていた。
『そういえば、さっきスケジュール帳に……』
他の誰かの筆跡で書かれた予定があった。
筆跡だけで性別を判断することはできないが、どう見ても男性の字に感じられた。
しかも「ダーリン♡」のような嫌な感じの言葉まで書かれていた気がする。
あの騒がしいやつのスケジュール帳に、そんなふざけた愛称がなぜ書かれているんだ?
いや、そもそもこの首都でクラリスにあんなふうに呼びかける相手が存在しているはずがない。
とはいえ、明確な相手もわからずにクラリスにちょっかいを出そうとした学園内の男子が何人かいたことはあった。
がっかりするほどみんな臆病で、まともに話しかけることさえできるやつはいなかったという話だ。
でも一体いつの間に……?
『は、別に俺が気にすることじゃないし。』
クラリスが誰を『ダーリン』と呼ぼうが『あなた』と呼ぼうが、それが一体何だっていうんだ。全然関係ない。
好きに呼べばいい。
『ああ、気にしないってば!』
彼はなぜかイライラが込み上げ、拳をぎゅっと握りしめたまま自習室を出ていった。
そして今日。
クラリスのノートにあの「借り物」の文字が書かれているのを見た瞬間、バレンタインは絶句してしまった。
彼は初めて、こんなときノアがいてくれたら良かったのにと思った。
『お前、こんな状況でも魔法使いの城でのんきに何してるんだよ……。』
正直言って、ノア・シネットのクラリスに対しての片想いは本当に重度レベルだった。
行けば行くほど好きすぎて死にそうな目つきを毎日浴びせてくるのだから。
もしこの状況をノアが知っていたら、神秘的な魔法でクラリスの男が誰なのかをすぐに暴き出していただろう。
……いや、その男の身体を破壊して消し去ることだってあり得た。
『俺がなんで気にするんだ。』
でもこれはまた何かの不運なのか?
勉強の本を手に取って怒ったような目つきで部屋から出ていくバレンタインの視界にクラリスの後ろ姿が映った。
どこかへ向かうその姿は普段とよく似ているようで、どこか違って見えた。
『後ろ姿まできれいだなんて……!』
最近はまともにとかしてもいなかった髪をきちんと束ねてまとめていて、今日はきちんと髪を整えてきたようだった。
さらに普段とは違う香水でも使ったのか、自分の手の甲に鼻を近づけて香りをかいでみた。
『一体誰の気を引こうとしてるんだよ。』
気づけばバレンタインは数歩離れた場所で彼女の後をつけていた。
なぜか悪いことをしているような気がしたが、彼はすぐにこの行動の正当な理由を見つけ出した。
『王宮の人間として当然のことだ。』
クラリスは滅びた王国の唯一の王族だ。
もし誰かが彼女に近づいてグレジェカイアの財産を主張しようとしたらどうする?
だからこそ、王宮の一員であるバレンタインには、彼女が不穏な行動を取らないか監視する義務があった。
『それだけだ。』
クラリスが向かったのは礼拝堂だった。
「……なんだよ。」
静かな礼拝堂の扉を押して入っていく後ろ姿を見ながら、バレンタインは苦笑いを浮かべた。
だって、礼拝堂で密会を楽しむ人なんているわけがないから。
あそこは常に万人に開放されている場所だった。
いつ誰が来るかわからない空間で秘密の恋愛を楽しむ人がいるだろうかという話だ。
『いや、むしろだからこそふさわしいのか?』
礼拝堂なら、偶然相手に会ったかのようにごまかせるだろうから。
バレンタインは、最後まで確認してみようという思いで礼拝堂の扉を押して開けた。
独特の香油の匂いが深く吸い込まれ、心の奥底から敬虔な気持ちが湧いてきたそのとき、彼は目撃してしまった。
礼拝堂の一番前に立つ二人の姿を。
一人はクラリスで、彼女はある男性と優しく向き合って立っていた。
いや、それだけではなかった。
彼女は明らかに何かを恥ずかしがっていた。
そうでなければ、あの妙にぎこちない表情を説明することはできなかった。
「何言ってるんですか?! 私の髪は清潔ですよ!」
そして彼女と楽しそうに会話している男は……。
「ふざけないでください。少なくとも私の『恋人』なんて、そういうことは言いません!」
エイビント・ベルビルだった。
「私の『恋人』なら、髪が汚いなんて絶対に言わないんですよ!」
は? あの野郎だと?
一瞬すごく気が抜けた気分になったバレンタインは、手に持っていた本をぽとんと落としてしまった。
「……?」
気配を察したクラリスが驚いて彼を振り返った。
まるで見てはいけないものを見たかのように、ぱっと驚くその表情……。
『クソ、なんで可愛いんだよ?』
彼はまたしても勝手にドキドキする自分の心臓を、どこかに投げ捨てたくなった。
「本当に……ひどいよ、お前。」
「わっ、王子様。違うんです!」
クラリスが慌てて弁明しようとしたが、バレンタインはそれ以上聞きたくもなかった。
この状況でも律儀に、あの取り柄のないライバルの手を握っていたのだから。
「なんであんなやつなんだよ!?」
「いったい何を誤解しているんですか?!」
クラリスはようやくエイビントンの手を振りほどき、彼の前に駆け寄った。
「私が好きでこうしてるわけじゃないんです!」
「別に好きなわけじゃない……?」
バレンタインはなぜか感情がぷつりと切れた気がした。
「そんなにきれいな顔で『ダーリン』って呼んでおいて……?」
「はい?」
「いや、だったら好きな相手にはどれだけ甘くするっていうの?」
「王子?いったい今、何を……」
クラリスが何がなんだかわからない様子でぽかんと見つめてくると、バレンタインは内心が爆発しそうで死にそうだった。
なぜわからないんだ?
毎日恋愛小説を読みふけっておきながら、こいつが何を言っているのかわからないなんてありえるのか。
「お前バカか?俺が好きだって言ってるんだよ、クソ!」
そして彼は逃げるようにその場を離れた。
最悪だ。
バレンタインは自分の部屋に戻って壁に頭を打ち付けた。
痛かったが、彼は愚か者だったので、このくらいの苦痛は当然だと感じていた。
二十回くらい頭をぶつけていたとき、ユジェニーがやって来て騒音苦情を申し出たので、やっとやめたのだった。
「いやもう、マジで最悪。」
なぜあんなことを衝動的に言ってしまったんだろうと。
「違うよな?いや、百歩譲ってああいうことをしでかしたとしても、しおらしく出てこなきゃ、あんなに堂々と出てきては……。
『あのお人好しのやつ、どれだけ困ってることか。まったく。』」
彼はまた冷たい壁にもたれかかった。
できることならドンと頭を打ちつけたかったが、ユジェニーがまた駆けつけてくるかもしれず、それもできなかった。
しかも、クラリスがそのまま立ち去るとも限らない。
落ち着かないと。
幸いなことに、彼にはひとつ希望があった。
それはクラリスが“空気を読む”ということにまったく縁がなく、しかも鈍感だということ。
つまり、クラリスには恋愛小説の古典的なルールがそのまま適用される可能性が非常に高いという意味だった。
「きっと、“友達として好き”って意味に勝手に解釈してるに違いない。」
そうだ、そうだよな。
バレンタインは自分なりの結論に満足しながら再び課題をめくった。
これなら解決は非常に簡単だ。
特別な相手ができたことをバレンタインに事前に言わなかったから怒ったんだと言えばいい。
だってクラリスは「好き」って言えるほど親しい友達なんだから、そんな話を後から聞かされたら怒るのは当然じゃないか。
その特別な相手が本当にあの巡査かどうかは後で改めて聞けばいいだけの話だった。
いや、合ってようが間違ってようが、あんな奴に「ダーリン」なんて呼ばせるなんてさ。
「……俺もまだ聞いたことないのに。」
バレンタインは、あの憎たらしいエイビントンが羨ましくて死にそうだった。
バレンタインはなんとなくカーテンを何度かめくってからようやく部屋を出る決心をした。
これ以上時間を引き延ばしても意味がないと思い、すぐにクラリスの部屋を訪ねてノックした。
返事はなかった。
『まだ礼拝堂にいるのか?』
そう思って階段の方へ向かうと、1階の中庭であわただしく左へ進んでいく淡いピンク色の制服が見えた。
彼女は何かを考えているのか、ひとりでずっとぶつぶつ言いながら木々の間をせわしなく歩いていた。
『……何してるんだ?』
いぶかしく思いながら階段を下りて庭の近くまで行くと、クラリスがひとりでブツブツつぶやくような声がかすかに聞こえてきた。
「ですから……私が……」
正確な内容は聞き取れなかったが、なにかを弁明しているようだった。
「……王子様は。」
そしてバレンタインを隠すような言葉も聞こえた。
それが妙におかしくて笑みがこぼれた。
クラリスが何を言おうか迷っている様子を見るのは本当に楽しかったからだ。
もっとも、彼女はバレンタインの正直な気持ちをこれっぽっちも理解していないようだったけど。
「はあ……本当に鈍感なんだから。」
彼はため息と少しの切なさを感じながら一歩前に出た。
気配を感じたクラリスが驚いて彼を振り返った。
視線が交わった瞬間、彼はクラリスの反応をいろいろと想像してみた。
もしかして勢いで怒ったりしないだろうか?
さっきは急に逃げ出したと思ったら、今度は急に現れて、不満そうな目でこちらを見つめてくるなんて。
今まで彼女に伝えようと必死に考えていた言葉をすっかり忘れてしまったのだった。
『きっとそうだろう。』
少し前の「好き」という言葉にどれほど真心を込めてしまったのか分からないまま、その件は何となく過ぎていった。
『最初はそう……なるものでもあるし。』
彼はどこかすねたように自分の気持ちをなだめるようにして、うっすらと笑みを浮かべながらクラリスの前に立った。
「……あ。」
ところがクラリスは彼をじっと見つめるだけで、怒るようなそぶりはなかった。
「なんで黙ってるんだ?君らしくないな。」
彼はそう尋ねかけようとしたが、やめた。
そうするしかなかった。
耳まで赤くなったクラリスが、震える両手をぎゅっと握りしめているのを見てしまったのだ。
そのうえ彼を見上げる瞳は、微かに震えていた。
非常に緊張しているのが明らかに見えた。
『え……?』
なんでこんな反応?
まさか、あの一言の意味がわかったってこと?あの鈍い子が?
『そ、そんなわけない。』
否定したかった。
だけど、なにか言おうとして口を開いたまま、じっと口元を引き結ぶその様子を見ていると……。
『ほんとに?』
やられた。バレンタインはどうしてもそうとしか思えなかった。
この、思わず口をついて出た告白をしっかり受け取ったって?
ふざけるな、自分の人生にそんなミスがあるはずがない。
『ち、違うってば、あんなの告白じゃない!なんでこういうときだけ察しがいいんだよ!』
自分が知っているどんな立派な騎士だって、あんな風に気持ちを表したりはしないはずだった。
だけど「王子様」となった彼は、そんな告白を中途半端に終わらせるわけにはいかなかった。
彼のプライドが――これは到底許されることではなかった。
「言ったじゃないですか、王子様。少し前に……。」
「お、お前!私たちの友情を踏みにじったな!私たちの深くて強い友情を!」
勇気を振り絞って話し始めようとしたクラリスを制して、バレンタインは慌てて友情を前面に出して叫んだ。
「えっ?」
するとクラリスはまたしても驚いた。
その様子を見ると、どうやらバレンタインがクラリスにとって本気だと思われていたようだった。
『まあ、そうかもしれないけど。』
とはいえ、今は違うと伝えねばならなかった。
彼にそんな度胸はなかった。
「で、でも僕が他の意味で君をす、す、好きだと思ってるなんて思ったの?」
嘘をつくのが得意な方でもなかったが、なぜかしどろもどろに言い切ってしまった。
もしかして、空気が読めるようになったクラリスがこれまで気づかれたらどうしよう。
彼は一瞬心配になった。
「何があったのかちゃんと言わないと、今度こそ本当に怒るからね。」
彼はあわてて話題を彼女の事情に切り替えた。
「……本当に違うんですか?」
そんな努力もむなしく、クラリスが気にしている様子は彼の心を少し痛めた。
「違うって何が?」
「ほら、王子様が少し前に。」
クラリスは少し周囲を気にして、慎重に声を落として言った。
「……好きだって。」
両頬が真っ赤になって、その話をしている顔がとんでもなく可愛らしかった。
思わず「そうだよ、俺もお前が好きだ!」と言ってぎゅっと抱きしめたくなる衝動が……。
『落ち着け、バレンタイン。』
彼はうっかり手を伸ばしそうになるのをこらえ、軽く自分の髪をなでて気を紛らわせた。
「君はどうしていつも私のことを嫌いだって言うの?もう私のこと嫌いになったの?」
「え?!あ……そんなことありません。」
「そう?よかった。僕たちの長い友情が固いから。」
バレンタインは「友情」という言葉に力を込めた。
もしこの世が小説の世界なら、その文字が強調されて太字になり、アンダーラインまで引かれていたことだろう。
「本当ですか?」
クラリスはまた同じ質問をしてきた。
「気にしなくてもいいよ。君が僕をどうにかしてみたいって気持ちはよくわかったから。」
「そ、そんなこと考えてません!私はただ、もしも……王子様が……」
「僕が何?」
「……お辛かったんじゃないかって。」
クラリスはうつむき加減に話しながら、やがてうなずいて話すのをやめた。
「とにかく、私も王子様のことが好きです。」
「………」
「……王子様?」
「いや、なんでもないよ。うん、それで。」
バレンタインは何度も咳払いをしてようやく心を落ち着かせることができた。
「あのときの、あのバタつきは何だったの?」
「えっと、それは。」
エイビントの話を始める段階になってようやく、ようやく彼が知っているクラリスに戻った感じがした。
「見てください。ほら、字があるでしょ!」
もうすっかり怒り気味の顔が可愛くて、バレンタインは詳しい説明が始まる前に思わず笑みをこぼした。
やっぱりクラリスとはこのくらいの距離感がちょうどいい。
まだ、まだね。