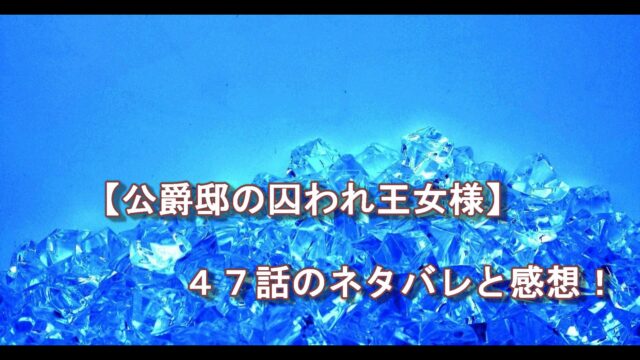こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

114話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 親娘②
クラリスとノアは侯爵夫人と一緒に三番目の城壁に戻ってきた。
実はノアは三番目の城壁で見張りをしていたのだが、今は公爵の要請を受けてクラリスと一緒に来ているのだ。
「はあ、どうしよう?」
つま先立ちして耳打ちするクラリスの声に、ノアは苦笑して肩をすくめた。
「少女が考えるようなことは起こりませんよ。ひと目見ただけで分かるなんて。」
「でも!」
クラリスは思わず大声を出してしまった。
前を歩いていたクノー侯爵夫人はもちろん、彼女を案内していた執事までもがクラリスを振り返った。
彼女は顔を両手で覆いながら、何でもないというふうに笑って見せた。
幸いにも彼らはそれ以上問いたださず、階段を上がっていった。
公爵夫人の部屋へと。
「もしかすると……魔法の力がなくても、二人が互いを見分けられるのかもしれないと思ったの。」
「今はその宝石の言葉を本当に信じてるんだね。」
「どうして信じずにいられるの?あれほど強い啓示を受けたのに。」
クラリスは小さなポーチの中に入っている宝石をそっとなでた。
ブリエルが倒れていた現場に落ちていたそれを、クラリスが拾って保管していたのだ。
公爵夫人の危機を知らせてくれたのはこの宝石だった。
[ピッピッ!私はシシの応援隊だよ!私と一緒にシシを守る光物は……]
うーん、ありがたいけど話が長くなるのは困るなと思った。
クラリスは冷たい宝石をポケットにそっとしまった。
「とにかくあまり期待しすぎないで。」
ノアは冷静に答えた。
侯爵夫人と公爵夫人が本当に親子だったとしても、共に過ごしてきた年月は他人として生きてきた時間よりはるかに短いはずだ。
ひと目でお互いを見分けられるはずがなかった。
ブリエルの部屋の前に着くと、控えていたノクという執事がすぐにドアを開けた。
そしてついに侯爵夫人が開かれたドアの向こうに足を踏み入れた。
「無断で押しかけてしまい申し訳ありません。ただ、様子だけ伺ってすぐに帰りますので……。」
優しいあいさつの言葉を続けていた侯爵夫人の話が、ふいに止まった。
まるで彼女の視線がベッドに座っているブリエルに触れた瞬間だった。
世界全体が止まってしまったかのような深い沈黙の中で、クラリスは両手を胸元でぎゅっと組み合わせた。
「……シシ?」
しばらくして、侯爵夫人がそっとその名前を呼んだ。
その響きには、深い恋しさと同じくらいの慎重さがにじんでいた。
クラリスは今、ブリエルを見つめ返していた。
実は少し前までは「お互いを認識できるかもしれない」という夢のような希望を語っていたが、実際にこんな状況になってみると、少し不安になっていた。
ブリエルは過去を見つけることに必死だった。
しかも、よみがえる記憶は一つもなかったのだ。
『それでも、きっと!』
クラリスは組んだ手にぐっと力を込めた。
今が、侯爵夫人が一生待ち続けてきたその瞬間なのだから。
だから、一度でも奇跡が起こってお互いを見分けられるようにと願いながら。
「申し訳ありません、奥様。こちらは私の妻の……。」
しかし、マキシミリアンが先に答えた。
彼は戸惑いながらも、侯爵夫人に落ち着いてブリエルを紹介した。
「ブリエル・セリデンです。」
クラリスは当然だと思いながらも、なぜか少しがっかりして視線を落とした。
その時だった。
「シシです!」
突然ブリエルがそう言った。
皆が驚いて彼女を見た。
しかし動揺しているのは、どうやら彼女自身も同じだったようだ。
「そ、それで……。」
彼女はしどろもどろになりながら続けようとした。
「もしかしたら、そうかもしれません。私、突然いくつかの記憶がよみがえって……それが私を“シシ”と呼ぶ場面だったので……」
もちろん、ブリエルが侯爵夫人の呼びかけに心を動かされたのは、ただその記憶のせいだけではなかった。
懐かしかったのだ。
侯爵夫人が“シシ”と呼ぶ、あの声の調子と雰囲気……なぜか知っている気がした。
なぜそんな気持ちがするのか、彼女自身にも説明できなかったが、確かにそうだった。
「……え?」
侯爵夫人とブリエルの間に立っていたマキシミリアンは、茫然と立ち尽くした。
彼の両目は混乱で震えていた。
「違うかもしれません……私がそんな偉いお嬢様だなんて、なぜか似合わない気もして……わかってはいるんですけど……」
「いいえ……違うわ。神よ」
まるで凍りついたように立っていた侯爵夫人が、ついに唇を開いた。
震える足取りでブリエルに近づいた。
「どうして……どうして違うはずがないの。どうしてあなたが……あなたが私の娘じゃないはずが……。」
彼女は震える手を差し出した。
「ああ、神よ。これが夢なら、どうか……。」
ブリエルはしばらくそのしわだらけの手をじっと見つめた。
侯爵夫人は、もしこれが夢で、目が覚めたときに消えてしまうのではないかと、恐る恐る触れようとすらしなかった。
それほど切なる思いを抱えている方だった。
しかし、ブリエルは……。
『どうせ彼らには私が必要なかったから捨てたんでしょ。』
親が自分をあっさりと捨てたと、何度も心の中で確信し、恨み続けてきた。
ついに、夫人の震える手がブリエルの頬に触れた。
どんな宝石よりも貴いものを触るかのように、とても慎重だった。
「……神よ、ひとつも……変わっていないわ。」
現実とは思えないこの状況に気づいたのか、夫人はブリエルの顔を両手で包み込んだまま、涙を流しながら言った。
「セシリア、私の……娘。」
涙が絶え間なく流れても、彼女は決してブリエルから目を離さなかった。
「……ごめんなさい、私……」
ブリエルはなぜか彼女と一緒に泣きたくなる気持ちを必死にこらえて、まずは謝らなければと思って口を開いた。
「私、自分が見つかるなんて思わなくて……それで……」
夫人は慌てて首を振った。
「あなたは何ひとつ悪くないわ。」
「でも私、どんな思いをしていたかというと……」
「こんなにも元気でいてくれて……ああ、神よ。」
彼女は何度もブリエルの頬を撫でながら、また撫でた。
「本当に私の祈りを聞き届けてくださったのね。」
「まさか……見つけてほしいと祈っていたんですか?」
ブリエルの言葉に、彼女はただ黙って頷いた。
「私はいつも……あなたの健康を祈っていたの。お願いだから……。」
「……。」
「たとえ私たちが会えなくなったとしても……あなただけは……元気で幸せでいてほしいと。」
ブリエルは、どうして自分がこれまで幸せでいられたのか、その答えをようやく知った。
二人もの優しい母が、彼女の幸せをそれほどまでに強く願ってくれていたからだ。
「……もしよければ。」
ブリエルは、唇の下でぎゅっと握りしめていた両腕をそっと開いた。
「私……抱きしめてもいいですか?」
しかし、その言葉が終わる前に、ブリエルはすでに夫人の胸の中に抱きしめられていた。
「……ああ。」
その胸から聞こえる心臓の音は、明らかに聞き覚えのあるものだった。
もはや何の説明も必要なかった。
ブリエルは両手を高く上げて、夫人の背をしっかりと抱きしめた。