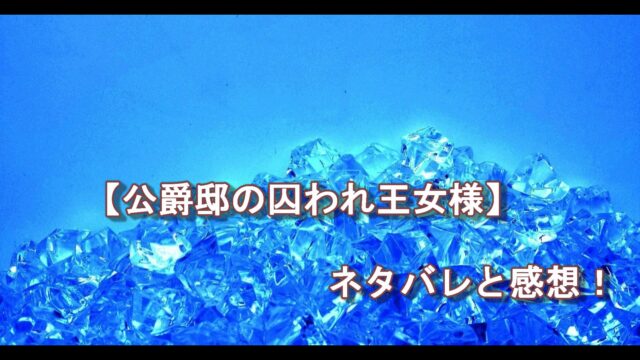こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

115話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 血縁調査
クラリスとノアは、二人が互いを認識して抱き合うのを見て、静かに部屋を後にした。
急いで飛び込んで魔法で彼らの関係を証明する必要は……もうないようだ。
いずれは彼らの関係を魔法的に整理する必要が出てくるかもしれない。
しかし今は、それよりもただ互いの存在を喜び合う時間が必要なように見えた。
「これでひとまず解決した……のか?」
ノアはしばしそう思ったが、まだいくつかの問題が残っていることを思い出した。
何よりも公爵家と王宮の関係をきちんと整理する必要があるように思えた。
果たして自分の妻をこれほどまでに大事にするマクシミリアン公爵が、王宮でどんな反応を見せるのか気になりもした。
『そしてまた……』
彼は残っている問題が何なのか整理しようとしたが、すぐ背後から聞こえてくる奇妙な音に足を止めた。
「ひっく。」
「……?」
振り返ると、クラリスが涙に濡れた顔で彼の後ろをとぼとぼついてきていた。
「お、お嬢さん?」
彼が慌てて声をかけると、抑えていた泣き声が爆発したのか、あえぎながら大声で泣き始めた。
「……!」
ノアは慌てて両手を差し出した。
「う、泣かないでください。いったいどうしてお嬢さんが泣いてるんですか?」
「奥様!ひっ、ひぐっ……」
どれほど泣き続けるのか、クラリスはようやく言葉を発しながら、再び嗚咽を漏らし泣き出した。
「どう見ても、まだ子どものようだな」
ノアは困ったような気持ちで自分の服のポケットを裏返して見た。
魔法使いのローブのポケットにはいろいろな物が入っていた。
小さな手帳、ペン、密封ビニール袋、そして綿棒もある。
しかし、クラリスの涙を拭うような物はどこにもなかった。
「ああ……」
彼は仕方なくポケットの中をあさりながら、視線をそらして再びクラリスを見た。
彼女は「よかったよね?」と言いながらまたもや嗚咽混じりの泣き声をあげた。
「よかったから、だからお願い、もう泣かないで?ね?」
彼は子どもをあやすような口調まで使ってなんとか泣き止ませようとしたが、クラリスの泣き声は止む気配を見せなかった。
ただひたすら「よかった、すごく幸せ……」と言いながら泣きじゃくるだけだった。
幸せならせめて笑ってほしいのに、なぜこうなってしまうのか、ノアには理解が及ばなかった。
何よりも、クラリスがこんなふうに泣くと、なぜか切なくなってしまって……。
「ああ、もう。」
彼は仕方なくクラリスの腕を引っ張って自分の胸の中にぎゅっと抱き寄せた。
幼い頃、何度かこんなふうに泣きじゃくるクラリスを慰めた記憶があった。
もちろんそのときは、クラリスが遠慮もなく彼の胸にしがみついて泣いていただけだったが。
「わかったから、もういい加減落ち着きなさい。」
彼は子供をあやすように、クラリスの背中をとんとんと優しく叩いた。
「うぅ……私ももう泣きたくないのに……。」
そう言いながらも、しゃくり上げる声が止まらなかった。
クラリスがすすり泣きを続けている様子を見て、どうすることもできずにただ見守るしかなかった。
「ひう……」
クラリスは幼くして彼の胸元に顔をうずめた。
「……!」
ここまで密着して抱きつくとは予想していなかったため、ノアはあまりの驚きにクラリスの背中に置いていた手を反射的に持ち上げて言った。
「お、少女!」
「う、うう…… ひっ、だめ……うれしすぎて……」
「そ、それは違う!誤解だよ、勘違いだ!」
「わかってる、でも……ひう……」
クラリスはそれでも彼にもたれかかったまま、ぬいぐるみのように小さな声でしゃっくりを上げながら泣き続けていた。
目が少し赤くなって……ノアはクラリスが可愛いと思ってしまった。
『金魚みたいな目が可愛いわけがない。』
そう自分に言い聞かせたが、彼の視線はそのふぐのような顔から視線を外せずにいた。
『そ、それなら世界で一番可愛いふぐだ……』
理性と本能が激しくぶつかり合うその瞬間、クラリスのすすり泣く声がまた聞こえてきた。
こうなった以上、他に方法はなかった。
幼い頃のようにぎゅっと抱きしめて慰めてあげるしか。
ただし、この行動には彼がクラリスに抱く恋愛的な好意やわずかな欲望などは一切混ざっていなかった。
あくまで友達として。
それも一番親しい友達として。
泣いているのをなだめようとする、極めて純粋な行動にすぎなかった。
……たとえ。
無意識のうちに自分の心臓がものすごい速さで跳ね上がり、今にも壊れそうだったとしても。
それは脳とは関係のない身体的な反応にすぎなかった。
ノアはしばし戸惑いながらも離していた手を慎重に動かした。
そしてついにクラリスをその腕の中に完全に抱きしめた瞬間──
「……ひっ!」
ノアは自分でも知らずに震えているクラリスの肩を押し出してしまったが、それは……
「……」
彼らの後ろからひょっこり現れたマクシミリアンがこちらを鋭い視線で見つめていたからだ。
ノアは背中に冷や汗が流れるのを感じた。
視線だけで人を制圧するとはこういうことかと思った。
いや、もしかして魔法か?
公爵は魔法使いなのか?
そんな疑問が頭をよぎったとき──
「ひっ……」
再びしゃくり上げるクラリスがこの状況をまったく気づいていないことが分かった。
そして彼の胸にもう一度顔をぎゅっとうずめて言った。
公爵の目は今にも光が溢れ出しそうなほど鮮やかに輝いていた。
ノアは何かを否定するように慌てて首を横に振った。
ただ何か……聞かれてはいけないものを聞いてしまった気がする、というその感じだけは否定できなかった。
ブリエルが侯爵夫人と時間を過ごせるよう、ブリエルの部屋から抜け出したマキシミリアンは(その直後、ものすごい光景を目撃して頭が真っ白にはなったが)とにかくロザリーに直接知らせることにした。
彼が屋敷にあるロザリーの部屋をノックして訪問を告げると、扉の向こうからドタバタと何かが散らばる音が聞こえてきた。
普段冷静な彼女の性格を考えると、これは気まずい話題だったので、マクシミリアンは話題をそらそうとした。
ちょうどそのとき、ドアが開いた。
いつものように見える彼女の部屋には、服や帽子、それに本などが床に散らばっていた。
マクシミリアンはその光景をしばらく見回した後、ロザリーをじっと見つめた。
「何かあったのか?」
彼の問いかけに、そうではないとしても、小柄な体のロザリーはそっと肩をすくめ、より小さく見えた。
「屋敷が……片付いたら、ここを離れます。」
「突然どうしてそんな話をするのか分からないな。」
ロザリーは何かを固く決心したような顔で、やっとの思いで口を開いた。
「私、ここを離れなければなりません、公爵様。」
マクシミリアンはまず、ロザリーを落ち着かせようと、近くの椅子に彼女を座らせた。
「私はあなたを責めるために来たのではありません。もちろん、辞職なども許しません。」
「お、お待ちください、公爵様。この愚かな私の戯言をお許しになってはいけません。」
彼女はすすり泣きながら目元をぬぐった。
「大切なお嬢様を失っただけでなく、尊い奥様にまでご迷惑をおかけしました。このような不届きな使用人がどこにいるというのですか?」
「シシは。」
公爵がそこまで話したとき、ロザリーのすすり泣きがさらに大きくなった。
「お、お嬢様……今頃どこかで泣いておられるのでは……。」
確かに泣いてはいるが。
それが喜びの涙であるとはいえ。
マキシミリアンは、自分さえまだちゃんと受け入れられていないという現実をどう伝えるべきか悩み、一瞬黙り込んだ。
『彼女が……シシだったなんて。』
以前、二人がどこか似た雰囲気を持っていると思ったことがあった。
しかし、それだけだ。
彼が思い浮かべる「シッシ」は「マクス!」と叫びながら彼の腕にしがみついてくるやかましい子だった。
だが、ブリエルは彼が知る限りこの世で最も優雅で美しい女性だった。
二人はまったく異なっていた。
「いや、よく考えてみると……」
ブリエルは時にハッと驚かせるような行動力を見せることもあった。
かつて彼と夜に出会ったときも、塀を乗り越えていたではないか。服を破りながら言ったのだ。
そのような一面は確かに「シッシ」らしかった。
いや、それだけではなかった。
彼女は誰よりも勇敢にクラリスを愛していた。
その子との関係の結末には悲しみしかないと分かっていながらも。
その感情を表すことにためらいがなかった。
それもまた、彼が覚えているシッシの性格そのものだった。
『ああ……。』
どうして今頃になって気づいたのだろう。
彼女がシシかもしれないという考えを一度くらいしてみてもよかったはずなのに。
彼はまだ涙を流しているロザリーの肩を静かにたたきながら、直接ひざまずき彼女の前に座った。
今は主人と使用人ではなく、長年シシを共に思ってきた友人として話を切り出した。
「ロザリー、これまで公爵夫人とシシが似ていると思ったことはあるか?」
「……!」
ロザリーはびっくりして顔を上げ、目に涙をいっぱいためていた。
「そ、そんな不敬な考えは決してしたことはありません。旦那様、奥様に無礼です。お二人が……たとえ似ていたとしても。」
「似ていたのか?」
「そ、それは奥様の無邪気な一面を見たとき……あ、いえ、旦那様。奥様を見て……でもシッシお嬢様を思い出して涙を流すような激しいことはありませんでした。」
もしかするとロザリーは、公爵夫人を見るたびにシッシのことを思い出す苦しみを必死に抑えながら過ごしていたのかもしれない。
「僕より立派だな。」
彼はうっすらと笑みを浮かべた。
「え、え?」
「だからあまり驚かないで聞いてほしい。君がまた記憶をなくしてしまったら、ブリエルが……いや、シッシが悲しむだろうから。」
『それはどういう意味ですか?』と問おうとする彼女に向かって、マクシミリアンが冷静な口調で言った。
ブリエルこそが、シッシだったのだと。
ロザリーは取り乱さなかった。
しかし、しばらくの間、きちんと息もできないほどに、じっとしていた。
「また医者を呼んだ方がいいかも」とマクシミリアンが急いで立ち上がろうとしたとき——
「神様、私の娘が……!」
突然、正気に戻ったロザリーが席から飛び起きた。
彼女が急いで向かったのは、北側の廊下を走っていくところだった。
「……?」
彼女を追って振り返った先には、後ろから追いかけてきたブリエルが、後ろにいるロザリーに向かって両手を大きく広げていた。
突然のことだが、公爵家では今夜盛大な晩餐会を開くことになった。
使用人たちは食器と食材を準備し始め、久しぶりに別宮の全員が忙しく動き始めたとき――
マクシミリアン公爵はノアを執務室に呼び寄せた。
そしてノアはまるで魂が抜けたような顔で、公爵の執務室の前に立っていた。
ノアはこれまで数々の困難な状況を乗り越えてきたと自負していた。
幼かった頃、彼を疎んじる大人たちと正面からぶつかって戦った経験も一度や二度ではなかった。
しかし、どれだけ多くの経験と勇気を積んできたとしても、今日公爵に向き合う勇気は湧かなかった。
とはいえ、このまま逃げるつもりもなかったノアは、固く閉ざされた扉をノックし、扉を開けた。
「魔法使いシネット。」
またしても恐ろしい目つきをされるのではと心配したが、幸いにも公爵は普段と大きく変わらない様子で彼を迎えた。
「……公爵様。」
「楽な席に座るといい。話すべきことが少なくないからな。」
執務用の椅子から立ち上がった公爵がソファに席をすすめ、それに従ってノアも向かいの席に腰を下ろした。
「まずは——」
公爵は無駄な時間を省き、すぐに本題に入ろうとしているようだった。
ノアはもしかすると、今日を最後にこの別宮を——そしてセリデンの出入りを禁止しようとしているのではないかと思った。
公爵はクラリスを大切にしていたので、当然といえば当然だ。
「心から感謝します。」
「……ああ。」
「妻が無事に戻ってこられたのは、すべて魔法使いシネットのおかげです。この恩は決して忘れません。」
ノアは頭を下げた。
「私の方こそ、奥様から受けた慰めのほうが多く、この恩に少しでも報いたいと思ったまでです。」
「それでも、一度命を救ってくれた恩をそのままにしておくわけにはいきません。必ず返します。それがいつであれ、魔法使いシネットが望む方向で。」
「ひとまず……承知しました。」
「そして魔法師団に正式に血縁検査を依頼しようと考えています。こういうことは、確実な手続きで明らかにするのが良いでしょう。」
ノアは姿勢を正して、公爵をまっすぐに見つめた。
「同意します。誤った結果を伝える過程で、魔法の純粋性を故意に傷つけた者がいたとすれば、魔法使い団もその人物を必ずや突き止めるでしょう。」
そして彼は、マクシミリアンに向かって軽く頭を下げた。
「魔法使い団を代表して、公爵様にお詫び申し上げます。我々の不手際によって、公爵夫人が大切な機会を失ったことを承知しております。」
今朝の新聞には、長らく空席だった「ケルノー侯爵」の名前に新たな主が現れたと記されていた。
もしブリエルが早く真実を知っていたら、こんなことは起きなかっただろう。
「その機会については、謝る必要はありません。」
「しかし。」
それは陰謀だった。
それも高貴な貴族による。
そのためならどんなことでも厭わない、そんな歴史が何度も繰り返されてきたのだ。
さらには魔法師団の調査まで。
時には私が持つ魔法的な力を利用して策略や権威を得ようとしたことがこれまで何度かあった。
「私の妻は、セリデン公爵夫人の座はそのために用意された誰かに与えるべきだと言っていました。たとえ、彼女が侯爵夫人になる権利を見つけたとしても。」
「そうでしたか……。」
ノアは思いもよらなかった夫人の答えに驚きながらも、慎重に自分の考えを述べた。
「むしろ、ケノーの人々ががっかりしたでしょう。奥様は立派な領主になられたかもしれません。」
「ふむ。」
マクシミリアンはノアのこの評価を特に否定しなかった。
いや、むしろ密かに同意するかのように静かに頷くほどだった。
「それと、魔法使いシネット。」
他に伝えるべきことがあったのか、
公爵が話題を変えた。
「はい。」
何か気まずい話題だったのか、マクシミリアンは答えずにしばらく黙っていた。
「いや、今は“ノア・シネット”と呼ぶ方がふさわしいかもしれないな。」
ノアはその瞬間、はっとして言った。
『あの』話をしようとしていたのは間違いなかった。
自然と肩がぴくりと動いた。