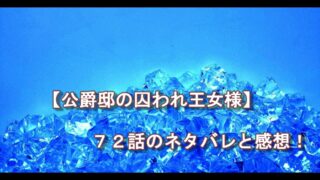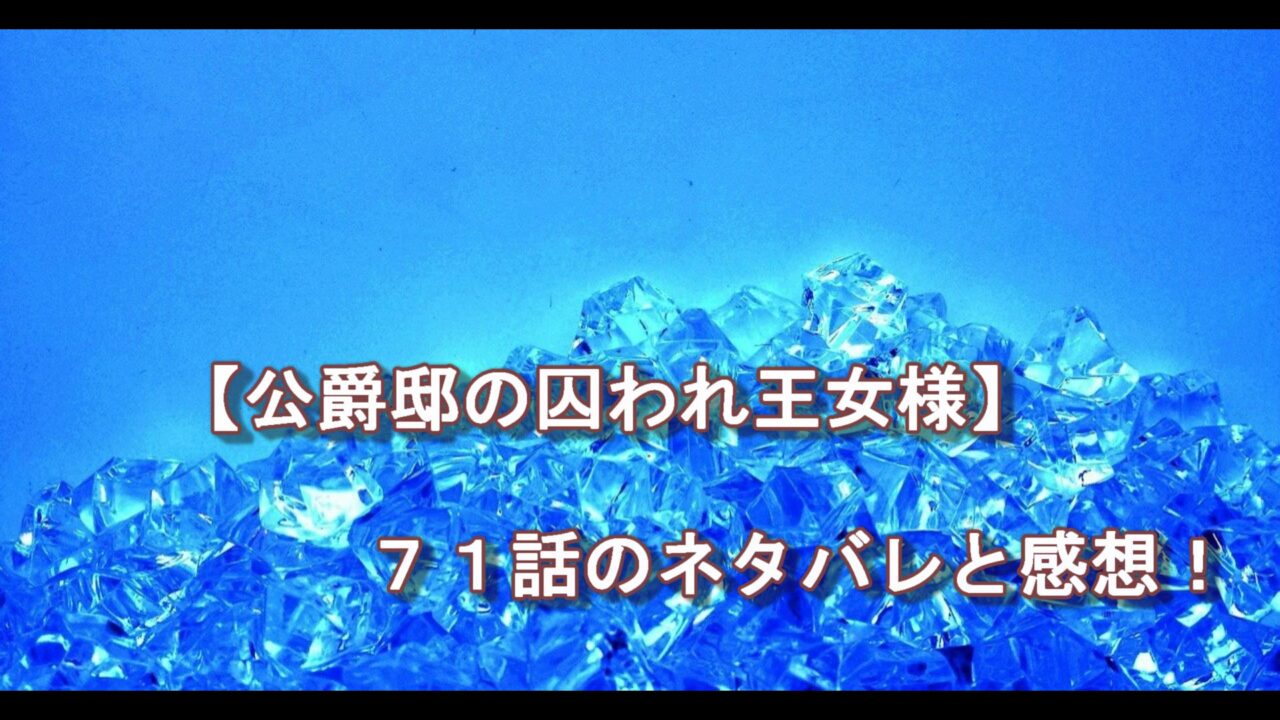こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
今回は71話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

71話 ネタバレ
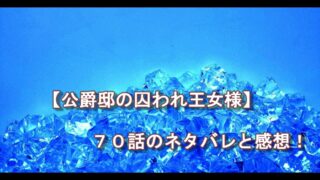
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- いつの間にか15歳
王都ハイデン。
セイファースの中心である美しい都市は、収穫の季節である秋を迎え、祭りが盛り上がっていた。
特に今年は豊作を祝う意味で、通常は決して超えられない二つ目、そして三つ目の城壁が一時的に開放されている。
いつも遠くから見上げるだけだった王宮を、しっかりと眺める機会を逃したくない人々であふれた。
そのため、ハイデンは遠くから訪れた観光客で賑わい、祭りはさらに活気づいていた。
みんなが祭りの熱気に包まれているこの時期、王都ハイデンの第三城壁の内側には、祭りとは全く関係のない時間を過ごしている者もいた。
勉強に支障をきたさないよう、ピンク色の髪をきっちり束ねて上げたクラリスは、この日も変わらず机に向かい真面目に座っていた。
彼女の年齢はいつの間にか16歳。
「立派な16歳」になるために目標としている公務員試験の受験資格年齢まで、あと1年しか残っていなかった。
今こそ、本当に今まで学んできたことを整理し、徹底的に暗記する時間を持つべき時だった。
・・・そんな時に。
「おい、お前の実力で寝られるのか?」
冷やかすような声に、クラリスは目を細めてゆっくりと目を開けた。
腕にぎゅっとクッションを抱えて眠っていたせいで、視界がぼやけていた。
「うわ、顔が2倍大きくなってるよ。」
日差しが強く、相手のシルエットさえもはっきりと見えなかった。
「バレンタイン王子様。」
もちろん、それでもクラリスが相手を識別するのに問題はなかった。
ここは第三城壁内の別宮だった。
彼女が公爵様に従って王都に来るたびに泊まるのはまさにこの場所だ。
どれだけ身分を分ける城壁が開放されていたとしても、このように王族の居住地へ足を踏み入れることができる人物は極めて限られている。
「なぜ会うたびに深刻な話ばかりされるんですか。」
クラリスにこうやって遠慮なく話しかける人物はバレンタインだけだった。
セイファースの貴族たちは優雅な人々であり、滅びた王国の王女であるクラリスを軽く見るようなことは考えたとしても、口に出すことは決してなかった。
それは今も彼女の首にかかったペンダントを見ればわかる。
それは、この王国で最も高貴な人物が彼女を直接見守っているという意味だった。
偉大な王が不幸なフォロー(庇護を受ける者)に配慮を示しているのだから、臣下たちがクラリスを無視することなどできるだろうか。
おかげでクラリスは、これまで貴族の子供たちとほとんど変わらない支援を受けていた。
彼女は何でも学ぶことができた。
フォローという立場を考慮して、乗馬や剣術は制限されていたが、いずれにせよそれらは公務員試験の科目ではなかったため、特に気にしなかった。
何にせよ、バレンタインの軽口は続いていた。
「俺は正直に言ってるだけだよ。お前の実力で眠れるなんて笑えるし、それにお前の顔は・・・」
窓際に立っていた彼は、すっと机に近づいて、机の上に身をかがめた。
明らかにまた何か皮肉を言おうとしているのは間違いない。
そのため、クラリスはかぼちゃ色の目をぱっちり開けて彼をじっと見た。
「どうしてそう見るの?」
「それは、これから王子様が私の顔をからかうつもりだからですよ!」
「からかうつもりなんてなかったよ。顔が腫れると、誰だって見た目が悪くなるものだっていう一般論を述べようとしただけさ。」
幼い頃から今日まで、変わらずにからかい続ける王子。
それでも幼い頃は、日差しのように明るい外見もあって、その生意気な性格がいくらか中和されていた。
しかしそれも、クラリスとともに16歳まで成長し、妙に生意気な雰囲気を醸し出すようになってから変わり始めた。
たぶん、だんだん鋭くなる眼差しとタイトな表情がその理由だろう。
さらに、今すぐにでも戦いを挑みそうな力強い眼差しも宿しており、「よく見れば王子様ではなく、むしろ騎士のように見える。」
そんな考えが一瞬よぎったが、クラリスはその思いを振り払った。
尊敬すべき王子様を騎士様だなんて。
「ここには何の用事でいらしたんですか?」
クラリスは少しぼんやりした表情で尋ねた。
すると彼は薄く笑いながら、クラリスの片方の頬を軽くつついた。
「怒ったの?」
「はい、怒っています。だから用件だけおっしゃって、戻っていただけると嬉しいです。」
「お前、お金持ってる?」
「えっ?」
「もし持ってたら、少しちょうだい。」
クラリスは呆れたようにバレンタインをじっと見つめる。
突然現れてお金をせびるだなんて、まるで強盗みたいじゃないか!
「・・・王子様はお金がないんですか?」
「うん、ないよ。」
彼はとても堂々としていた。
「いや、どうしてお金がないなんてことがあるんですか? 罪人でも非常用の資金くらいは持っているものですよ!」
「君だって王女だった時に現金を持っていたことなんてないだろう?」
それが正論だったため、クラリスは言葉を失った。
「お金をくれないなら仕方ない。手を出してみて?」
「えっ、はい?」
ためらいながら手を差し出すと、彼は遠慮なくそれをつかんで引っ張った。
「一緒に行くしかないね。」
どこへ・・・?
そう聞こうとしたクラリスは、古い柱のそばで彼の横顔を確認し、すぐに返事を飲み込んだ。
幼い頃のバレンタインは第三城壁の中でしか過ごしたことのない子供だ。
今では成長して何度か城壁外の世界を経験しているが、好奇心旺盛なその性格は変わらなかった。
それでも彼は依然として外の世界を見ることに深い興味を抱いていた。
「王子様、城壁の外に出ようとしているんですか?」
彼は薄く笑みを浮かべた顔で答えた。
この笑顔は幼い頃から変わらないもので、クラリスは彼がこの瞬間を本気で楽しみにしていることを感じ取った。
「・・・仕方がないですね。本当に少しだけですよ?」
勉強するべきことが山のように積み重なっているが、クラリスは一瞬彼に付き合うことに決めた。
バレンタインと「遊んであげる」と言いながら祭りの会場に出たが、結局楽しんでいるのはクラリスのほうだ。
そうなった理由はいくつかあるが、ひとまずクラリスの人生観である「やらないと後悔するから!」という考えが、何でも全力で楽しむ方向へと彼女を導いていた。
物事を試してみる性格が大きな理由だった。
そして、もう一つの理由は、「石」を使って目標を達成するゲームが大規模に行われていたから。
商人が投げ入れておいた石の中には、「少しばかりの魅力を見せてくれるなら、完璧な軌跡を描けるかもしれないよ」と言いながら取引を提案してきた友人がいた。
クラリスはその取引に応じ、結果として、祭りの期間中誰も成功していなかった中心点を的中させることができた。
賞品は祭りで使える商品券だった。
お金のない王子と一緒に来ていたので、ちょうど良い贈り物になった気はするが・・・。
予想以上の金額であることが問題だった。
「どう考えてもこれを全部使って帰るのは無理ですよね?」
クラリスは厚い商品券の束を持ったまま、バレンタインをじっと見上げた。
それに対して、クラリスよりさらに背が高く成長したバレンタインは、今では頭ひとつ分大きく見えるようになっていた。
近くにいると少し見上げなければならず、気まずさを感じるほどだった。
「同い年なのに、どうしてこんなに差があるの・・・?」と、クラリスはしばしば不満を抱いた。
実際の年齢より1歳若く見えるクラリスに比べ、バレンタインは最近、大人と誤解されるほどに成長している。
成長を羨むクラリスにとって、それは少し苦しい事実だった。
それでも彼は、さりげなく見下ろしながら微笑んで言った。
「まぁ、そろそろ戻るべきだろうな?」
その姿はあまりにも自然で、威厳すら漂っていた。
通りすがりのお嬢様たちがこちらを一瞬振り返る様子を見れば、明らかだろう。
クラリスの目には、彼がかっこいいというよりも、かっこつけているようにしか見えなかったが。
「お前についてくる騎士も、そろそろ時間を確認しているようだ。」
彼は少し離れた場所にいるベンチの方向を指差した。
別にベンス卿のためにそう言ったわけではありません。」
クラリスが心配していたのは、バレンタインの方だ。
今回も彼は、公爵の別邸に行くと言いながら従者の目を逃れ、こっそり外に出てきたのだから。
彼女の考えを察したのだろう。バレンタインは静かに笑う。
「こんな無駄な心配をして!」
「いえ、そんなことでは・・・。」
「もういいよ。もう少しだけ行ってみようか。お前みたいに商品券を使い切ることはできないんだから。」
彼が先に歩き出し、クラリスは心配そうに彼の後をついていった。
「私はただ、問題を大きくしたくないだけです。」
「今さら私が少し宮殿を抜け出したくらいで、従者たちが母上に報告するわけでもないさ。それに今では私も年長者だろ?いつまでも子供扱いはされないよ。」
「16歳は子供ですよ。」
「君もそうだろう。」
振り返ったバレンタインは、クラリスの前を通り過ぎる際に、彼女の白いリボンを軽く引っ張った。
ほどけたリボンは、彼の手の上にふわりと落ちた。
「子供が使うようなリボンなんていつまでもつけていないで、この機会に1つ買ったらどうだ?これ、結構古びてるし。」
クラリスは驚いて、自分の肩に落ちた髪を慌てて整えた。
「返してください、大切なものなんです。」
「君、本当に大切にしているものが多いよね。毎回、俺が何か持って行こうとすると、大切だって言って取り返そうとするんだよね?」
「それは、王子様!」
クラリスは思わず少し声を荒げたが、周囲を意識してすぐに声を落とした。
「・・・バレンタイン様が本当に大切なものばかり持って行かれるからですよ! まったく、早く返してください!」
その慌てる様子を見下ろしていたバレンタインは、なぜかとても満足そうに微笑んでいた。
「大切なものを次々と奪われる」という言葉が、どこか良い響きを持っているようだった。
「分かったよ、今返す・・・。」
「それはノアと1つずつ分け合ったものなので、無くしてしまうと困るんです。」
リボンを差し出したかと思うと、彼は再びそれを背中の後ろに隠した。
クラリスは額にシワを寄せながら彼に食い下がった。
「・・・返してくださるって言いましたよね?」
「1つだけ確認して。」
「早くしてください。」
「そのノアって奴、男じゃなかったっけ?」
「男性もリボンを使います。特にノアのように美しく長い空色の髪を持っていれば、なおさらです。」
「・・・ふん。」
彼は透明な瞳をゆっくりと転がした。
まるでノアの姿を想像しているかのようだ。
クラリスは彼の想像を助けることにした。
「ノアは本当に綺麗なんですよ。いつも仮面をつけているから知っている人はほとんどいませんけどね。」
「ふーん。」
「最高の魔法使いという点は以前にお話しましたよね?それに、冷たい体温がとても心地よいんです。」
「・・・お前、そいつの体温をどうやって知っているんだ?」
「どうして分からないんですか?」
クラリスは当然といった様子で答えた。
「友達だからです。」
「俺よりも親しい?俺の体温は知らないだろう!」
「知っていますよ。」
クラリスはリボンを直しながら乱れた髪を整えつつ、落ち着いた口調で答えた。
「36.5度です。もちろん、平均的な数値として、ですが。」
「おう・・・分かってくれてありがとう、親切な友達だな。」
「そんな、とうとうノアに興味を持ち始めたんですか? 私、ずっと言っていたじゃないですか? 二人が会えば本当に楽しいことになるって。」
セイファースに来て以来、クラリスはこれまでたった二人の親友を作った。
ノアとバレンタインだ。
友情が深まるにつれ、彼らがあまりにも大切な存在になったクラリスには、一つの小さな願いが生まれた。
それは二人を同じ場で会わせること。
しかし、二人は互いの存在を知ってはいるものの、一緒に会おうとはしなかった。
クラリスは何度か二人を引き合わせるために予定を組んでみたが、結局、どちらからも拒否の返事が返ってきた。
「俺が何をしに会わなきゃいけないんだ。」
それからも変わらず、今でも同じ返事が返ってくるだけだった。