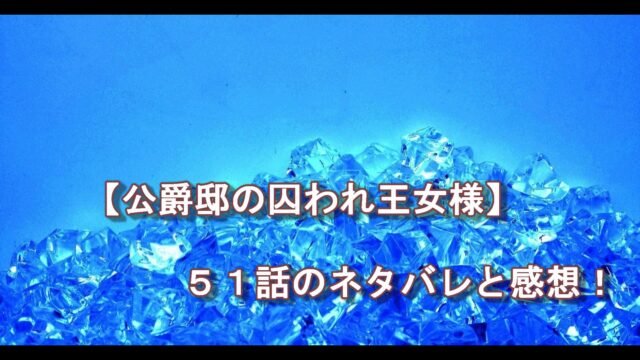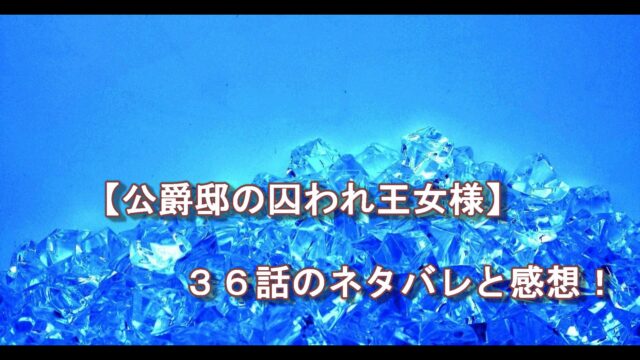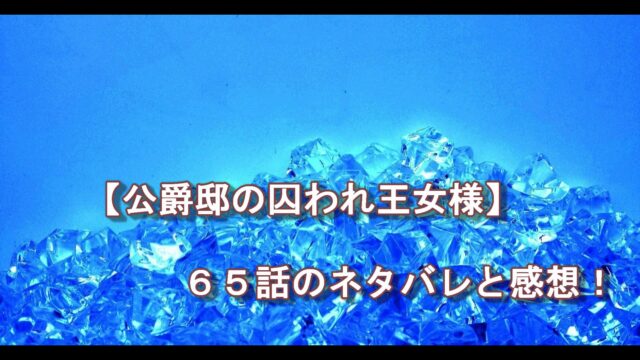こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

127話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- お悩み相談
クラリスは、バレンタインが迎えに来るのを待たず、ベンス卿の助けを借りて、一日早く修道院へ戻った。
もちろん、ノアとカムス・ヴァイアルの件を話すために。
「まずは、彼が何者なのかをはっきりさせないと。牢に伝言を送って、印象操作を探らせる、というのはどう?」
手短に説明を終えたクラリスの提案に、ノアは予想どおり反対した。
「彼に、少女のゴーレムを見せるわけにはいかない。」
「見つからないように気をつければいいわ。仮に彼がゴーレムを見たとしても、私がゴーレムマスターだとまでは特定できないでしょう?」
「……そうだな。彼には、潜在的な魔力で相手を感知できるほどの力は、ほとんどないから。」
「法師団長に就任予定のアルステア・アストラだ!今すぐ開けろ!」
だが、その叫びが返事を得ることはなかった。
力強さを込めた声であっても、沈黙は破れない。
「……今すぐ、だ」
彼はかすれた声でそう呟き、冷たい窓枠に額を預けた。
理由も分からぬままここへ連れて来られて、気づけば四十日あまり。
考え得る限りの魔法を駆使し、脱出を試みたこともある。
だが、結果はすべて徒労に終わっていた。
魔法で錠を外して外へ出た瞬間、待ち構えていた騎士たちの力に押し潰され、再び地下へ引き戻される――その繰り返しだったのだ。
魔法の中には、他者の行動へ直接干渉するものも存在する。
しかし、それを扱えるのは白きローブを纏う者たちのみ。
床に崩れ落ちた彼は、昨夜、看守が置いていった水桶の中に残っていた水を、すべて飲み干した。
「……魔法使い団が、きっと僕を探しているはずだ。」
彼は掌の中に、白い光を生み出した。
「魔法使いアスト様、どうか……僕を助けてください。」
切実な想いを込めて放たれた小さな光は、牢の外へと静かに流れ出ていった。
ここに閉じ込められて以来、彼は毎日、アストに向けて光を送り続けていた。
もし魔法使いアストがこれを見つければ、魔力を識別して、それがルカのものであると確認し、光を辿って彼を助けに来てくれるはずだ。
――いや、もしかすると、すでに城の近くまで来ているのかもしれない。
『貴族たちが、あの方の行く手を阻んでいるのだろうか?』
腹立たしくはあったが、ここは、くだらない連中の権力がより強くはたらく王都ハイデンだった。
彼らが魔法使いアストに無礼を働いているのではないかと思うと、ルカの胸は重くなった。
『僕のせいだ……。愚かにも、捕まってしまったから……』
疲れ切った身体を、冷えた石の床に投げ出した、そのときだった。
純白の光がひとつ、彼の眼前にふわりと現れた。
少し前に放った光とは比べものにならないほど、澄み切った輝き。
「……魔法使いアスト!」
ああ、やっぱり近くにいたんだ!
ルカの光を見つけ、応じてくれたに違いない――そう確信した、次の瞬間。
「……違う?」
光は宙に、連なるハサミの印を描いた。
「……ああ。つまり、貴族たちは取り合ってはくれない、ってことか」
すると今度は、さらに大きなハサミの印が描かれる。
――そういえば。
追跡用の光が、ここまで明瞭に意思表示できる魔法だっただろうか。
少なくとも、彼や彼の同僚たちには不可能だった。
そもそも、狙った相手に確実に届かせること自体が彼にとっての最善だった。
『普通の魔法使いには不可能なことだ。魔法使いアストラなら……』
自尊心は傷つくが、魔法使いシネットほどの存在であれば、こうしたことも可能ではないだろうか。
「まあ、シネットは人間じゃないからな。」
彼が小さく呟いた、そのときだった。
光がぱっと跳ね上がり、空中に大きな円を描いた。
「……魔法使いシネット?」
驚いてもう一度呼びかけると、光は同じ形の反応を示した。
『彼が……なぜ?まさか……』
ここに閉じ込められているのが、魔法使いシネット本人なのか?
そう考えた瞬間、彼が王家出身の公爵と親しくしている、という事実が脳裏をよぎった。
『まさか……魔法使い団に害をなす何かを企てている?その条件として、爵位まで約束されたとか……』
人間社会の名誉に目がくらみ、貴族に迎合する魔法使いとなった恥ずべき前例は、過去にも――それでも――彼は、相手を探し当てることができた。
魔法使いシゼットは、魔法使い団から追放されるほどの立場にあったからこそ、貴族たちの甘い誘いにも、より容易く絡め取られたのだろう。
「……魔法使いの恥さらし、だな」
彼は、少し前に空にしていた水桶を逆さにし、シゼットが送り込んだ光を、その中に閉じ込めた。
光には物理的な質量がないため、倒れた桶はびくともせず、そのまま床に留まっている。
「カミュ・ヴァイアル!」
曲がりくねった廊下の向こうから、彼の偽名を呼ぶ騎士の声が響いた。
「よく耐えたな。――もう出ていい」
「……え?」
ルカは思わず声を上げたが、騎士は笑みを浮かべたまま、牢の扉を開けただけだった。
修道院に少し早く到着したため、クラリスは空いた時間を使って自習室で勉強することにした。
どうせノアが送った光が戻ってくるまでは、特にやることもない。
こういうときは、歴史の年代表を暗記するのが一番だった。
クラリスは、何度も見返して角がよれてしまった暗記メモと、白いノートを抱えて、自習室へと向かった。
年代表を完璧に覚える一番の方法は、白い紙に自分の手で書き出していくことだ。
そうすれば、あとで暗記メモと見比べたときに、何が足りないのかが一目で分かる。
クラリスは慎重に自習室の扉を押し開けた。
すると、ちょうど自習室から出てきたエイヴィン・ベルビルと鉢合わせしてしまった。
「おや、早いですね。」
彼はまだ、クエンティンの頼みを忠実に守っている最中だった。
「……あ、はい。少し立て込んでいまして」
「サンクレア様は、お元気ですか?」
「叔父は元気にしています。ただ、少し無理をしがちなのが心配ですが……」
「それは何よりです。どうか私からの安否も、必ずお伝えください。いいですね?それから――返事も頂きたいのです。私をどう評価しておられるのか、そして、将来的に推薦状を書いていただけるおつもりがあるのかどうかも」
彼は、言われれば胸の内を隠そうともしない。
そういう意味では、むしろ驚くほど率直な男だ。
「ひとまず、伺ってみます」
「では、公爵様からの推薦状も頂けるか、併せて確認してもらえますか?」
「……は、はい!?」
「優秀な人材を見出し、世に送り出すのも公爵の責務でしょう?もちろん、協力してくださいますよ。その点も含めて、きちんと確認して――そうですね、来週までに知らせてください」
彼は、何事も当然のように言い切って、通信を終えた。
「……分かりましたか?」
あまりにも堂々とした非常識な物言いに、あっけに取られて言葉が出なかった。
クラリスは口を開けたまま、彼の厚かましい顔を見つめることしかできなかった。
「分かりましたかってば!」
彼がさらに一歩踏み出して声を荒らげた、そのとき――
「いや、分からないけど?」
苛立ちの混じった返事が、クラリスのすぐ背後から飛んできた。
気配を感じなかったため、クラリスとエイヴィンは同時にそちらを振り向いた。
バレンタインだった。
冬物のコートに帽子までかぶり、ほんのり冷気をまとっているところを見ると、今しがた修道院へ戻ってきたところらしい。
「君さ、この子と一回手をつないだからって、急に存在しなかった友情が芽生えたわけ?」
バレンタインはそう言いながら、クラリスの頬を軽くつねった。
少し痛かったせいで、彼女は思わず彼の手を振り払った。
「そんなはず、ありません!」
「おっと……痛っ。いやほんと、容赦ないな。で、どうしてあいつの戯言を、あんなに大人しく聞いてやってる?言い返しもしないでさ」
彼はクラリスの両肩を掴み、くるりと向きを変えてエヴァンの正面に立たせた。
「いつも通りでいいんだ、いつも通りに。子どもを木っ端みじんに蹴散らすつもりで行け。な?」
クラリスは彼の手から逃れようともがきながら、ヴァレンタインに向かって叫ぶ。
「普段は、そんなことしてません!」
「してない?通りがかった荷車をぶち壊しながら言う台詞か、それ。まったく……お前みたいな剛腕、初めて見たぞ。――おい、どこ行くんだ?」
クラリスから視線を外したヴァレンタインは、顔を上げてエヴァンを呼び止めた。
彼はゆっくりと席を立ちかけ、途中でぴたりと動きを止めると、無理に作ったような笑みを浮かべた。
「……あはは」
「本当に気をつけろよ。こいつ、石投げでも最後までやり切るタイプだから。」
「私がいつ……!」
クラリスは反論しかけて、言葉を飲み込んだ。
よく考えてみると、以前の祭りで、彼女が石を投げて景品券を落としたことがあったのを思い出したのだ。
だが「石投げ」という言葉に少し怯んだのか、エイヴィンは背中を丸めたまま、そそくさと自分の方へ逃げていった。
「無礼なやつを追い払ってくれて、礼なんて言わなくていい。」
バレンタインはクラリスの腕を放し、ぱっぱっと手を払った。
「……そんなつもりじゃありませんでした。」
「言うべきだろ。俺が助けたんだから。」
「王子さまは、袖をちょっと引っ張っただけじゃないですか。」
クラリスは唇を尖らせ、そのまま先に自習室へ入っていった。
彼も後について入り、出席簿に帰室時刻を書き込むと、クラリスの隣に腰を下ろした。
「なあ、どうして急に一人で先に戻ってきたんだ?」
「ちょっと、やることがあって……」
“やること”という言葉に、彼はクラリスが持ってきた暗記用のメモへ、ちらりと視線を落とした。
「それ、覚えるため?」
「ええ、そうです」
どうやら彼が続きを言いそうだったので、クラリスは先手を打つように、白紙を一枚引き抜いてヴァレンタインの前へ差し出した。
「連名で書くのはどうです?一緒に」
「お、いいね。俺もやるよ。最近の悩みを、正直に吐き出す感じでさ」
――連名。
その言葉に、クラリスはあまり良い思い出が結びつかず、思わず首を縦に振れなかった。
「……賛成です」
テーブル越しに、賛同の声が上がった。
ユジェニーだった。
どうやら今しがた降りてきたらしく、彼女はクラリスの隣に腰を下ろし、白い紙を手に取った。
「こんにちは、マクレッドさん。奇遇ですね?」
「ええ。ちょうど私も年代表を覚えに来たところです。競争は脳の働きに良いですから。」
「……僕は、悩み事みたいなのはあまり聞きたくないんだけど。」
バレンタインがため息まじりにそう言うと、ユジェも一歩も引かずに答えた。
「どうか最善を尽くしてください。私は、王子殿下の取るに足らない悩みを聞くために、自分の時間を無駄にしたくありません。」
二人が同じように鋭い視線で睨み合い始めたため、クラリスは慌てて「じゃあ、始めましょう!」と声を上げ、二人の間に割って入った。
三人はそれぞれペンを手に取っても、軽口の応酬をやめなかった。
「悩みがあるなら言ってみなよ。それで一生、からかわないから。」
「王子という立場の人間が口にできる言葉の中で、これ以上に卑劣な台詞はありませんでした。」
「もう、本当に……お願いですから集中してください。これは遊びじゃないんですから」
クラリスの必死な訴えが、ようやく彼らを現実へ引き戻した。
三人は姿勢を正し、連名の書簡を書き始める。
――四十分後。
クラリスは、頭を抱えていた。
自分にどんな“悩み”があるのか、ひねり出さなければならなかったからだ。
灰色のローブの魔法使いに関する件――それが本心からの懸念であるのは確かだが、さすがにこの場で打ち明けるわけにはいかない。
もっと個人的で、差し障りのない話題である必要があった。
(あ……そうだ。慌ただしさに紛れて、すっかり忘れてた)
その問題なら、相談する価値はある。
そう思って顔を上げると、ユジェニーとヴァレンタインが、期待に満ちた眼差しでこちらを見つめていた。
「え、ええと……つまりですね……私の“友人の友人”の話なんですけど」
クラリスは慎重に言葉を選びながら、口を開く。
「少し前に、その子が陛下に助言を求めたらしいんですが……どうしても、答えが見つからなくて……」
クラリスは、慎重に話を切り出した。
「Aさんと友だちのBくんが手をつなぐ必要がある状況だったんです。でも、Bくんが急にAさんの手を取らずに、ハンカチを挟んで、端と端をそれぞれ持とうと言い出したんです。それが……悩みなんです。だから正確に言うと、私の友だちの友だちであるAさんの悩みなんですけど。」
バレンタインは眉をひそめた。
「それのどこが悩みなんだ?手をつながなきゃいけない理由でもあるのか?」
「今まではずっと、普通に手をつないできたのに、急にハンカチを使うなんて、変だと思って……そう感じたみたいです。」
「まあ、Bくんがそうしたかっただけじゃないのか。」
まったく助けにならない答えだった。
ちょうどそのとき、ユジェニが「分かった!」と叫んで、手を高く挙げた。
「Bくんには恋人がいて、それをAさんに知られたくなかったのよ。手をつながないのは、Aさんの恋人の気持ちを考えてのことです」
きっぱりと答えた彼女は、自分の言葉に納得したように、小さくうなずいた。
「そ、そんなはずありません!」
B君に向けて――つまり、ノアに恋人がいるという前提に対して、クラリスは自分でも驚くほど即座に否定していた。
だが、ユジェニーの「じゃあ、どうしてそう思うの?」という問いかけには、言葉が詰まってしまう。
なぜ反射的に否定してしまったのか――それが自分でも分からなかったからだ。
「そ、それは……」
曖昧に言い淀みながらも、ようやく辿り着いたのは、ひとつの理由だった。
ノアに恋人がいないと、確信できる理由。
「もし、そうだったら……私が……いえ、Aさんが知らないはずがありません。二人は、いちばん近い友達同士なんですから」
「親しい友人同士であっても、秘密がないとは限りませんよ」
クラリスは反論できなかった。
彼女自身も、ノアに秘密を抱えていたのだから。
「う……」
図星だと察したのか、ユジェニはクラリスの肩を軽くたたき、別の可能性も示した。
「それとも、Bくんには“よく見せたい相手の女性”が別にいるのかもしれませんね。」
「よく……見せたい女性?それって、好きな人ができたってこと?」
「ええ。ただし、まだはっきり決まった関係ではないから、友だちには話していないのでしょう。」
クラリスは「そうなんだ」と言って、ゆっくりとうなずいた。
ユジェニは、AさんがこれからもBくんと良い関係でいられるよう願いながら、少し前にきれいにまとめておいた年代表を自分のノートに挟み込んだ。
「ねえ、でもさ。」
しばらく二人の会話を黙って聞いていたバレンタインが、あごに手を当ててクラリスを振り返った。
「Aさんの“友だちの友だち”が、わざわざ君に悩み相談をしたって?」
「ええ、そうです!」
「……つまり、君には“悩み相談をするほど親しい友人”がいる、ってことか?」
「王子殿下は、私をどういう人間だと思っていらっしゃるんですか?」
「いや、そういう意味じゃなくてさ。ほら――ユジェニー・マクレア。お前、この子から相談を受けたいと思うか?」
彼は首を傾げながら、テーブル越しにユージェニーを振り返った。
新しい問題集を取り出していたユジェニーは、静かに顔を上げて答える。
「ええ」
「……は?」
そのままユジェニーは、今度はまっすぐクラリスを見つめた。
「いずれ、私もあなたの部屋へ伺います。心の準備が整ったときに」
クラリスは少し驚きながらも、すぐに小さくうなずく。
「私は、いつでも構いません。――いつでも、歓迎しますから」
「ありがとうございます。」
バレンタインは口を開けたまま、二人を見比べた。
「マクレッド、お前……俺の意見を否定するためなら、本当に何でもやるんだな?」
「私は王子殿下のお問いに『はい』と答えただけです。お分かりにならないかもしれませんが、それは肯定の代表的な表現です。」
「出題者の意図を読めって言ってるんだよ!」
「重ねて申し上げますが、王子殿下は出題者ではありません。」
ユジェニは再び問題集へと視線を落とした。
「俺は本気で、あいつには絶対に勝つ。いいな?お前も俺の友だちなんだから、あいつにだけは絶対に負けるなよ。」
バレンタインも急に闘志を燃やし、姿勢を正すと、すぐにペンを握った。
クラリスは、恐ろしい勢いで勉強を始めた二人を交互に眺めながら、「やっぱり、勉強になるとこの二人は似ている」、そう思って、クラリスは小さく笑った。
気分よく歴史の勉強を終えた彼女は、本とノートをまとめ、席を立つ。
「勉強しないの?」
不機嫌そうな表情でヴァレンタインが投げかけた言葉に、クラリスは同じように顔をしかめて答えた。
「部屋でやりますから」
そうは言ったものの、内心では、そろそろノアの“光”が戻ってきていないだろうかと気になっていた。
「先に失礼しますね」
クラリスはヴァレンタインとユジェニーに軽く挨拶をし、少しの間、自習室を見回した。
――どこかに、ノアはいないだろうか。
白いローブを纏う彼は、修道院の中では比較的目立つ存在だ。見つけやすいはずなのに。
(……いないか)
もっとも、もし彼が自習室に来ていたのなら、真っ先にクラリスやヴァレンタインのもとへ顔を出していたはずだ。
彼女は、ほかの受験生たちと親しく過ごすことを、少し気まずく感じる性分でもあった。
クラリスは静かに自習室を出て、階段を上った。
ちょうど二階の廊下の掲示板に、ノアのローブが見えた。
クラリスの部屋の近くだ。
「光が戻ってきたみたい……?」
クラリスは残りの階段を駆け上がった。
そうして、踊り場を二つほど残したところで。
「ノ……!」
声を上げて彼を呼びかけたクラリスは、途中で慌てて唇をぎゅっと結んだ。
そこは、ノアがほかの受験生と一緒にいた場面だった。
とはいえ、ここは修道院であり、受験生同士が会話を交わすこと自体は、まったく自然なことだ。
しかもノアは、とても優秀な成績を収める人物なのだから。
当然のように、皆が彼と親しくなり――胸の奥が、ちくりと疼いた。
――いや、たとえそうでなかったとしても。
ノアに友だちが増えるのは、きっと良いことだ。
(……いいこと、なんだけど)
彼の白いローブの向こうに、ちらりと見えた少女が、楽しそうに笑っている。
その光景を目にした瞬間、どうしてか胸の内が落ち着かなかった。
(嫌……なのかな)
ふと浮かんだその疑問に、クラリスは慌てて首を振る。
(違う。ただ……私は……)
少し前に、ユジェニーが口にした言葉が、脳裏によみがえった。
ノアは「本当に見たい相手」がいるから、クラリスの手を取らなかった――そんな意味の答え。
(もしかして、その相手って……)
クラリスは、今もなおノアと熱心に話し込んでいる少女から目を離せずにいた。
「……きれい……」
同年代くらいに見えるのに、どこか大人びた雰囲気をまとっている。
無邪気さの奥に、静かな落ち着きが垣間見えた。
(……私、何考えてるんだろ)
自嘲気味に、クラリスは小さく息をついた。
ほかの人をじっと見つめながら、あれこれと考えるなんて、とても無礼なことだ。
クラリスは、まとわりついて離れない視線を無理やり振り払い、階段をとぼとぼと下りていった。
ゆっくりと一階へ向かう足取りが、だんだんと重くなっていくのは、どうしてだろう。
『恥ずかしい……私はどうしてこんなに自分勝手なんだろう』
クラリスは、ノア以外にも良い友だちを作ろうとしているのに、彼に新しい縁が生まれることを、一緒に喜べない自分に気づいてしまった。
「はあ……」
階段を下りきったクラリスは、肩がすくむほど大きく息を吐いた。
中央庭園から流れ込んでくる澄んだ空気のおかげか、少し混乱していた心が、幾分軽くなった気がした。
「……お嬢さん?」
そのとき、すぐ背後から聞こえたノアの呼びかけに、クラリスはびくりと驚き、思わず声を上げてしまった。
「ノ、ノア!?」
通りすがりの受験生たちまでが揃ってこちらを振り返ったため、クラリスははっとして、慌てて彼らに頭を下げた。
「……ごめんなさい」
受験生たちはすぐに興味を失ったようで、疲れた目をこすりながら、それぞれ自分の部屋へと戻っていった。
「……ふぅ」
気まずさに耐えきれず、クラリスが自分の髪先をいじっていると、再びノアが静かな声で詫びてきた。
「すまない、少女。驚かせるつもりはなかった」
「う、ううん。私も分かってるから」
クラリスは、できるだけ普段と変わらない調子で答えようと努めた。
それが、なんだかとても不思議だった。
“今”は確かに、いつも通りなのに。
それなのに、“いつも通り”話すために、わざわざ意識して力を入れなければならないなんて。
「……少女、何かあったのか?」
ノアの問いかけに、クラリスは小さく息をのんだ。
「え!?どうして?」
「それは、君が……」
「わ、私が何?」
そう問い返し、ノアをまっすぐ見つめたその瞬間、クラリスはようやく自分の失敗に気づいた。
いつも通り話しているつもりでいながら、肝心のノアを、きちんと見ていなかったのだ。
『本当に……馬鹿みたい』
クラリスは無理やり口元を引き結んだ。
どうか、このぎこちなさに彼が気づきませんようにと願いながら。
「急にどうしたのかは分からないけど、君が必死に何かを隠しているのは、はっきり分かる」
「そ、そんなことない!隠すだなんて……そんなの、ノアが――」
「僕が?君から?」
「ああ、もう……」
クラリスは思わず両手で顔を覆ってしまった。
やはり、ノアに嘘をつくのは無理だ。
「……その、ほら……あるじゃない」
クラリスは、ようやく目だけをそっと上げてノアを見た。
触れていた頬が、なぜだか少しだけ熱を帯びている気がした。
「この前の式典で……ノア、私の手、取らなかったでしょ」
「あ……」
彼は一瞬、記憶をたぐるような表情を見せ、すぐに小さくうなずいた。
「そ、その……今まで、そんなことなかったから。どうしてだろう……って、考えてしまって」
「それを、そんなふうに悩んでいるなんて思わなかった。もし少女が嫌な思いをしたなら、私が謝――」
「ち、違うの!嫌だったわけじゃない」
クラリスは、それ以上ノアの顔を直視できず、逃げるように庭園のほうへ視線をそらした。
「……もしかして、ノアが“ちゃんと見たい”と思ってる人が、いるのかなって……」
言葉はそこまでで、自然と途切れた。
「僕が……ですか?」
ノアの返答は、なぜか自分はそういう立場にはなれない、とでも言うような含みを帯びていて、クラリスは思わず、彼に向かって言葉をぶつけた。
「ノアがどうっていうのよ。顔だって綺麗だし、性格だっていいじゃない!」
「少女の感性は、決して一般的とは言えません。何より“よく見せたい相手”だなんて……」
そこで、彼はふっと言葉を止めた。
答えを探しているようにも見えて、クラリスはなぜか落ち着かない気持ちで、その先を待った。
「……いえ、いません。そういう相手は」
「ノア、今の言い方、ちょっと引っかかったわ」
クラリスの眼差しが、きっと鋭くなる。
「本当?そもそも、あの予式場で、私が誰かに“よく見られたい”なんて思う余地があったと思う?」
「それは……確かに、そうですが……」
その場には、彼らとエヴィントン以外に他の受験生はいなかった。
「……じゃあ、私の勘違いだったの?」
「見事に的を射ているよ、少女。」
あまりにもはっきりした答えに、クラリスはなぜか笑みをこらえきれなくなった。
別段、可笑しな話をしているわけでもないのに。
「だったら……あの日、どうして手を取らなかったの……?」
彼女がそう問いかけ、差し出されていた手の理由を聞こうとした、その時。
向かい合う二人の間へ、小さな光の粒がひらりと舞い降りてきた。
ノアは、そっと手の甲の上にその光を受け止める。
「…………」
彼は一度、静かに目を閉じた。
短い沈黙ののち、再び瞼を上げたとき――その眼差しは、先ほどまでとはまるで違っていた。
「少女。」
魔法使いとしての顔に戻り、ひどく真剣になったその表情に、クラリスは息をのむ。
クラリスもまた緊張しながら、彼をじっと見つめた。
「なに……があったの?」
「詳しいことはわからない。その文字に宿った光が伝えられる情報が、あまりにも少なくて。ただ、僕は今すぐ出発しなきゃいけない気がする」
「出発って、どこへ?」
「正確な場所はわからない。でも、ここからそれほど遠くはないと思う。少女はここで……」
「私も行く!」
「それは、あまり良い考えじゃ……」
彼の言葉が終わるよりも早く、小さな光がぱっと宙へ舞い上がり、修道院の出口へと向かっていった。
クラリスが即座にそれを追いかけると、ノアは大きく息をついてから、諦めたように言った。
「……門が消えてしまった以上、司祭たちに知らせるのも時間の問題でしょう」
「入ってきたとき、少し前庭を散歩していたと言えば、きっと見逃してもらえますよ」
週末を除き、修道院から一定距離以上離れることは、規則違反だ。
「……そんなに簡単なら、苦労しないんだけどね」
気づけば彼らは、すでに修道院の正門を抜けていた。