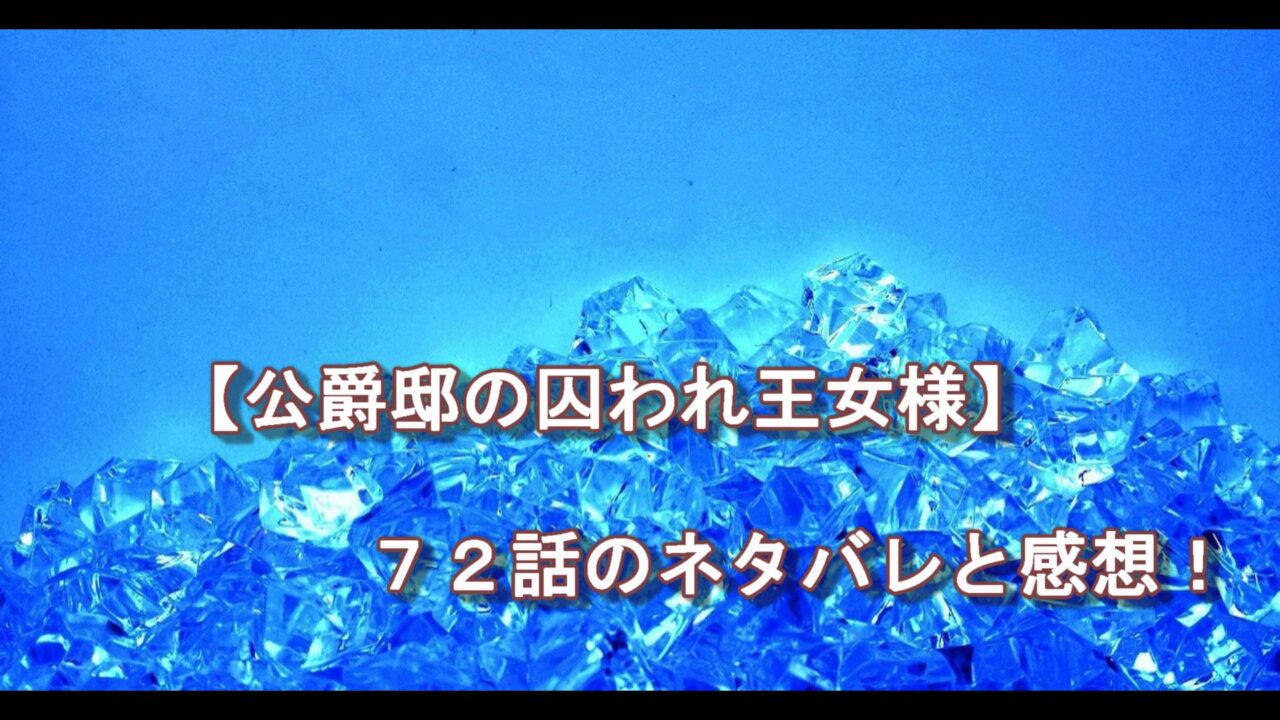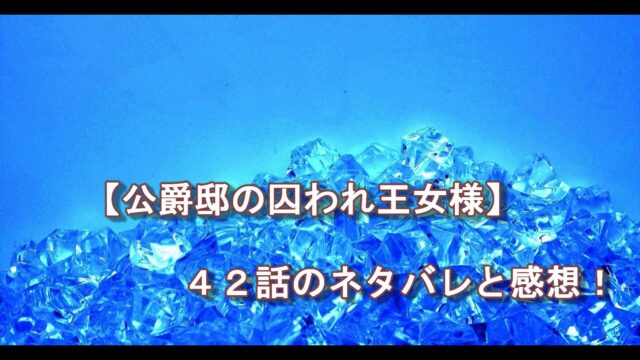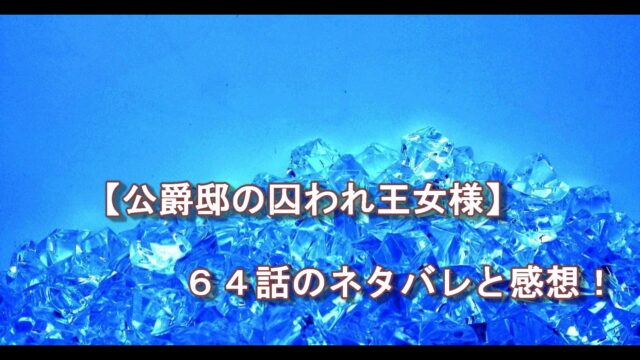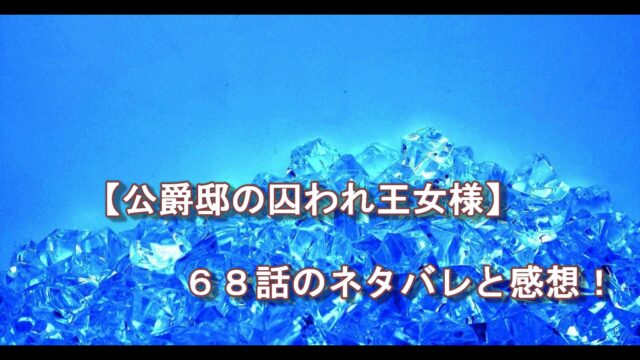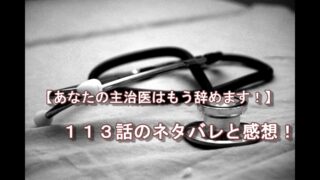こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
今回は72話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

72話 ネタバレ
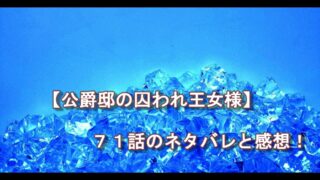
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- いつの間にか15歳②
「少し前にノアへの関心を示していましたよね?」
「気のせいだ。俺が召使いなんかに興味を持つわけがないだろう?」
「召使いじゃありません。友達なんです。」
「どうでもいい。」
「私は二人がとても気が合うと思うんですけど。」
「悪いけど、俺はそうは思わない。」
そう言いながら、バレンタインはクラリスの手首に白いリボンを丁寧に結び直してくれた。
「やっぱり気が合うと思いますけどね?」
「何だって?」
「実はノアもそう言っていたんです。」
クラリスはクスクスと笑いながら、少し前にノアと交わした会話を話し始めた。
今回の祭りの期間中、クラリスが「王都に来てバレンタインに会ってみない?」と提案した際、ノアは「召使いと会うのは嫌だ」ときっぱりと断ったのだ。
「面白くないですか?ノアも・・・いいえ、バレンタイン様と同じことを言ったんですよ?」
「俺も面白くない。お前以外の友達なんて面倒だ。」
彼はクラリスの手首に結んでいたリボンをパッと手放し、数歩先に歩き出した。
しかし、すぐに立ち止まり、クラリスがちゃんとついてきているか確認すると、リボンを売っている店に連れて行き、新しい赤いリボンを2本買った。
クラリスは新しいリボンが特に必要というわけでもなかったのに。
「俺にも1本くれ。」
さらに、強引に1本を奪っていく始末!
「せっかく商品券で何か買う予定だったのに・・・。なんでリボンなんですか?王子様が使うことなんてないじゃないですか。」
「何言ってんだ。」
彼は自分の金髪の上にリボンをうさぎの耳のように結び、特有の大袈裟な表情を見せた。
「男もリボンを使うんだ。特に俺みたいな美男なら、なおさら似合うだろう。」
クラリスは反論したかったが・・・、その鋭い眼差しに、赤いリボンが見事に似合っている事実を認めざるを得なかった。
奇妙な光景ではあったが、彼の持つ美しさは少しも失われていない。
もしクラリスが彼の内面を知らなければ、他の女性たちのように、つい目を奪われてしまったかもしれない。
「・・・驚くほど似合いますね。」
「知ってる。でもそろそろ戻ろうか。戻る途中で話すべきことがある。」
「話すべきこと?」
ちょうど人が多いエリアを通りかかるため、クラリスは彼の腕に寄り添うほど近づいて歩いた。
「もしかして、首都院のことですか?宗教に関わる高貴な司祭たちがいる場所でしょう?」
「そうだ、でも俺が言ってるのは、そこで暮らしながら公務員試験を準備している人がいるって話だ。」
「うーん・・・。」
クラリスはとても古い記憶を思い出した。
「クエンティンおじさんが何度かその話をしてくれましたよ。」
彼は面白い話をたくさんしてくれたが、その中には首都院で勉強していた頃の話もあった。
彼が言うには、首都院は朝から晩まで勉強に集中する場所で、友達を作ったり恋人に会ったりする場では絶対にないということだ。
その後、首都院で出会ったカップルの記事が新聞に載っても、彼はそれを認めようとはしなかった。
ちなみに、彼はいまだに独身のままで、公爵の秘書官の職に就いて長年仕事を続けている。
彼はいまやお金を貯めても使う場所がないと言い、昨年末には多額の寄付をしたと聞いた。
「なぁ、他に何か考えてたんじゃない?」
クラリスは、クエンティンが早く良い縁に恵まれることを願ってはいたが、その事実をバレンタインに伝えることはなかった。
彼がまた嫉妬を爆発させるに違いないからだ。
「全然そんなことありませんよ!」
必死に否定しても、バレンタインの疑念を払拭することはできなかったようだ。
彼の目つきがさらに鋭くなる。
「嘘だ、嘘もつけないくせに・・・。」
話の途中で、彼はクラリスの腕を掴み、自分の方へ引き寄せた。
その勢いでクラリスは彼の方へ倒れ込みそうになり、一瞬「これが新しい嫌がらせの方法なのか?」と思ったが、そうではなかった。
彼女が立っていた場所を一匹の馬車馬が猛スピードで通り過ぎていったのだ。
「危ないな・・・。なんでこんなところを走るんだよ。おい、大丈夫か?ぶつからなかった?」
彼はまだクラリスを自分のそばに引き寄せたまま、危険な勢いで走り去った小さな馬車をじっと見ていた。
「えっと・・・。」
クラリスは驚いた心を落ち着けるために深呼吸をして、やっと答えた。
「はい、少し驚いただけです。ありがとうございます。全然ぶつかっていません。」
「そうか?」
バレンタインは再び彼女を見て、穏やかに微笑んだ。
「よかった。大切な馬車が壊れるところだった。」
「え?」
クラリスは彼の顔をじっと見つめた。
その瞬間、彼が少し前に言った「危険だ、なんでこんな道を走るんだ」という言葉の意味を理解した・・・。
「君みたいな頑固者にぶつかったら、どんな馬車でも耐えられないだろう。祭りで馬車が壊れたら困るからな。」
「困る?」
「頑固者」という言葉は、クラリスにとっては明らかに良い褒め言葉なのだが、どうしても彼の言葉を素直に受け止められないのが不思議だった。
彼は徐々に深まるクラリスの沈黙を無視し、再び第三城壁へと向かった。
「首都院は、君が率直に話す価値があるくらい素晴らしい長所があるんだ。」
「また私をからかう話をしようとしてるんですか?」
「いや、違う。本当に驚くべき長所なんだよ!僕を信じられないのか?」
『信じられません!』
クラリスは喉元まで込み上げる答えを飲み込んだ。
なぜなら、それが本心ではなかったからだ。
バレンタインはいつも皮肉っぽい口調で話していたが、決定的な瞬間にはいつもクラリスの側に立って考えてくれていた。
「・・・分かりましたよ。何ですか?」
「まさにメダル評価試験があるってことだ。」
「え?」
「実際の環境に近い場所で、他の受験生たちと一緒に試験を受けるんだよ。」
「ああ。」
それは特に深く考える必要もない、非常に明白な長所だった。
公務員試験の受験可能年齢は16歳から。
クラリスは初回の試験について「雰囲気に慣れるだけでも成功」との話を何度も耳にしていた。
しかし、チャンスが2回しかないクラリスにとって、そのような目的で貴重な機会を無駄にするわけにはいかなかった。
首都院で行われる試験はたとえ本番ではないにせよ、確実に大きな助けになるだろう。
「実りあるようだね。そう思わない?」
「はい、そうですね。」
しかし、クラリスがその長所を活かせる機会は限られていた。
彼女はシェリデン公爵の権限を超えて行動することはできなかった。
「よかったね。それじゃあ、入試の日までしっかり準備しておいて。」
「それは・・・」
クラリスは彼をじっと見つめた。
「王子・・・いや、ヴァレンタイン様が首都院に行かれるという意味ですよね?」
「ああ、君一人で首都院に行くことはできないだろう。首都院との協約によれば、無防備な未成年者が首都院の建物に入ることはできない決まりなんだ。だから僕が一緒に行って君を守らなきゃいけない。」
「私は首都院に行くなんて言ってないんですが?」
「試験を受けてみたくないのか?」
「試験は受けたいです!」
「じゃあ行くことになるね。君は自分がやりたいことを決して諦めない性格だから。」
クラリスは否定することができなかった。
「でも、費用というか・・・後見人としての許可を得なければなりません。そして私は罪人のような立場なので・・・好き勝手に過ごすことはできないってことですよ。」
必死に釈明してみても、ヴァレンタインは鼻で笑っただけだった。
「兄上が君の教育に一銭でも惜しんだことがあるのか?」
「・・・ありませんでした。」
いや、正直に言うなら、過分なほどの投資を受けてきた。
試験に関すること以外にも、クラリスが興味を示すと、各種楽器や天文学、外国語、薬草学などに触れる機会を得られるよう、短期講師を派遣してくれるほどだった。
「公爵様の許可も必要だし、決定するには時間がかかりそうだと思います」
「そうだな。」
ヴァレンタインは冷淡に答えた。
何にせよ、彼はクラリスが首都院に行って試験を受けるということを、すでに確信しているようだった。
しかし、世の中の事はすべて簡単に解決するわけではないものだ。
クラリスが王の後援を受け、豊かな生活を送れるようになったとはいえ、その本質はどこまでも罪人である。
シェリデン公爵は彼女を監視する義務があり、その目の届かない首都院へ送り出すことには気が進まないだろう。