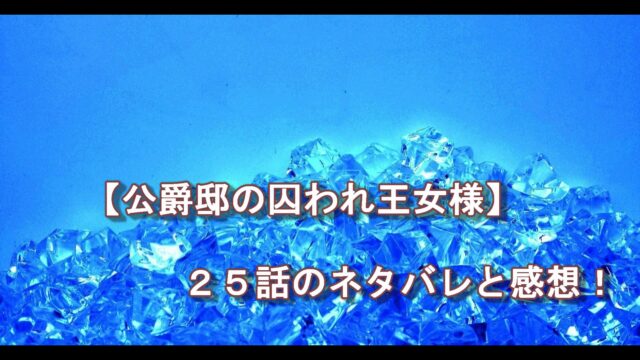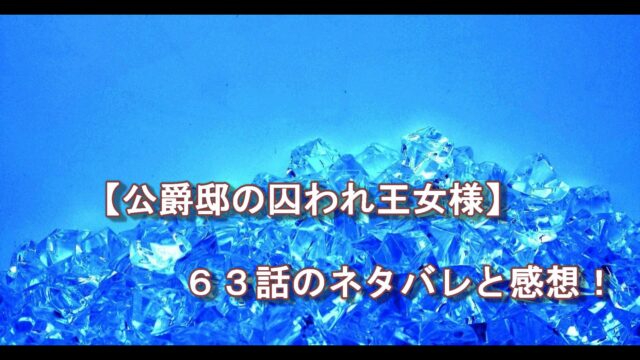こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

95話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 贈る花⑥
「最後の質問の前に、少し休憩しませんか?」
「そう?」と話しながら、侯爵夫人は三人に了承を求め、一旦席を立った。
「やはり気づいているようですね……。」
クラリスは渋い顔をしたが、両隣の反応には驚かされた。
「そんなはずがない。」
「完璧な答えじゃなかった?」
まったく違った。
たとえクラリスが求愛について何か知っているという印象を与えることで場が収まるとしても、それ以外に知識があるわけではなかった……。
ともかく、二人の答えがひどく的外れだったことはわかった。
クラリスは先に席を立った。
ノアとバレンタインが同時に彼女を見上げると、彼女は肩をすくめた。
「私もちょっと失礼するわ。」
その後、慎重に廊下へと出た。
周囲を見渡すと、侯爵夫人はセシリアが背丈を測った跡の前でじっと立ち尽くしていた。
クラリスは考え込んだ末、慎重に彼女のそばへと歩み寄った。
遅れてそれに気づいた侯爵夫人は、「ごめんなさいね」と申し訳なさそうに呟いた。
「大丈夫です。」
「ただ……少し考えてしまったんです。私が笑う資格なんてあるのかって。」
「……夫人。」
「本当にごめんなさい。こんなに楽しい時間を過ごすのがあまりにも久しぶりで、気持ちが整理できなくなったみたい。私がこんなふうに過ごしていてもいいのかしら。娘の誕生日まで……もう、あと一週間しか残っていないのに。」
クラリスは彼女の気持ちが何となく理解できた。
幼い頃、自分も似たようなことを悩んだことがあったから。
幸せになることは、果たして自分勝手な行為なのだろうか……と。
「えっと、私はですね、夫人。」
クラリスは両手をそっと重ね、話し始めた。
「私……母の顔を知りません。」
カーター夫人は驚いたように視線を向けた。
「私が幼い頃に亡くなったので、母の声も、香りも……何も知りません。私が知っているのは、ただ名前だけなんです。」
「……そう。」
「でも、それでも——」
クラリスはようやカーター夫人を見つめた。
悲しい話をしているつもりはなかったので、あえて微笑みを浮かべたままだった。
「私は母が大好きです。何も知らないけれど、本当に大好きなんです。だって、母が私をこの世界に生んでくれたじゃないですか?」
「……」
「だから、時々願うんです。母の人生に、たくさんの幸せがあったらいいなって。」
母が最後にどうなったのかは分からないけれど、彼女の日常が幸せで満たされていたことを願う。
「……ありがとう。」
クラリスの言葉に耳を傾けていた侯爵夫人は、そっと涙を拭いながらコップを握った。
「そう……そうね。私が娘の人生に笑顔があふれることを願うのと同じように……あぁ。」
ふと夫人は、ロアとバレンタインが待っている応接室を見渡した。
「お客様をお待たせしてしまいましたね。つい、話し込んでしまって。」
「大丈夫です。皆、夫人のお話に夢中でしたから。」
「まぁ、そうかしら。お二人とも、とても興味深いお客様ですね。私自身、思わず声を出して笑ってしまったほどです。それに、どうやらお二人ともクラリスをとても気に入っているようですよ。」
「そ、そんな……!」
クラリスは、思わず声を上げてしまった。
彼女は凍りついたように両手で口を押さえ、言葉を飲み込んでしまった。
「え?」
「いや……その。」
ためらいながら、クラリスは最終的に夫人にすべてを打ち明けることにした。
彼らが夫人の期待に応えたくて、嘘の関係を演じていたことを。
「申し訳ありません。でも、これ以上、嘘をつき続けるのは正しくない……と思って。」
クラリスは彼女の表情をうかがったが、夫人は怒るどころか、むしろ興味深そうな顔をしていた。
いや、それどころか、さらに面白がっているような……そんな雰囲気すらあった。
「でも、紳士たちがクラリス嬢に求婚したがっているのは事実でしょう?」
「えっ? そんな、ありえません!」
クラリスは凍りついた表情で、二人との関係を説明した。
「実はあの二人、私が女性だということをほとんど忘れて生活していると思いますよ?」
クラリスは、彼らが性別の違いをほとんど意識せずに過ごしていることを伝えた。
「子供の頃は、カエルやトンボを捕まえたり、大人に見つからないように汚れた川底で遊んだりもしていました。そんな私にどうやって女性としての魅力を感じろというんです?」
クラリスは、未だに呆然としている二人の前に立った。
カエルを捕まえて楽しむノア。
川で汚れたものがついたと文句を言うバレンタイン。
今でもたまに、彼らは幼い頃のままのように見えることがある。
そんな二人と「求愛」という言葉が結びつくはずもなかった。
「せいぜい『仲間』とか『友愛』なら、まだ成立するかもしれませんけどね。」
クラリスの説明を聞いても、夫人の表情は納得しているようには見えなかった。
「年配の私の目を信じてみるのも良いですよ。あと数年もすれば、彼らはさらに立派な紳士になり、間違いなくクラリス嬢に熱心に求婚するでしょうから。」
「それは……」
クラリスはしばらく口を閉じた。
どうやら夫人に、もう少し話を聞かせたほうがよさそうだと思ったのだ。
「私にはありえません。なぜなら、私自身、そのような気持ちを……受け止めることができる人間ではないのです。」
「クラリス嬢はどう思いますか?」
「私はですね、夫人。」
クラリスはしばらく自分の服の裾を指でなぞった。
ここ数年、彼女は「王の側近」として紹介されることが多くなった。
本来は囚人であるという事実を忘れたわけではないが、その肩書が話題に上ることは次第に減っていった。
だからだろうか。
久しぶりに自分の「囚人」という身分について話すのは……少し難しかった。
「囚人です。」
それでも、クラリスは勇気を振り絞って言葉を発した。
「……え?」
「こうしてお会いする前に、先にお伝えすべきでした。申し訳ありません。隠していたわけではないのですが……。」
しどろもどろに説明していたクラリスは、意識的に落ち着きを取り戻し、背筋を伸ばした。
そして、たった一言で自らの罪を告白した。
「私は、クラリス・レノ……グレジェカイアの者です、夫人。」
その名に続く、滅びた国の名前を聞けば、誰もがクラリスの罪を理解するだろう。
静かだった応接室の空気が、さらに沈み込んだようだった。
静寂と、張り詰めた緊張感が広がっていく。
『……あぁ、どうしよう。』
もし夫人が囚人の存在を侮辱されたと感じたら、彼女はどうするだろうか?
クラリスは、この場に居続けてもいいのかと自問した。
ペンダントでも差し出すべきかと悩んだ。
せめて、夫人の気持ちを少しでも和らげるために。
だが、改めて自分の身分を強調するのは余計なことのような気がして、クラリスはただ静かに頭を下げるだけに留めた。
重たい沈黙が続き、やがて夫人が一歩踏み出した。
伏し目がちだったクラリスは、近づいた気配に驚いて、とっさに後ずさった。
「王女様だったのですね。」
侯爵夫人の言葉には、すでに失われた王国の名を知る者だけが持つ、深い理解と敬意が滲んでいた。
クラリスはとっさに首を振った。
「いえ、私は……。」
「初めてお会いしたとき、親しみを感じたのは偶然や運命ではなかったのですね。」
「え?」
まるで喜びすら感じているかのような夫人の表情に、クラリスは改めて顔を上げ、じっと彼女を見つめた。
彼女はクラリスの両手を優しく握りしめた。
「グレジェカイア、それが私の祖国です。」
「……え?」
「もう永遠に消えた名前だと思っていました。まさか、世の中の片隅で王女様が生きていらしたとは……私は知ることすらできませんでした。」
「そ、そのようにお呼びになるのは困ります!」
クラリスは、万が一誰かに聞かれるのではと不安になった。
彼女を王女と呼ぶことは、すなわちグレジェカイアの復興を訴える反逆行為と見なされかねない。
「どうかクラリスと呼んでください。今までずっとそうしてくださったように。」
夫人は残念そうにしながらも、静かに頷き、固く手を握り返した。
「もし知っていたなら、力になれたのに……」
「そのお気持ちだけでも、ありがたく思います。ですが、私は心強い守護者がいらっしゃるので。だから、それほど心配しなくても大丈夫ですよ。」
「……でも、なんだかしんみりしてしまいますね。」
夫人はクラリスの事情を深く思いやったのか、再び涙をぬぐった。
「これからは私も力になります。大したことはできませんが、それでも、私たちは遠い親戚くらいにはなれるはず。他人のふりをすることはありません。」
「親戚ですか?」
夫人は自らの遠縁の曾祖母がグレジェカイアの王妃であったことを明かしながら、少し苦笑した。
「若い人には、少し縁遠く感じるかもしれませんね?」
「そんなことありません!」
クラリスは嬉しそうに目を輝かせた。
「私と夫人の間には、確かなつながりがあります!こんなことって……!私の血を引く方に、今まで地上で出会えたことはなかったんです!」
同じグレジェカイアの血筋というだけでなく、家門としてもつながりがあるのなら、それはより特別なことだった。
だからこそ、きっと……
(家族みたいだ。)
クラリスは夫人への親しみがますます強まったことを感じた。
「私も夫人を助けることができればいいのに。」
たとえば、行方不明のセシリアを探す手伝いをするとか。
しかし、クラリスにそんなことができるだろうか?
優秀な魔法使いたちですら彼女をいまだに見つけられずにいるのに。
「クラリス。」
夫人に呼ばれ、ハッとして再び彼女を見つめた。
すると、夫人はブラウスにつけていたブローチを外し、クラリスに差し出した。
「突然だけど、これを受け取ってくれる?」
「え……?」
青い宝石がついたブローチは、一目見ただけでも価値のあるものとわかる。
「私は……十四歳の時、初恋の人を追ってこっちにやってきたの。これは祖母が私に持たせてくれたブローチなのよ。」
「それなら、これは夫人の大切な宝物じゃないですか!」
「祖母は、さらにその祖母から受け継いだものだとおっしゃっていました。」
「……。」
「つまり、厳密に言えばこれはグレジェカイア王室の宝石なのです。私はクラリスがこの宝石の持ち主になるのがふさわしいと思います。」
そう言って、夫人はそれをクラリスの手のひらの上にそっと置いた。
「私は受け取れません……。」
当然、クラリスは拒もうとした。
彼女は罪人であり、与えられた報酬以外の私有財産を持つことは許されていなかった。
ましてやグレジェカイア王国の宝物など!
異国の人間がそんなものを持つなど、到底許されるはずがない。
『この事情を説明すれば、夫人も納得してくださるはず。』
そう思い、クラリスは返そうとした……。
【バン! 私と一緒に遺跡でお宝を探すのは誰だ!キラキラした輝きを手に入れよう!】
「……。」
【遺跡探索チーム、現在メンバー募集中!素晴らしい宝石を持ったお宝は、みんな応募してね!】
……宝石が発する言葉を聞いて、なぜかもう少し持っていなければならない気がした。