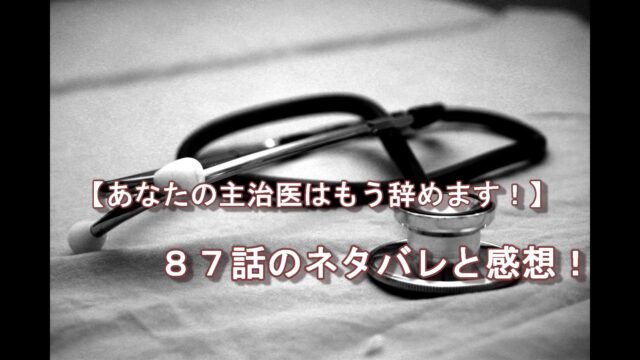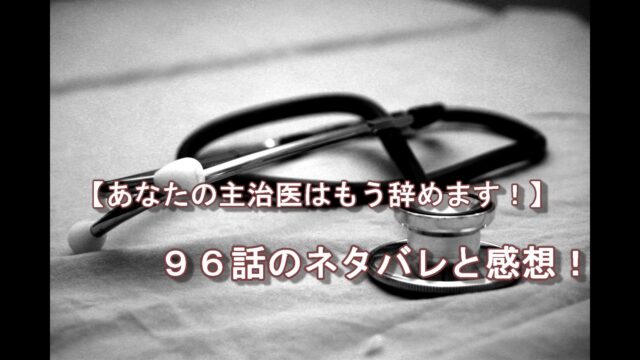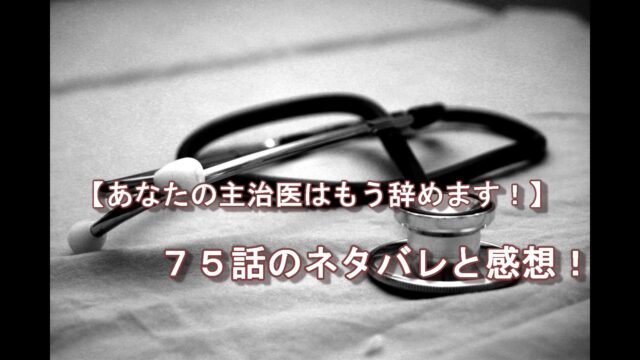こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

149話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 医療ボランティア
イザベルはお茶を飲みながら、優雅にカタログを眺めていた。
「これも可愛いわね。うん、これもいい感じ。」
彼女が見ているカタログには、若い女性向けのアクセサリーがたくさん載っていた。
「昔、シオニーがこういうスタイルが好きだったわよね。リチェも気に入るはず。とりあえず、これは色違いで注文して……。」
軽くショッピングを終えた彼女は、隅に置いてあった靴のカタログを手に取った。
その時、ノックの音がした。
「お母様、エルアンです。」
「入りなさい。」
イザベルは靴のカタログを惜しそうに閉じ、目を細めた。
エルアンは慎重に礼をし、イザベルの前に座った。
「頼みがあって参りました。」
「そう?話してみなさい。」
「数日間、工場の作業を手伝っていただきたいのです。」
「それは嫌ね。」
イザベルは即座に首を横に振った。
「あなたが建国祭の後に怪我をして来た時も、少し前に倒れて首都で治療を受けた時も、私が公爵用の仕事はすべて引き受けていたわ。その後も、ペレルマンの領主に気に入られるように、しばらく滞在することを積極的に勧めていたのに。」
彼女の黒い目が冷たく光った。
「それなのに、まだリチェとの結婚の日取りも決めていないし、教会の許可も得られていないって? それで、あなたが私の息子だって?無能ね……。」
「それは……。」
「私は経営が性に合わないの。こうやって優雅にお茶を飲んだり、リチェに贈るプレゼントを選んだり、のんびり過ごす生活が合ってるわ。小さな貴族出身だと無視されないように、一生懸命働いているふりはしたけど、実は生産性のない一日が一番好きなのよ。」
イザベルは再び靴のカタログを手に取った。
「じゃあ行きなさい。あなたは働きなさい。私はこれから休むわ。」
「それでも、全くの無収入というわけではなかったのでは?」
エルアンは控えめな声で言った。
「今やペレルマン家の人々も、私を無視して追い出すことはなくなり、警戒はしているものの、ある程度は受け入れつつあるようです。リチェもずっと説得を続けています。」
「証拠は?」
「他の領主たちの前で、正式な婚約者のように振る舞っても、特に否定されることはありません。」
「ほとんど乗り越えたのね。」
「そうですか?」
「私はこの分野ではかなり洞察力があるのよ。その証拠に、今この席に座っているんじゃない。」
イザベルはさっぱりと髪をかきあげ、少し低い声で続けた。
「それで、今後の計画は?」
「そのために来ました。」
エルアンはきっぱりと答えた。
「メイリス公国で魔力爆発による山崩れが起きて、今回、国立医療研究チームがボランティア活動に行くそうです。私も一緒に行きたいです。」
「それは当然よ。そして、支援は決まったの?他の家門が入れないようにしないとね。」
「最初に名乗りを上げたのが神殿だったので、すでに全額を寄付することに決めました。」
神に対する復讐を密かに誓ったエルアンは、一生の間、神殿が神の名を讃えるような活動を極力妨害するつもりだった。
「それなら、また領地の仕事を私が引き受けることになるの?」
イザベルは先ほどの拒絶を繰り返し、深く息をついた。
そしてエルアンに向かってきっぱりと命じた。
「支援者の立場でついて行くにしても、絶対におどおどして後ろに下がらず、リチェの隣にぴったりくっついてしっかり聞くのよ。わかった?」
「はい、わかりました。」
エルアンはきっぱりと挨拶して出て行った。
一人残ったイザベルは、しばらく考えるような表情で窓の外に視線を向けた。
「ふむ……メイリス公国ね……。」
アルガがメイリス公国に行くと聞き、彼女の古い記憶が蘇り始めた。
シオニーとアルガ、自分自身とケイラルンが、今のリチェとエルアンくらい若かった時代。
「良くない記憶があるはずなのに行くなんて……医者は軍医ね。あの人の性格なら、シオニーを忘れるわけがないけど、公と貴族の関係が変わったのかしら。」
過去を思い出している彼女の顔に、ひんやりとした微笑みが浮かんだ。
「リチェ、これ頼んでもいい? 健康な鹿の糞で育てたダルペンギ料理。」
「でも、それまで頼んだらちょっと多すぎませんか?」
「でも全部、まだ食べたことのないものばかりじゃない。」
叔母と祖父が首都に上京したため、久しぶりの家族食事会だった。
国立医療研究チームが出航した後、父はついに伯爵位を受け、私は伯爵令嬢となった。
私と父は首都の伯爵邸に滞在し、一緒に通勤し、叔母と祖父は元の領地へ戻った。
領地を空けるわけにはいかなかったからだ。
しかし、叔母と祖父は余裕ができると、いつも首都に上がってきて一緒に時間を過ごした。
そんなときは、首都にある有名なレストランを巡って家族食事をするのが自然になっていた。
「私たちはあまりにも長い間離れていたから、あなたの好みを知らないのよ。できるだけ多く知っておかないと。」
叔母は結局、新しい食材で作られた実験的な料理をすべて注文し、簡潔に言った。
セルイヤーズ公城でも美味しいものは実際に食べたことがあると何度も言ったが、叔母と祖父はこの世に存在するあらゆる味を経験させたいようだった。
「私たちは逃してきたものがあまりにも多い。」
祖父は笑いながらそう言った。
「君が人生で初めてお菓子を食べる瞬間とか、初めてファーストフードを食べる姿とか。とにかく、君が初めて体験することを全部一緒に味わいたいんだ。」
私はなぜか胸が痛み、すぐにメニュー表を開いて追加の注文をした。
「すみません、こちらに熊の足裏肉と熟成ホワイトワインを一本追加してください。風味がどんな感じなのか、全く想像もつかないので。」
「父さん、そしてセイリン。」
父はぶっきらぼうな表情でナプキンを広げながら言った。
「みんな、幼いリチェがプディングを大事そうに食べる姿を見たことがないだろう?私はそれを見て、追加でプディングを注文することにしたんだ。」
「目の前に娘がいるのに、それに気づかないことがそんなに自慢なの?」
「それでも、これは自慢できるわね。」
「まあ、本当に……。」
叔母は涙をこらえつつ、攻撃を試みたが、結局はため息をついて父に切実に訴えた。
「どうやって食べたの?ちゃんと小さく切って食べたの?それとも、ゆっくりと飲み込んだの?」
祖父もまた情熱的に話に加わった。
「どんな味のプリンだった?追加で頼んだものも同じ味だった?」
父の首をかしげるような表情を見て、私は思わず笑ってしまった。
どれほど私を気遣ってくれているのか、私がこの家で初めて育ったわけではないのに、まるで守られているような無償の愛情を感じた。
すでに国立医療研究機関はその地位を確立し、各国に研究成果を発表し始めてから二ヶ月が経過していた。
この二ヶ月の間に発表された研究成果が、以前王室医療研究機関が二十年間にわたって行ってきた研究よりも有益であることを誰もが認めていた。
「国立」という肩書きを持つだけでなく、私たちは王族だけでなく全国の医師たちが治療できない希少疾患の患者たちを受け入れることができるようになった。
私は研究に打ち込み、才能を思う存分発揮し、その結果、自然と名声も高まっていき、とても嬉しく思っていた。
もちろん父も、長年不合理だと考えていた体制が完全に刷新され、終日私と一緒に過ごせるようになったことを大いに喜んでいた。
「それはそうと。」
叔母はいつの間にか出てきたアペタイザーを私の前に置きながら言った。
「一度道路が工事中だったけど、あれはセルイヤーズ公爵領とつながる工事だったよね?」
「うん……はい。」
どれだけ母親が領地を守っていても、エルアンがいつまでも公爵領を避け続けることはできなかったので、彼は結局公爵領へ向かうことになった。
その後すぐに、セルイヤーズ公爵領と首都をつなぐ直通道路の工事が始まった。
本来、セルイヤーズ公爵領と首都はそれほど遠くはなかった。
ただ、少し遠回りしなければならなかったが、その時間を短縮するためのものだった。
今でも時間さえあれば、少しでも顔を見せようとして首都に通っているのに、道路まで整備されているなんて。
完成すれば毎日でも来るのではないかと思い、父は否定しきれない期待の色を隠せなかった。
「今回、メイリス公国の奉仕活動にも唯一の支援者として参加したそうだな。」
父は眉間にしわを寄せた。
「たぶん、ついてくるんじゃないか。」
私はすでに使用人を通じて一緒に行くという意向をこっそり受け取っていたため、何も言わずに黙ってお茶を飲んだ。
医療レベルがあまり高くないメイリス公国で大規模な地滑りが発生し、多くの人が負傷した。
ジェンシー公妃は帝国に支援を要請した。
地滑りの原因は魔力爆発であり、それにより患者たちがさまざまな合併症を引き起こしているという話を聞いた。
そこで、南部領を統治する計画を立てることになった。
困難なときも、裁判のときも私を助けてくれた人だから、もちろん私は直接行って助けたいと思っていた。
もちろん、私が行くと言ったら、父もついてくると言ったし、皇室からも皇族の依頼だったので、簡単に許可が下りた。
「お父さん、そろそろ許可してもらえませんか?」
私はそっと父にメイン料理をよそってあげながら、にっこりと笑った。
「お互いの命を救ったのだから、もしかしたら私よりももっと深い縁で結ばれているのかも……。」
「リチェ。」
父はナイフをピタッと止め、ゆっくりと置いた。
「笑顔を見せて、甘えた声を出すなんて……。あの公爵に学んだことは間違いなかったな。やっぱり、私の娘にとっても新たな存在だったんだな。」
「え?」
「ただじっとしているだけでも可愛いのに、そんな笑顔まで見せたら、世の中でできないことが何もなくなって、みんなが君の言うことを聞いてくれて、とんでもないお姫様になっちゃうよ。」
私は結局スプーンをぎゅっと握りしめながら口を閉じた。
ディエルの話によれば、今、父は「エルアンを受け入れなければならない」という事実を頭では理解しているものの、心の中ではとても納得できない状態だという。
エルアンが父を救ったという事実のせいで、今はただ嫌だ嫌だと言いながらも、完全に拒絶することができない段階まで来ているようだった。
心の底から受け入れるためには、かなりの時間がかかるか、あるいは何か別の事件が起こらなければならないようだった。
「そうだ、その公爵の仕事はゆっくりと考えなさい。」
祖父はワイングラスを持ち上げながら、状況を整理した。
すでにゆっくりと考えていたので、時間がかなり経っていたと答えようとしたが、何の意味もない気がして口をつぐんだ。
1日20時間も張り付いていたというエルアンの表情を思い出すと、その日すぐに破れた彼の夢が痛々しく感じられた。
「メイリス公国にはいつ出発するんだ?」
「3日後です。あ、ディエルも行きます。研究チームの一部だけ行くので、人手がかなり変わると思います。」
「あ、ディエルも行くの?」
私は研究チームの仕事で忙しかったため、ディエルにも長い間会えていなかった。
「そうか、もう出発させたんだな。宿舎や治療所のようなものを建てる準備をしているのだろう。」
私は、ディエルに「リチェと公爵様の宿舎をできるだけ遠くに離してくれ」と熱心にお願いしている父の姿を思い浮かべながら、静かに肉を噛み締めた。
まあ、支援を断ってついてくることを無理に止めるわけにもいかないしな。
「それにしても、ボランティア活動とは……。昔を思い出すな。」
父は喉を鳴らしながらため息混じりに言った。
「シオニーがあのとき、俺に告白してきたんだ。」
その瞬間、叔母がナイフで肉を切りながら冷たく言い放った。
「話は端的にしなさい。どこの軟弱者に関わった話なのか。それで、いつも不平不満を言っていたあの人を、シオニーが機会を与えたのよ。もちろん、あの人があなたたちにこびへつらっていたのも、気に入っていたからだけど。」
「え?それはどういう意味ですか、叔母さん?弱い人だったんですか?」
「ただ、シオニーに気に入られようと、あなたのお父さんを前にしても見え透いた態度を取っていた人がいたのよ……。あ、ちょっと待って、その人はメイリス出身じゃなかった?名前は確かシ……。」
「やめなさい、セイリン。」
父は目を見開き、苛立ちを露わにした。
これまで父から聞いていた恋愛話は、すべて楽しく美しいものばかりだったのに、叔母の話を聞いていると、どこかで美化されたり、脚色された可能性があるのかもしれないという考えが浮かんだ。
「何はともあれ、正義は勝ったんだな。」
「うん、お父さんが正義だったの?」
「当然だ。その卑劣なやつがシオニーの婚約を奪おうとしている間、俺は黙々と命を奪われかけた子供を救ったんだ。だから、俺が正義じゃないわけがない。」
話に脈絡がなさすぎて、まったく状況を把握できなかったが、お父さんはそれ以上詳しい説明をしてくれなかった。
しかし、私はすぐに察した。
どれだけお母さんとの結婚が成功していたとしても、そのときの記憶はお父さんにとって、二度と思い出したくない苛立たしい出来事だったのだろう。