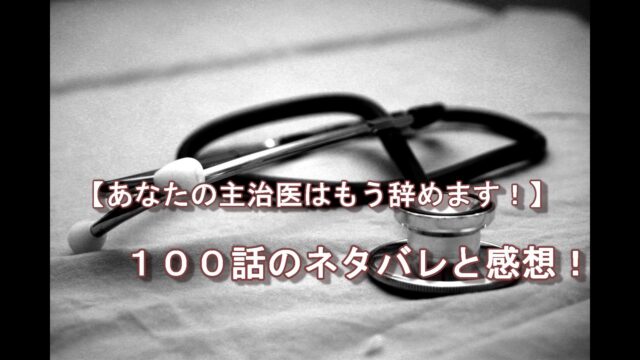こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

150話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 医療ボランティア②
みんなが眠る夜、私はこっそり家を抜け出して、裏門の前で静かに立っていた馬車に乗り込んだ。
馬車に乗るや否や、エルアンが私をひょいと抱き上げ、膝の上に座らせ、首筋に口づけをした。
「会いたかった、リチェ。」
「最近会ったじゃないですか。」
「それで、君は僕に会いたくなかったの?」
「そんなことないです。会いたかったです。」
馬車がどこかへ向かう間、私はいつものように彼の体にもたれて座っていた。
「君と一緒にいると、いつも夢を見ているみたいだ。」
エルアンは私の目に口づけし、こう言った。
「こうして君と肌を合わせているときは——」
倒壊した展望塔の残骸の中で初めてキスをしたとき、だからこそお互いの気持ちが通じたのだと感じてから、すでにかなりの時間が経っていた。
父のせいで長く一緒にいることはできなかったものの、恋人としての時間はそれなりに経過していたが、彼の愛情表現は一向に収まる気配がなかった。
「そんなことをあまり言いすぎると恥ずかしいよ。」
「うーん……。」
彼の指先がそっと私のまつ毛を撫で、それから優しく降りていった。
「本当に恥ずかしくなること、やってみようか?」
首都がどれほど広大か、どれほど明るい光に満ちているかは知っていた。
しかし、この瞬間だけは、暗闇の夜が優しく揺らめき、霞んで見える景色がまるで私たちの世界のすべてであるかのようだった。
「じゃあ…… 目で見たら……」
私は彼の腕をつかみ、低い声で言った。
「……判断力が鈍るのに。」
「わざとだよ。分かってるでしょ。」
彼の荒い呼吸には、熱を帯びた切なさが混ざっていた。
慎重な手つきの中、時折強く引き寄せられるその力のせいで、考えを続けるのが難しかった。
「20時間も一緒にいられなくて…… 会うたびにこうなんですか?」
ぴんと張り詰めた体のあちこちに、彼の体温が伝わってきた。
「違うよ。」
私はおなじみの重みを感じながら尋ねた。
彼は甘い吐息を漏らしながら、私にささやくように言葉を紡いだ。
「いつか20時間一緒にいても、こうしていたい。」
彼が私の腰を抱き上げ、瞬く間に体勢が変わったものの、視界には相変わらず彼の漆黒の瞳しか映っていなかった。
結局、馬車が目的地に到着したとき、私は力が抜け、ほとんど彼の胸に寄りかかるような状態になっていた。
私たちは父の目を避けて、時折こうしてデートに出かけることがあった。
最初の頃、私はエルアンに「いつまでもこうしているわけにはいかないし、いずれ父に話すべきだ」と伝えたが、彼はただ微笑んで首を横に振った。
結局、時間が解決する問題であり、父が心を開いて直接認めてくれるまで待ちたい、というのが彼の考えだった。
「僕は君と結婚するつもりだから大丈夫だよ。どれだけでも待てる。」
自分のせいで無理やり再会したことで、家族に負担をかけたくないと言い、代わりに長い間会わないと目の病気になりそうだから、こうしてこっそり会おうと提案した。
『お父さん、ごめんなさい……』
密会のために伯爵邸の多くの使用人たちを騙した私は、再び一線を越えてしまった。
私たちは夜中にサロンへ行き、絵画の鑑賞をしたり、一緒に服を仕立てたり、有名な菓子専門店で夜食を食べたりもした。
もちろん、エルアンがいつも特別に遅い時間に手配してくれたので、いつも私たち以外には誰もいなかった。
今夜は、以前の建国祭の時に一緒に風景を眺めたあの屋上に再び訪れたのだ。
「お父さんも受け入れられるきっかけが必要なのよ。どんなにダメだと強く拒んでいたとしても、自分で何度もその考えを繰り返しているうちに、やがては受け入れることになるでしょう?」
私は彼の手の甲を撫でながら言った。
「時間が経てば、きっとそのきっかけが訪れるはず。私は絶対に手放さないから、心配しないで。」
エルアンなら、本当に絶対に手放さない気がした。
「その間、君が嫌がることはしない。」
一緒にいるとき、彼は私をほとんど放さずに、どこかしらに触れていた。
傷つけたり痛めたりすることなく、私を腕の中に閉じ込め、微動だにできないようにしていた。
私が身をよじっても、彼はさらにしっかりと抱き寄せて、最後まで私を手放そうとはしなかった。
私は彼の胸の中で不機嫌に言った。
「じゃあ、その短所を直してください。世の中のすべての男の人が絶対に好きなわけじゃないんですよ。前にベルト男爵がエルアンを見て、そのまま逃げたじゃないですか。大事な話の途中だったのに。」
ベルト男爵は、共に医療研究陣に属している同僚で、通りで少し話をしていたが、エルアンに会った途端、目も合わせずに急いで挨拶をして去ってしった。
私の裁判のとき、ベルロンが「セルイヤーズ公爵の婚約者」と言いふらしたせいで、首都のほとんどの貴族たちは皆そう信じていた。
その噂に父が「無駄に他の奴らに近づけば、もっと面倒なことになるぞ」と言って、はっきり否定しなかったことが唯一の救いだが。
「ああ…… そうだね、直さないと…… でも、どうやって?どうして君を好きにならないことができる?」
「普通の人なら、誰かの婚約者だと知られている女性を恋愛対象として見ないものです。」
「でも、普通じゃない男もいるだろう?俺は……君が皇太子と踊っていたとき、本当に目が離せなかった。君とは恋人関係でもなかったのに、絶対に手放せないと思った。そんな奴がまた現れるかもしれない。俺は君のことになると、いつも不安なんだ。」
私は両手で彼の頬を包み込んだ。
そして、まっすぐ彼の瞳を見つめた。
「不安にならないで。私があなたを愛しているのだから。」
春の心地よい風が、そっと私たちを包み込んだ。
「新しく見つけた家族に囲まれて、本当に幸せ。良いこともあるし、研究の仕事も楽しいので、毎日が楽しいのも本当です。でも何より、エルアンとこうして肌を合わせて愛を語れることが本当に幸せです。」
彼は急いで飲み込むように私をじっと見つめた。
「だから約束して。仕事のせいでどうしても避けられない男の人に対して、嫉妬しないって。私を信じてくれればいいんだよ。前にエルアンにもきっぱりと線を引いたのに、他の男には不安になるの?」
私たちの間に一瞬静寂が流れ、彼は穏やかな声で言った。
「僕は君の言うことなら何でもちゃんと聞くよ。約束する。」
以前の可愛らしい姿は驚くほど消えてしまったけれど、彼がそんなことを言うたびに、なぜか昔のことを思い出して、心がじんわりと温かくなった。
「君がそんなことを言ってくれたら、どんなことでも聞いてあげたくなるよ。実際、こうして君の目を見つめているだけでもう冷静ではいられなくなる。」
「毎日会ってるのに?」
「だからこそ、君の前ではいつも冷静じゃいられないんだ。」
「それを自覚しているなら幸いですね。それでも一応、冷静なフリはしてくださいね。あなたには社会的な立場があるんだから。」
私は彼の額に自分の額をそっと合わせて微笑んだ。
「メイリス公国に行っても、礼儀を守らないといけませんよ。わかりましたか?私の仕事の邪魔はしないでくださいね。」
「……あそこは良くない記憶がある場所だよ。君が逃げようとした場所じゃないか。」
「だからこそ、良い記憶に塗り替えなきゃいけません。」
「うん……」
「良いことをしに行くんだから、私たちにもきっと良いことが起こりますよ。」
メイリス公国へは、任務のために行くのは確かだけれど、エルアンが一緒だということがさらに嬉しかった。
どんなに忙しくても、同じ空間で一緒に過ごせるというだけで、どれほど幸せか分からなかった。
「リチェさん!」
メイリス公国に到着すると、真っ先に駆け寄ってきたのはジェンシー公妃だった。
「こんなにありがたいことがあるかしら……!医者を何人か送るだけでも十分なのに、ペレルマン公女が直接来るなんて!」
「負傷者が多いと聞きました。被害は大きいのですね。」
「それでも私が帝国出身だからこうして支援も受けられて助かるわ。ああ、それとこちらは……」
メイリス公国を統治するエゼット大公は、都合により首都を離れられなかった。
そのため、ジェンシー公妃だけが山崩れの現場に向かうことになったが、彼女のそばには一人の若い男性が立っていた。
「シリオン・ジュニア・エフォン・レイニー伯爵よ。大公が直接来られなくて申し訳ないと言い、医療チームを歓迎するとして代わりに送ったんだよ。」
さらに詳しい紹介を聞いてみると、その男性はエジェット大公のいとこだった。
だから、ジェンシー公妃と一緒に大公を代表して来たのだ。
金髪に緑色の目を持つ彼は、私と同じくらいの年齢に見える青年だったが、大きな眼鏡をかけて、きちんとした服装をしていた。
「こんなに遠いところまで来てくださり、本当に感謝いたします。ボランティア活動の期間中、私が現地責任者として引き続き滞在する予定ですので、不便なことがあればいつでもおっしゃってください。」
シリオンが先に父に挨拶をした。
しかし、シリオンを見つめる父の目つきが、ほんの少しだけ複雑そうだった。
「シリオン・ジュニア……レイニー?もしかして、お父上と同じお名前ですか……?」
「はい。同じくシリオン・レイニー伯爵です。」
シリオンが明快に答えると、ジェンシー公妃が穏やかに会話に加わり説明した。
「こちらでは、お父様と同じ名前を息子に受け継ぐことは珍しいのです。」
シリオンは私にも礼儀正しく、手の甲に軽く唇を当てた。
その瞬間、父の表情が曇ったことに私は気づかなかった。
シリオンは私たちの後ろで、警戒の視線を向けるエルアンに対しても、きちんと礼を示した。
「ああ、セルイヤーズ公爵様ですよね?ボランティア活動支援団を組織するのに後援をしてくださったと聞きました。実は、後援をしていただかなくても、私たちの費用くらいは何とかなるのですが……」
「いいえ。メイリス公国にお役に立ててうれしいです。」
エルアンはきちんとしているが、どうにか礼儀正しく答えた。
簡単に皆が挨拶を交わすと、父は上着を脱ぎながら言った。
「では、早く移動しましょう。もしかしたら緊急を要する患者がいるかもしれないから。」
あまり歩かないうちに、ディエルがすでに主導して設置しておいた簡易治療所が見えてきた。
ディエルは馬車の中で、召使たちが運んでいる薬草の量を確認していたが、私たちを見つけるとすぐに駆け寄ってきた。
「無事に到着されたのですね。お疲れさまでした。」
「もうすぐ夕方だから、無駄に時間を費やさずに、少しの時間でも患者たちを診察したいのですが。」
「はい、あちらが診療所です。あそこにいるのが伯爵様で、その隣がリチェ様、そしてその隣が……。」
どうせ順番に診察することになるのだから、まずは私たちのために用意された席を案内しようとしたディエルだったが、最後にエルアンを見つめた。
「そして、セルイヤーズ公爵様は、そちらにお座りいただければ結構です。」
「……あそこ?」
「はい、支援者様ですので、一番良い席で海の景色を見ながら……」
ディエルは一番上に用意された席を指しながら言った。
日差しを遮る天幕に、ふかふかの椅子、各種料理が並ぶテーブル、さらには召使い一人まで控えていた。
そしてその席に座れば、美しいメイリス公国の海まで一望できるようになっていた。
ディエルが本当に気を使って整えたのは明らかだったが、エルアンは特に感動する様子もなく、控えめに首をかしげただけだった。
「つまり、僕は特に何もしなくていいってこと?」
私にはエルアンが本当に心から疑問に思って尋ねているように見えたが、ディエルの目つきはどこか切なげに私を見つめていた。
結局、私はディエルの代わりに優しく話さなければならなかった。
「何もすることがないよりは、エルアンは医学的な知識がまったくないから、休んでいていいってことじゃないですか?」
エルアンは私の言葉に目をぱちくりさせて尋ねた。
「じゃあ、ディエル・モレキンは医学的な知識があるのか?医者じゃないのは同じだろう。」
「いや、そこで私がなぜ……。」
「じゃあ、君はこれから何をするつもりなんだ?」
「まあ、私はリチェお嬢様とペレルマン伯爵についていって、あれこれ手伝うことになるでしょうね。結局、患者を運んだり、寝具を整えたりする役割の人が必要ですから……。」
ディエルが少し沈んだ声でうつむくと、エルアンが少し興味を持って言った。
「じゃあ、それは僕がやらなきゃいけないんだね。」
「え?」
「君も僕も同じようなものじゃない?それに力も僕の方が上手く使えると思うけど。」
「うん…… じゃあ、私は……」
「特に行く場所がないなら、君があそこに座っていなよ。」
エルアンは、自分のために用意された特等席を指さして、淡々と言った。
「じゃあ、そうします。」
それでディエルは、少し戸惑いながらも特等席に座り、気を落ち着けるように準備された飲み物を飲みながら、この国の青い海を楽しむことができた。
「エルアン、あれをちょっと運んでください。」
「この患者の服を脱がせて、傷の消毒をお願いします。」
「簡易ベッドをちょっと片付けてください。この患者をすぐに運ばなければなりません。」
「仕事を少し持ってきてくれますか?あ、それとついでに鎮痛剤も3つお願いします。」
エルアンが私のそばにいるために、ディエルの役割を引き受けたのは、これ以上ないほど良いことだった。
ただ彼がただウロウロするだけなら、忙しいこの時期に邪魔になるだけだからだ。
おかげで、ディエルはすっかり休暇気分を満喫していたし、エルアンは初めて誰かの指示を受けながら動いていた。
もちろん、その「誰か」が誰なのかは言うまでもなかった。
彼は最善を尽くしていた。
「リチェ様、何か必要なものはありませんか?」
彼が私の指示を聞いて薬を取りに少し離れた間、シリオンが近づいて声をかけてきた。
ジェンシー公妃は再び首都に戻っており、彼が残って色々と便宜を図ってくれていたが、彼はエルアンがいないときにだけ私に話しかけてきた。
「はい、ちゃんと持ってきてくれてありがとうございます。」
「もし帝国に比べて不足しているものがあれば、何でも言っていただければ私が手配いたします。」
「いいえ、すべて問題ありません。」
「ですが、私の父も若いころに帝国にいらっしゃったことがあるのですが、メイリス公国とそれほど違いはないとおっしゃっていました。むしろ、ここメイリス公国の方が住みやすいくらいですよ。地理的に少し外れていますが、鉄鉱石などの天然資源が豊富で、歴史的にも大きな悲劇がなかったのです。」
「ああ、そうなんですね。メイリス公国の利点、よく分かりました。別に知りたかったわけではありませんが。」
少しずつ患者の診療に集中しようとしていた私は、話が長引きそうな予感がして距離を置こうとした。
しかし、彼は会話をやめるつもりがないようだった。
「セルイヤーズ公爵とは婚約者だったとか。」
「どうして知っているのですか?」
「モレキン殿が教えてくれました。」
シリオンは柔らかく微笑みながら、さらりとした金髪をかきあげた。
「お母様の一方的な決定で、ペレルマン子爵様にまだ許可をもらっていないということですよ。」
「まあ、それは事実なんだけど……」
「ペレルマン子爵様は本当に心が優しい方ですね。」
彼は私の目を見つめ、眼鏡を軽く直した。
「こんなことは言いたくなかったのですが……」
「あ、じゃあ言わないでください。無理にしなくても大丈夫です。」
彼は私の言葉を無視して、少し低い声で尋ねた。
「お母様の遺言を守るために、公爵との関係を続けていらっしゃるのですか?」
実際、いくつかの状況を見れば、そう推測されても仕方がないようにも感じた。
しかし、それは違うということをはっきりさせるために、私は冷静に振り返り、本格的に答えようとした。
「リチェ!」
私たちの間に割って入ったのは、他でもない父だった。
「ルーシー・カルロニが痛みをひどく感じているようだ。」
「え?」
「まだ幼いから、耐えるのが難しいのだろう。行って鎮痛剤を打ってやれ。」
その程度の鎮痛剤なら父がすぐに投与できるはずだったが、どうやら父は私が若い男性であるシリオンと話しているのが気に入らないようだった。
「一緒に行きましょう、フェレルマン嬢。」
シリオンはにこやかに微笑みながらついてきた。
「率直に申し上げますが、実は私はリチェ様の緑色の瞳を初めて見たときから、とても美しいと思っていました。」
『何だ、この脈絡のない告白は?』
私はジェンシー公妃を思い出しながら、最低限の礼儀を守らなければと心を落ち着けた。
「え?子爵様も緑色の目をお持ちですよね。まあ、珍しくも……」
「だからこそです。」
彼は私の前に立ちはだかる父を積極的に避け、さらに話を続けた。
「僕が持っている美しいものと同じものを持っている人だから……」
私が身を引いて言葉を止めようとしたとき、父が鋭く彼を睨みつけた。
「今、何をおっしゃいましたか?」
「え?」
「どこで私の娘に手を出したのかと聞いているのです。」
私は、父がこれほど攻撃的なのを初めて見て驚いた。
もちろん、エルアンをひどく嫌ってはいたが、それはすべて過去の因縁のせいだ。
首都で新たな貴族たちが私に話しかけたり、わずかに好意を示したりしても、ただ冷たい視線を送るだけで、ここまで大っぴらに苛立ちを見せることはなかった。
「セルイヤーズ公爵を快く思っておられないと聞いています。」
かなり穏やかな印象を持っていたが、やはり人の心の内は分からないものなのか、シリオンは慎重に様子をうかがった。
彼は全く引かない様子だった。
「それでは、私はどうでしょう……」
「絶対に嫌です!」
私はためらうことなく言った。
父は鋭い目つきで彼を見つめていた。
「妄想するのはやめて、私の娘に興味を持つのをやめてください。本当に不愉快ですから。」
遠くでエルアンが薬箱を持って近づいてくるのが見えた。
そして、改めてメイリス公国のためのボランティア活動で、エルアンは一生懸命働いており、シリオンは私の隣で笑顔を浮かべているだけだった。
「先生……」
しかし、そんな考えも、私が面倒を見ている患者の中で一番幼いルーシーを見た瞬間、全て吹き飛んだ。
今年で9歳になったルーシーは、今回の山崩れで両親を亡くし、自身も大きな怪我を負っていた。
「……とても痛い……。」
山崩れによる物理的な負傷に加え、魔力の暴走による副作用もひどくなっていた。
「熱が上がり続けるのはよくないな……。ルシ、ご飯もしっかり食べて、たくさん休むんだよ。一番良いことを考えるようにしてみて。」
私は鎮痛剤を投与しながら、優しく声をかけた。
この幼い子供が最悪の状況に陥らないかと心配だった。
「……はい。」
鎮痛剤を打たれると、彼は少し震えながらも眠りに落ちてしまった。
幼いルシを見て、私は一息ついた。