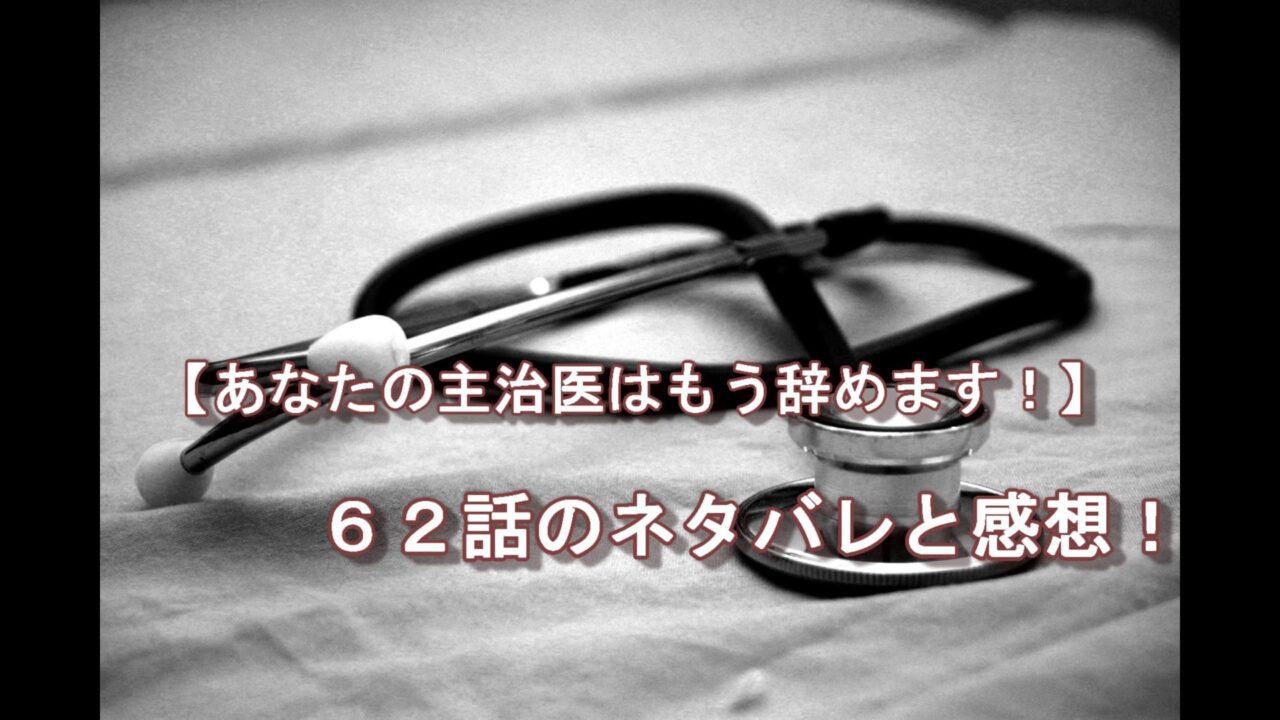こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
今回は62話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

62話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 狩り大会②
エルアンをはじめとする騎士やその他の貴族たちは狩りのために森の中へ旅立った。
私は他の貴族の令嬢のようにティータイムを持つ必要もないし、狩りに趣味もなかったので、当然兵舎に残ることに。
アーロンは薬草の手入れを口実に狭い小屋に閉じ込めて、ディエルは私と一緒に私の小屋を整えていた。
まだハエルドン皇子との神経戦を思い出すのか、彼の表情はあまり良くなかった。
「もちろん君が負けるとは思わないが・・・」
ディエルは私の顔色をうかがいながら口を開く。
「ハエルドン皇子様が皇室の医療研究室を負わせそうもないし」
いざ他人の前に出る人は私なのに、ディエルがさらにそわそわしていた。
「それに君の条件がフェレルマン子爵に謝ることなら尚更だ。一体どうしてそんな条件をつけたんだい?」
「言い間違えたことを訂正するだけよ」
当然、娘を探すのに気が気でなかったため、慎重な研究実績を出すことはできなかったが、フェレルマン子爵の医学実力は確実に認めるところだ。
陰で実力がなくて逃げたとか言われるような人ではない。
「私が悪口を言うのは大丈夫でも、他人が悪口を言うのは我慢できない。とにかく私の代父なんだから」
「でも・・・」
ディエルは荷造りをしているときに首をかしげながら言った。
「これは私も聞いたことだけど、ハエルドン皇子様とフェレルマン子爵様は医療研究室が共にする時から仲が良くなかったそうだ」
「なんで?」
「そうだな・・・フェレルマン子爵様はその時誰もが認める天オで、一本気な面があって人の言うことをよく間かなかったはず。いくら皇子様だと言っても、間違っていたら間違いだと堂々と言ったはずだよ」
「医学で間違っていることを間違っていると言うのは当たり前じゃないの?人の命がかかっているのに」
「それでも憎たらしく見えるからね。しかも結局、子爵様が全部当たったはずだから、もっとだ」
「それならもっとよかった」
私は腕を組んで瞬きをした。
「フェレルマン子爵がここに来るそうだから、正式に謝罪を受ける機会になるわ」
「フェレルマン子爵が来るの?北部にいらっしゃるじゃないか。お帰りになるにはまだまだ」
「私の身辺に異常があると急いで帰ってくると、フェレルマン子爵邸に手紙を送ってくださったそうだけど」
「君の身辺?何の異常?」
「さあ?」
「まさか、この前にあった実の親詐欺事件?」
私は物思いにふけってうなずく。
「たぶんそう・・・。手紙が届いた時間と、そこからすぐ出発するとかかる時間を計算すれば、それくらいになるような気もするし」
ディエルは複雑な表情をしていた。
どうやら、皇家と絡むのが怖いようだ。
自分一人で一生懸命頭を回転させているようだったが、結局はため息をついて呟く。
「まあ、セルイヤーズ公爵家が後ろにいるから、大したことはないね」
「そうなの?」
「先代のセルイヤーズ公爵が亡くなると、ほとんど姿をくらましたけど、それでも一番大きくて裕福な領地である上に、今公爵はあちこちで注目されていて・・・ちょっと待って、リチェ」
ディエルは再び私の荷物を整理する途中、瓶に入っている試薬を持ち上げて見せた。
「これ、あの時の・・・龍の爪が入った親子検査試薬じゃないの?」
「あ、うん。血液検査なんだけど、これを使うと魔力検査はしなくてもいいんだよ」
「そうすれば、時間がぐんと減るだろうね」
「もしお互いの血が同じ色で反応するなら、血縁関係の確率が70%以上だと見なければならないわ」
私は何気なく説明した。
「しかし、龍の爪が入って商用化するには収盆率が良くないの。フェレルマン商団で商品化するのは難しいでしょうね」
「じゃあ、なんでこれをここに持ってきたの?」
それはフェレルマン子爵に見せるために持ってきたものだ。
娘が金髪で緑眼ではないかもしれないという話を聞いた時、少しでも慰めになればと思って。
「子爵様に見せたら喜ばれるんじゃないかなと思って」
「そうなんだ」
ディエルは試薬を机の上に置き、軽くうなずいた。
そして、これまで何があったのかディエルに話そうとした瞬間。
急に兵舎の外から人の気配が聞こえた。
「どちら様ですか?入ってもいいですよ」
ひょっとしてセイリン卿が到着したかと思って明るく言ったが、兵舎に入ってきた人は私が初めて見る貴族の令嬢だった。
「リチェ・エステルの兵舎で合ってる?」
「はい」
私は整理していた本を置いて椅子を勧める。
「私がリチェ・エステルです」
彼女の目は荷物を整理している私とディエルを上下に見回した。
エルアンはどんな貴族のものよりも華やかで広い兵舎を用意してくれたが、荷物の整理をする下女は私が断った。
薬物と薬草が多く、自分でした方が気楽だったからだ。
特別な言葉がなくても、私の兵舎を訪ねてきたこの貴族の令嬢は「やはり平民など」という考えをしているのが目に見えた。
ナタリー・イルター・ルウェリッチと言って、伯爵家の娘であることを明らかにした彼女に、ディエルが慎重にお茶を差し出す。
私は一体どうして伯爵の令嬢が直接私の兵舎に来たのか分からない
「私は皇室医療研究室の所属で、先ほどハエルドン皇子様からお知らせを聞いたの」
綺麗に手入れされた赤い髪を耳の後ろに流し、ナタリーは優雅に話す。
「同じ年頃だと言って、あなたの相手に私を指名してくれたのに、あまりにも状況が馬鹿げているわ」
「何が馬鹿げているのですか?」
「皇子様が皇太子様の体面を生かしてくださるとして対決を提案されたなら、あなたが勝手に尻尾を巻くべきだった。そんなに気が利かないの?ああ、平民だから誰も教えてくれなかったのかしら?」
まるで蜂が刺すように鋭い口調だ。
「ええと・・・皇子様の提案を断るのも礼儀に反するようで、断る理由もありませんでした」
「じゃあ、私が礼儀を教えてあげる」
ナタリーはあごを上げて言った。
「今からでも諦めなさい」
「え?」
「申し訳ないと、生意気だと、実は公爵家の主治医の助手なんかに何が分かるというのか。平民のくせに身の程に合わない夢を持ってしまったと謝りなさい」
私は黙って静まり返っていた。
ナタリーのきちんと手入れされた爪とまっすぐな姿勢をしばらく見ていた私は静かに口を開く。
「私は今回のことで皇室医療研究室に入る考えは完全にやめました。ですから、私と一緒に勤務することになるのではないかと心配しなくても大丈夫です」
私の淡々とした言葉にナタリーは満足そうな表情でうなずいた。
「そうだね。限界を認めるのはいい態度よ」
彼女は首を整えた後、澄まして付け加える。
「あなたが噂のように、皇太子さまの側室になれるかどうかはまだ分からないことよ。まだ生意気に振舞ってはいけないわ」
「知っています。私がそんなはずありません。側室だなんて、そんな考えはありません」
宴会で初めてのダンスをした時、そのような噂が睡るだろうということは覚悟していた。
でも元々そういう複雑な席に行くつもりは少しもない。
ジェイド皇太子もあまりにも人が軽いので、そのような世紀の愛をしそうにはなかった。
私の返事に彼女はやや和らいだ口調で話す。
「それなら、私が公爵家の女主人になるかも知れないのに、敢えてあなたが私に逆らう必要はないじゃない?」
ルウェリッチ伯爵家なら、よく分からないが、とにかく大貴族の一人であることは明らかだ。
狩り大会に来る前に、イザベル夫人があちこちから無駄な縁談の手紙が入ってくるようだとため息をついた時に見た名前でもある。
「申し訳ありませんが、そういうふうに言うと、私がよく見えなければならない方がとても多くてですね。そんなことを言ったのは令嬢だけではなかったんですよ」
ベティアは、堂々と「美容試薬でも作り出せ」と堂々と要求までしたからだ。
私はナタリーが少し気分を害しているように見えるのを見て話を続けた。
「これくらいになると、令嬢の方々が私によく見えなければならないのではないかと思うほどです」
「え?」
「とにかく皇室の医療研究室に行かないということ以外はすべて嘘です」
平民が貴族に真実を話してはならないと帝国法は指定されていない。
「テーマも超えていないし、公爵家の主治医の助手でも私はいつも天オでした。それは身分とは関係ないことだと思います」
「この生意気なやつが!」
彼女が私の頬を叩くように手をさっと上げると、ディエルは震えながら急いで割り込んできた。
「お嬢様、リチェは公爵様が大切にする人材です。後患に耐えられますか?」
私は穏やかな顔で肩をすくめる。
「それはそうです。公爵があんなに元気になったのは私のおかげですから」
そして、たじろぐ彼女の手を見つめながら、素早く付け加えた。
「それに、私の父はフェレルマン子爵です」
ただの子爵家でも薬草流通としては最大のフェレルマン商団を率いる家柄だ。
医学と関係のある人なら地位を問わずドキッとするしかない言葉だった。
「また、私は大げさで我慢強い方なので、私がやられたことはあちこち早いです」
私の平然とした言葉に、彼女はどうしようもないかのようにゆっくりと手を下ろす。
それから歯を食いしばって、かみ砕いて吐き出すように言った。
「まあ、平民だから守る名誉がなくて恥をかいても構わないなら、あなたの思い通りにしなさい」
ナタリーは恐ろしい顔をして飛び起きる。
そうしても一つも怖くなかった。
エルアンやイザベル夫人が他の使用人たちに見せる表情に比べれば何でもなかった。
「あなたは負けるしかない。時が経ってから、あの時ナタリー・イルター・ルウェリッチが貴族らしい慈悲を施したものだと思い、涙が出るでしょうね」
彼女はまつげをぶるぶる震わせ、結局後ろを向いて挨拶もせずに出て行ってしまった。
突然の宣戦布告。
リチェと戦うナタリーの実力はどの程度なのでしょうか?