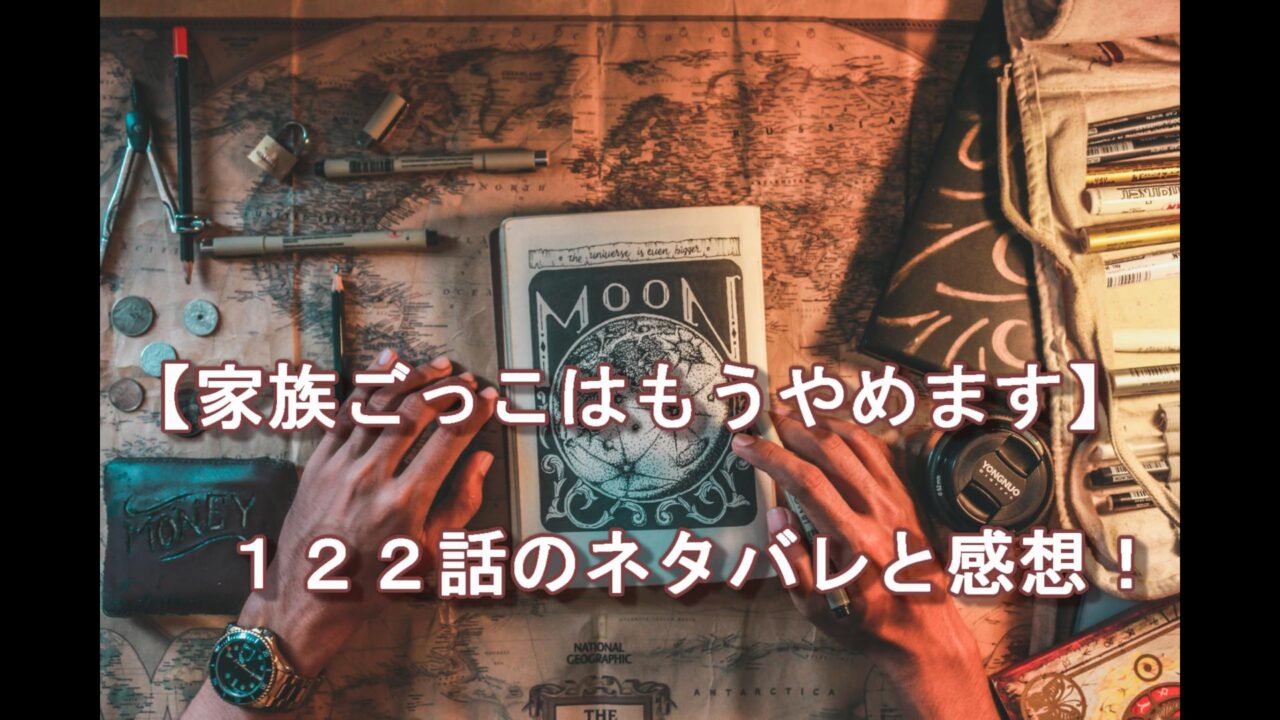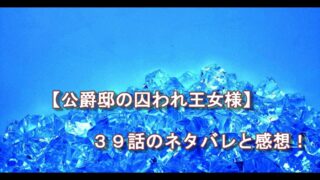こんにちは、ちゃむです。
「家族ごっこはもうやめます」を紹介させていただきます。
今回は122話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

122話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 勝利パーティー③
ナビアは人を通り越して、ついに皇帝の前に近づいた。
「偉大なる皇帝陛下にお目にかかります」
「これは久しぶりだね!ウラジーナ侯爵も、エセルレッド公女もこのように宴会に来てくれてありがたいね」
ユリッヒは余裕を持ってナビアとエルキンを歓迎する表情をしていたが、心の中はそれほど穏やかではない。
(エセルレッドの影響力があまりにも大きくなって、今は彼らに対する時、一国の王のように待遇しなければならない状況だね)
これは帝国に二つの太陽があるのと同じだ。
バキアと魔導連合国を打ち砕いて大陸の覇者になった自分が、エセルレッドの機嫌をうかがうのは話にならないことではないか?
(いったいエセルレッドは何がそんなに特別で、他人は一つ得ることも難しいものをすべて持つことができるのか!)
さらに、ファミリアデパートも「エセルレッド」の所有だという。
神様がいればこんなことはできないことだった。
(倒れていたエセルレッドがこんなにまぶしく登場するとは誰が知っていたのか・・・?)
ユリッヒはイライラしてナビアを見る。
人の心も知らずにあの子は容貌さえ神の恩寵でも受けたように美しかった。
(ラルク、あの人の外見からして神様のものだったから・・・)
ようやくユリッヒは傲慢でも、持つ力も全て神のようだった男、ラルクの姿が見えなくて
不思議に思う。
「ところで、公女はどうして侯爵と一緒に来たのかな?」
ナビアは待っていたかのように真剣な表情で話す。
「父は幼い頃から持っている持病があり、外出するのが難しいです。どうか不忠をお許しください、陛下」
それは納得しがたいが、説得力のあるのことだ。
10年前、ちょっとだけ姿を現したラルクは全然辛そうには見えなかった。
しかし、彼が30歳を過ぎても外部に姿を現さなかったのも事実。
(どこまでが真実なのか?何を企んでいるんだろう?)
ユリッヒは突然にっこり笑う。
エセルレッドが特別なだけに、自分にも特別な子供がいた。
ユリッヒは誇らしげな表情で言った。
「そういえば、公女もうちのクリード皇子と久しぶりに会うのだろうね?」
それは皇室とエセルレッドの間に特別な縁があるという事実を想起させるための発言。
エセルレッドを友好勢力に引き入れるには、子供同士の結婚同盟ほど確実なものはない。
(まだエセルレッド公女にパートナーがいないから)
アレスの側室に入れたり、クリードと結婚させたりすれば、ちょうどよさそうだった。
どうせならクリードと縁があるから、そっちの方が攻略しやすいんじゃないかな?
「クリード」
皇帝はナビアが何か答える前にクリードを呼んで近くに呼ぶ。
クリードはすぐにナビアに近づいた。
ただ距離が近づいただけなのに、2人の間にお互いだけが感じられる微妙な緊張感が流れる。
ナビアは何でもないようにうまく表情を隠していたが、昨日のことを思い出し、喉が渇いているようだった。
「・・・そうです。幼いころに束の間お会いしたことを除けば顔を見たことがないですが」
ナビアは、クリードがあまりにも昔の縁なので、特に親しくはないと線を引く。
しかし、ユリッヒは執拗だった。
「ははは!ままごとをしていた時の縁というのは、振り返ってみると本当に大切なものだ」
ここでさらに線を引くのも、全く自然なことではない。
いずれにせよ、ナビアとクリードは幼い頃の思い出を共有する仲であり、二人とも一流のすべての血統であれ、非常に優れていた。
互いに一目惚れするのも無理のない状況だ。
クリードはナビアに近づき、手の甲にキスをする。
唇が触れたところが火に焼けたように熱かった。
「エセルレッド公女、私と踊っていただけますか?」
紳士なら当然踊る相手がいない淑女に、特にそれが社交界にデビューする日ならさらに踊ることを申し込むのが慣例だ。
ただ、これが慣例のように感じられないのが問題だった。
ナビアは頬が薄いバラ色に染まっているという事実も感じずにうなずく。
「いいですよ」
彼女の許可が下りると、クリードはここに来て以来初めて微笑んだ。
彼の笑顔に人々がざわめくほとだ。
クリードはエルキンに軽く目礼した後、ナビアを連れて宴会場の中央に出る。
その間にクリードは低い声でつぶやいた。
「ふむ・・・今は私の匂いがしない」
ビクッ!
ナビアは鋭い目をしてクリードをそっと睨みつける。
「もし誰かが聞いたら誤解するような言葉はやめてください、殿下」
「何の誤解?」
「だから、う一ん、私の臭いとか、そんな発言はちょっと・・・」
クリードは首をかしげた。
「それは変なことですか、お嬢さん?」
「・・・」
突然、ナビアは一人で淫らな考えで言葉を曲解した人になった。
呆れた気持ちで唇をぎゅっと閉じる。
ここでもっと話してからは自分だけがおかしくなるという賢明な判断から始まった行動だった。
ナビアはため息をつきたい気持ちを抑えながら、視線を正面に固定しようとする。
頬が冷める暇がなかった。
クリードは彼女をちらりと見下ろして、かすかな笑みを浮かべながら自分もそれに従って正面を見る。
その笑顔があまりにも甘く、クリードを見守っていた人たちが胸をぎゅっとつかんで弱音を流す。
間もなく二人はダンスフロアに立った。
アレスとヴィヴィアンが立ったところから少し離れた場所だ。
楽団が演奏する準備を終えた。
ナビアは自分に対する執拗な視線に思わず首をかしげ、アレスを発見する。
アレスはナビアをじっと見つめながら、周りから少しずつ変に思われるほどだった。
ナビアは彼にかすかな微笑みさえ見せなかった。
奇異で歪んだ欲望に応えてくれる考えなど少しもない。
その時、黒い手袋をはめた大きな手がナビアの頬を優しくかすめる。
ナビアはびっくりして覗線をそらした。
二人の視線が近い距離でぶつかり合う。
このままクリードが頭を軽く下げれば、すぐに湿った息が入り混じって、ねっとりとした接触が続くような距離。
(一体私がとうしてこんな考えをするの・・・)
ナビアは少し泣きたくなった。
自分がこんなに淫らな考えができる人だという事実を初めて知ったからだ。
クリードを相手にしてはならない悪い想像をしたという罪悪感を感じた時だった。
「頬にまつげがある」
優しい笑顔とささやくような低い声に、ナビアはぎこちなくうなずいた。
「馬車から降りる前に姿を点検した時は大丈夫だったけど」
ナビアは自分の頬を掃こうとしたが、そのままクリードの手に引かれて彼の腰を握らなければならなかった。
「もう大丈夫」
ナビアの目が疑いで細くなった時、ダンスが始まる。
クリードは幼い頃、シャンデリアの代わりに日差しが入ってくる窓際でお互いに手を取り合って踊った時を思い出し、小さく笑った。
「私たちが一緒に踊るのも久しぶりですね」
十歳にもならない少女と少年が見せびらかすように着飾って互いに礼を尽くす。
ぺこりと挨拶の後、姿勢を整えると、彼らを眺めながら嬉しそうに笑っているマーガレットとシュレーマンが、オルゴールのぜんまいを巻いてくれた。
一筋のオルゴールの音に合わせて踊るワルツ、そばをぐるぐる回るチェサレ、おやつを持ってきて一緒に彼らの踊りを見物するシャーロット、噂を聞いてやってきたミネルバ。
むっつりした表情で現れたラルク。
ナビアも同じ時代を思い出し、笑みを浮かべる。
幸せだった子供の頃を思い出すと、なんだか心がくすぐったい。
一番幸せだった瞬間を共有する仲というのは、こんなにも切ないものなんだ。
「今の演奏も素敵ですが、オルゴールに合わせたダンスも良かったです」
ナビアの言葉にクリードは目を輝かせる。
「それでは今日、オルゴールに合わせて踊ってみましょうか?」
アレスの側室になんて話を聞いたらクリードが国を滅ぼしてしまうのでは?
ナビアがクリードを意識している様子が明らかですね。