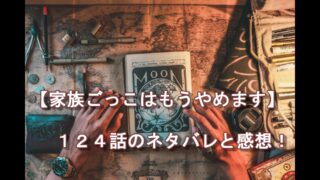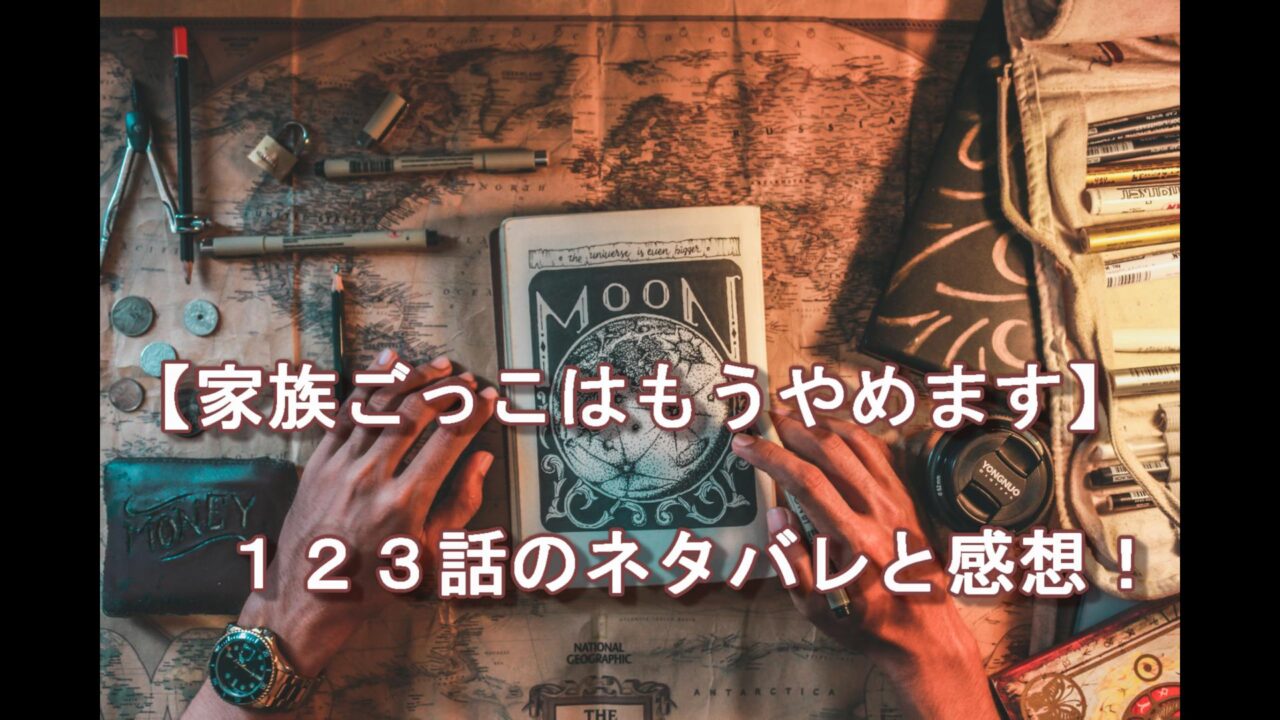こんにちは、ちゃむです。
「家族ごっこはもうやめます」を紹介させていただきます。
今回は123話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

123話 ネタバレ
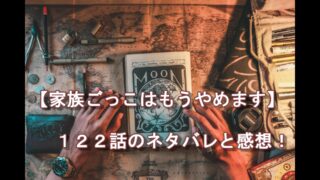
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 休憩室での再会
その瞬間、すぐに答えが出なかった。
ナビアは小さな声で、唇を少しもぐもぐさせながら言った。
「・・・公的な場でのそんなお話はお控えください」
誰かが彼らの唇の形で会話を類推することもありうるので、気をつけた方が良い。
それで踊るために人々と距離がかなり離れているにもかかわらず、きちんとお互いに敬語を使っているところだった。
「小言屋」
クリードがからかうと、ナビアは眉間にしわを寄せながら睨みつける。
「だから好きです」
正確にはナビアが何をしても良かった。
ナビアは完全に言葉を失う。
あんなに幸せそうに笑っていいと言っていたのに、他に言うことがあるはずがなかった。
体の奥が引き締まる思いだった。
そのためか、少し息が苦しくなる。
曲が終わると、ナビアはエスコートされてダンスフロアを後にした。
クリードは召使いを呼んでコップを選び、それからナビアに差し出す。
「あ、ありがとうございます・・・」
そうでなくても喉が渇いた。
ダンスを一生懸命踊っていたからではない。
ナビアは今日の宴会に出席することに抵抗があった。
これまで顔を合わせる必要がなかった嫌な人間たちにたくさん会わなければならないから当然のことだ。
しかし、今そういうのは気にならないくらい他のところに気を取られていた。
これが幸いなのか、新しい不幸なのか分からなかったが。
その時、クリードが尋ねる。
「休憩室で少し休みますか?」
ナビアは危うくコップを落とすところだった。
「え、え?」
(今こいつが何を言っているんだ!?)
休憩室に行って休もうというのは、他人の視線が届かない場所で関係を持とうという社交界の隠語。
クリードは、ナビアが過敏に反応すると、また不思議そうに首をかしげた。
「不便な靴を履いて踊っていて足が痛いみたいなので」
「・・・」
(知らずに言ったんだね)
確かに、クリードがそんなはずがない。
ナビアは熱い顔に手をこすりつけながらうなずいた。
「うん、そうしましょう」
ナビアは休憩室に行って瞑想する必要性を感じた。
しきりに淫蕩な考えが浮かんできて気が狂いそうなのだ。
「エルキンおじさん、いや侯爵には私が申し上げます」
クリードは幼い頃、ナビアを一緒に呼んで、口癖になったおじさんの声を素早く訂正した。
彼はナビアを最高の休憩室に案内した後、隠密に魔力をかけて出ていく。
万が一のことを防止するためだった。
ナビアは一人で休憩室に残ると、熱い頬を冷やすためにバルコニーに出る。
気分があまりにも熱くなり、冷たい空気に心と体を冷やしたかった。
いつの間にか夕焼けになっていた。
黄金色の地平線から始まり、きれいなピンク色で空が蚕食されていく。
こんなに綺麗なピンク色の空が珍しいのに、今日に限ってどうして夕日もこんなに美しいのか。
ナビアの気分はさらにそわそわした。
「・・・下級?」
その時、痺れるように熱くなった気分を崩す声が横から聞こえてきた。
「下級じゃないか」
その言葉を使う人は一人しかいない。
ナビアは冷ややかな表情で首をかしげた。
すぐ隣の部屋とナビアが使用している部屋のバルコニーは、わずか一歩余りの距離を置いて並んでいる水準だった。
そのすぐ隣のバルコニーにウッドがいた。
彼は短く切った赤い髪と、その間に大きく伸びて硬くなった体つきで、滑らかな外見を誇っていた。
まあ、そもそもアグニスの人たちが外見だけはしっかりしていたから。
ウッドは今日の宴会に満足していなかった。
アカデミーでクリードと仲が良くもなく、サラともぎこちなかった。
サラがウッドに関心を示さないこともあったが、ウッドもやはり恋慕する心が薄れていたためだ。
ヴィヴィアンとの仲は幼い時すでにこじれていて、同じ席にいるのもイライラする。
それで、アグニスに割り当てられた休憩室にずっと閉じこもって酒を飲んでいた。
そうするうちに突然隣のバルコニーにナビアが現れたのだ。
「君がなぜここを・・・?」
ウッドはそうつぶやいて口をつぐんだ。
エセルレッドなら皇室の貴賓だけが使える休憩室を割り当てられるのに十分だったからだ。
「ここで見ることになるとは思わなかった。久しぶりだね?」
「・・・」
ナビアは子供の頃と同じように彼に話しかけなかった。
ウッドは眉間にしわを寄せる。
敢えて下級なんかが、という言葉が口に出なかった。
ナビアは誰よりも大貴族のように見えた。
美しい外見、繊細な形のドレス、由緒ある宝石セットなどが問題ではなかった。
ナビアは特別な雰囲気を持っていた。
自分を見る目つきやあざ笑うように流した口角でさえ優雅なほどだ。
ウッドは奇妙な気分に襲われる。
アグニスにいる時はいつもレベルの低い身なりでいたのが脳裏に鮮明だった。
今のナビアは生まれながらにして高貴な者特有の雰囲気を漂わせていた。
しかし、それがどうしたって?
ウッドはワインの瓶を持ってナビアに近づく。
「大貴族になって生きてみてどう?エセルレッドがこんなにも大きくなるとは誰も思わなかったよ」
「・・・」
ナビアはあえて答えなかった。
ウッドはニヤリと笑いながらワインをーロ飲んだ。
「ところでそんな事実が何が重要なの?私はお前どんな女なのか知ってるけど」
ウッドはバルコニーを飛び越え、ナビアの目の前に立る。
ナビアは後ろに下がる代わりに、頭を上げてウッドを見た。
ピンク色に染まった空の光が、ナビアの流麗な目鼻立ちに舞い落ちる光景は、まるで夢のようにうっとりしていた。
「きっとそのおかしな能力で得た地位だろう。そうじゃない?」
綺麗な顔が恐怖に染まるのが見たかった。
ナビアは息がつくように近い距離で、自分を皮肉るウッドに向かって手を伸ばし、彼のあごをぐっと引っ張ってきた。
「何だよ・・・!」
「それを知っているのに、私の近くに来たの?」
ウッドは唇を固く閉じる。
全身を襲う緊張感に瞳が細かく震え、ナビアの赤い瞳を限りなく眺めるようになった。
「そう、その赤い瞳」
青いところか、真っ白に飛び上がるスパークに包まれていた赤い目の正体が、今では分かった。
ごくり。
自然と乾いた唾が喉に入る。
ナビアは彼を叱るようにあるいは言い聞かせるように静かにささやいた。
「あなたは知っているだろう、ウッド」
ナビアの反対側の手がウッドの頬を滑らかに握った。
その誘惑的な手振りは、実はソフトな脅迫だった。
「私と接触すると、どんなことが起きるのか」
ウッドはナビアの手を離し、一歩後退する。
妙に心臓がドキドキし、体が熱く燃え上がる気持ちを否定しようとするかのように、彼が激しく怒嗚りつけた。
「私があなたの能力を告発しないと思う?」
「告発しなさい。私には関係ない。でも、とりあえず気をつけた方がいいんじゃない、お兄さん?私が間違ってでも貴重な体に傷をつけたらどうする?」
ウッドは唇をかんだ。
とにかくあの女はとても言葉では勝てなかった。
それが悔しかった。
腹が立った。
そのため、心臓がこんなにもドンドンと音を立てて走っているのだろう。
ウッドは自分の気持ちを正当化するために何か言いたかった。
「エセルレッドがすごいことになったのは認める。でも貴族社会は癒着が重要だよね。エセルレッドがどんなに飛んで這っても協力する家門がなければ結局孤立するということを知らないの?」
他の人たちが決心してエセルレッドを孤立させ圧迫すれば、少なからぬ被害が生じるだろう。
ナビアは笑い出した。
ウッドは鋭い雰囲気にふさわしくない印象を受け、当惑する。
(これはどういう狂った考えなの?)
あのおぞましい女の人が笑うのがいいって?
そんなはずがない!
ナビアは笑顔でウッドを見た。
そういうのが変に・・・綺麗に見えた。
ナビアが綺麗に見えた。
あのナビアが・・・。
久しぶりにウッドと再会。
すっかり堕落したウッドですが、ナビアに対しての何か仕掛けてこないか心配です。