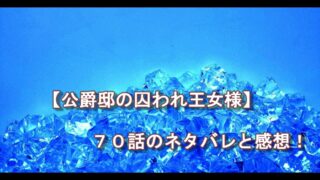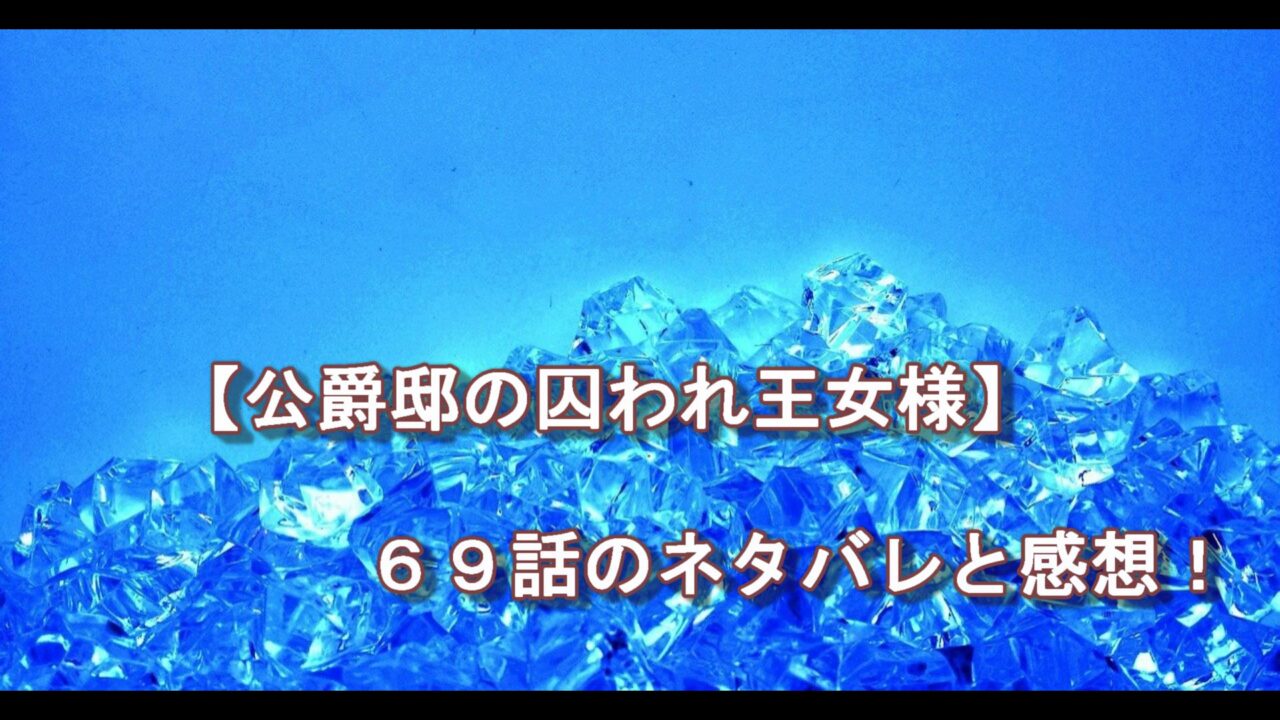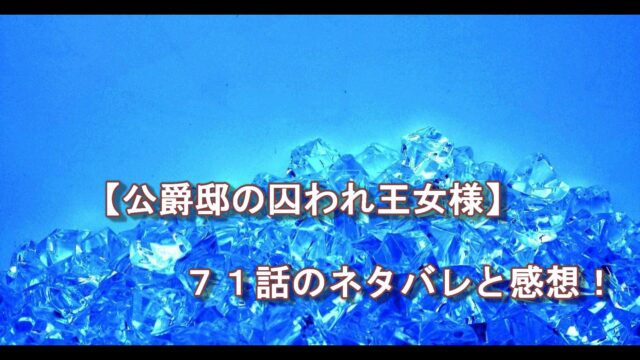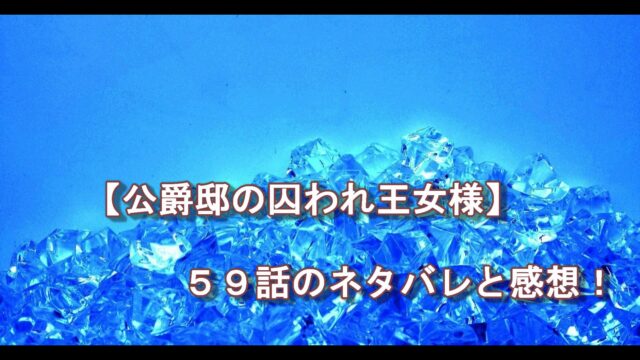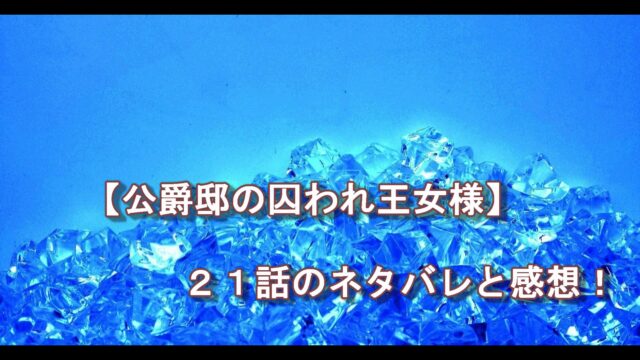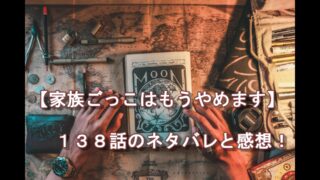こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
今回は69話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

69話 ネタバレ
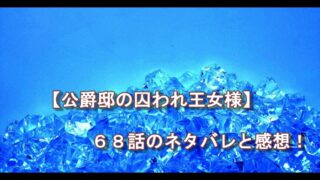
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 特別な日③
「今日はクラリスが一人で木の上に登った記念日ですよ。」
「・・・え?」
「ですから、祝福を受けるにはとても良い日だということです!」
「でも、公爵夫人、これは祝福を受けるほどのことではありませんよ。」
「どうしてですか?その場に立っているだけでも本当に一生懸命でしたよ。」
彼女は木のすぐ前に歩み寄り、クラリスの顔の高さまで手を伸ばして再び話した。
「おめでとうございます、クラリス!」
「それは・・・木登りのことですよね?」
再度確認するように尋ねた彼女の質問に、公爵夫人は笑みを浮かべながら肯定する。
「もちろんです。」
「ありがとうございます。正直に言うと・・・嬉しかったです。」
「それでは、降りてきてくれますか?」
ブリエルが再び両腕を高く上げてクラリスを助けようと尋ね、クラリスは枝を握りしめる。
「でも、私、すごく重いですよ。」
「それはいいことですね。」
ブリエルが再び腕を差し伸べたため、クラリスは慎重に膝を折り、彼女の腕と肩を頼りにするようにしながらゆっくりと地面へ降りた。
「怖くなかったですか?」
ブリエルは地面に降りたクラリスを念入りに観察し、怪我をしていないか確認する。
「はい!とても楽しかったです!」
「楽しめたならよかった、本当に良くできましたね。」
クラリスは彼女の頭をそっと撫でてくれる手の感触が好きだ。
そして、温かく見つめてくれる視線も。
両手をもじもじと動かしながら、この心地よさを感じていたクラリスは、ある疑問が浮かんだ。
「夫人はどうしてこんなにも・・・優しいんですか?」
「当然そうするものですよ、大人ですから。」
「それでも・・・。」
クラリスは「そうでない人もたくさんいるのに」と言いかけて口を閉じた。
夫人の言葉を否定したくない気持ちからだ。
「本当は私も知っています。そうでない大人がいることを。」
ブリエルはクラリスの心をすぐに察して和らげようとした。
一方の手でそっと彼女の手を握りながら、こう言った。
「私も昔は伯爵夫妻にたくさん世話になりました。」
「夫人もとても大変だったでしょう。」
「全然そんなことはありません。なぜなら・・・」
彼女の目にはすぐに懐かしさが込み上げてきた。
「私にはとても優しい母がいたのです。」
「今も病院にいらっしゃる方ですよね?」
「はい、そうです。その方は私を愛してくださったのです。血のつながりはないのに。だから私も幼い頃はクラリスのような疑問を抱いたことがあります。」
「本当ですか?」
「はい、私は母に迷惑をかけているとずっと思っていました。でも母は・・・」
ブリエルは一瞬言葉を止める。
クラリスは彼女が何か特別な言葉を思い出して慎重に口にするまで、嬉しそうに待った。
「それは当然のことだとおっしゃいました。」
「・・・」
「ある日突然、目の前に現れた女の子を愛さないわけがない、と。きっと・・・それは運命だったのでしょうね。」
「運命・・・ですか?」
それはまるで本から出てきそうな言葉。
現実ではなかなかお目にかかれない幻想的な話のように感じた。
「はい、ちょっと難しいでしょう?私も幼い頃はその意味が分かりませんでした。全く知らない女の子がちょっと可愛らしく思えてきて、愛するようになるなんて。不思議ですよね。でも、そうなるとやっぱり・・・嬉しくて、不思議ですよね。」
「はい、少し・・・そうですね。」
「そうでしょう?」
彼女は肩をすくめながら、クラリスの手を前に持ち上げ、慎重に振った。
「ところで、最近の話なんですけれど。」
そしてブリエルは、微笑みを交えた穏やかな声で話を続ける。
「母の言葉に少しずつ勇気づけられるようになったんです。」
クラリスは驚いた目でブリエルを見上げた。
「その方は本当に・・・何の理由もなく私を愛してくださったんです。」
「・・・」
「それは何かしらの見返りが必要な感情でもなく、何かを求めるわけでもなく、自分を犠牲にすることさえ考えないような、純粋な愛情だったんです、クラリス。」
「・・・奥様。」
「ただ、ある日突然目の前に現れた女の子が、とても愛おしかっただけのことです。母は本当にそうおっしゃいました。それで全てが終わったんだと思います。」
「・・・」
「丁寧にしてくれてありがとう、クラリス。」
クラリスは言葉にならない気持ちを口の形だけで伝え、彼女をしっかりと抱きしめる。
同時に、しっかり握ったブリエルの手を離したくなくて、彼女を掴む手に少し力を込めた。
木を握って擦れたことで少し汚れてしまった手も、ブリエルはクラリスの手をしっかりと握り続けてくれた。
クラリスはなぜか、とても大きな誕生日プレゼントをもらったような気分になった。
その正体が何なのかはっきりとは分からないけれど。
ブリエルはクラリスの部屋の前まで一緒に来てくれた。
「ロザリーにお風呂の準備を頼んでおきますね。少し休んでください。今日は本当に・・・」
話を止めたブリエルは周囲を見回す。
ベンス卿がこちらを見守っていることを察したのか、そっと声を落とした。
「おめでとうございます。」
クラリスは驚いて短い言葉を返した。
「木登りを祝ってくださるんですか?」
「もちろんです。」
彼らは秘密の合言葉を交わす子どもたちのように微笑み、くすくすと笑った。
「最後まで諦めずに木に登り続ける姿、とても素敵でした。立派な成果を収めましたね。おめでとうございます、クラリス。」
まるで誕生日を祝われているような気分だ。
クラリスは心の中で『これは木登りの話なんだから。』と自分に言い聞かせ、落ち着こうとした。
「祝っていただいて、本当に嬉しいです。」
胸の奥で喜びを噛み締めつつ、彼女がそう返事をしたとき、クラリスのすぐ後ろで扉が開いた。
「・・・!」
驚いて振り返ると、まさに慌てふためいた様子のマクシミリアンがクラリスの部屋から出てきた。
彼は困惑した目でクラリスとブリエルを交互に見ながら、どうやら二人の会話を聞いていたらしい。
(どうしよう? 公爵様が誕生日を祝う話と勘違いされているに違いない!)
クラリスの顔は青ざめた。
「こ、公爵様。」
震える声を聞いたマクシミリアン数歩後ろに下がる。
彼は子どもを怖がらせるつもりはなかったため、できるだけ平静を装おうとしたが・・・。
視線がクラリスと交わった瞬間、彼女が震えているのを見て、その努力は無駄に終わったようだ。
「聞いた。」
「ご、誤解です・・・!」
「木に登ったって?」
「はい?」
クラリスは、思いもよらなかった話を聞いたかのような表情を浮かべる。
マクシミリアンは、目を細めつつも警戒するように質問を投げかけた。
「少し前に庭師が話してくれたんだけど、違ったのか?」
少女は大きな青い瞳をぎこちなく転がしながら、ゆっくりとうなずいた。
「あ・・・そうです!そうなんですけど・・・。」
「・・・うん。」
マクシミリアンは何か言いたそうだったが、それ以上話すのをやめた。
どうやら彼の登場によって、クラリスの気分が少し台無しになったようだ。
(まあ、誕生日に自分を見て喜ぶことなんてないだろうけど。)
パーティを禁止したのはもちろん、数年後には彼自身の手でクラリスの首を斬る予定であったからだ。
今日はこんな日に相手をするのが一番気まずい相手だ。
彼はそっと身体を引いて、自分の執務室に戻ろうとした。
たとえクラリスが彼に話しかけようとしたとしても、その動きは少し早まっていただけだった。
「その・・・私に何かおっしゃることがありましたか?」
「初めて木に登ったという話を聞いただけだ。」
「・・・それでわざわざ来てくださったのですか?」
マクシミリアンは当然のように顎を引いた。
実は今朝まで彼は、木登りに成功した子供を祝うべきという事実を知らなかった。
それを教えてくれたのは、彼の賢明な夫人であるブリエルだ。
『公爵様、私が育った村では、木登りに初めて成功した子供を無条件で祝福するものなんです。』
彼は王子として、セイファース王国の各地域に多様な風習が存在するという事実を常に尊重していた。
彼女が語る風習を聞いたことはなかったが、特に奇妙だとは思わなかった。
彼自身も幼少期に木登りに夢中になった経験があり、その成功時に感じた非常な達成感は忘れたことがなかった。
弟ライサンダーに木登りを教えたのもマクシミリアンだ。
とはいえ、彼が木から落ちて怪我をしたために木登りは成功しなかったが、その後、護衛のアメルダに大目玉をくらったのもまた事実。
いずれにせよ当時のマクシミリアンも、もしライサンダーが成功していれば「おめでとう」と言っただろうし、ブリエルが教えてくれた風習にも何となく納得できた。
ただ、一つだけ気になるのは・・・今日がクラリスの誕生日だったらということだ。
子どもは一度も自分の誕生日を明かしたことはなかったが、公爵夫妻はグレゼカイアから連れて来た際の出生記録でその日を知っていた。
それゆえ、公爵は今日くらいはクラリスが木登りに成功しないことを望むという複雑な気持ちを抱いていた。
他の誰でもないマクシミリアンが子どもに「おめでとう」と言葉をかけるのは、少々異様に見えたからだ・・・。
もし怪我をしないかと心配でもあった。
「うん・・・そうだな。」
彼は曖昧に答えながら少し間を置き、一歩横に身を引いた。
「そろそろ休むといい。」
子どもをいつまでも褒め称えているわけにもいかない。
マクシミリアンはブリエルにも軽く頭を下げると、早々にその場を後にした。
彼が去った後、クラリスは少し開いた扉の前で静かに立ち尽くしていた。
部屋のドアの隙間に何かが置いてあるのを見つける。
それはケーキだった。
真っ白な生クリームとイチゴが山のように飾られており、本当に愛らしい姿をしていた。
「まあ、公爵様がこれを渡しにいらしたようですね。」
「私に・・・ですか?」
「ええ、もちろん。」
信じられない気持ちで大きく目を見開いてしばらく動けなかったが、クラリスは慌てて体をひるがえして廊下に飛び出した。
幸運にも、マクシミリアンはまだ執務室に戻っていなかった。
クラリスは慌てて足音を立てながらその後を追いかける。
屋敷ではいつでも礼儀を守らなければならないことを、この瞬間ほど強く意識したことはなかった。
後ろから聞こえる足音に気づいたのか、マクシミリアンは振り返った。
「公爵様!」
「・・・クラリス。」
「あ、えっと・・・あの、廊下を走ってしまって申し訳ありません。でも、どうしてもお話したくて・・・。」
クラリスは荒い息を整えながら冷静になろうとし、両手を胸の鼓動を押さえるように軽く握りしめた。
こんな日にお祝いのケーキをもらうなんて初めてのことだった。それが誕生日ケーキではないにしても。
「えっと、初めてです。あんなに大きなケーキをいただくのは…・・・。」
「感謝するなら料理人に言いなさい。彼が少し気を遣って作っただけだ。君が病気だった日に砂糖を用意できなかったのを気にしていたようだ。」
「それでも・・・私は公爵様にもお礼を言いたいんです。あれは私を祝ってくれるケーキ・・・。」
クラリスは、彼が不快に思わないように、慎重に表情を変えずに話した。
「つまり、私が木登りに成功した記念のケーキなんですね?!」
誕生日ケーキだと誤解しないことで、公爵の気持ちも幾分軽くなるはずだ。
いや・・・もしかしたら、公爵はクラリスの誕生日を意識していなかったのかもしれない。
ただ単に、完成したケーキを渡したかっただけかもしれない。