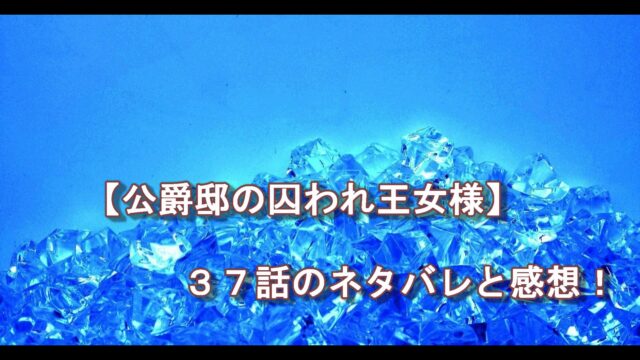こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

126話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 犯罪の可能性
ノアを……殺そうとした?
そんな魔法使いがいたって?
「どういうこと?」
クラリスがもう一度問い返したが、今度は答えが返ってこなかった。
焦る気持ちのまま、彼女はノアの顔へと身を乗り出した。
しかしノアは、彼女との間に手を差し入れて制し、静かに言った。
「少女よ、これ以上答えがないのなら、ここでやめておいた方がいい。」
「でも、聞かなければならない答えがあるの。」
「……それは?」
「それ、は・・・」
クラリスは彼の顔から、そっと両手を離した。
「ローブが……誰かを……ノアを」
「殺したい、ってこと?」
最後まで言い切る前に、彼は当然のように言葉を継いだ。
「……どうしてわかったの?」
彼はとぼけた様子で、かすかに微笑む。
「僕が死ねば、誰かが白いローブを手に入れられる。だったら、殺したくならないわけがないだろ?」
「……なるほどね」
「ローブの色は、努力だけで決まるものじゃない。むしろ、生まれ持った才能に大きく左右されるんだ。特に白に近づけば近づくほど――」
つまり、ある一定の段階を越えて、さらに上へ行くには、強者が死ぬしかない。
そんな意味合いだった。
「殺意と向き合うことは、私にとってとても慣れたことです。」
「……それは、ひどいわ。」
クラリスは、ぞっとするような出来事をまるで何でもないことのように語る彼の様子に、理由もなく胸が締めつけられ、不安を覚えた。
「ノアを魔法使いの城へ送るの、嫌なんでしょう?」
「少女は、私をあまりにもか弱く見ている。」
「でも。」
「私は、私を殺そうとする者たちより弱かったことなど一度もない。生まれたときから、ずっとそうだ。」
彼は持ち上げた手の上に、赤い光の塊を生み出した。
長く伸びた光は、彼の指の間をすり抜けていく。
「私を殺せる人間は、この世界にただ一人しかいない。そう確信している。」
「それって……誰なの?」
クラリスが尋ねると、彼は答える代わりに、その赤い魔法をクラリスの手の上へ移した。
まるで生きているかのように、彼女の指の間を――影下の魔法は、わずかに熱を帯びていた。
クラリスはようやく、これが決して優しい類の魔法ではないのかもしれない、と察する。
「いや、僕が実演してみせただけさ」
そう言うとノアは、再び光を掴み取り、握り潰すようにして霧散させた。
「いずれにせよ、ドルが話していたことは、あまり気にしなくていい。表情を見る限り、もう手遅れみたいだけどね」
『僕がノアのことを気にせずにいられるわけないだろ。好きなんだから』
「……その言葉、ドルにも言ってあげなさい」
「ん?」
「ううん、何でもない」
クラリスは再び、椅子の上にぽすりと腰を落とした。
「それより、灰色のローブの魔法使いについては、何も分からないままなの?」
「うん。今のところ、手がかりはなさそうだ」
「やっぱり、私が魔法使いの城へ行くしかないわね……あ。」
クラリスは、何かに思い当たったように拳で自分の手のひらを軽く打った。
「ノア!」
彼は再び、つばの広い仮面に手をやり、少し触れてから顔を上げて答えた。
「な、何でしょう?」
「もしかして……あの灰色の魔法使いの城と名前、知ってる?」
「……当然、知っていますが。」
名前を尋ねるクラリスの胸の内までは読み取れず、ノアは静かにうなずくだけだった。
「これは、今日中に片づけていただけると助かります。」
ライサンダーは、会議室の大きな机越しに、母であるアメルダが差し出した薄い書類を受け取った。
「それはそれとして……我が息子の顔色が、あまりにも優れないように見えるのですが。少々心配ですわね」
彼女はテーブルを回り込み、ライサンダーの隣に腰を下ろした。
「何か厄介なことでもあったのですか?」
濃い茶色の瞳をした彼は、静かにライサンダーを見つめ返した。
それは、彼女の中にすでに“欲しい答え”があることを示してもいた。
「……兄上が」
そう口にしながらも、こうした話題を好まないと思いつつ、ライサンダーは本能的に、彼女の望む答えを差し出してしまう。
たとえ王となり、どれほど年を重ねようとも、ライサンダーはアメルダに逆らうことができなかった。
「お出かけになられたのです」
「あら……それはさぞ、ご苦労なさったでしょうね。で、今回は何を要求されたの?本当にもう、奥様を人質に取って、この機会に我が息子をいたぶろうと企んでいるのではなくて?」
「……違います。罪人の赦免を願われただけで……」
「罪人の赦免ですか?」
アメルダが興味を示すように問いかけると、ライサンダーは一瞬、言葉に詰まった。
ほかのことならともかく、クラリスに関する自分の考えや計画だけは、母に知られたくなかった。
「ええ。ですが、断りました。」
彼はできるだけそっけなく答えた。
幸い、アメルダはそれ以上追及してこなかった。
「立派ですね。本当に正義感のある判断だと思います。今になって考えてみると、公爵が策略を巡らせて、私たちのかわいいデビナをそそのかし、あんなことをさせたのではないか、という気もしてきます。幼い頃から女性をたらし込む才がありましたから。王室の弱みでも掴みたかったのかもしれませんね。」
「兄上は決して、そんな……!」
そう言って否定しようとしたライサンダーの手首を、アメルダは静かに押さえた。
その瞬間、彼の首筋にまで鳥肌が立ち、幻聴が耳に流れ込んできた。
泣きながら、何かを訴える叫びだった。
おそらく――幼い頃のライサンダーの記憶だろう。
『あ、あの……母上の手が……痛いです。お願いですから……叩かないでください。ね? 僕が悪いんです。ぼ、僕が……ダメだったんです……』
震えながらそう訴えるライサンダーは、実に出来の悪い息子だった。
だが、彼がどれほど愚かな過ちを犯そうとも、母は決して鞭を取らなかった。
愚かな息子を“人”に育て上げるために、彼女は何度も手を振り上げ、そのたびに掌は痛々しいほど赤く腫れ上がった。
『誰であっても、あなたの代わりにこの痛みを引き受けることはできません。いいですか、ライサンダー。これは、私があなたを愛している証でもあるのです』
ライサンダーは、自分を唯一愛してくれる存在の手を、いつも無残にしてしまう自分自身が、どうしようもなく嫌だった。
「……いずれにせよ、息子よ。公爵夫人の件を理由に、求められることをすべて叶えてやるわけにはいかない――そのことは、理解していますね?」
「ええ。」
彼が求めた内容は、次のとおりだった。
・事件を調査する権限。
・ハイデンに出入りしたすべての聖職者の出入記録を閲覧する権限。
・デビナおよび魔部、ならびに怪人たちに対する処罰権。
・デビナに関する宮廷記録の閲覧権。
「デビナについては、婚姻が無効となった時点で、彼女に関する記録もすでに焼却されてしまい、公爵にお渡しできるものは何もなくなってしまいました。もう少し早くご要望いただいていれば、そうはならなかったでしょうけれど。」
しかし、アメルダがデビナの記録を消したのは、事件が起きてから一日も経たないうち。
たとえライサンダーであっても、その点を口に出すことはできなかった。
「それに、魔部や怪人たちは獄中で自殺してしまいましたから、処罰権も行使できなくなりました。亡くなった者を生き返らせて、公爵に差し出すことなどできませんでしょう?」
彼女は本心から残念がっているかのように、静かに言葉を続けた。
「城壁の出入りに関する記録――それくらいなら、お見せすることはできますが……比較対象がなければ、どれほどの意味があるかは疑問ですね」
アメルダは、少し前にライサンダーへ差し出していた書類へと、ちらりと視線を落とした。
「……まあ。それでもよろしいのでしたら、どうぞ。お好きなだけご覧なさい」
ライサンダーはようやく、彼女が最初に渡してきた書類に目を通した。
各城壁へ送られた、協力要請の公文書。
城壁を越えた者、あるいは城外へ出た者に関するあらゆる記録の閲覧権限を、セリデン公爵に一時的に付与する――そう記されていた。
……さほど意味のある権限には見えない。
少なくとも、今のところは。
週末、ハイデンの別宮。
「……すまなかったな、クラリス」
修道院から戻ったクラリスの部屋に、クエンティンが訪ねてきた。
「最近一か月のあいだに、二度目の聖域に入った人物の中で、君が探していた者はいなかった。それで……何だっけ。ルカ・メイビスという男だったな?」
「はい。使用人の資格で入っていた可能性もあります。」
クラリスは、公爵夫人を追った際の出来事を公爵に報告していたが、その中には「夫人を乗せた馬車が、聖門の検査を受けることなく、そのまま通過した」という証言も含まれていた。
その話を聞いたとき、公爵は「聖門の出入り管理記録を確認する必要があるな」と、ぽつりと漏らしていた。
クラリスは、その言葉をはっきり覚えていた。
しかし、そうはいっても、ただの囚人にすぎないクラリスが、出入り記録の確認を直接頼めるはずもない。
そこで彼女は、ここではノアの名を使った。
「必ず調べてみる――そう約束してもらったわ」
彼は、『少女の頼みとあらば、公爵も無下にはしないだろう。ただし、これは魔法使い団の案件だからね』
そう添えて、わざわざ手紙を書き、クラリスへ託してくれた。
ルカ・メイビスという名の記録が存在するかどうか――その確認を依頼したのだという。
「それで、各邸宅の使用人に至るまで洗い出してもらったけれど……その名前は、どこにもなかったそうよ」
「ああ……私、考えが甘すぎたのかしら?」
悔しさを滲ませて言うクラリスに、向かいのクエンティンは静かに首を振った。
「普通は、名前まで変えて侵入するとは思わない。ましてや、第二城壁を越える際に必要な身分証――パスの類は、そう簡単に偽造できるものじゃないからね」
「……それってつまり、偽造が“完全に不可能”というわけではない、ということですよね?」
犯罪の可能性を口にするのをためらい、クラリスは思わず声を落とした。
……というのも、なぜか心配になって、次のように付け加えて言ったのだ。
「わ、私がそうするつもりだという意味じゃありません。絶対に。」
するとクエンティンは面白がるようにくすくす笑い、クラリスの頭を手のひらで軽くぽんぽんと叩いた。
「分かってる、分かってる。もし君が身分を偽ることになったとしたら、それはきっと公爵さまの意思があってのことだろう。」
「公爵さまは、私の身分を偽らせたりはなさらないと思います。公正な方ですから。とにかく……」
クラリスは、少し疲れたように見えるクエンティンの顔を、心配そうに見つめた。
「もうお休みください。もし私のせいで、退勤が遅くなってしまったのなら、ごめんなさい。」
「いや、いいんだ。いいんだよ。一日の予定に、きちんと退勤時間があるってだけで、十分満足だ。」
「……え、公爵さまって、そんなにお仕事が多いんですか?」
「そういうよりも、私の方が先に探し回って、仕事を放っておく方が、むしろ多いくらいだよ。夜、部屋で横になっていると、あれこれ考えが浮かんでくるだろう?」
そう言われてみれば、以前、鐘を博物館へ寄贈する話も、クエンティンが公爵に報告する前に、彼自身が思いついて動いたことだった。
彼はそうやって、思いついたことに一人で没頭し、結果として毎日を慌ただしく過ごすタイプなのだ。
「……ああ、そうだ。これは今朝、ふと思い出したんだけど」
彼は、何かを思い出した様子で、廊下に積んであった書類の山を漁り始めた。
「……?」
何枚もの書類がさらさらと床に落ちたため、クラリスは慌てて拾い集めながら、彼が探しているものが見つかるのを待った。
「――あった、ここだ!」
彼が取り出したのは、一枚のメモ。
走り書きの文字で、いくつかの事柄が箇条書きに並んでいる。
「一日中その名前を追いかけていたせいか……ルカ・メイビスという名前が、まるで呪いみたいに、頭から離れなくなっていてね。だから、こんなことまで試してみたんだ。」
クラリスは書類を抱えたまま、彼が差し出した紙をそっと覗き込んだ。
そこには、ルカ・メイビス(Luca Mavis)という名前の文字を並べ替えて作った、新しい名前――いわゆるアナグラムが書き連ねられていた。
luv Macias
Camus vial
Caval Lmus
Mils Vacua
同じようなものが、百通り以上もあった。
「やってるうちに朝になるのも忘れてさ。どう?ちょっと面白そうだろ?」
クラリスは、これが本当に面白いのかは分からなかったが、とりあえずうなずいた。
「はい。一見すると、まったく別の名前みたいですね。」
「だろ?ほら、まったく違う名前さ。じゃあ……どれにしようかな。」
彼は自分で作った一覧の中から、カミュ・ヴァイアルという名だった。
「この名前で該当しそうなのは、第二城壁への入城記録だけ。出城の記録は見当たらない。常駐の使用人でもないんだ。おかしいだろ?」
「え……?」
クラリスが思わず身を強張らせると、彼は自分なりに整理していた資料を、さらにしばらく繰りながら、こう説明を続けた。
「こういう場合、本来なら城門で別途取り調べを行って、状況を確認することになる。ところが……ここで、非常に不運な出来事が起きた」
「あ、ほら。ここにある」
彼が差し出したのは、『未帰還者調査報告書』の写しだった。
「住人の私物に手を出そうとして、騎士に連行された、と記録されている。まったく……気の毒な話だよね」
クラリスは目を大きく見開いたまま、カミュ・ヴァイアルという人物の行動履歴を追った。
――それは、ちょうど彼女がクノー侯爵家を訪れていた、その日のことだった。
二つ目の聖域を出た。
手紙を手にしたままノアと向き合った、まさにその頃のことだった。
「こ、この人、どうなったんですか!?連れていかれた後は?」
「うーん……本来なら裁きを受けるはずなんだが、手続きも何もなく牢に入れられたらしい。しかも二つ目の聖域の地下牢へ、だ。」
そこは、よほどの重罪人しか送られない場所だ、と彼は付け加えた。
「た、ただ物を盗んだだけですよね?もちろん悪いことですけど……」
「少し厳しすぎるな。何を盗んだのかは分からない。被害届も別に出ていないようだし。いずれにせよ、こいつは今後、使用人として働くことはできないだろう。」
「じゃあ、もう牢から出ている可能性もありますか?」
「君もこういう話、けっこう好きなんだな?」
彼は、同志に会えてうれしいとでも言うように、にやりと笑い、眼鏡を直した。
「周りの人たちは、僕にとっては取るに足らないことだって言うんだけどね」
「ううん。私は、無駄だなんて思いません。……それで、どうなったんですか?」
「とりあえず、牢に入れられてから先は、僕の権限では閲覧できる書類がなくてさ」
「あ……」
クラリスが残念そうに声を落とすと、彼はどこか苦笑めいた微笑みを浮かべた。
「……だから、少しだけ“コネ”を使って調べてみた。これは内緒だよ?」
コネ――それは、まさに大人の世界で当たり前のように使われる、曖昧で生々しい言葉だった。
「クエンティンさんって、本当にすごいです!」
「はは。この程度さ。これも全部、僕に対する周囲の信頼があってこそ、できたことだよ」
「そうですね。私もクエンティンさんには、何でもお話ししたくなっちゃいます。……それで?結局どうなったんですか?」
「今も牢にいる。裁判すら、まだ受けていないそうだ。珍しいだろ?」
「まだ、ですか?」
「そうだ。他人の物に手を出してはいけない、というのは厳しい決まりだからな。分かったか、クラリス?この男も、どうやら君と同い年くらいらしい。これからどう生きていくのか、心配だ。」
クラリスは、灰色のローブをまとった魔法使いが、自分と同年代の少年だということを覚えていた。
カムス・ヴァイアルがルカ・メイビス本人だという確証はない。
だが、その可能性は決して小さくないように思えた。
「もちろん、私は他人の物を盗んだりしませんよ。おじさま。でも……」
「ん?まだ気になることがあるのか?」
「そのカムスという少年が、どの家門の使用人なのか、記録は残っていましたか?」
「ああ、盗難に遭う可能性のある家門のことか?もちろんだ。家門が発行する徽章がなければ、雇用関係を証明することはできないからな。」
「どの家門なのか、私が尋ねても……いいですか?」
「おかしくはないよ。その家が何か悪事を働いたわけでもないのにね。驚くな――レノクス侯爵家だ」
それはどこかで聞いたことのある名だった。
どの派閥に属する家門だったかまでは、はっきり思い出せないが。
クエンティンは、にやりと笑って答えを補足する。
「優れた橋渡し役になるには、有力貴族をあえて外側に置く判断も必要なんだ。しかもレノクスは、知っておくべき存在だろ?陛下の外戚なんだから」
「え?」
「それに――君と親しくしている、ヴァレンタイン王子殿下の外戚でもある」
……つまり。
王妃陛下の実家が、カミュ・ヴァイアルを牢に放り込んだ、という意味になる。
「もし……カミュ・ヴァイアルが、本当にその魔法使いだったとしたら……?」
クラリスは、嫌な予感を振り払うように、急いで王都へ戻らねばならないと思った。
ノアにこの事実を伝えなければならないと。