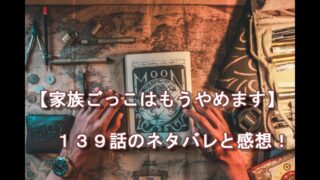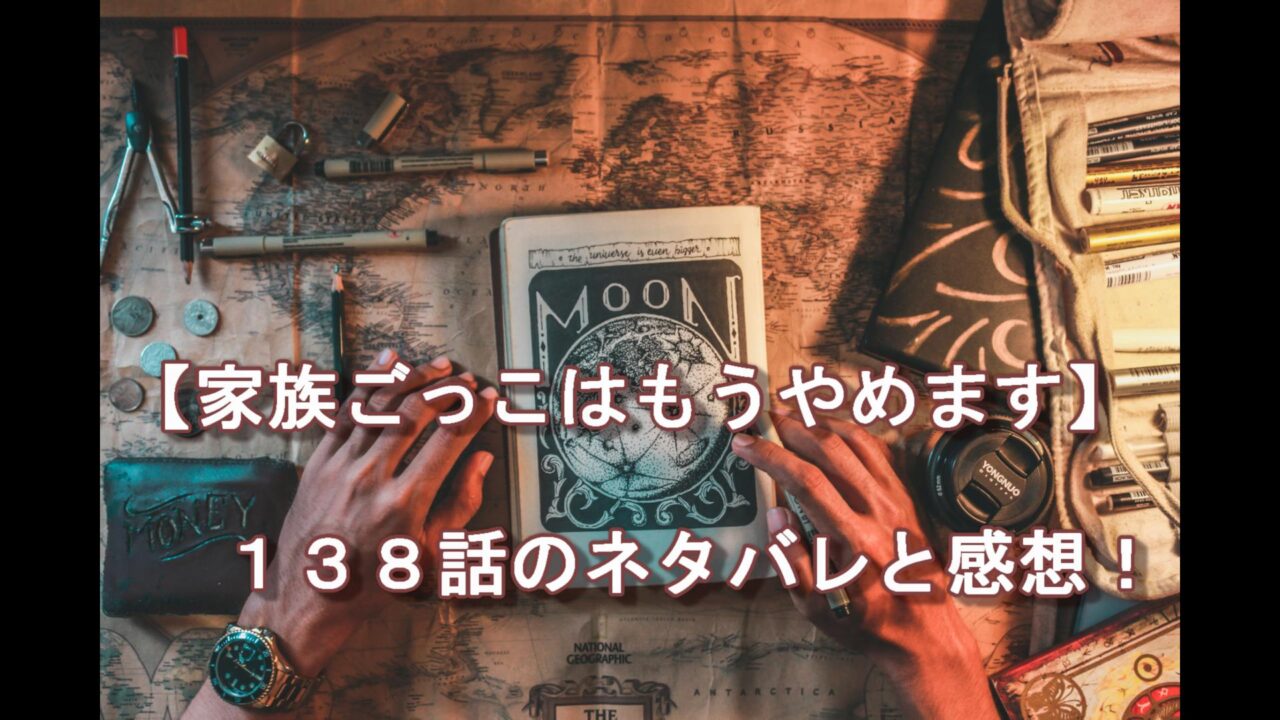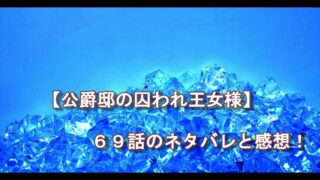こんにちは、ちゃむです。
「家族ごっこはもうやめます」を紹介させていただきます。
今回は138話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

138話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 幸せな童話③
ナビアは舞踏会でクリードと交わした会話を思い出した。
(あの時、オルゴールに合わせて踊った話をしたけど、お父さんも覚えているのかな?)
「私、小さい頃、クリードとオルゴールに合わせて踊ったことがありました。踊ったこと、覚えてる?お父さん?」
ラルクは口元を歪ませて少し笑いながら答えた。
「もちろん。お父さんは背が合わなくて、君と一緒に踊るのを諦めたんだよね。それで、あの時から気にしてデビュタントを失敗させたくなくて、急にオルゴールに合わせて踊ろうと思ったのかい?」
あの時は、チェシャレが二人のそばにやって来て、まるで幼い子供のように周りをくるくると回りながら踊っていた。
ナビアは思わずくすっと笑い、ラルクの手を取る。
舞踏会でもなく、派手な演奏曲でもないけれど、動くたびに宝石のようにきらめくナイトウェアとスリッパのおかげで、特別なパーティーの主役になった気分だった。
そんな中、ナビアは何か自分が見逃していることがあるような気がして、しばし考え込んだ。
何かが気になったのだ。
話題に関する答えを聞けなかったようだが・・・。
「ああ、黄金の輝き!お父さん、それでその黄金の輝きは何だったんですか?」
ラルクは少し黙り込んだ。
(神経をすり減らした跡だと言えば、どうしてそんなものを溜めたのかと聞かれそうだな)
そう考えると、娘の質問に嘘をつくわけにはいかず、結局すべてを正直に話さなければならないことに気づいた。
しかし、そんな話をして娘に罪悪感を抱かせたくはなかった。
「うーん、それ?まあ、なんていうか、新しく得た力ってところかな。」
ナビアは、ラルクが自分のために苦労したことを意図的に語らないようにしていることに、敏感に気づいていた。
「実はニックスから全部聞きました。」
「やれやれ、あの詐欺師め。」
ラルクは眉間にしわを寄せて不満げに言った。
「ニックスって奴はたちが悪いんだ。あまり親しくするな。」
まるで悪い友達と付き合うなと忠告する父親のような言葉だ。
ただ、ラルクが言う「悪い友達」は彼自身の神様というところが問題だった。
「うーん・・・そんなことがあるんでしょうか?」
ナビアは苦笑いを浮かべる。
ラルクは、どうにでもなれという態度で自分の偉業について軽く流すのだった。
「じゃあ、お父さんが一番強いってことですか?」
「うん。お父さんは火神だった頃から他の神よりも強かったんだ。」
ナビアは、無限に生きる回帰者であることが何か特別なことなのかと思いながら、驚嘆の表情を浮かべた。
もっとも、ラルクにとってはそれが当たり前で、何の疑問も抱くことなく自信満々だった。
オルゴールの演奏が止まる。
ラルクはその場でナビアの手を取り、軽々と抱き上げると、そのままダンスをするようにベッドに連れて行った。
ナビアは笑い声を上げ、まるでお父さんのいたずらに喜ぶ小さな少女になった気分だった。
「さあ、お嬢さん、もう寝る時間だ。遅く寝ると背が伸びないぞ。」
「これでもうほとんど育った気がするんですけど・・・こんなに大きくなったことは今までありません。」
「お父さんみたいに大きくなりたければ、早く寝ないとだめだぞ。」
ナビアは目に眠気を感じながらも、すぐに眠ることが惜しく思えた。
いや、むしろ怖かったのかもしれない。
(もしこれが夢だったらどうしよう?)
あまりにも切実に望んだことだから、幸せな夢を見ているだけだったらどうしよう?
ナビアは黙って笑みを浮かべながら父の手を握る。
その表情は一見すると全く不安を感じさせない、しっかりとしたものだった。
しかし、ラルクには無意識にナビアの心配が伝わっていたようだ。
彼はそっと娘の髪を撫でながら言った。
「お前が寝て起きた時にも、私はここにいる。だから心配するな。」
「はい。」
ナビアはその言葉に考えを巡らせ、少しだけ気持ちが落ち着いた。
ラルクは微笑んだ。
(そんなに表情に出ていたのかな?)
彼女は静かにベッドに横たわる。
ラルクは布団を丁寧にかけ直し、髪を整えてあげると、ベッドの端に腰掛けた。
「寝たいなら目を閉じないと。」
彼はいたずらっぽく手のひらを広げてナビアの顔の半分を覆った。
ナビアは顔の半分が隠れた状態で、唇だけを動かして秘密を打ち明けるように小さくささやいた。
「お父さんが戻ってきたらどうなるか、ずっと想像していました。」
ラルクはしばらく言葉が出なかった。
幸いにも娘の目が布団で隠れていたので、動揺が顔に出ずに済んだ。
彼はどういうわけか冷静でいられた。
彼は可能な限り穏やかに聞こえる声で話す。
「どんな想像?」
「うん・・・お父さんが笑っている姿を思い浮かべたんです・・・。」
ナビアは小さく微笑みながら、詰まった声で答える。
「だって、私はお父さんを見る瞬間から幸せになるんですから。」
「・・・。」
「だからお父さんにも幸せに笑っていてほしい、そう思ったんです・・・。」
無理に申し訳なさそうにすることもなく、まるで長い旅から戻ってきた人のようにお互い微笑み合った。
「お父さんが幸せならいいなと思います。」
ラルクは何も言わなかった。
ただ、そっと手を下ろし、いつの間にか目を閉じている娘の顔をじっと見つめていた。
ナビアは長い旅の前の記憶よりも少し成長していたが、幼い頃の面影がまだかすかに残っていた。
その顔を見ていると、否定しようのない幸福感が胸に満ちてきた。
ラルクはどうしようもなく幸せを感じた。
「そうだな。君の言う通り、幸せだ。」
娘が幸せだと言う。
そしてそのことで自分を見てさらに幸せになれると言うのだから、どうしてそのように思わないでいられるだろうか?
彼は気付かぬうちに、既に幸せな笑顔を浮かべていた。
ナビアはもう少し遅く眠りにつきたかった。
でも世界で最も安全な、冷たい冬の香りの中で心をすっかり委ねて、そっと訪れた眠りに身を任せていく。
「もう、どこにも行かないでください・・・」
ナビアはラルクの手をしっかりと握ったまま、眠りについた。
ラルクは柔らかな眼差しで、愛しい娘に優しい声で囁いた。
「もうどこにも行かないよ。今日からは安心してぐっすりおやすみ。」
神だろうと悪夢だろうと、お父さんが全部追い払ってあげるから。