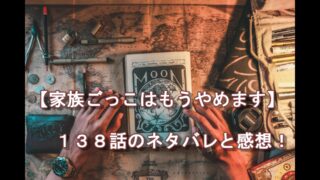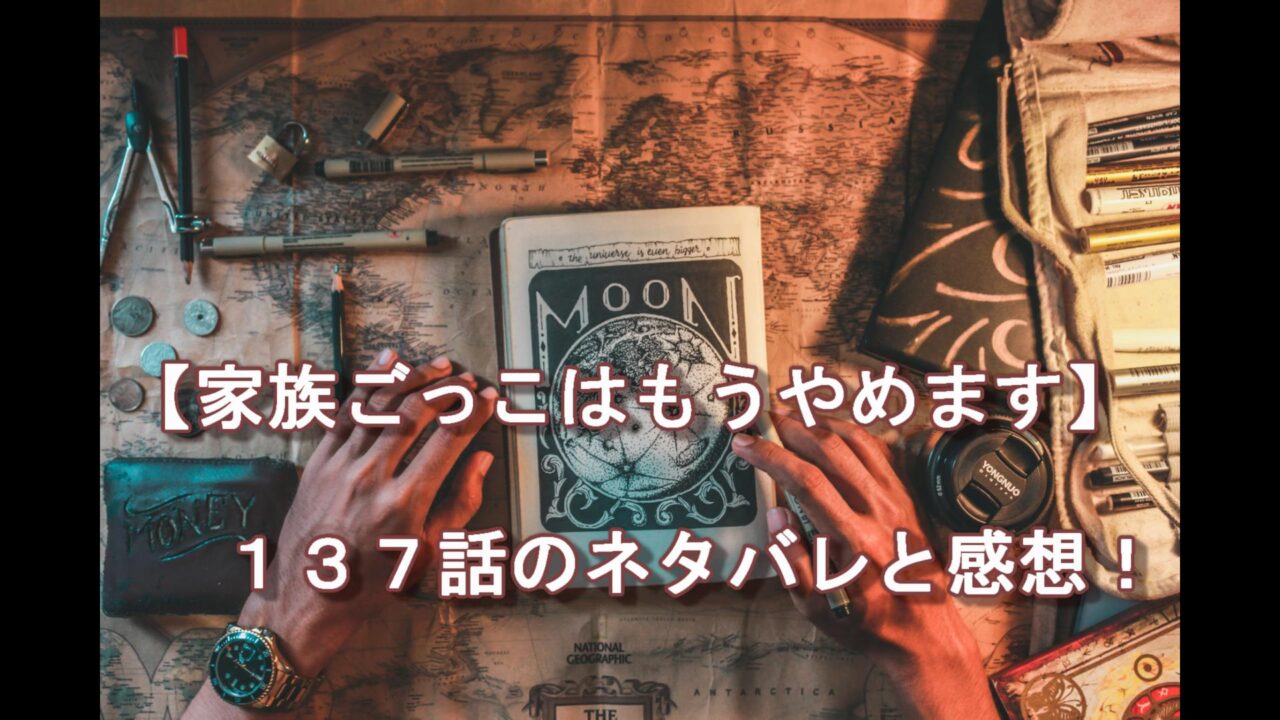こんにちは、ちゃむです。
「家族ごっこはもうやめます」を紹介させていただきます。
今回は137話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

137話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 幸せな童話②
ニックスはナビアの表情が妙に変わっていく様子を見つめながら、薄く笑みを浮かべて言った。
—そうしたいのかい?
「はい?」
ナビアは心が浮き立つような感覚に動揺しながらも、ニックスを見つめる。
—君の表情、すごく幸せそうに見えるよ。
幸せだった。
いろいろな苦労はあったけれど、父が目覚めた日だから。
(ニックスが話したいことは、きっとクリードについてだろう。)
ナビアはクリードを思い浮かべた。
どこかぎこちなく新鮮な気持ちが、彼女の胸に甘美な痛みをもたらす。
鼓動する胸元に手をそっと当ててみる。
これは・・・恋なのだろうか?
—クリードの話をするたび、君が笑っているのに気づいていないのかい?
「私が・・・ですか?」
ナビアは、自分でも知らず口元を触れた。
私、笑っていた? 無意識だったなんて・・・。
—貴族にとって結婚は社会的にとても重要な問題だろう?それなら、これからは言うことをよく聞いてくれる若くてハンサムな婚約者を探しなさい。
ナビアは困惑した表情でフォークをいじり、軽く震えた。
「本当に・・・神様がこんなに俗っぽくても大丈夫なんですか?」
—神にも目があるんだから、若くてハンサムな方がいいに決まってるだろう?
ナビアは思わずフォークを握りしめた。
正直なところ、ラグナとエリクに囲まれて美的感覚が磨かれたため、クリードはどこか異質に感じられる。
けれど、見た目が理由で惹かれているわけではなかった。
彼と一緒にいる時の安堵感や、自分が寄り添った時に感じた力強い腕の安定感、そして逞しくて男らしい彼の体つき——それが胸を打つ理由だった。
(私、何を考えているの?)
ナビアはなぜかまた暑くなり、手で頬を冷やさなければならなかった。
—はあ、良い時代だな。
ニックスはまた意地悪く笑い、ナビアをからかう。
ナビアは小さく息を吐いて、ついに笑い出してしまった。
(私が恋愛の話をするなんて。)
長い人生でこんなことが起きるなんて思いもしなかった。
ニックスはドレッサーに寄りかかりながら、ゆっくりと別れの挨拶をした。
—さて、私はそろそろ行くとしよう。
「もう行くんですか?」
ナビアは名残惜しさを抑えられず、ニックスの手を掴んだ。
ニックスはまるで孫娘と別れる前のおばあさんのように、優しくその手を包み込むように握り返す。
「また会いたいです。」
—私もまた君に会いたいよ。こうして愛おしい女神と話し、心が通じ合うなんて、本当に運がいい神だ。
「私こそ運がいい女神なんですよ!」
ニックスは穏やかに笑い、ナビアの手をそっと握り直した。
そしてある瞬間、その動きが止まった。去ったのだ。
「別れというのは、いつだって寂しいものね。」
ナビアは人形をしっかりと抱きしめる。
あっという間に時間は過ぎていった。
夜明けになり、疲れが襲ってきた。
それでもナビアは眠らずに部屋をうろうろしていた。
そのとき、待ちわびていたノックの音が聞こえた。
「トントン。」
「お父さん。」
窓から差し込む月明かりでナビアが眠れないことを察したラルクは、仕事を終えて彼女の部屋を訪れたのだった。
ナビアは嬉しそうに微笑み、ドアへ駆け寄り勢いよく開けた。
「お父さん!」
「まだ寝ていなかったのか?」
ラルクはナビアの髪を軽く撫でながら、心配そうな顔をした。
「眠れなくて。」
嘘はかなり白々しかったが、堂々とした態度で嘘をついた。
ラルクは「嘘をつくな」と言いながら、ナビアの髪を痛めないように注意深くほぐしながら部屋に入る。
いつの間にか彼は長い髪を丁寧に整えていた。
その様子にナビアは、久しぶりに見る父親の姿が新鮮に映った。
「なんだか、初めてお父さんに会ったときみたい。」
そう言うと、ラルクはニヤリと笑った。
「まだ若くてハンサムで感動しているってことかな?」
「いいえ、髪が長いという意味です。」
「素直じゃないな。」
ナビアは正確な事実を述べただけだったが、素直でないわけではなかったので、少し戸惑っていた。
「そうだ、お父さんはもともとこうだったんだ。」
元々、厳格だと非難する余地のない人。
ラルク・エセルレッドは、もともとそんな人だった。
ナビアはふとした瞬間に、新しい父親が自分のもとに帰ってきたと強く感じた。
それで、これまでの努力や苦労のすべてがこの瞬間のためだったのだと理解し、ラルクをしっかりと抱きしめる。
「お疲れさまでした、お父さん。」
ラルクは穏やかに微笑みながら、彼女を優しく抱き返した。
「君のほうこそ。」
飾り気のない、率直な言葉だったが、それがまたラルクらしかった。
ナビアは小さく笑いながら、慎重に質問を続けた。
「ところで、アレス皇帝に仕えたというその件はどうなったのですか?ちゃんと解決したんですか?」
「うん、心配いらない。」
「火神との契約は終わったんですか?これで、帰還も均衡も全部終わりなんですか?」
「うん。完全に終わりだ。」
「でも、あの黄金の光って何だったんですか?」
ラルクは質問を矢継ぎ早にする娘を見て、少しおかしそうに笑った。
「どうしてそんなに気になるんだい?聞いたところによると、五歳の子どもは何かするたびに『なぜ?なぜ?』って聞くらしいけど、うちの娘は五歳だったのかな?」
ナビアはすぐさま口をへの字に曲げた。
それを見て、ラルクは「わかった」と言わんばかりに唇を引き締めた。
「その表情はだめだよ。父さんにお小言を言う前の表情は」
「そんな表情、どこがですか?」
「今まさにそんな表情してたじゃないか!」
ナビアは眉をひそめて首を傾げた。
ラルクは回れ右をしたナビアの手をつかんで軽く揺さぶりながら尋ねた。
「今日は君のデビュタントだったんだよね?」
ナビアはいつの間にか話題が変わったことに気づかず、肩をすくめた。
「はい。世界で一番騒がしいデビュタントになっちゃいましたけど、それでもまあ成功した方だと思います。」
とにかく、父も戻ってきて、望んでいたこともすべて手に入れたんだから、このくらいなら十分成功といえるデビュタントではなかっただろうか?
ラルクは難しいのか、という表情で微笑みながら聞いた。
「誰と踊ったんだ?」
「クリードと踊りました。」
「一回?」
「はい。その後、こんな事件が起きたんです。」
ラルクはあたかも良かったとでも言うかのように微笑んで指を弾いた。
すると、ナビアが着ているナイトガウンがキラキラと輝き、ダイヤモンドでできたドレスのように見えた。
白いアンゴラのスリッパもドレスのようにきらきらと輝いていた。
どんなデビュタントドレスも今のこのガウンよりも特別ではないように感じた。
「わあ・・・。お父さん、まるで童話に出てくる妖精みたいだよ。」
「本当にそう思う?」
ラルクは娘の純粋な感嘆の言葉を聞き、思わず微笑んで軽くからかった。
彼はオルゴールの箱の蓋を一生懸命開け、音楽が流れ出すと、コンソールテーブルの上に置いた。
そして優雅な動作でナビアに手を差し伸べた。
「私と踊っていただけますか、お嬢様?」