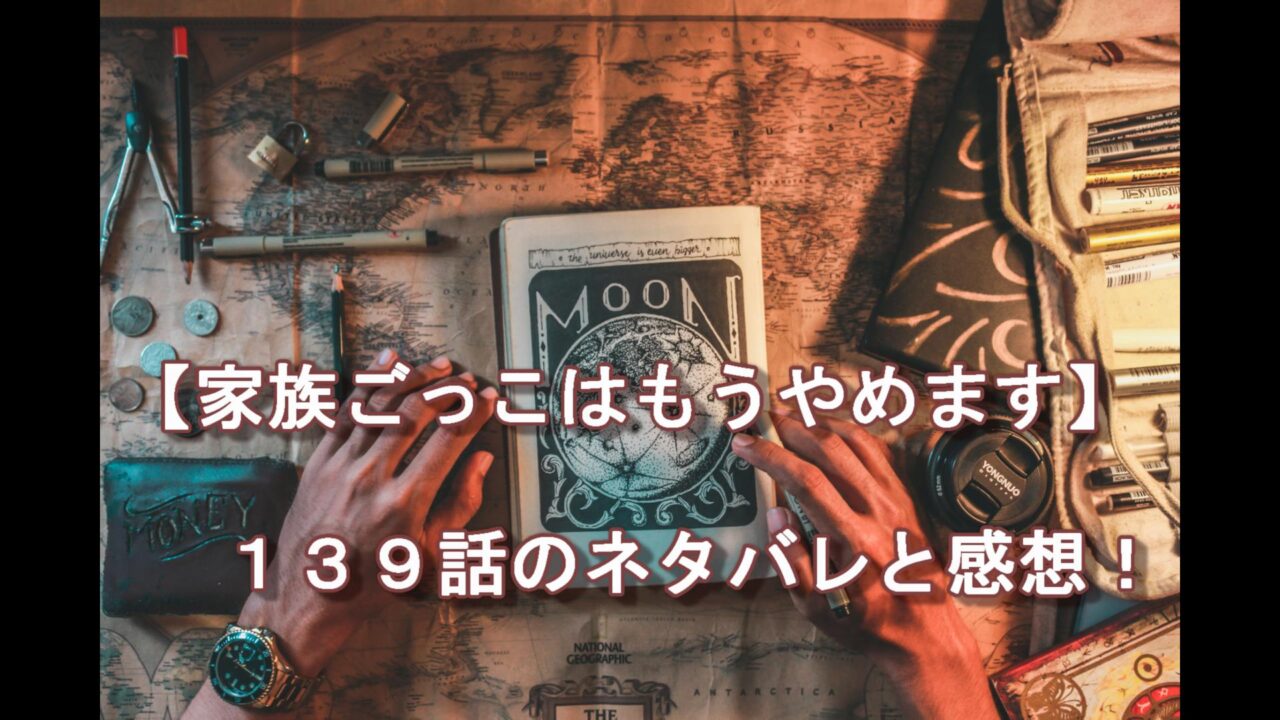こんにちは、ちゃむです。
「家族ごっこはもうやめます」を紹介させていただきます。
今回は139話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

139話 ネタバレ
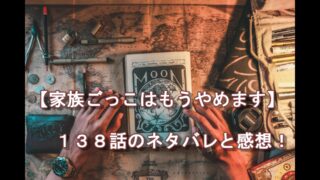
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 学者たちの陰謀
朝、世界がひっくり返った。
皇帝が暗殺されたのだ。
彼の妻と息子が罪に問われ、それを実行するために悪魔と手を組んだと言われていた。
皇権に強い反発心を抱いていたある文学者が書いた小説のような出来事が現実に起きたのだ。
「それが本当に悪魔の仕業だったのか!」
時代は大きく変わり、宗教の力がかつてほどではなくなった今でも、悪魔は依然として恐ろしく、人々を震え上がらせる。
神聖な侮辱は非常に重い罪とされ、民衆の怒りは燃え上がっていた。
「関係者を全員捕まえて処罰せよ!」
「連座した者たちの罪を暴け!」
彼らの声は乾いた山に広がる火の手のように瞬く間に大きくなった。
政治的に派閥が分かれていた貴族たちも、今回の事件に関しては世論に異を唱えることができなかった。
当然ながら、彼らもまた被害者だったのだから。
「すべての元凶は、皇帝が悪魔と手を結んだことだ。」
ある者たちはこう口々に言い始めた。
最も尊い皇帝が悪魔に堕ちたという事実に、誰もが震える。
そして、その罪がどこまで広がるのかを誰もが恐れていた。
「皇帝の家族も、もちろん処罰するべきだ!」
「血を流すことでしか、贖いはできない!」
その声は、無限に広がり続け、ついには王国全体を包み込むほどだった。
市民たちの怒りと恐怖は、ひとつの波となって膨れ上がり、止めようのない勢いを持っていた。
しかし、その中で誰もが気づかなかったことがある。
それは、皇帝の死が、意図されたものではなく、何者かによって仕組まれたものであったこと。
そして、その仕組んだ者たちが、今や新たな力を手に入れていたことだ。
ナビアは少し驚いたように目を見開く。
彼女は一瞬、何が起きているのか理解できなかった。
「まさか、お父様がその・・・」
「私がその者たちに関わっていた。」
ラルクは静かに答える。
彼の目はどこか遠くを見つめるように、深い思索にふけっていた。
「これから先、私たちの戦いはどんどん激しくなる。しかし、君に伝えておきたいのは、それでも私は必ず君を守り続けるということだ。」
ナビアはその言葉に安心感を覚える。
父がいれば、何があっても乗り越えられると感じたから。
しかし、同時にその重い言葉の意味が心にのしかかるようにも思えた。
「お父様が守ってくれると言っても、それは私だけじゃなく、国の未来にも関わるんですよね?」
ラルクは少し黙った後、頷いた。
「君が想像している以上に、これからの戦いは厳しい。でも、覚えておいてほしい。どんな困難も、乗り越えられないものはない。」
ナビアは深く息を吐き、覚悟を決めたような表情で頷いた。
ナビアが自分の手の中に収まっていれば、躊躇なく帝国と大陸を支配できただろう!
ニカンはその子がずっと自分の娘だったらどうだったのか、思いを巡らせるのを止めることができなかった。
「ナビアに呪いをかけたのだから、彼女を取り戻すことはできないだろうか? ラルク、その小さな問題さえなければ・・・。」
これまでナビアと対話する機会がなかったのは、躊躇なくラルクとエルキンが妨害したせいだった。
ニカンは必要に応じて自分に有利な状況を作り上げていった。
「ご主人様、リンドです。」
「入りなさい。」
執事が入ってきて、困惑した表情で報告する。
「エドワード・ウェイン伯爵との接触に失敗しました。手がかりを追ったところ、彼はエセルレッドに身を寄せたようです・・・。」
ガン!
「なんて役立たずだ!」
エドワードは徐々にアグニスと距離を置きたいと思ったのか、数年前にアカデミーを出た後、ほとんど消息を絶っていた。
ニカンもまた、それほど大きな役には立たないエドワードへの関心を薄れさせていたが、突然エセルレッドが急変した態度を見せた時から、再び彼に目を向け始めた。
その時、エドワードが言った。
『申し訳ありませんが、私はこの件から手を引かせていただきます。』
『お前はすでに私と同じ船に乗っている。呪いに関する事実をエセルレッドに告発すれば、お前だけが死んで終わるという話だ。』
するとエドワードは、面白い話を聞いたかのように微笑んだ。
『悪くない話ですね。』
「見つけ出したら必ずその首を刎ねて殺してやる・・・!」
ニカンが歯ぎしりしながらそう思っている時だった。
一人の使用人が執務室の扉をノックして入ってきて報告する。
「ご主人様、少しお会いしたいという方々がいらっしゃいます。訪ねてきた中にネイト伯爵もいました。」
「ネイト伯爵? そこはかつてエセルレッドの側近だった家門ではないか? もう政治活動は完全に引退したものと思っていたが。」
「彼らの集団は、この件を解決する方法を持っていると言っています。」
解決する方法だと?
ニカンは妙な気分に襲われる。
どうやらただの噂話やくだらない提案をしに来た人々ではないという直感があった。
「・・・会ってみよう。」
彼はすぐに客人たちを応接室に案内するよう命じ、乱れた服装を整えてその場所へ向かった。
応接室の扉が開くと、五人の男たちが席についていた。
彼らは立ち上がり挨拶をした。
「アグニス公爵様にお目にかかれて光栄です。」
その中の一人の老人がネイト伯爵と思われた。
他の者たちの服装は、ジェントリ階級の知識人のように見える。
ニカンの疑念に満ちた視線に気付いた学者風のすっきりとした服装の男は、片方の眼鏡をかけ直しながら自己紹介を始めた。
「私たちは長い間、セウォル神学を研究してきた者たちです。ええ、正確にはエセルレッドを研究対象としている学者たちとお考えいただければいいかと思います。」
エセルレッドと神学に一体どんな関係があるというのか?
ニカンはとりあえず全員に座るよう促した。
「それで、その研究がこの件をどう解決するというのかね?」
今回は、金縁の丸い眼鏡をかけた痩せた学者が答えた。
「私たちはエセルレッド公女がニクスの化身であると確信しています。宴会場で発揮された力は、化身の権能だったのでしょう。」
「化身・・・?」
「それだけではありません。その場で悪魔とされた明確なアレス皇子の状態も、外部の神の影響だった可能性があります。」
そう言って彼は懐から一冊の本を取り出し、テーブルに置いた。
その本は『万神典』という題名だった。
ニカンは疑念の目でその本を見つめる。
(どうしてこの本からこんな不気味な気配が漂ってくるんだ・・・?)
本からはまるで殺意を帯びたような感覚が感じられた。
それは宴会場で感じたものとさらに似ているものだ。
邪悪な気配にも似ている。
ただし、こちらの方がより洗練されているように感じられた。
学者はその本をニカンの前に押し出しながら言った。
「これは、皇后陛下が直接お受け取りになった本です。これによってアレス皇子の体に神を宿らせたのです。」
「これを私に話す理由は何だ?」
その問いに対し、ネイト伯爵が答えた。
「新たな神を作るのです。」
「・・・。」
(狂っている。完全に狂っている。)
まるで正気を失った狂信者と向き合っているような不気味な感覚がニカンを包み込んだ。
そのせいか、心臓がドキドキと激しく脈打ち始めた。