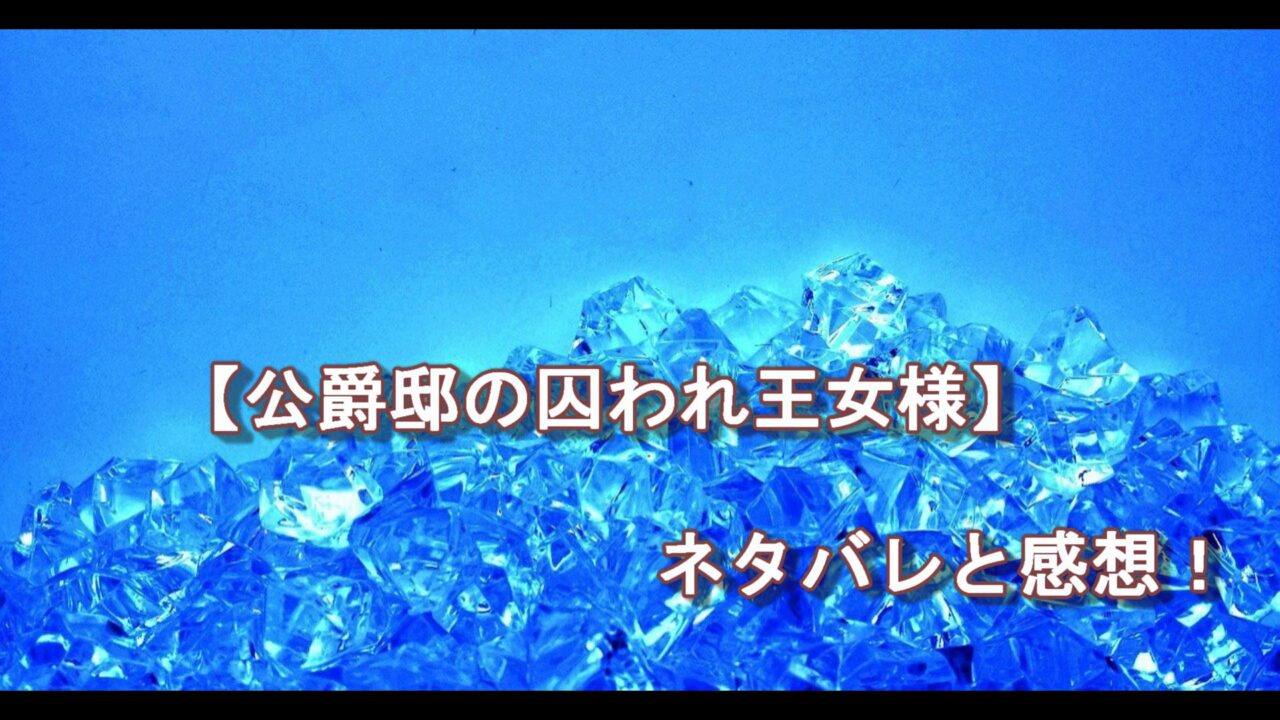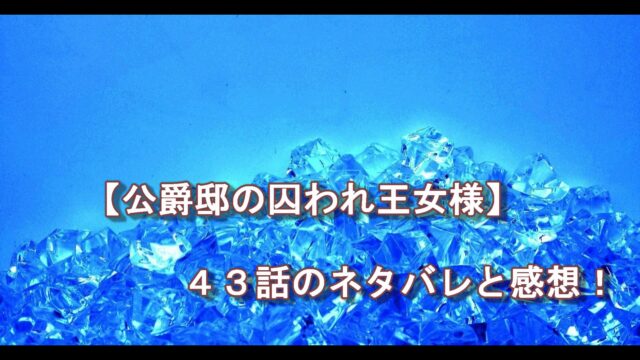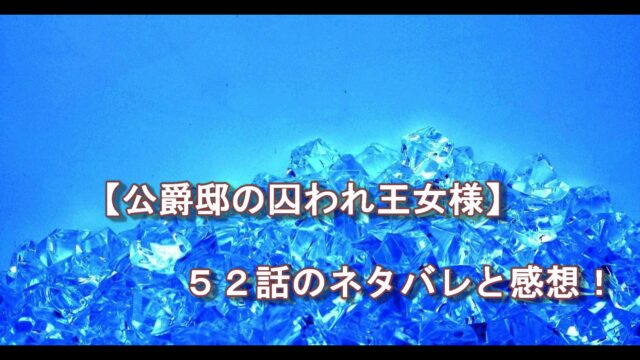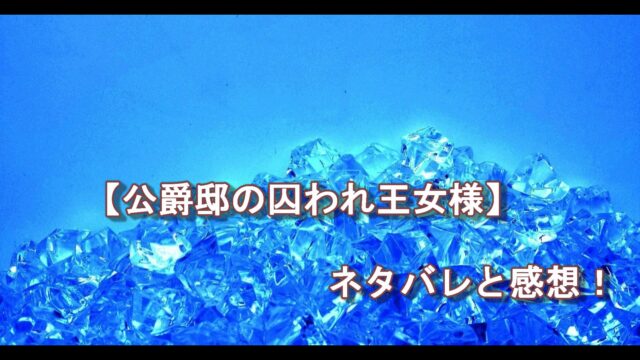こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
今回は74話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

74話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- いつの間にか15歳④
マキシミリアンが宮殿に戻ると、彼はすぐに魔法使いの城に行くことになったことをクラリスに伝えることにした。
彼はクラリスの反応を想像してみたが、それは次のようなものだ。
『魔法使いの城?わあ、本当に嬉しい!』
外向的で孤独を嫌うクラリスは、いつも友達を欲しがっていた。
「魔法使いの城ですって・・・楽しみですね。」
しかし、マキシミリアンが話した話を聞いたクラリスの反応は、彼が思っていた以上に控えめなものだ。
明らかに喜んではいるものの、何か別の不安が彼女の感情を抑えているように見える。
「何かあったのか?心配していることでもあるのか?」
彼は遠慮なく尋ねた。
無駄な言葉で時間を引き延ばすようなことはしない。
なぜならクラリスが無駄に時間を使うことを嫌っているのを知っていたからだ。
「今日、王子様から首都園について聞きました。」
「公務試験の準備に関する話だったかな?」
「はい、そうです。公爵様もご存じですよね?」
「何度かクエンティンの話を聞いたことがある。」
しかし、詳細については知らなかった。
ただ、少し前に説明を受けたことは覚えている。
マキシミリアンは小さく息をついた。
首都園について話してくれたのは、つい昨日出会ったライサンダーだった。
「首都園で学べば模擬試験を受ける資格が得られる。私の後見人がそこで有益な経験を積むのはいいことだと思うんだけど、兄上はどう思いますか?」
「いいね・・・やってみるといいだろう。」
「ヴァレンタインも同じ時期に行くことになるから、安全面では心配しなくて大丈夫ですね。」
「ヴァレンタイン王子も一緒に行くんですか。」
その瞬間、マキシミリアンは自分でも気づかないうちに顔をほころばせていた。
ライサンダーが拍手して笑う。
「クスクス、ああ・・・本当に!兄上がまるで娘を持つ父親のように振る舞うなんて!」
「そんなことはありません。ただ・・・」
ヴァレンタインが何かしら抜けている部分があるという事実を少し気にしていただけだった。
彼と会った後、クラリスが何度も戻ってきて非常に激しい憤りを露わにしたという話を聞いたのだ。
そんな弁解の余地もなく、ライサンダーの話が続けられた。
「いやあ、あの王女を生かしておいてよかったね。少しくらい未練が残るだろうけど。」
しばらくクスクス笑っていた彼は、さらりと流れる金髪をかき上げながら再びマキシミリアンを見やった。
一瞬微笑みが消えた顔には冷淡な光だけが残っていた。
「こんなに面白い子が・・・3年後には死ななきゃならないなんて。」
「法ですから・・・。」
マキシミリアンは、いつもと変わらぬ落ち着いた口調で静かに答える。
しかし、その答えは最後まで続けられることはなかった。
何故だか自分でも理由がよくわからなかったのだが。
「そうだ、後悔を残さないための法だよ。滅びた王国の主とその血族に。」
ライサンダーは話を続けるのをやめ、口を閉じたかのように見えた。
「即刻処刑される。そして・・・葬儀は行われない。」
またしても奇妙な感覚がマキシミリアンの息を詰まらせる。
彼の人生において常に「基準」として存在してきた法が、今回は彼の心臓を痛めつけるように押し付けてきたように感じられた。
まるで・・・。
「それが王だ。」
沈黙が長引きそうになったとき、ライサンダーが再び口を開いた。
マキシミリアンは考えを振り払うようにし、自分の椅子の隣に目をやりながら軽く微笑んだ。
「便利な役割だね。」
「いいえ、王は万人を代弁する存在です。全てを誰よりも大切にし、重い責任を一人で背負っている。」
「何?クスクス・・・。まあ、兄上ならそういう王になれただろうが。」
彼は目の前に差し出された書類を手に取り、マキシミリアンの前に示した。
「俺は母上が送ってくるこの書類に印を押すだけだ。」
「・・・。」
「彼女の大きな意志さえ守れば、俺の自由は常に保証される。酒を飲もうが、女と会おうが・・・心に浮かぶ罪悪感を告白しようがな。」
その瞬間、マキシミリアンの体がピクリと震える。
「もう、本当に!」
彼の反応が楽しかったのか、ライサンダーは再び愉快そうに笑い出した。
だが、それもほんの一瞬のことだった。
彼はその場に立ち上がり「でも、兄上。」
なぜか苛立ちが混ざった表情を浮かべて前に近づいた。
その瞬間、軽い酒の匂いが漂った。
「あの子は絶対に許さない。必ず兄上が自らその首を斬り、私の前に持ってきてください。必ずそうしてね。うん?」
「・・・」
その言葉にマキシミリアンは何も答えられなかった。
「公爵様、私が首都で勉強するのは過剰なことなのでしょうか?もちろん、今まで家庭教師をつけていただいたのも十分すぎるくらいですが・・・。首都には他にもたくさんの人がいますし。」
マキシミリアンは昨日の記憶を掘り起こすようにして答える。
「君の身分は何だっけ?」
「えっと、それは・・・。」
クラリスは自分の首に掛けられたペンダントを握った。
「私は全王家の庇護対象です。16歳になるまでは。」
「そうか。それなら、君に過剰なことなど何もないよ。むしろ問題があるとすれば、それは首都にあるだろうね。」
マキシミリアンは、クラリスが模擬試験に関心を持っているのではないかと考え、昨日から調査を進めていた。
その過程で、首都院のとんでもない規則をいくつか発見した。
「首都院では間食を一切提供せず、食事を一日三回に制限しているらしい。」
「食事制限なんておかしいですね、公爵様。」
「食事というのは、回数を減らしてはいけない。活動量に応じて柔軟性を持たせるべきだ。セリデン邸宅のようにな。」
「でも、私はいつも三食だけですよ。」
「さらに、義務的な運動時間が一律で決まっているらしい。毎朝庭を走るんだと。」
「それは・・・良いことではないですか?」
「運動時間というのは、個人の能力や毎日の体調に応じて調整するべきだ。絶対的な時間や強度を押し付けるのは、かえって健康を害する場合もある。」
マキシミリアンの表情は真剣だ。
首都院での団体生活がクラリスにとって良い選択なのかを慎重に考えている。
正しい成長を妨げる要因があまりにも多かった。
「何よりも、彼らが誇る『自習室』の机や椅子も、それほど良いものではなかったな。」
「まあ、公爵様!高価な机を使うことが、必ずしも勉強がうまくいく理由にはなりませんよ。」
「寄宿舎で提供されるベッドも、公爵家のベッドと比べたら比べ物にならないレベルだ。」
「どんなベッドも、セリデン邸で私が使っているベッドと比べたら、そういう結論になるでしょうね?」
「いずれにしても、良い家具は背中の健康と密接に関係している。それは一生の生活の質に影響を与えるものだ・・・。」
マキシミリアンは、自分でも気づかぬうちに「一生」という言葉を使い、言葉を失う。
「公爵様は本当に親切すぎますね。」
それが、数年後に彼女の命を奪った人物を指す話ではなかったため、マキシミリアンの表情はさらに硬くなった。
彼はゆっくりとため息をついた。
「いや・・・私は。」
「私を本気で心配してくれているじゃないですか。」
「それは。」
「わかっています。私が17歳まで健康に成長しなければならないからですよね?」
「・・・そうだ。」
「心配しないでください。私は公爵様の期待に恥じない17歳になりますから。」
そして彼の手に白い紙が渡される。
マキシミリアンはなぜか分からない苦しさが押し寄せ、クラリスと離れることができないという思いに駆られた。
急いで紙を握ると、すぐ傍から立っていたクエンティンが入ってきた。
「クラリス。」
「はい?」
「私はもう行かないといけないようだ。お前が望むのなら都にも行けばいい。父上もそれを望んでいるようだし。」
「父上が望んでいるとおっしゃるのですか?」
「そうだ。お前が本当に行きたいのであれば、行けばいい。」
その言葉にクラリスは目を大きく見開き、マキシミリアンの前へと歩み寄った。
いつも腰のあたりでちょこまかしていた小さな子供だったのに、今では彼の胸の高さほどまで成長していた。
むしろ成長しなければよかったのに、と思う。
マキシミリアンは、そんな考えが自然に浮かんでしまった自分を責めながら口を開いた。
「もし許されるなら、私は行きたいです!」
「・・・もちろん許す。」
「まさか公爵様が私を引き止めることはないとは思いませんでした・・・。」
「お前がやりたいことをさせるのも、私の務めの一部だ。」
「ありがとうございます。」
「そして、これからはクエンティンがサポートすることになるだろう。」
「え・・・それは本当ですか?」
公爵に呼ばれて来たものの、扉のそばで立ち尽くしていた彼は、突然任務を押し付けられたことで無意識に戸惑っている様子だった。
「そうだ、クラリスが首都学院に入学することになる。お前は首都学院で学んだ経験があるのだから、この任務に最も適任だろう。」
「いやいや、公爵様。それはもう何年も前のことですよ!」
彼が反論しようとした時、クラリスがクエンティンの前に歩み寄り、礼儀正しく挨拶をした。
「私を助けてくださるなんて、本当にありがとうございます、クエンティン叔父様。」
「え? ああ・・・。」
「知らない場所に行くことになって少し怖かったのですが、叔父様が助けてくださるなら、何一つ心配することはなさそうです。」
クエンティンはすぐににっこりと笑顔を浮かべる。
もともと子どもを見ると可愛がる性分だったが、数年一緒に過ごすうちにさらに愛着が湧いたのか、彼はクラリスをまるで自分の娘のように丁寧に扱おうと心に決めたかのようだ。
彼は胸を張り出し、両手をバンと叩き合わせる。
「そうだ!心配することは何もない。首都学院なんて、全て私の手のひらの中にある場所も同然だ!何でも任せろ、わかったか?」
「はい、おじさま!」
「はぁ、可愛いなあ。相変わらずこんなに幼いとは、どうしてくれるんだ。」
彼は相変わらず可愛がりながら、クラリスの髪をやさしく撫でていたが・・・。
「・・・っ!」
ふと険しい目つきで自分を睨みつけるマクシミリアンに気づき、その手をそっと下ろす。